EDITOR BLOG

調査報道は鴎外史伝に学べ
Σtoicaのタイトルロールで、なぜ鴎外史伝を調査報道の鑑としているのか、怪訝に思った人もいるだろう。説明しておこう。
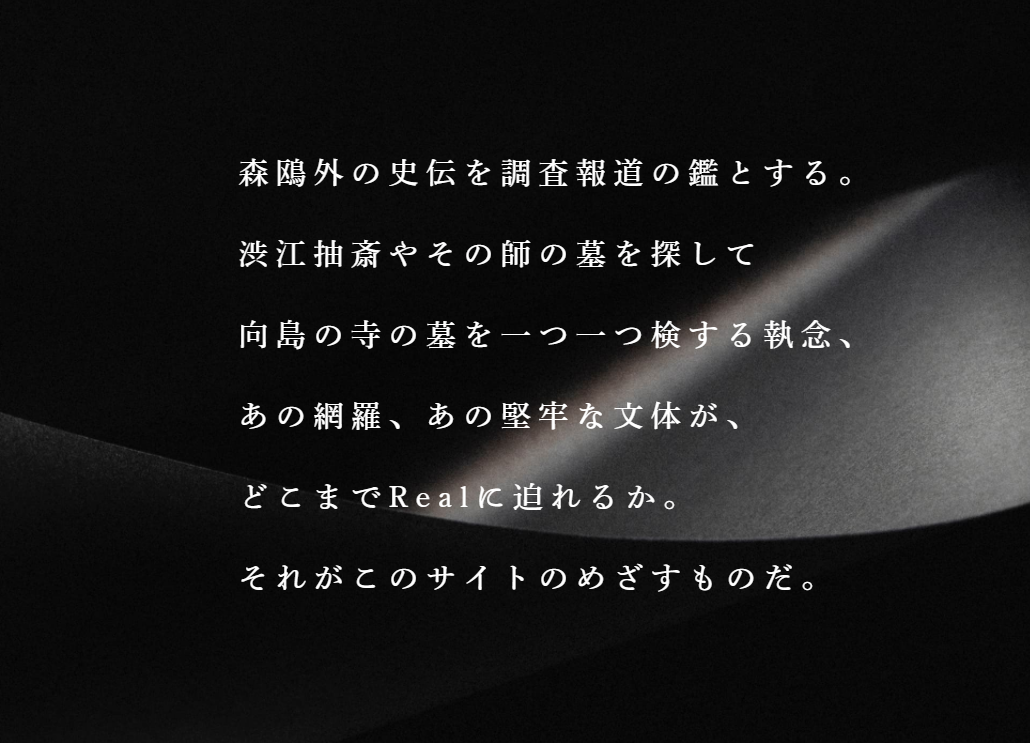
たとえば、古武鑑や江戸切絵図の蒐集家だった痘医、渋江道純の号が抽斎だと突き止めるのに、ここまでやるかと思うほど鴎外は足を使った。史伝第一弾の『渋江抽斎』は、墓碑探偵の堂々たるInvestigative reporting(調査報道)と思えてならない。以下のあたりを読むと、足まめに谷中の墓地と書物の間をうろうろしている鴎外の姿が、鮮やかに浮かんでこないだろうか。
わたくしは谷中の感応寺に往つて、抽斎の墓を訪ねた。墓は容易く見附けられた。南向の本堂の西側に、西に面して立つてゐる。「抽斎渋江君墓碣銘」といふ篆額も墓誌銘も、皆小島成斎の書である。〔海保〕漁村の文は頗る長い。後に保さんに聞けば、これでも碑が余り大きくなるのを恐れて、割愛して刪除したものださうである。『喫茗雑話』の載する所は三分の一にも足りない。わたくしはまた後に五弓雪窓がこの文を『事実文編』巻の七十二に収めてゐるのを知った。国書刊行会本を閲するに、誤脱はないやうである。(森鴎外『渋江抽斎』その八)
鴎外は官衙の一室で抽斎の嗣子、保と対面できたけれど、毎度すんなりいくとは限らない。抽斎の考証学の師、市野迷庵や狩谷棭斎、医学の師である伊澤蘭軒から池田京水へとたどって、京水の墓が行方知れずと気づいた。
保は幼いころ詣でたその墓が向島にあったことを覚えているが、寺の名を記憶していない。医史学の富士川游に「常念寺の傍」と聞き、鴎外も幼時向島小梅村にいたから土地勘があったのだが、「本堂の周囲にある墓をも、境内の末寺の庭にある墓をも一つ一つ検した」にもかかわらず、みつからない。
養父瑞仙の墓が向島嶺松寺にあり、その傍らに葬られたと『事物文編』にあったので「再び向島へ往つた。そして新小梅町、小梅町、須崎町の間を徘徊して捜索したが、嶺松寺といふ寺はない。わたくしは絶望して踵を旋したが、道のついでなので、須崎町弘福寺にある先考〔父〕の墓に詣でた」
手繰る糸がぷつっと切れて天を仰ぐ瞬間は、記者なら嫌というほど覚えがある。藁にもすがる思いで住職に聞くと、嶺松寺は廃寺になったという。諦めきれない鴎外は、檀家のない墓は共同墓地に合葬されると聞いて、念晴らしに巣鴨の染井霊園まで足を運んだ。何ひとつ実らない。富士川が「湮滅の期に薄っていた墓誌銘の幾句を、図らずも救抜してくれた」ことをもって、ささやかな慰めとせざるをえなかった。
いい執念だ、鴎外。孜々とした努力を惜しむヘッポコ記者は、この空振りが貴重なことを知らない。でも、江戸幕末と「横町の溝板」でまだすれ違うことのできた明治ですら、事績の朽ちるのはかくも早いのだ。が、この執念こそが、調査報道には必須であることを、いまや思い知るべきである。
<2021年11月5日>
COVIDゆえに我在り(ブログ再開の弁)
己が火を木木の蛍や花の宿(芭蕉)
何波かコロナの津波が襲来するだろうと見越して、紙媒体としての季刊誌ストイカを休止した1年前は、巻頭のアフォリスムを光源氏の蛍の歌にした。実は再開するときはこの芭蕉の句にしようと心に決めていた。暗闇の木々にぼうと光って明滅する蛍に、自らの魂の火をみつめる俳人の姿がふさわしいと思えたからだ。
元禄3年、47歳の発句だが、破格の措辞である。尋常の語順なら「己が火を宿す蛍や木木の花」だが、それじゃつまらない。わざと「己が火を」を宙ぶらりんにして「花の宿」という体言止めにした。主客を反転させた倒装法は、杜甫をまねていると吉川幸次郎はみる。いつも笈に杜工部集を持ち歩いていた芭蕉は、連れの支考と道々「紅豆は啄み残しつ鸚鵡の粒」といった奇抜な語法を論じていたのだ。

電灯のない時代に蛍の光はどう見えたのだろう。『日本誌』のケンペルが、タイのチャヤプラヤ川で蛍の群れが息を合わせるように明滅するのに遭遇し「光のコーラス」に見えたという。それを人間の脳波の「引き込み」現象と同じメカニズムではないかと考えたのが、サイバネティクスの祖、ノーバート・ウィーナーだった。
20年後、アーサー・ウィンフリーの『生物学的時間の幾何学』がそれを数学モデルにしてみせた。振動子が特異点を超えると螺旋波やスクロール波が生じる。蟋蟀の合唱の同期モデルも、スティーブン・ストロガッツとダンカン・ワッツがつきとめた(『SYNC』)。
サイバー空間のコーラスも、実は原理を同じくしている。ネトウヨもSNSイジメもそれと大同小異なのだ。フェイクの拡散と同調、すなわち付和雷同のメカニズムを見事に説明できる。そしてコロナの消長でさえ、このコーラスの原理が貫徹して、だれもが心の底で第6波を覚悟していながら、束の間の息抜きを楽しむほかなくなっている。
油断ではない。新政権がWith Colonaの美辞麗句を並べようが、総選挙がどんな結果に終わろうが、日本がアナログの「昭和」から脱するのは容易でないと見越している。水際作戦や人流抑制という前時代モデルでは辻褄合わせすらできなくなった。ウイルスと人間はとうに主客が反転している。cogitoでなくCOVID「ゆえに我在り」ergo sumなのだ。
パンデミックの「コーラス」に対するには、おそらくこの「倒装法」のロジックが必要になるだろう。しばらく休んでいたこのブログも再開します。
<2021年11月1日>
紙よさらば ストイカ4・5号合併号
オピニオン誌ストイカ4・5合併号は、ずしりと重く76ページもあって、前号の36ページから一挙に40ページも増やしました。グローバリズムの転換点になると直感した2月から、オピニオン誌として新型コロナウイルス感染の特集をやりたいと虎視眈々と狙っていたのですが、第二波のピークを過ぎかけた(あるいは第三波の始まり?)いまを措いてやるタイミングはないと信じ、一気に2冊分をつくりました。
冒頭の「コロナ禍」偶然の僥倖は続かないは、バイオ医薬品規制の第一人者であり、厚労省の新型インフルエンザワクチン開発研究に係る専門会議議長を務めた、尊敬する医学研究者、早川堯夫氏に半年がかりで書いていただいた長大な論考である。知り合ったのは4年前に起きた熊本の化血研(科学及血清療法研究所)騒動の際、再建に送り込まれた理事長だったときです。当時の塩崎恭久厚労相の教条的な民営化に一歩も引かない硬骨漢ぶりに驚き、いつか論を書いてもらおうと思って、ついに宿願を果たしました。
長文とはいえ、医療行政の表も裏も知る人の苦言ですから、腰を据えて読んでください。人類の帰趨を決めるパンデミックに対し、真の専門家が何を考えているかを、いっさいの功名心とは別に警鐘を鳴らしています。いままでの死亡率や感染率の低さは、宿主(ヒト)またはウイルス側の僥倖(幸運)にずぎず、パンデミック対策の「日本モデル」が成功したとはとても言えないこと、医療崩壊を防いだといっても、従来医療・介護では崩壊に近いしわ寄せが起きたことを自覚し、第三波に備えるべきことを13項目挙げています。菅新政権がインバウンド需要喚起のため出入国規制を大幅緩和しようとしているいま、ぜひとも政官民とも呼んでいただけたらと思います。
続く救いの「ワクチン」四大ハードルは、開発途上のコロナ・ワクチンが、今冬のインフル流行期と重なる第三波にはどうやら間に合いそうもないことを、東大農学部出身で獣医師の資格を持つ、医療ジャーナリストの星良孝さんに書いていただきました。彼が日経BPの記者・編集者時代に知り合い、独立してからの活躍に期待していたところでした。さすが専門家で、一口に副作用といっても何が起きる懸念があるのかを詳細に書いていただき、目から鱗の思いがすると思います。
pros(賛成)とcons(反対)は、河野太郎前防衛相が置き土産とした地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の計画断念の衝撃の後、日米安保同盟はどこへ向かうか、そして改憲のレガシーを残せなかった安倍首相が去ったあと、憲法の自衛権には何が必要かを論じていただきました。前者は軽々な敵地攻撃論は同盟に支障で、安倍前首相の談話や自民党政務調査会の提言などで、にわかに「敵(基)地攻撃論」または「策源地攻撃論」が賑やかになり、これに対して自衛艦隊司令官の香田洋二氏が、日米の盾と矛を分担する同盟が揺らぎかねないと警鐘を鳴らしました。
それだけではありません。河野太郎前防衛相による「英断」は、すでに1787億円の国費を投じる契約を済ませているため、その責任問題もあり、買った装置をどう再利用するか、など地上イージスの代替案が必要になります。さらにトランプの〝押し売り〟に安倍前首相が応じた側面もあっただけに、バイ・アメリカンの圧力は依然続いており、「河野太郎の置き土産」後始末に高い代償を伊藤博敏記者に書いていただきました。
また現行憲法でも「敵地攻撃」が、憲法が認める自衛権の範囲内で実施しうるというのが政府見解であり、自らが破壊されるまで自衛権を行使してはいけないとしたら、自衛権が存立しないからです。本来なら敵地攻撃能力の保有は憲法問題でないのだが、安保関連2法案を「違憲と」とした憲法学の通説が邪魔して、実際には有事が発生すると、自衛隊員一人一人の自然権的な自己保存の権利によって遂行されるにすぎなくなってしまうので、篠田英朗東京外大教授に自衛権「憲法学通説の歪み」直せを書いていただきました。
安倍「一強」政権の終わりで、「改憲」とともに「領土」のレガシーもすっかり遠のきました。ロシアは改憲してプーチン大統領の任期延長を可能にし、さらに「領土割譲禁止」の条項を盛り込みました。それはしかしプーチンの強さでなく、いったん辞める時期が決まったら国内が混乱しかねないという「内憂」を孕んだものなのです。米欧から締め出されたファーウェーはロシアに接近、米国も対ロ関係を見直して対中包囲網にひっぱりこむ綱引きが始まっています。その中で反政府指導者、ナヴァルニー氏が神経系の化学兵器ノヴィチョクで暗殺されかけました。こうした複雑な連立方程式のなかで日本の対ロ外交をどう立て直すべきか、畔蒜泰助・笹川平和財団主任研究員に辞められぬプーチンの「内憂」を書いていただきました。
故竹下登氏の「盟友」フィクサーの実母の悲劇を中心とした伝記、福本邦雄外伝が最終回を迎えました。母の情死に隠れた、獄中の別れた夫との一子争奪戦は、ついに満六歳目前の邦雄少年の誘拐に発展します。それから3カ月後、睡眠薬をあおるまでに尾崎士郎に激烈な抗議の手紙を書き、朦朧と無明の淵をさまよいながら「ピエロよ、みんな――踊ってさえいればいいのにね」と呟いて死んでいったのはなぜなのか。その謎に迫ります。
コラムは巻頭のapholistsが「源氏物語」幻の巻から「時ぞともなき思ひなりけん」。山本一生氏の流視逍遥は、私もニューヨークでオフィスを訪れたことのある調査報道のオンライン・メディア「プロパブリカ」のピューリッツァ賞受賞レポートに基づく秀作ドラマ「アンビリーバブルたった一つの真実」です。レイプという重いテーマを、少女の孤立化と刑事の追跡という二つの時間軸で描く構造を論じたものです。
石田哲大氏の風味花傳は、「慈華」(いつか)という昨年12月にオープンして、コロナの荒波に遭遇したレストラン。中華で「非日常」を追う試みを応援したい。池田卓夫氏のBasso Continuo(通奏低音)は、深作欣二監督の息子、深作健太氏が挑んだベートーヴェンのオペラ『フィデリオ』の大胆な読み替え演出。アウシュヴィッツの標語Arbeit Macht Freiを掲げた四つの壁の物語に託された意味を探ります。
<2020年10月11日>
編集部注・以上が合併号の内容紹介でしたが、結果としてこの号が、紙媒体としての旧「ストイカ」の最後となりました。実は刊行後、転移箇所を突き止めるための放射性物質による検査で1カ月半、大阪大学付属病院に東京から週一ペースで通院を続けることになりました。
20年12月には紙媒体としての続行に見切りをつけ、オンライン全面移行のハラを固めて、その準備に入りました。合併号によって20年1月の第6号をスキップ、準備の時間を稼ぐつもりでしたが、コロナの大波が何度も襲来し、オンライン公開が遅れました。
ストイカ3号を滑り込みで刊行しました
しばらく無音でしたが、季刊のストイカの3号(2020年4月号)の準備と編集と発送にかかりきりでしたので、ご容赦ください。すでに2月から新型コロナウイルスの雲行きが怪しくなり始め、まだ歩き始めたばかりのオピニオン誌の刊行を続けられるか、また1,2号は無料でお送りする非売品だったのを、春号から有料化して年間購読にしようと考えていたので、この時期に移行できるかの判断がつかず、ずいぶん思い悩みました。
しかし、3月に入ってパンデミックの長期化が視野に入ってきたとき、このような逆風下でも出すことに意義があると考え、登録者の方々にご購読依頼を発送するとともに、編集を開始しました。緊急事態宣言間際にどうにか刷り上げることができ、発送作業を始めたので、いわば滑り込みで刊行しました。パンデミックがどこまで続くか見通せず、日本の経済・政治・社会がどう激変するかも五里霧中ですが、体力の続くかぎり寄り添って刊行を継続したいと考えています。よろしくご支援のほどお願いします。
<2020年4月18日>
映画CATSはフランチェスカに一見の価値
アナ雪2やスカイウォーカーに興行成績で負けているだけに、この映画をこき下ろすのが流行になっている。へそ曲がりだから、ほんとにそんな駄作かと思ってみてみたが、あの回転舞台の臨場感はないとしても、合格点をあげていい。
豪華キャストに新曲「ビューティフル・ゴースト」までてんこ盛りにしたのに、CGを使っては夢が壊れるというのは、結局、舞台版のイメージを壊すなと言っているだけのこと。90年代にロンドンで舞台を見たが、舞台だって超ロングラン上演でかつての精気を失っていた。顔見世興行によくあるように、スターをそろえすぎて、その時間配分のやりくりが大変だったことはうかがえる。テイラー・スウィフトとイドリス・エルバの扱いはさぞかし苦心したろう。
しかしロイヤル・バレエのプリンシパル、フランチェスカ・ヘイワードの演じる白猫ビクトリアは素敵だった。その身ごなしは計算されつくしていて、ほかのダンサーたちと違う。だが、彼女はケニアのナイロビ生まれ。実物の写真を見ると、かすかに褐色の肌をもつ美女である。それが白い化粧を施し、捨てられた上流社会の白猫を演じさせたあたりに、この映画が反感を呼び覚ました理由がある気がする。それを確かめるためにも、彼女は見ておく価値があると思う。
「レ・ミゼラブル」もそうだったが、俳優たちは撮影現場で歌ったらしい。本来、踊り手のフランチェスカも「ビューティフル・ゴースト」を歌っていた。それを下手と言っては気の毒だろう。この映画への酷評は、どれもないものねだりをしている。映画評など好き好きだから、目くじらを立てるには及ばないが、すくなくともT・S・エリオット好き、「メモリー」好きにとって、この映画は十分楽しめる出来である。
<2020年1月23日>
新歌舞伎版「風の谷のナウシカ」初日
12月6日、東京・新橋演舞場で公演が始まった新歌舞伎「風の谷のナウシカ」の初演を見に行った。宮崎駿の原作漫画は徳間の「アニメージュ」で1982年から延々と12年間連載した長編で、84年に公開されたアニメ版「風の谷のナウシカ」は、まだ連載開始からほどない時期だったため、冒頭部分のエピソードから構成されており、長編全体のごく一部にすぎない。そのアニメから35年目でとうとう歌舞伎化された今回の上演は、その全編を昼の部と夜の部の通し狂言で見せるというのである。
80年代にアニメ版を見て宮崎駿の世界(当時、まだ制作プロダクション「ジブリ」はなかった)に魅了された子どもたちも、いまや40代以上。歌舞伎を楽しめる年齢になっているから、それを歌舞伎にとりこむというチャレンジは興行的にも成功が見込める。一足先に人気コミックス「ワンピース」をヒットさせた市川猿之助のスーパー歌舞伎に刺戟されて、貪欲にコミックスを取り込む歌舞伎界の活況はなかなか見上げたものと言える。
この公演用に特注された舞台の幕は、映画のタイトルロールの壁画を染め上げたものだ。てっぺんにメシアの予言「その者青き衣をまといて金色の野に降り立つべし」の絵が描かれ、アニメ版ではそれがクライマックス・シーンとなっているが、歌舞伎版は前半の3分の1程度でそこに到達してしまう。5年越しの夢を実現させナウシカを主演する尾上菊之助は、単にアニメ版をなぞるだけではなく、あくまでも歌舞伎の様式を維持したままアニメをも歌舞伎化できることを示そうとしたかに見える。
中村七之助演じるクシャナとともに、その衣装もコスプレではなく、歌舞伎の和装のバリエーションとしてデザインされている。そりゃそうだろう、42歳の菊之助がいくら女形の容姿に恵まれているとはいえ、秋葉原のコスプレみたいな装いで飛び出してきては、ちょっと気持ち悪い。女形は衣裳こみの芸でもあるからだ。
ナウシカが自在に空を舞うグライダーのような「メーヴェ」、そしてピストル型の「ガンシップ」など、宮崎駿好みの飛行体をどう舞台化するかは、演出のGⅡも頭を絞ったろう。澤瀉屋一門が得意とする宙づりを使うことは予想できたが、さすがにアニメのダイナミズムを要求するのは酷で、初日ゆえか菊之助もメーヴェに乗るのは恐る恐る。体を横に倒すのもいくら腰をケーブルで吊ってあるとはいえ、見ているほうがハラハラする。
案の上、公演3日目の8日昼の部で、菊之助が花道で乗っていたトリウマがつまずいて転落、左ひじを亀裂骨折する怪我を負った。同日の夜の部は中止、9日から登場するというが、大立ち回りなどは大変だろう。
<2019年12月7日>
「ガラスの蜂」とテキーラ・サンライズ
12月12日発売の翻訳『ガラスの蜂』の見本刷が届いた。
ご覧のように帯(腰巻)は黄色から深紅へのグラデーションになっている。この色をデザイナーに説明するのに、カクテルの「テキーラ・サンライズのように」とお願いした。で、完成を祝して銀座のバーでテキーラ・サンライズを注文、ふたつを並べてシャメしたわけだ。
なぜテキーラ・サンライズにこだわったか。ガラスの蜂の胴が紅茶色、目が黄色なのでそのトーンを合わせただけでなく、文中にガラスの蜂が花の蜜を吸って集めた蜂蜜が、しだいに濃くなって蜂蜜色になっていくシーンがあるからだ。さらにもう一つ理由がある。
満目青山はわが心にあり、の「弱法師」が西方を仰ぐとき、見えぬ目で見る壮大な日没の光景を連想してほしかったからだ。「近代能楽集」で弱法師を現代劇にした三島由紀夫も、大空襲で焼け落ちる帝都を幻視させている。ユンガーの小説の主人公も、ドイツ国防軍の軽騎兵部隊に所属し、夜空を焦がす戦火を見たにちがいない。
それはヒエロニュムス・ボスの祭壇画「快楽の園」の三連右の地獄の地平に見える炎だろう。「ガラスの蜂」もこのボスの祭壇画にヒントを得た箇所が多数ある。
店頭に並ぶのはもうすぐ。ドイツ語からの翻訳は、小生の宿願の一つでした。手に取ってご覧いただけたら幸いです。
<2019年12月3日>
I'll be backの大戦果
フェイスブック方面ではお知らせしたが、「ストイカ」がまだ季刊なので、途中でつかんだスクープをタイミングよく打つには、インターネットに頼らざるをえない。そこで臨機応変に記者を集めて取材し、それをオンライン媒体で打つチーム「ストイカ」の仕組みを実験してみた。
それが東洋経済オンラインで11月21日に打った「衝撃事実!GPIF理事長『処分』は謀略だった」である。
それに先んじて現代ビジネスで伊藤博敏記者が「激震…GPIF「理事長スキャンダル」の裏に潜むセクハラと人事抗争」を公開したが、彼はチーム「ストイカ」の一員であり、根はひとつだと思って構わない。
もうひとつ、チームに加わったのが日経の後輩でいまはウォーターサイド・ラボラトリーLLCを持つ樫原弘志君である。彼もnoteにサイトを開いていて、理事長処分の理由となった「情実採用」の真偽を確かめたのだ。驚くことに、GPIF監査委員会の岩村修二・元東京地検特捜部長は、理事長の出身母体に照会すらしていないズサンな調査だったことが判明した。「予断」で強引に結論を出す特捜の悪癖をいまだに続けているのだ。
東洋経済オンライン記事はYahooニュースに転載されたが、セクハラの一語にビビったか、編集「介入」があり、できるだけ目立たないよう下位にしまいこまれた。経済の部門に入れられたが、検索しないとみつからない片隅ニュース扱いである。これを突破してくれたのが、「ストイカ」創刊でもお世話になったブロガーの山本一郎君である。
彼はYahooニュースに「無縫地帯」という個人コラムを持っており、そこで22日に「GPIFでセクハラをめぐる怪文書騒ぎが発生」でフォローしてくれたのだ。東洋経済オンラインでは取材先など諸般の都合があり、セクハラ理事の名を伏せたが、山本君は自力で厚生労働省などに取材して独自に写真や怪文書のコピーを入手、気兼ねなく理事の名や不自然すぎる盗撮写真などを公開した。皮肉たっぷりの山本一郎節で、笑わずにはいられないが、おちょくられたほうは悲鳴を上げているにちがいない。
とにかくチーム「ストイカ」の試みは大成功。ネットで散らすショットガン戦法と、だんだん暴露度が高まる雲竜型で、新聞、テレビ、雑誌をぶっちぎることができた。で、『ターミネーターニュー・フェイト』で久しぶりにお顔を拝めたシワ(シュワ)ちゃんか、シワ(サラ)・コナーのようについ凱歌をあげたくなる。
I'll be back.時代は変わった、と。
<2019年11月23日>
翻訳「ガラスの蜂」12月12日発売
「満目青山は心にあり」で予告していた初のドイツ語の翻訳ーーエルンスト・ユンガーの『ガラスの蜂』(田畑書店、税込3080円)が、表紙デザインも決まり、最終校了して印刷に入りました。発売は12月12日(木)です(一報を⒓月2日としましたが、間違いでした。訂正します)
表紙裏に載せた写真は、作者が第一次大戦でドイツ兵士最高の勲章、プール・ル・メリットを最年少で受賞したときの記念写真。鉄十字章しかもらえなかったヒトラー伍長とは段違いの戦功で、ルーデンドルフ参謀総長らと肩を並べました。なかなかハンサムです。そのドイツがいままた落ち目、旧東独地域でAfDが躍進しているのを見るにつけ、その屈辱の根深さを思い知らされます。
NHKキャスター、有馬嘉男氏がベルリンの壁崩壊30周年でドイツを取材、既得権を失った旧東独市民で、いまはAfD支持の老夫婦を取材していましたが、いかにも意思の弱そうな夫に比べ、妻の鋼のように冷たい目が気になりました。あの目はシュタージ(東独の情報機関)に密告していたに違いないと思わせる怖さでした。有馬キャスターはその過去を問うていない。
まだ敗戦の傷が癒えぬ1957年に書かれたこの小説も、いや、メモワールというか、エッセイというか、何とも類別しかねる作品が発する鋭い視線とどこかで共通しているのかもしれません。
帯には内田樹氏の推薦文をいただきました。彼が師事したユダヤ人哲学者、エマニュエル・レヴィナスもフランス軍に従軍、捕虜として生き延びたので、反対側の占領軍にいたユンガーと対称していただこうとお願いしました。こんな文章です。
ユンガーのものを読むのははじめてです。大戦間期のドイツで「敗戦と近代化によってドイツが失ったもの=もう一度蘇らせるべきもの」に固執するユンガーの喪失感にカール・シュミットやマルチン・ハイデガーに通じるものを感じました。
モンテロン、ヴィットグレーヴェ、フィルモア、ローレンツといった軍人たちについて、わずかな行数で彼らの相貌をありありと現前させる「ポルトレ」の技にも驚かされました。
僕自身はこれまで大戦間期のフランス知識人のものを多く読んできましたけれど、ここまで濃密な身体性を持った同時代の書き手はフランス人作家には見出し難いと思います。ドイツ・ファシズムの感性的な淵源について、学ぶことが多かったです。
ぜひ多くの読者に送り届けて欲しいと思いました。
訳文もみごとでした。
(注)「ポルトレ」とはフランス語でportrait(英語読みだとポートレート)のこと。
おそらく内田氏は高校と大学では少し学年が下の後輩で、同じ空気を吸ったはずです。あらためてお礼申し上げます。
アマゾンでも予約販売が始まりました。よろしくお願いします。
<2019年11月14日>
ストイカのオンライン有料サロンを始めます
10月に創刊した季刊オピニオン誌「ストイカ」(非売品)は、単に定期刊行のマガジンだけでなく、もっと多様なチャネルを持ちたいと考えています。そこで紙媒体とは別に、阿部重夫個人のオンライン有料サロン「ストイカ・プレミアクラブ」を並行して始めることにしました。11月15日から申し込みを開始、12月から正式スタートします。
理由は「ストイカ」を既存マスメディアのような一方通行のモデルでなく、購読者(audience)またはファンとの双方向モデルにしたいからです。言いたいこと、訴えたいこと、さらに暴露したいことがあるのは、ジャーナリストに限りません。書く特権にあぐらをかくだけの孤軍奮闘では、いずれフェイクニュースの洪水に呑みこまれます。
そこで逆手をとってFacebookの機能を使い、「ストイカ」のコアとなるプラットフォームを形成することを考えました。目的はただ一つ。戦後の経済・社会・政治のあらゆる前提が崩れていくなかで、想定外の危機に備えて「プランB」を用意するディスカッションの場を設けることです。そこでの議論を踏まえて「ストイカ」でこれまでにない政策や戦略を訴えたい。
このサロンは、いわば「ストイカ」の拡大編集会議とも言えます。ディープな情報だけでなく、玉石混交のデータを精査し、目先だけでなく中長期的に最適な代案が何かを、サロンのコアメンバーで模索し、思いがけない切り口、「アルキメデスの支点」を探りあてようとするものです。
例えば、諧謔の達人ニーチェにこんな警句があります。「人間が神のヘマの産物だって?神こそ人間のヘマでは?」。さて、「笑点」なら春風亭昇太に座布団を何枚もらえるか。これだけで千万言費やすより一発で逆転の発想がわかる。先入観やイデオロギーに囚われた「無知」も、プランBを持たない言論の「無責任」も、容れる余地はありません。
そのスクリーニングの装置として、いいニュース、ダメなニュースを幅広く格付けし、その根拠や寸評をつけながら、輪を広げてランキングを公表する「ニュース格付け」の構想を整えていきたいと考えています。
サロンはファンディング(資金調達)も兼ねています。どこにも尻尾を振らず、また現状に安住しないメディアをつくるには、どうしても「一口馬主」が必要です。われこそは「ストイカ」の一口馬主たらんと思い、その余裕があって、かつFacebookのアカウントをお持ちの方はぜひどうぞ。そこまではまだ難しいという方には、編集委員の間宮淳氏とともに開いたFacebookの公開グループ「新オピニオンメディア「∑toica」」(無料)があり、また将来の雑誌「ストイカ」の有料購読という選択肢があります。
<2019年7日>
日経のベトちゃんドクちゃん
日経同期の永野健二君が小生とほぼ同時期に手術してまだ入院しているので、21日の月曜、大阪までお見舞いに行きました。
小生は消化器と泌尿器科、あちらは循環器科と、故障場所は違うのですが、お互いいつまた会えるかという身の上でもありますので、奥さんに写真を撮ってもらいました。永野君は先月、社長だったBSジャパンの番組にちらっと映っていて、渋沢資本主義についてひとくさり語っていました。見落とした人もいるかもしれないので、最新の近影を載せておきましょう。
永野はすこし痩せたけど、口は昔と変わらず、例によって能弁。日経時代は48年入社組のベトちゃんドクちゃんと言われていた(顔も文章も行動もまるで違うんだけど、よく酒を飲んで延々と議論していたので)だけに、待ちかねていたように滔々と永野節が止まらない。
友あり、遠方より来る、を地でいく。小生はただニコニコ笑っているだけですが、それでも言いたいことがいっぱいあるらしく、もどかしそうでした。入院が長くなると暗くなるけど、これで気が晴れるといいな。内心は喋らせすぎてくたびれてしまうのではないかと、ハラハラしてましたが。
医師が来たので、小生は一時退席。待っているあいだ、待合室の窓から彼方に見える大阪万博の太陽の塔と大観覧車を眺めていました。70年万博は永野も小生も見ていない。大学紛争直後だったのと、小生は父がすい臓がんで入院していたのでそれどころではなかったからだ。そんなことをぼんやり考えながら、いまにも雨の降りそうな千里の森を眺めていた。
朗報を聞いた。近々、つまり10月末から11月初めにかけて永野君は退院できそうだとのことです。23日は試験的に病院の近所に外泊だとかで、その支度に奥さんは忙しい。ラップトップPCが置いてあったけど、ベッドで根を詰めるとからだに障るから、ミニノートに新聞などのスクラップを貼りつけているのがほほえましい。もう50冊を超えたそうな。
彼ははっきり言った。「本を書きたいんだ」。
新潮社から出した「バブル」と「経営者」の続編の構想を温めている。その一念、よく分かるな。残んの時はたとえ限られていても、紙ナクバ空ニモ書カン。保田與重郎もそう言った。その意気、こちらも負けていられない。
<2019年10月23日>
Voice of Soulsをあなたにも
ストイカとほぼ時期を同じくして10月1日、私の知っている記者が個人で会員誌サイトを立ち上げた。今春、日経BP社を辞めた金田信一郎君である。タイトルはご覧のようにVoice of Soulsとカッコいい。その心意気と壮図に拍手を送るとともに、ストイカも緩やかに組んで応援することにした。
創刊号#01の記事は2本。彼に会って「君の得意分野は何?」と聞くと、「人物ものかな」と答えたが、創刊記事のメーンはその人物ものである。
北海道日高振興局管内にある浦河町では、精神障碍者100人以上が町中で暮らしているが、その活動の中心である「ペテルの家」の精神科医、川村敏明氏のストーリーだった。その川村氏が障碍者たち10人余を連れて上京、象牙の塔の東京大学で彼らが教壇に立ち、明治以来100年にわたって障碍者を隔離し、薬と注射漬けで黙らせてきた官学の面々が生徒になって、奔放な彼らの話に笑い転げるという「倒錯の構図」を書いたルポである。
私が浪人か大学時代に見たピーター・ブルックの映画『マラー/サド』を思いだした。原作はペーター・ヴァイスだった。正式のタイトルは「マルキ・ド・サドの演出のもとにシャラントン精神病院患者たちによって演じられたジャン=ポール・マラーの迫害と暗殺」と長たらしい。フランス革命のさなか、シャラントン精神病院に収容されていたサド侯爵が、患者を使って少女シャルロット・コンデに浴槽で殺された革命家マラーの暗殺劇を演じさせるという内容で、最後は患者たちがナポレオンを称えて狂乱状態に陥る結末だったと記憶している。いわばそれがこの「倒錯劇」のカタルシスで、私とあまり年齢の違わない川村先生もあれを見たのではないかと思った。
とにかく金田君のルポでは、東京帝大教授だった呉秀三の「二重の不幸」という発言が引用されている。
「ガン患者は周囲から優しい言葉をかけられる。だが、精神病患者は厳しく責められ、壁の中に押し込められてしまう」
なるほど、私には耳に痛い。現在、精神病院に入院させられている患者は30万人、彼らに比べればガンとの闘病など楽なのか。隔離の精神科治療に凝り固まった官学の総本山に乗り込んで、川村氏は「東大を救いにきた」と豪語する。患者を切り捨てて隔離し、黙らせているだけでは何も解決しない。要は患者にも表現させろ、そうすれば緊張も緩和するというのだ。
金田君自身、1年前の日経ビジネスでJR東海のリニア新幹線計画を批判する特集を掲載、葛西敬之名誉会長を激怒させ、恐れをなした日経本社の圧力で口を封じられて退社にいたった経緯がある。幽閉され、沈黙させられる精神障害者の解放とは、一直線に自らの体験とつながっている。骨のある彼がこの記事で語ることはそのまま、川村氏の挑戦とシンクロしている。
いいルポだから、ぜひ読んでごらんなさい。入会は個人なら一人月500円とワンコインだそうだ。
もうひとつの記事は、「BIGの終焉」と題して自ら書いた東電首脳の一審無罪判決への批判である。オピニオンだが、ミシェル・フーコーの『監獄の誕生監視と処罰』の引用から始まる。
「権力に有益な知であれ不服従な知であれ一つの知を生み出すと考えられるのは、認識主体の活動ではない。それは権力=知であり、それを横切り、それを構成し、ありうべき認識形態と認識領域を規定する過程であり闘争である」
ああ、パノプチコンの本ですね。なるほど精神科医の話と地続きになっているわけか。健常者の「強固な世界」のほうが、確かによほど狂っている。ほとんど裁判の使命を放棄したかに見えるほどやる気のない東京地裁判決文と、元副社長の武藤栄被告の「外部機関に長期評価の信頼性を検討してもらおう」という他人任せ、中越地震の後始末に追われていた同じく元副社長の武黒一郎被告も「今度は津波か」と面倒くさそうに言うだけの無気力とが重なっている。それを金田君は、権力と知が一体になった「病」と見ている。
こういう試みをストイカは全面的に応援しよう。彼なら世を震撼させるネタも書いてくれそうだから、私では手に負えないものも提供しよう。そして彼に続いて、大手メディアを飛び出した志のある記者と連合軍を組もう。これ以上、刀折れ矢尽きた記者のなれの果てをみたくないから。
とにかく彼のサイトの動画はスタイリッシュで、見とれてしまうのでぜひご覧になってください。
<2019年10月18日>
玉三郎と児太郎の「二人静」
日本舞踊にも能楽にも詳しいわけではないが、あえて素人談義を試みよう。歌舞伎座の10月公演で、玉三郎と児太郎の「二人静」を観たからである。もちろん、ストイカの番外編である。
覚えていますか。「難破船」や「Desire」などで燃え尽きてしまった中森明菜が、市川昆の映画『天河伝説殺人事件』の主題曲(松本隆作詞)をカバーして「二人静」と題して歌っていた。主演の岸恵子の二面性、美女と般若を匂わす「あやめたいほど愛しすぎたから」「添い寝して永遠に抱いてあげる/いい夢を見なさいな、うたかたの夢を」という歌詞が耳に残っているが、作詞家がオリジナルの能の曲「二人静」を知っていたとは思えない。
無理もない。映画で「二人静」を舞うのは、能の宗家の跡目を争う異母兄妹が稽古しているシーンだけで、あとは「道成寺」の釣鐘落としなどだから、市川昆も単に能を意匠として採り入れただけで、とりたてて「二人静」を土台にした脚本を考えていたわけではなかったろう。むろん、玉三郎と児太郎の「二人静」は能が下敷きである。
しかし、こちらは源義経に吉野で別れた静御前の霊が、若菜摘みの里の女に憑いて、二人で「相舞」を舞うという曲だけに、能面をつけた演者二人が呼吸を合わせるのが難しい(能面の小さな目の穴から見た視野は狭く、どうしても所作がずれる)ため、明治の宝生九郎知英が廃曲にしたこともあるという。そこで「相舞」をできるだけ減らそうと、静御前を橋掛かりの前で床几に座らせ、静が憑いた里の女にひとり舞わせて、最後に二人で「相舞」するという「立出之一声」という江戸中期に観世元章の演出がよく行われる。
歌舞伎座では1963年12月公演で、七代大谷友右衛門と二代中村扇雀が演じているが、こちらは萩原雪夫原作で、頼朝役に八代目沢村宗十郎や侍女が大勢出てくるなど、かなり歌舞伎化した演出だったらしい。歌舞伎公演データベースで見るかぎり、これは一度きりであり、今回は原曲にもっと近づけ、能舞台の鏡板を思わせる老松の背景や囃子方をそろえている。ほかに竹本や長唄囃子連中、さらに舞台途中で背後から筝曲方がせりあがってくるなど、邦楽総出のような凝った音楽を奏でていた。
玉三郎も児太郎も面をつけるわけではないから、歌舞伎版は存分に「相舞」ができるはず、と思ったが、おそらく二人も感じたであろう難しさは、静御前の霊が、里の女にとり憑くという霊肉の交感を、女形が「相舞」でどう演じるかということにある。おそらく女形の芸を後代に伝えようと意識し始めた玉三郎が、自ら児太郎にとり憑くかのような重ねあわせがそこに生じ、観客もそれをスリリングに感じられるかどうかが試されている。
能の原曲では、神事である若菜を摘む里の女(児太郎)に、だれとも知れぬ女(玉三郎)が声をかけ、「わらはが罪業のほど悲しく候へば、一日経を書いて、わが跡弔ひてたび給へ」と社家に頼んでくれと迫る。名を問い返すと、「もしも疑ふ人あらば、そのときわらははおことに憑きて、詳しく名をば名のるべし」と言いおいて、かき消すように消えてしまう。
里の女は神社に帰って、神職にことの次第を説明するが、「まことしからず候ふほどに」と口にした途端、声が変わる。「なにまことしからずとや、うたてやな、さしも頼みしかひもなく」と静御前が憑依しているのだ。ここが難しい。ここからは『ブレドランナー2049』のように、Kの家庭用AI、ジョイと別の女が重ねあわされながら微妙にずれることになる。
神職は「言語道断、不思議なることの候ふものかな、狂気して候ふはいかに、さていかやうなる人の憑き添ひたるぞ名を名のり給へ」と問い返す。しかし児太郎はどうみても狂気のトランスに囚われたようには見えなかった。後ろにいつのまにか現れた玉三郎が控えているからで、「つつましながら我が名をば、静かに申さん恥ずかしや」とこたえてはじめて、静御前の名をほのめかす。それなら静御前は舞の名手だから、ここで舞を舞ってみよ、と言われ、先に舞台袖に音もなく退いていく玉三郎を追うように、白拍子の衣装を捧げ持つ児太郎も退いていく。ここが問題だった。歌舞伎座の舞台は幅広すぎて、能の橋掛かりより距離がある。能では義経が落ちて行く次第が語られて間遠に感じられないが、歌舞伎はそこを端折っているから、児太郎はしずしずと退いてはいられず、どうしても小走りに退くかに見えてしまう。
そこで観客は憑依のトランスを破られる。琴などのサウンドでもそれをカバーできない。やがて現れた白拍子姿の二人は、能よりもはるかに息の合った「相舞」を舞うのだが、扇を返す手や、袖をふりあげる腕の動作などどうしても年季の入った玉三郎に目を奪われて、二人には見えない。児太郎は所作が固く見えて、師匠に手取り足取りで懸命についていくかのように見える。能では二人の名人の所作が微妙にずれるのを楽しむ演出もあるというが、ここではあまりに玉三郎が圧倒的で、憑かれて操られる里の女の二重写しが浮かんでこない。立出之一声で「相舞」になった二人が相対し、縦に並んで静が里の女の肩にそっと手を置くように、玉三郎が片手を児太郎の肩に触れた瞬間、ようやく二人が一人になった気がした。
つくづくこの曲は難しいと思う。
これは役者が役に乗りうつられ、他者を演じるというより、いつしか他者を演じさせられることに通じている。児太郎もおそらくそう思ったろう。能の「二人静」の最後は、こんなリフレーンで終わる。
静が跡を弔ひたまへ、静が跡を弔ひたまへ。
<2019年10月17日>
CyDEFの赤い鳥居
ちょっと奇妙なマークである。赤い鳥居にうねる波、羽らしきものが宙に浮かんでいる。10月9-10日に東京・六本木の政策大学院大学(GRIPs)で11日には横須賀のYRPに会場を移して開かれたサイバー・ディフェンス・ワークショップ(略称・CyDEF)のシンボルである。
2016年の米大統領選で、ロシアがサイバーとリアル両面から大規模な選挙干渉を行なったことは、トランプ大統領がいくら「魔女狩り」だとムラー特別検査官のチームを封じ込めても、インテリジェンス社会では既定の事実になっている。同年に起きた英国のEU(欧州連合)離脱の国民投票でも、ロシアがサイバー攻撃をしていた形跡があり、その後も仏大統領選はじめEU各国で極右が躍進、さまざまに偽装を凝らしたロシアからとみられるサイバー攻撃が常態化していることは、ネット・セキュリティー業界の常識だ。
もはやネットの戦場では有事と平時の区別がない。NATO(北大西洋条約機構)は、90年代にロンドン駐在だったころに何度か取材したが、そのころはまだサイバー攻撃などがなく、もっぱら地上戦とミサイル配備、核拡散といったリアルな兵器と戦略が中心で、現代のようなサイバーとリアルを組み合わせたハイブリッド戦略は姿を見せていなかった。NATOのサイバー防衛の本拠であるCenter of Excellency(この響きがいい、単なるHeadquarterでは昔風のリアルな司令本部のイメージ)が、バルト三国のうちのネット先進国、エストニアに置かれていて、そこからこのワークショップにNATOの軍人専門家が来ると聞いて、六本木のシンポ会場に行ってみた。
「ストイカ」創刊号でIoT(インターネット・オブ・シングス)の楕円曲線暗号が、プレステのようなゲーム機とAI(人工知能)による機械学習によって破れる時代が来るという卓抜な記事を書いてくれた、元日立の数学者、後保範さんと、文春新書で「ダークウェブ」や「フェイクウェブ」の著作もある高野聖玄君を誘ったら、忙しい時間を割いてくれた。開会と基調講演が行われたメーン会場のメディア席には、主催者がこの3人の席を確保してくれて、椅子の背に「ストイカ」という紙が並んでいた。大手新聞などがほぼ一席なのでちょっと恥ずかしい。が、幸い、立食のランチでエストニアから来た制服組や、日本のサイバー・セキュリティー関係者と知り合うことができて大きな成果だった。欧米の制服組はぴんと背筋を伸ばしていて、姿勢がよく、エリートだけに受け答えもしっかりしている。
残念ながらチャタムハウス・ルール(英王立国際問題研究所ルール)が前提なので、誰がどんな講演や発言をしたかの詳細は書けない。しかし、ロシアのサイバー攻勢がまだ極東には向けられていないといっても、油断できない。attribution(属性=攻撃者は転送などで複雑な偽装を凝らすが、そのログや手口を解析して推定される攻撃者のことをこう呼ぶ)が朝鮮半島または中国と目される事例が頻繁に起きていることは実証されている。
ワークショップのセッションを渡り歩いて、聞いているうちにだんだん背筋が寒くなってきた。もし来年の東京五輪を混乱させ、日本に恥をかかせたいaggressorがいたら、その攻撃は防げるのだろうか。そうした攻撃が電力、交通などインフラにもたらすダメージは、想像を絶するものがある。
それはまた、ストイカが開拓しなければならない分野でもある。建前上、公的な情報機関が存在しない日本では、民間も単なるインフォメーション収集でなく、インテリジェンス機能を持たなければならないと信じるからである。ブレグジットと米大統領選でフェイスブックを使った干渉に関与したケンブリッジ・アナリティカをいち早く報じ、調査報道したのは、スイスのダス・マガツィーンや英国のガーディアン紙だった。
六本木のワークショップではまだサンドボックス(砂盤演習)でしかないが、日本にもCenter of Excellencyが必要ではないか。GAFAやBATHといった米中のプラットフォームが前門の虎だとするなら、官製ハッキング機関やその別働隊が闊歩するサイバー空間の攻撃は後門の狼にあたる。侵入者を防ぐゲートウエーをどう固めることができるか。
CyDEFのシンボルが赤い鳥居になっているのは、そのゲートウエーの意味だろう。そういえば、アニメ『天気の子』の陽菜も、代々木の廃ビルの屋上に祀られた小さな神社の鳥居をくぐった途端、すべてが一変した。
そこにニュースのヒントがありそうな気がする。
<2019年10月16日>
トホホの再び検査入院
やれやれ、けさ主治医から携帯に電話が入り、「検査データが取れていなかったので、どうしますか。検査をこれで見切るか、再度検査するかですが」と言われた。
ええっ、先日の1泊2日の検査入院で鼻から食道にチューブを通されて一昼夜、ひたすら我慢の子だったのが、すべてチャラとは。幼稚園さくら組みたいに首からぶら下げたPH検定器には、液晶画面に刻々と数値が映っていたのに、記録するチップの接触が悪かったのかしら。落胆。
ま、命にもかかわるだけに、もう治ったと勝手に見切るわけにもいかず、近々再検査でまた丸2日を費やす羽目になりそう。悔しいが仕方がない。
せめて無駄な2日でなかったと思いたいのは、ただぼんやりと病室で窓の外の東京タワーをみつめる間に、上の写真の手前に置いてあるThe New Yorkerを熟読できたことだ。とりわけ読みでがあったのは、同誌スタッフライターのD・T・MAXが書いたルポDr. Robot。
他人事ではない。自分が3年前に手術を受けたのが、ここで特集されている手術支援ロボット「ダヴィンチ」だからだ。最新のME機器で高額でもあり、執刀医も熟練を要するため、どこでも使っているわけではない。勧められたのは、腹腔に小さな穴を開けるだけで、メスを使うより侵襲性が低く、術後の痛みもわずかで治りも早いという理由からだった。どの紹介サイトもいいことづくめで、もはや「神の手」なんか用済みと言わんばかり、ほんとかいなという気がちらと胸をかすめる。
The New Yorkerの記事は、そうした疑問に答えてくれるいいルポだった。正直、手術台の上でマナイタの鯉となったときは、部屋の隅に蟹の脚みたいなものがぶら下がった機械とコンソールがあるのを見ただけ。マウスピースをつけて麻酔薬を静脈注射するや、たちまち昏睡したので、どう操作していたのか、まったく見ていない。
詰め過ぎたトランクみたいに臓器が詰まった人間の内臓を、遠隔操作する機械の手で腑分けして、患部を精密に切り出すなど信じ難い。シカゴの病院にいるイタリア人の名医、ピエール・ジュリアノッティの離れ業は、本人が血を見るのが苦手で、一時は外科医を諦めようと思ったというくらいだから、エレガントの極に見える。
実はこの7月に私は腹腔鏡手術も受けたので、ダヴィンチとどう違うのか、と内心思っていた。確かに腹腔鏡にコンソールはなく、遠隔操縦ではないが、こちらも全身麻酔で昏睡していたから、なんとなく執刀医が手術台のかたわらにいる気がしただけで、腹腔鏡をどう操作していたかは見ていない。
ジュリアノッティは機械の手に乗り移って、自分の手が拡張した感覚になるという。それは3Dで、患者の身体に浸透していくようなバーチャル感らしい。これに対し、腹腔鏡は2D感覚だという。かつて医学が神業と思われた時代のように、ダヴィンチはトランス(忘我状態)を呼び覚ますのか。
「スターウォーズ」のジェダイのごとく、訓練を積まないとその域に達しないことは想像できる。開発当初は心臓のバイパス手術に使えると宣伝したが、不慣れな医師の失敗例があって訴訟が起き、5億5千万ドルの和解金を支払う羽目にもなった。そこで米国で多い前立腺がんの切除手術に売り込み先の重点を移し、それが成功して日本にも上陸したらしい。
次の標的分野は、逆流性食道炎だそうだ。な、なんと7月の腹腔鏡手術は、その難治性の逆流性食道炎が理由だった。腹腔鏡の名人もやがてはダヴィンチに席捲されることになるのか。手術がもう少し後年なら、腹腔鏡でなく二度目のダヴィンチ手術になったかもしれない。
ダヴィンチを開発したIntuitive Surgicalが独占的利潤を謳歌する時期はもうすぐ終わるらしい。特許の期限が切れるのだ。おいしい分野だけに、ライバルが虎視眈々と狙っている。資金潤沢なメドトロニックが開発中のマシンは、ダヴィンチの向こうを張って「アインシュタイン」と命名された。
ダヴィンチ創業者のフレッド・モルも独立し、現在はジョンソン&ジョンソン傘下で、ポータブルな手術支援ロボットを開発している。携帯電話の5Gが浸透すれば、地球の反対側にいる患者の手術でも、致命的なタイムラグが極小になり、大病院の手術室でなくともロボット手術ができる。
もともとは、インターネットの祖でもあるDARPA(米国防省傘下の国防高等研究計画局)の着想だった。海外の戦場で負傷した兵士の手術を本国から操作するというアイデアだったが、それをモルは復活させる気だ。
そこまでいけば手術支援でなく、自動手術ロボットを期待したくなる。医師のほうがロボットを支援する役回りになれば、主客が転倒する。善し悪しは別として、AI(人工知能)とおなじく、人間か機械かの葛藤になる。
「あたし、失敗しないから」
ドクターXの決め台詞は、米倉涼子ではなく、ダヴィンチの機械音声が発する日――そんな時代がすごそこに来ていると自らの身体で思い知った。
<2019年10月12日>
山本一郎君の応援ブログ
知人の山本君から「ストイカ」創刊に応援のブログをいただきました。「人生最後の戦い」とはいささか面映ゆい気がしましたが、とにかく効果てきめんでnoteのサイトにフォロワーと「スキ」が相次ぎ、創刊号無料贈呈のための登録メールやFAXがみるみる集まってきて、アルファブロガーの威力を改めて実感しました。あらためてお礼申しあげます。
これはのんびり構えていられないと、金曜から郵送先のリスト化を手作業で始めたのですが、後から後から申し込みが届くので手が追いつかず、土日もラグビーW杯日本・サモア戦の時間帯(さすがにこれは都内某所で歓声を挙げてました)以外はエクセルと格闘、日曜夜までかかっても追いつけなくなりました。もはや人手を借りるしかないという事態です。いずれにせよ、創刊号のメーン記事でもあるマイナス金利とNY銀行間市場の異常事態の続報を土日に書こうと思っていたのですが、ちょっと先送りして、リストと郵送を優先することにしています。
とはいいながら、7日は1泊の検査入院で、ラグビーの「シンビン」ではないけど一時戦線離脱。病の隙間を縫って雑誌をつくっているのか、雑誌の隙間を縫って通院しているのか、どうも見分けがつかない綱渡りの日々ですね。「忙中閑あり」どころか「病中忙あり」の感じです。ストイカ到着に少し時間がかかりそうで、しばしお許しあれ。
<19年10月6日>
満目青山は心にあり(独立宣言)
闘病すでに4年。三度の手術、一度の放射線照射、さらに化学療法を経てなお根治できない。これでは激務に耐えられないと判断し、13年余前に創刊した月刊誌の仕事を辞すことにしました。調査報道の第一線に立つという私の使命も幕引きが近いと信じます。
謡曲に「弱法師」(よろぼし)という名曲があります。沈む日を拝んで浄土への転生を祈ろうと、四天王寺の西門に杖をついて現れる盲目の俊徳丸の物語です。入り日が落ちていくと、群衆がいっせいに拝みだすのを気配で察し、「さりながら盲目なれば、そなたとばかり、心あてなる日に向かひ」じぶんは拝むしかない。満目青山は心にあり、「おう、見るぞとよ、見るぞとよ」と声を発しますが、足もとはよろつき、行きあう貴賤の人びとに突きころばされ、「人は笑ひ給ふぞや、思へば恥づかしやな」と身を伏せます。
シテの弱法師には能面があって、眉間に微かに皺を寄せ、呆けたような無性に哀れな表情です。落語にその翻案「菜刀(ながたん)息子」がありますが、あのオチは哀しくて笑えない。これからは、弱法師のように過去も明日もない世界です。映画「死ぬまでにしたい10のこと」(原題 My Life Without Me)のようにリストをつくってみました。
ドイツ語の本を翻訳してみたい。これは田畑書店にお願いして、エルンスト・ユンガーの小説『ガラスの蜂』を10月に出版する予定です。ドローンの黙示録といった内容で、ドイツ語は大学で教わったきりなので後輩の助けを借りました。
リストの次は、映画の字幕を手伝ってみたい。これは文春と博報堂DY MaPのおかげで9月27日からシャンテ系で公開される『ハミングバード・プロジェクト』で実現しました。
その次はザ・ニューヨーカーのように知的に「美しい雑誌」をつくることです。いままで言わなかったことに口を開きたい。ユークリッドの『原論』(ストイケイア)にあやかり、またストア派のように禁欲的という意味を込めて「Σtoica」(ストイカ)と名づけました。
こうしてリストをひとつひとつ消化していけば、いつか「私のいない世界」にたどりつくでしょう。ベンヤミンの幻の雑誌「新しい天使」のごとく、後方へ退いていく「しんがり戦」は、たとえ虚空に吠ゆ、であっても一声を発し、一礼して去らんとするものです。いましばらくは、弱法師のように「今は狂ひ候ふまじ、今よりさらに狂はじ」と念ずる日々です。
<2019年9月1日>
議決権行使の公表、病みつきになる面白さ
8月に入ると、スチュワードシップコードの受け入れを表明している機関投資家が、3月決算企業の株主総会で一つひとつの議案に対してどのように議決権を行使したのかを公表するシーズンがそろそろ始まる。
議決権行使結果のチェックは意外に面白い。横並び意識が強い金融機関の間でも、個々の議案に賛否が分かれているケースが少なくないからだ。機関投資家ごとに投資対象企業との利益相反の度合いに差が生じるせいでもあるのだろうが、それよりも投資家ごとに賛否を判断する基準が異なっていることが大きいだろう。議案に反対する場合はその理由も示され、会社提案を追認するだけの時代からは様変わりした。
投資信託会社や生命保険会社などの大手機関投資家のなかで議決権行使結果を開示する動きがちらほらと出始めたのは2016年頃だ。その後も行使結果を公表する機関投資家は増え、基準の見直しも随時行われているから、投資家内部でも議論が盛んなテーマなのだろう。
事後的な検証を可能にし、企業統治の方向性や問題点を考える上でも有益だ。学者ならこれをもとに論文を書けるし、我われジャーナリスト稼業にとっては意外や、ネタの宝庫でもあるのだ。
機関投資家によって公表時期がまちまちなうえに、年に数回にわたって公表する投資家もあれば、年に一回しか公表しない投資家もあるのが玉にきずだが、面白いことには変わりない。投資対象企業によっては「企業統治の観点からは会社提案に理があるが、業績面では株主提案に従って人心を一新してもいいのではないか」といった具合に、判断が悩ましいケースも少なくないから、なおさらだ。
なかでも今年はLIXILグループのお家騒動が話題になった。株主を味方に付けた瀬戸欣哉氏側の勝利となったが、その実、クビの皮一枚の差でかろうじて選任された取締役も多く、これを瀬戸氏側の勝利と呼べるかどうかは微妙なところだ。しかし薄氷の差で勝敗を分けた背後に、投資家のどのような判断があったのか、検証も進むだろう。
事後的ではあるが、人知れずお家騒動が勃発していた事例も見つかる。ほとんど話題に上ることはなかったが、北関東のある電機メーカーは昨年6月の株主総会で創業家株主と現経営陣とが取締役の人選を巡って鋭く対立した。当時の経営陣に対して「ステークホルダーの利益に資する経営が行われていない」として、創業家側は同社の役員OBを中心とした取締役候補を立て、株主総会に提案した。会社側は当然、これに対して真っ向から反対せざるを得ない。
結局、株主総会で取締役の入れ替えを求める創業家の議案は、機関投資家たちの反対で否決され、創業家は経営からも完全に排除された。ところが当時の経営トップはこの3月に大きな損失を計上して退陣を余儀なくされた。株主資本は大きく目減りし、取引金融機関に私的整理を求めるのではないかと言われるほど、財務内容は悪化している。株主は、ガバナンスの議論は上手でも、商売は下手な経営者をどう評価するのかという究極の選択も迫られていたのだ。
右か左か、戻るか行くか、賛成か反対か。国家財政も社会福祉も外交も防衛も、待ったなしの二者択一だけがあって、その中間がない時代なのだ。判断に悩まされるのは企業統治に限った話ではない。
不信だけが残ったLIXIL「画期的」株主総会
3月決算企業の株主総会が集中する6月27日が過ぎた。日産自動車やスルガ銀行、レオパレス21など世間の耳目を集めた総会が終わり、その中には特定の企業の将来ばかりでなく、日本の企業統治のあり方を左右したり、新たな問題を浮かび上がらせたりした総会もあった。
特にLIXILグループの総会は「後学のために総会に出席しよう」とわざわざLIXIL株を買って株主になった大学教授もいたくらいだ。議決結果を見れば「シャンシャンではない株主総会とはこういうものか」と唸りたくなるような内容だし、過去にさかのぼれば旧トステムと旧INAXが経営統合する前から経営学上の研究対象になりそうなエピソードや、今に通じる逸話が数多くある。
トステムと経営統合する前のINAXは、当時をよく知る関係者の言葉を借りれば「技術力があるうえに現預金をたっぷりと積み上げていた優良企業だったが、株価対策もろくに講じていない田舎企業でもあった」という。そのため当時は、海外から買収の標的にされやすい会社のトップ3に入っていた。「実直なモノづくりの会社」は「市場に正面から向き合おうとしない会社」であることが少なくない。飛んだり跳ねたりの株価対策は、マネーゲームに付き合うようで軽薄に見えたからだろう。INAXもその典型例だったのだ。
そのためかつては会社を乗っ取られそうになり、八方手を尽くしてこれを回避した過去もあったという。今風に言えば、自己資本比率が高くて手元流動性も潤沢だが、株価純資産倍率(PBR)が1倍を大きく割り込んだまま放置されている優良銘柄が海外のアクティビストに狙われるようなことがあったのだろう。
トステムの創業者、潮田健次郎氏が生前、日本経済新聞に書いた「私の履歴書」によると、トステムとINAXの経営統合はINAX側から膝を折って申し入れてきたのが発端だったという。その背景には「意に染まない乗っ取りを受け入れるくらいなら」という、INAXの危機感が働いたのかもしれない。
LIXIL騒動はトステムを起こした潮田家と、INAXの伊奈家という2つの創業家のお家騒動ととらえる向きが多かったが、世代間で考え方や価値観の違いが浮き彫りになった騒動でもある。伊奈家出身の伊奈啓一郎・LIXIL取締役が投資ファンドと連携し、臨時株主総会を開いて潮田洋一郎氏の解任を諮ろうとしたとき、INAXの元会長で一族の長老である伊奈輝三氏に協力を求めた。
「騒ぎを起こすな。社内で何とかならないのか」とたしなめる輝三氏に対し、啓一郎氏は「社内でどうにもならないからお願いしているんです」と説得したという。会社や世間を騒がせるのは恥ずかしいという体面と、現代的なガバナンス感覚が世代間でぶつかり合っていたのだ。
しかも啓一郎氏は取締役でありながら、内部告発者のような役割を演じた。これに業を煮やしたLIXILは「取締役会の内容を外部に漏らすのは守秘義務違反ではないか」として、啓一郎氏を排除するために東京証券取引所に相談を持ち掛けたほどだったという(東証では伊奈氏の行動に法令違反はないと判断したようだ)。こうして経営トップの解任を諮るため、現役の取締役が臨時株主総会の開催を請求するという前代未聞の展開になった。LIXILの総会はガバナンスの発展史のなかで大きな一里塚をなすに違いない。
とは言え、「研究対象として面白い」などとばかり言っていられないのも確かだ。定時株主総会で選任された取締役はほとんどが賛成率50%台という低さで、首の皮一枚で選任された候補も少なくない。「株主と会社のダブル・ノックダウン」というべき内容で、株主提案に対する賛意が十分に集まったとは言えず、新経営体制は早急に混乱を収拾しなければ来年の株主総会はどうなるかわからないのだ。
株主総会で生保を凍らす「殺し文句」――団体保険解約ちらつかす企業
「これはいずれ大きな問題になる。大きな問題として提起してやる」
株主総会シーズンを前に海外の投資ファンド関係者がいきり立つ問題がある。議案に対する賛否を表明するうえで、機関投資家と受益者の間に生じる利益相反がそれだ。投資家と企業の間で建設的な対話を促すスチュワードシップ・コードにも関わる問題と言い換えた方が、より切実な響きがあるかもしれない。これまでも同様の問題があっただろうが、今年はとりわけわかりやすいケースで衆人環視の下、機関投資家は踏み絵を迫られる。
スチュワードシップ・コードは①機関投資家が受託者責任を果たすための明確な方針の策定、②利益相反を防止するための方針策定、③投資先のモニタリング、④投資先企業との建設的対話による問題解決、⑤議決権行使と行使結果、行使基準の公表、⑥受益者に対するスチュワードシップ責任の報告、⑦投資先企業との対話やスチュワードシップ活動を適切に行うための実力を養う努力――の7つからなる。
今年の総会で注目され、あるいは問題になるかもしれないのは、利益相反の項目に生命保険会社がどう取り組み、受益者の利益のためにどう行動するか。いうまでもなく生保は受益者の代理人として機関投資家として上場企業の株式も多く保有し、株主総会ではその代理人として議案に賛否を示す。
しかしLIXILのように会社と株主の間で意見が割れていて、しかも会社が団体生命保険の顧客である場合、どうするのか。会社側から「団体保険の契約を解除する」と言われても、受益者の代理人として期待される役割を貫ききれるのか。生保は大株主として有価証券報告書や大量保有報告書にも名前が記載されることが少なくない。
ある大学教授は企業統治を研究テーマにしている勉強会に参加した際、出席していた生保関係者から「グループ保険を止めますよと、会社から脅されることがある」と打ち明けられた。冒頭の海外ファンド関係者は、ある上場企業の議案への賛否を巡って会社側と対立の真っ最中だが、同様の脅し文句で会社側が生保の賛成票をさらっていったことに「スチュワードシップ・コードの精神や企業統治そのものを歪めかねない」とおかんむりだ。
機関投資家は議決権をどう行使したのか、また賛否の理由は何だったのかを開示する生保が増えているが、批判に耐えられるだけの説明ができるかどうか。スチュワードシップ・コードの本家である英国でも利益相反は避けられないものとの前提に立っており、悩ましい問題なのだ。
もちろん生保もこうした事態が生じることは想定の範囲内であり、ある生保では利益相反が生じる恐れのあるケースとして「当社及び当社グループ会社との保険契約や投融資等の取引がある投資先企業への議決権行使する場合」を挙げている。
LIXILの騒動でも株主側の関係者が「(株主と共同歩調をとっている)瀬戸欣哉前最高経営責任者(CEO)は生保に事情を説明して回っている」と言うくらいだから、会社側も同じように賛成票を取り付けようと必死になっているのは間違いないだろう。また、こうした課題は生保だけのものでもない。
"Comply or Explain(順守せよ、さもなくば説明せよ)"がスチュワードシップ・コードの精神だ。生保はどう説明するのか?その公表は8~9月になる。