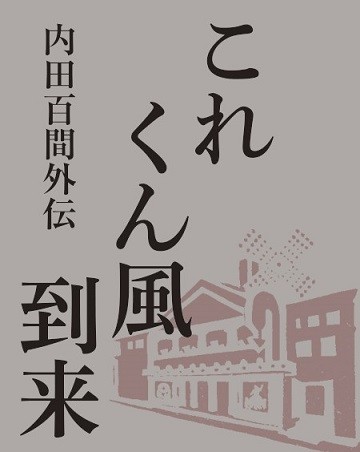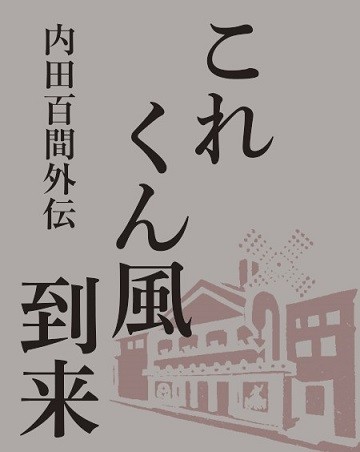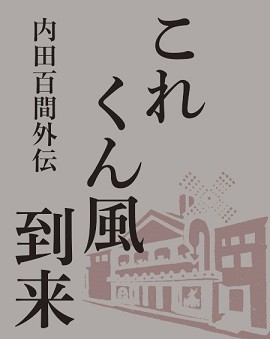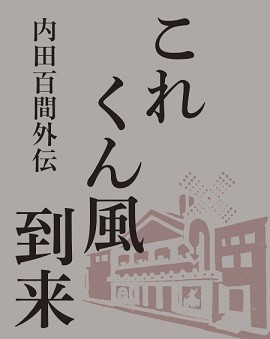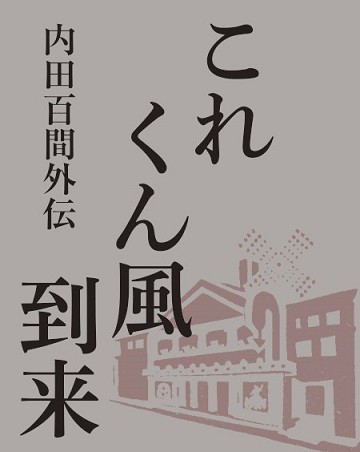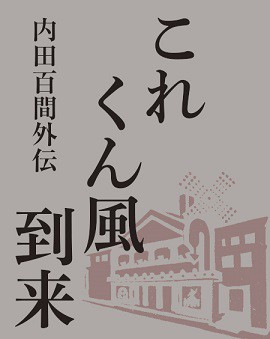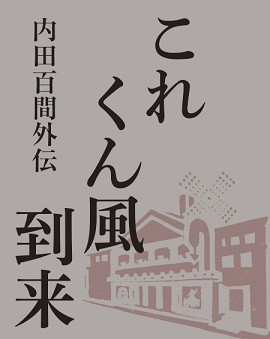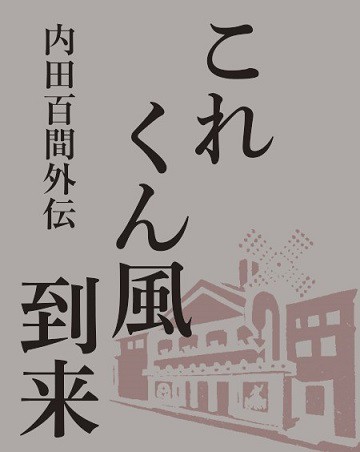百間外伝 第13話 阿房列車の人模様【戦後/中】
「国鉄文士」の殻を破る跳躍台
戦争が終わるや、国労が結成され、国鉄は政治の季節に入る。中村武志や平山三郎ら「作家の卵」たちも編集や執筆などに動き出すが、創作と闘争のはざまに立たされた。昭和25年に百間が平山を連れて旅立った「阿房列車」シリーズは、国鉄文士たちが独り立ちする跳躍台となった。=敬称略、約1万1900字

中村武志が国鉄復職
百間の日記に運輸省機関誌のことが出てくるのは、昭和21年夏のことであった。
「中村、平山来。平山を連れて来たのは鉄道の雑誌に原稿を書かせようとの為なり。大分前から中村に頼まれてゐるがいつもことわつて相手にならぬからである。今日も引受けはしなかつたが結局止むを得ざる可し」(百間日記・21年8月6日)
この年の2月27日、国鉄労働者の全国的な組織として国鉄労働組合総連合会が結成された。さらに3月15日からは東京で第一回の中央大会が開かれ、国鉄総連の組合員数は50万人を超え、全従業員の96%に達したと発表される。
国鉄当局はこの数字に危機感を抱き、組合の左傾化を防ぐために機関誌の発行を検討する。編集長は『大和』の三崎重雄かと思われたが、広島で終戦を迎えた三崎は組合の活動に熱心だった。そこで中村武志の名があがる。
中村は、戦争末期に国鉄を離れていた。
「会社に帰る途中、三立工業に中村武志君を訪ねて見たがゐないから名刺を托して置いた」(同・20年6月11日)
戦争が終わると、阿佐ヶ谷でおでん屋「べんがら屋」を開こうとするがまとまらず、続いて帰還した平山三郎と出版業に乗り出す。ちょうどそのころだろう、編集長の打診がきたのは。数えで37歳だった。

21年5月、中村武志は国鉄に復職し、機関誌『国鉄情報』の編集に取りかかる。編集長とはいっても部下はわずかに1名、むろん平山三郎であった。
7月には最初の編集会議が開かれ、担当課長から、組合対策のための機関誌なので、反共論文などをおもに掲載するとの方針が示された。
中村編集長は疑問を投げかける。
「向こうは、共産主義という立派な主義、主張があります。それを反対するだけではどうでしょう。説得力に欠ける。素手で闘うようなものです」
「では何を武器に闘えというのかね?」
「ヒューマニズムです。人間性の恢復に重点をおきたい」
「そんな悠長な。食料不足だというのに、ヒューマニズムも何もないもんだ」
議論を重ねたのち、編集長の提案は退けられ、担当課長の編集方針が確認される。ところが編集長は、会議の決定など気にすることなく、思いのままに原稿を依頼した。
内田百間も頼まれる。
「午後、昨夜平山に約束した国鉄情報の原稿『藝』を続けて、終る、六枚すんだところへ平山来、麦酒一本とお酒二合持つて来てくれた。原稿渡す」(同・21年9月3日)
運輸省機関誌『国鉄情報』の創刊号は、21年10月10日に刊行された。

天野貞祐「生活への勇気」を冒頭に、中野好夫「解放から自主的建設へ」など29頁からなっていて、百間の「藝」や、大井征が訳したシャルル=ルイ・フィリップの「小猫のバタ漬」などもあった。
中村編集長は方針を述べる。
「終戦後既に一年二カ月経過したにも拘らず、われわれはいまだに昏迷と虚脱から完全に脱出してゐないのではなからうか。われわれは敗戦によつて初めて人間の権利と自由を得る事が出来た。が、その興奮と有頂天とに災ひされて、□□な自己反省なしに軽々しく行動してゐることはないだろうか。常に現実を正しく把握し、心を内に潜めて、われわれの為すべきことに各々の誠実と良心とをかけてゆきたい。本誌の死命も自らその線に添ふべきものと考へてゐる」(「編集後記」)
一部は印字が潰れていて、□□は判読不能の部分である。
平山三郎も書いている。
「日本再建といつたやうな大きなかけ声よりも先に、まづ人間自身の内部の混乱から□□しなければならぬと反省したい。ルネサンスが、人間にかへり、といふ叫びからはじまつたとは、別な意味で私達は私達自身に返へりたい。そこから五十年百年の精神のいとなみを地味にやつてゆきたいと思ふ」(同)
創刊号を見た担当課長は、中村を外し、自分で編集すると通告した。だが2・1ゼネストを控え組合対策に手一杯で、ほどなく諦め、すべてを編集長に任せる。第2号はそのため、予定より遅れて22年4月に出版された。
その後は3カ月ごとに刊行され、24年2月の第9号からは『国鉄』となる。
雑賀進と『交通ペン』
昭和21年秋になると、御殿場で農業に従事していた雑賀進も動き始める。
現場からの要望が相次いだこともあって、12月には『検査界』復刊第1号を刊行した。わずか24頁だったが、印刷した5千部はただちに完売し、追加注文も後を絶たなかった。12月末には東京へと帰還、翌22年4月には、住居と鉄道日本社の事務所を兼ねたバラックを西神田に建て、本格的に出版業へ復帰する。
11月、百間がそのバラックを訪れた。
「運輸省の篠原平山の手紙を持参す、雑賀と云ふ人の招待に就き昨夕平山と打合はせたる件也」(百間日記・22年11月19日)
雑賀はかねてから、百間文学を「盲愛」し「百閒宗の狂信者」を自任していた。
「午後平山迎へに来て一緒に神田三崎町の雑賀の家へ行き麦酒を飲みて酔払ひたり、多分半打飲みたるならん。平山送り来りたれども平山の方がもつと酔つてゐた様也。帰る途中の事、帰つてからの事記憶になし」(同・11月22日)
雑賀進が、その記憶を埋めてくれる。
「夜十一時を回ってからようやくお開きになったが、それからが大変であった。拙宅の玄関前から表通りに出るまでの路地は三間ほどあったが、先生は例の『春の弥生のあけぼのは……』という今様を口ずさみながら、二歩進んでは三歩下るという独特の六方を踏んで、この距離に約四十分を要し、先生が帰ったら十二時を回っていた。みんなヘトヘトに疲れてしまった」(「実説内田百閒」『小説新潮』昭和46年12月号)
翌23年1月、鉄道日本社は総合文化誌『交通ペン』を創刊した。

(左上の表札に創業者「雑賀進」の表札が残っている、2008年撮影)
雑賀進は熱く語る。
「私は昭和十四年の秋から、この雑誌を計画し、九年目にようやく緒についた。長い戦争がそうさせたのである。九年の歳月は短くない。その間に醸成されたものが、今ほとばしる思い、そしてどんなにこの雑誌を愛しているか。『交通ペン』を出すために、私は今まで生きて来たようなものだ」(「編集後記」)