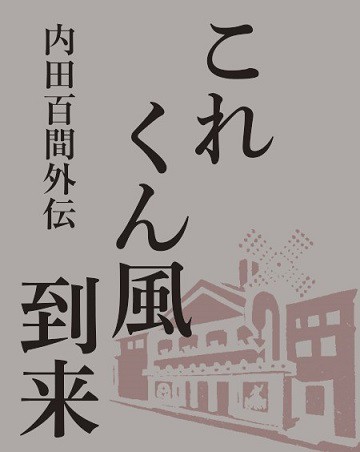
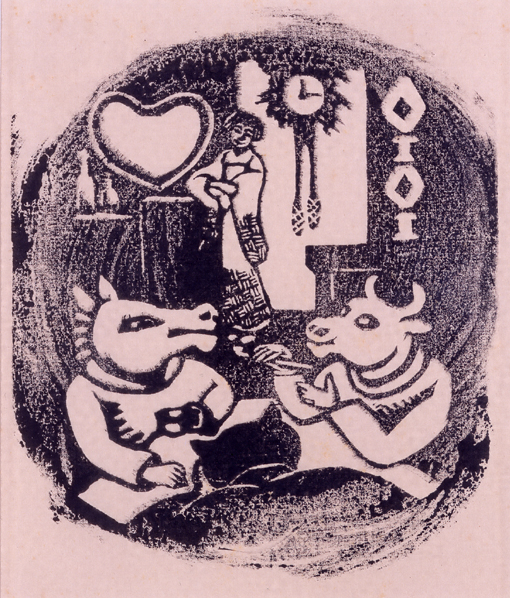
鹿肉のおねだり
始まりは、昭和14年(1939年)12月15日の宴であった。
1日と15日が百間の面会日なので、昭和14年最後となるその日には御馳走を用意した。
「今日の十五日は、馬にした。会者、栗村、多田、大橋、谷中、内藤、村山、大森」(昭和14年12月15日)
訪欧飛行の栗村盛孝、法政の元学生の多田基、風船画伯こと谷中安規、俳誌『東炎』同人の大森桐明、内藤吐天、大橋古日、村山古郷の7人が参集し、馬肉の鍋、サクラ鍋が供された。寒い冬にサクラということで、薬学博士の内藤吐天は「玄冬観桜の宴」と名付ける。
じつは2月にも馬食会が催されていて、そのときは多田基と内藤吐天は欠け、かわりに元学生の大井征と妹尾義勇が加わっていた。馬肉が初めてという者が多かったが、馬のロースを5斤買ってきて、きれいに食べ尽くした。
二度目となれば慣れたもので、玄冬観桜の鍋をつつきながら、鹿を入れたらどうかなとの声が上がり、馬鹿鍋だとの笑い声が続く。
百間はこれに、「鹿は新年会にします」と応じた。当てがあったのである。
「迎年の楽しみの一つは今から三十四五年前に亡くなつた私の父の友人が今でも神戸に健在してゐる。そのをぢさんに頼んで、あちらは丹波の山が近いから、山の獣が手に入り易からうと思つたので、鹿の肉を送つて貰ふ様におねだりした」(「玄冬観桜の宴」『都新聞』昭和14年12月31日号)
亡父久吉の友人とは、吉田金太郎のことであった。

岡山時代に吉田金太郎は、木綿問屋を営むとともに芝居小屋を経営したり、大阪の相場に手を出したりしていた。だが日清戦争後の不況で本業が経営不振に陥ると、明治36年には神戸に出て吉田金太郎商店を設立、株式の売買を業として大きな成功を収め、兵庫県の多額納税者となる。
住居が岡山教会の近くだったことから、吉田は早くから敬虔な基督者となり、神戸に移ってからも神戸教会の有力者として活動した。諏訪山の麓にあった吉田の大邸宅には、しばしば救世軍の山室軍平や組合教会の渡瀬常吉などの有力者が訪れ、集会が開かれた。
父の友人だったので顔見知りであったが、音信は途絶えていたようで、大正時代の百間の日記には出てこない。途切れた糸をつなぎ合わせたのは、金太郎の息子、吉田信だろう。
吉田金太郎には、前妻との間に4人、後妻との間に7人の子供がいた。後妻の長男の信は、神戸一中、六高を経て東京帝国大学法学部に進み、昭和2年に卒業すると、東京日日新聞社の記者となった。
昭和9年1月、百間の「学校騒動記」が『東京日日新聞』に掲載される。東京日日に寄せた最初の文で、4月に「百鬼園小什」、9月に「解夏宵行」と続いた。吉田記者はいつしか、百間が六高の先輩であることを知り、神戸に帰省したときに父親に話してみる。父親は、もしかしたら久吉さんの息子ではないかと語り、調べたところ、どうやら間違いないことがわかったのだろう。
「午後、帰つたら、父の友人神戸の吉田金太郎氏の夫人と息子の信君とが待つてゐた」(昭和12年2月28日)

ずいぶんと印象深かったようで、すぐに一文を草している。
「或る日外から帰つて来ると、玄関に見馴れない靴や女の穿物があつて、家の者が神戸の吉田さんと云ふ方が親子連れで入らしてゐると云つた。座敷に上がつて挨拶をすると、老婦人が私は吉田の家内だといつた。……老婦人の傍に、若い紳士が坐つてゐる。それが吉田さんの息子だといつた。すると代からいへば、私と同じ関係に在る筈だが、私より十何年も若さうである。初対面の挨拶をして、何の気もなしにその顔を見てゐると不意に私の気持が縺れて来た。父の友達であつた吉田のをぢさんがそこに坐つてゐると思ふ気持に似てゐる」(「父執」『東京朝日新聞』昭和12年3月25日号)
この日が吉田信との「初対面」であった。その後はしばしば行き来し、神戸からもたびたび贈り物が届けられる。
昭和14年秋に百間は、本社が台湾にある明治製糖の役員で、岡山の中学の先輩でもある中川蕃に誘われ台湾旅行を試みるが、神戸出港の前には吉田家に立ち寄る。
「午後、芦屋に亡父の友達吉田金太郎氏を訪ふ」(昭和14年11月8日)
そのときに鹿肉の話でも出たのかもしれない。すでに「おねだり」するほどの関係になっていたのだろう。
