EDITOR BLOG

第二の男
編集とは夢を見ることだ。誰かにそう言われた。でも、誰だったかもう思いだせない。
ほんとにそうだと思う。編集長はいちばん夢見る人でなくちゃいけない。売れ行き?世間の耳目?読者の喝采?いや、そんなせちがらいことじゃない。時代の夢、誰もの眼前にありながら、誰もまだ気づいてない夢を見るのだ。羊水に浮かぶ胎児の如く。
だから、天啓のようにスクープのセレンピディティーも訪れる、と信じよう。夢を見ないやつは、永遠にスクープなんか抜けないよ。
そんな夢として、温めてきたアイデアがある。「第二の男」(「第二の女」でもいいけど)。雑誌に限らずメディアは常にトップの男(または女)ばかり追いかける。誰もが憧れる存在だからだが、光のあたる存在なんて、そばで見ると結構ありきたりで、しかも「裸の王様」で存外つまらない人物も多い。他人が強いる「あらまほしき像」に本人も慣れてしまって、無意識に合わせようとするからいよいよつまらない。
いっそ、その陰にいる「第二の存在」のほうが面白い。オセロに対するイアーゴもいれば、織田信長に対する明智光秀もいる。現代の経営者だって、トップの下で「虎の威を仮る狐」もいれば、股肱の臣もいるだろう。参謀もいれば、道化師もいるし、「第二」の生態は実は千差万別。影武者なら無事でいられたのに、雌伏ののち天下をとれば、たちまち転落する輩もいる。これぞ面白いと思って、その連載企画の準備を進めている。
どんな風なものになるか、ここに予告編を掲載しよう。11月号で載っている英国の「ブレア後継」のブラウン蔵相(日本の新聞の肩書きは、日本に合わせて蔵相から財務相に変更されていますが、原語はChancellor of the Exchequerだから、やはり「蔵相」のほうがふさわしい)の記事の別バージョンである。
本誌のザ・タイムズの政治論説主幹の寄稿より、こちらのほうが「第二の男」の趣旨に近く、予告編としてブログに載せることにした。筆者に感謝する。まさに企画にぴったりなのだが、まだ企画が始まっていないので、こういう形で掲載しよう。
ブラウンにはロンドン駐在時代の96年、まだ労働党が野党で「影の蔵相」だった彼に直接インタビューしたことがある。ウェストミンスターの議事堂の地下、うなぎの寝床のような細長い部屋だった。腹心のエド・ボールズ(日本にフィナンシャル・タイムズ紙特派員として赴任、日銀などを取材していた時代に知った)の紹介である。
スコットランド訛りの重たい口調だが、頭の回転は素晴らしく速かった。当時は独身で、「ホモセクシュアルは首相になれない」とのジンクスからブレアに首相の座を譲ったと言われた。その後結婚、それでも「偽装結婚」と噂され、一子が生まれて涙を浮かべていたから、それなりに努力したのだろう。かねてからブレアが禅譲を密約しているとの噂があったが、じっと待つこと9年。ようやく首相の座を眼前にしたが、形勢がよくない。はたしてこの「第二の男」の運命やいかん、である。とにかく、こんな記事である。
*****
中道左派の新しい政治哲学と注目された「第三の道」を掲げ、43歳で20世紀最年少の英国宰相となったトニー・ブレア首相(50)が9月初め、1年以内に辞任する意向を表明した。イラク戦争を分岐点に低迷を続けた求心力は回復せず、後継に道を譲ることになった。最有力候補は、ブレア氏とともに「ニューレーバー(新たな労働党)」の改革路線を引っ張ってきたゴードン・ブラウン財務相(55)。好調な経済の立役者としての評価が極めて高い重量級の政治家だ。しかし、内向きな性格や説教口調の弁舌が災いし、「首相の器」かどうか、いぶかる声が高まっている。
9月下旬、英イングランド北部のマンチェスターで開かれた労働党の年次党大会は、ブラウン氏にとってブレア氏の後継者としての存在を印象づけるための大舞台だった。「トニー・ブレアと10年近く、ともに働いてきた。英国史上、最も長い首相-財務相の間柄だ」。ブラウン氏は大会2日目、数千人の党員を前にそう演説した。そして、「ニューレーバーのさらなる刷新」を訴え、次期首相への意欲をあらわにした。
ブラウン氏は英スコットランドの牧師の家庭に生まれ、若いときから労働運動に身を投じた。1983年の総選挙で下院議員に初当選。ブレア氏とは同期で、2人は党内の若手成長株として「影の内閣」のポストを競うように駆け上った。スミス党首(当時)が死亡した直後の94年5月、2人はロンドン北部のレストランで密会。ブラウン氏は保守党から政権を奪取するため、国民的人気があったブレア氏に党首を譲る代わりに、10年以内に「禅譲」するとの約束を取り付けたといわれる。
97年の総選挙で労働党は18年ぶりに保守党を圧倒的多数で倒し、ブレア政権が誕生。ブラウン氏は政権の事実上ナンバー2として財務相に就任した。まず財務省から中央銀行であるイングランド銀行に金融政策の決定権を移し、独立性を高めるという大胆な改革に踏み切った。その一方で、ブレア氏が積極的だった欧州単一通貨ユーロの導入を事実上阻み、経済全般の責任者は自分であるとの存在感を示した。
ブラウン氏の強力な指導力のもとで、英国の失業率は独仏の半分の約5%に抑えられた。低金利政策により住宅購入が刺激され、消費も拡大した。サッチャー保守党政権が80年代に行った市場経済型への構造改革を巧みに取り入れ、財界の信頼も獲得。若者や失業者の職業訓練の強化や低所得者の税控除など弱者への配慮も示した。「社会正義と効率的経済」。このニューレーバーの売り文句は、有権者の支持をつなぎとめる要となっている。
「この百年で最も優れた財務相」(ブレア氏)。10年近くに及ぶ実績から、ブラウン氏は党内外でそう評価されている。だが、首相としての手腕については、疑問符がつきまとう。内向きで独善的とも表される性格から、人を寄せ付けない印象を一掃できないでいる。人なつこくて、弁舌に優れ、笑顔を絶やさないブレア氏とは対照的な存在だ。
ブレア氏が1年以内に辞任する意向を表明した直後、クラーク前内相は保守系の新聞デーリー・テレグラフのインタビューで「(ブラウン氏は)細かいことまで自分ですべてコントロールしようとする完璧主義者。彼の最大の弱さは、人の言うことに耳を傾けられいことだ」と酷評した。
当のブラウン氏も、自身の性格的欠陥に気づいてはいるようだ。9月の年次党大会に先立ち、民放のスカイテレビのインタビューで、生後10日で長女を亡くした思いを打ち明けた。「何かが失われているという感覚をいつも抱いている」とうっすらと涙を浮かべながら語り、隠された人間的な一面をのぞかせた。
だが、党大会演説では自らを「非常にプライベートな人間」と認めつつ「今も昔も、労働党には政策だけでなく魂が必要だ」と相変わらずの説教口調に終始した。「次の首相」を値踏みしていた聴衆は、一応の拍手は送ったものの、興奮は長くは続かなかった。
党員らが不安を抱くのにはわけがある。10月9日で40歳となるデービッド・キャメロン党首のもとで、保守党が労働党を上回る支持率を保っており、2009年にも予想される次の総選挙で政権交代を射程にとらえつつあるからだ。
昨年12月の党首就任以来、キャメロン氏は「金持ち政党」と見られがちな保守党を中道右派政党に脱皮させる考えを明確に打ち出した。今年5月の統一地方選では「環境にやさしい党」というイメージを新たに売り出し、労働党に勝利した。その後も、貧困や若年雇用など労働党が得意としている分野に切り込む方針を矢継ぎ早に打ち出し、同氏の高学歴と見栄えの良さも手伝って、総選挙の勝敗を左右する中間層への支持を急速に拡大している。
9月下旬、ICM社がまとめたブラウン、キャメロン両氏に関する意識調査によると、「次の首相」としてブラウン氏を推したのは32%にとどまり、キャメロン氏より3ポイント下回った。ブラウン氏が「人柄がよい」と答えたのは17%で、キャメロン氏の52%に大きく水をあけられている。
かつて「禅譲」を約束したとされるブレア氏は最後の党大会で、ブラウン氏を後継に指名しないまま、ニューレーバー改革の遺産を後世に託す意向を示した。その担い手のひとりであるリード内相(59)が、ブラウン氏の対立候補として党首選に出馬するとのうわさが現実味をおびてきた。また、労組と太いパイプを持ち、教育改革に巧みな手腕を発揮するジョンソン教育・技能相(56)を擁立する動きもある。
英政界では、来年5月に党首選が行われ、来夏に新たな首相が選出されるとの見方が強い。党首選に正式に出馬表明しているのはブラウン氏のほか、党内左派の議員グループ代表のマクドネル氏(55)だけ。現時点ではブラウン氏の優勢は揺るぎないが、英政界に詳しいロンドン大経済政治学院のトラバース教授は「党首選は血の海になるだろう。予期せぬ結果が出ることもあり得る」とみる。保守党の支持率が労働党を5%程度上回り続ければ、ブラウン氏以外の候補擁立が党内で一気に加速するとの指摘だ。
ブラウン氏は党大会の演説で、イングランド銀行の独立に匹敵する大改革への野心をのぞかせた。教育など公共サービスの権限を中央から地方に大胆に移譲するだけでなく、英国史に刻まれる「成文憲法」を成立させようというのだ。
だが、労働党内にはすでに悲観論が漂っている。党史を振り返ってみると、76年にウィルソン政権を引き継いだキャラハン党首はその3年後の総選挙で、保守党のサッチャー氏に敗れた。ブラウン氏はキャラハン氏と同じ末路をたどるのではないか――。不安は募るばかりだ。
不思議の国のウサギ6――セレンディピティー
9月の予告スクープは、勝利宣言を出したあとで「気持は分るけど、自慢しちゃいけない」と言われた。おっしゃる通り。新聞協会賞をとったあとで、特別紙面をつくって自賛するのがみっともないのと同じだ。あまり勝ち誇ると、出る杭は打たれるものだ。
「10月中の日中首脳会談」というサプライズを奪われた首相官邸は、憮然とするだけならまだしも「誰が漏らした」と猜疑している。誰が弊誌のコピーを持ち込んだのか、「台湾カード」に触れたくだりに李登輝・台湾前総統もご機嫌斜めだという。
自戒をこめて反省しよう。スクープとはそもそも「罪つくり」なのだから。しいて言えば、9月13日午前6時を期してFACTAオンラインのメルマガ特別版で報じたのは、結果的に早すぎたことによるハレーションだと思う。
13日時点では、日中の折衝は正式にはまだ始まっていなかった。始まるのを知っているのは安倍氏周辺らごく少数の人間で、秘密裏に進行中だと信じていた。当方の取材源を明かすわけにはいかないが、問題は情報漏洩ではなく、ジグゾーパズルの数点のピースだけで全体の図が見えるかどうかの構想力、あるいは仮説構築力である。
少しだけ種を明かせば、あのスクープの発端は、ごくわずかの徴候から首相官邸がどう動こうとしているかの仮説を立て、その全体の絵に合わせて手持ちのピースを置いて確かめてみたものである。ある意味でこれはインテリジェンスの実験だった。
セレンディピティー(serendipity)という言葉がある。ジョン・キューザックとケイト・ベッキンセールが主演するラブ・コメディで知った。NYのロックフェラー・センター前のスケートリンクが映っていたのが懐かしいが、たあいない映画だった。
先日、タクシーで通りかかったら「コレド日本橋」(旧東急百貨店日本橋店)のビルでそんな名の店をみつけた。ははあ、こんなところまで。でも、一昔前までよほどの辞書好きでもなければ知らなかった単語である。映画ではやるまでは、誰もが「?」と首をかしげたはずだ。しかし、インテリジェンスもまた、さらには真のスクープもまた、このセレンディピティーなしでは成立しない。
ものの本によれば、18世紀の英国の文人ホーレス・ウォルポールが、意図せずに都合よく掘り出し物を発見する「セレンディップ(セイロンの別称)の3人の王子」というペルシャのお伽噺に感心したことに始まるそうだ。テキサス大学のロイストン・ロバーツ教授らのベストセラー本がそれを甦らせて流行させたらしい。
アルキメデスの風呂、ニュートンのりんごなど、瓢箪からコマ式に大発見を思いついた例が、万人の夢をかきたてるのだろう。「ひらめきの才覚」とでも訳せばいいものを、カタカナにして有り難がっているのは、ちょっと不思議な光景ではある。しかし、インテリジェンスもスクープも、ひらめきだけでもまた成立しない。検証というフィードバックが必要なのだ。
すでにそのフィードバックが始まっている。北朝鮮が核実験を強行する前日の北京。安倍晋三新首相と胡錦涛主席の共同プレス発表に盛られたキーワード「戦略的互恵関係」(strategic partnership)の真の意味である。
発表の文面を仔細に閲し、周辺取材をしてみると、予告スクープで言及した「台湾(切り捨て)カード」という切り札は使われなかった可能性がある。裏返しに言えば、台湾の切り札なしで、何によって北京を納得させたかである。靖国参拝をあいまいにした安倍新首相の訪中を中国が諒としたのは、日本が別のカードを切ったからではないのか。
訪中がほぼ固まった段階で、中国の公使が「(安倍首相が)参拝しないとの確信を得た」と口走ったのが気になる。安倍政権は今回の交渉の過程で、参拝自粛をにおわすなんらかのリップサービスを中国にした可能性があるのではないか。それが明るみにでれば、安倍ブレーンとなった岡崎久彦、中西輝政、八木秀次らが黙っていないだろう。
しかし、この自粛カードでは「台湾カード」ほどの決定的な効果はないだろう。つまり「戦略的互恵関係」の持続期間はそう長くは期待できない。せいぜい、胡錦涛主席の訪日までか。靖国がこじれて関係険悪化に困っていた胡錦涛政権と、対アジアで民主党などの批判を封じたい安倍新政権の「呉越同舟」の日中和解かもしれないのだ。
北朝鮮に対する制裁が、船舶の海上臨検などによって日中や米中がこじれれば、たちまち危うくなる程度の「戦略的互恵関係」なのだ。両国政府とも腹の底ではそう割り切っているはずだ。FACTAのセレンディピティーはそう告げている。
不思議の国のウサギ5――殿戦
さて、国連決議である。編集長としては極めて悩ましかった。
核実験の予感はあった。すでに9月20日発刊の10月号でも、10月10日の建軍記念日あたりを予測する記事を掲載している。7、8、9日の3連休は危ないと思って、週末には誌面差し替えの準備をした。が、予感があたっても、締め切りと作業工程の関係から、たちまち追い詰められることは分っていた。
10月20日発売のFACTA最新号では、日本時間15日未明の決議採択まではとても間に合いそうになかったからだ。こういうとき、締め切りのある定期刊行物は、読者の目が届かないところで「不毛な殿(しんがり)戦」を行う。
殿戦ってご存知ですか。軍の本隊を粛々と撤退させるため、最後方で追撃してくる敵を追い払い、時間を稼ぐ戦いのこと。敗戦処理とはちょっと違う。この最後方部隊が崩れれば全軍が壊走に追い込まれるため、最後まで背中を見せずにじりじり退却していく胆力が要り、もっとも難しく、かつ被害も大きい。バビロンの奥地から黒海まで逃れた「アナバシス」のクセノポンや、秀吉など名将は、みなこの殿戦をつとめている。
雑誌の場合、締め切りと発刊日のあいだのブラックホールにことが起きるのが最悪。今回はそのケースにあたり、まだ採択にいたらない段階で、あたかも採択したかのように書く(読者の手元に届くときには決まっているから)というアクロバットを迫られた。
精神医学者の木村敏流に言えば、まさに「ポストフェステ」(祭りの後)を装った「アンテ・ェステ」(祭りの前)という精神分裂状況に陥るのだ。台風がまだ来ていないのに、すでに上陸して、被害が出ているかのように書く苦しさである。
では、嘘っぱちを書いているかというと、もちろんそうではない。ぎりぎり読みに読んで、ミスリードしないように書くのだ。あとで破綻をきたさないよう、読みを研ぎ澄ます。しかし、それは「ポスト」(事後)に読む読者が、なあんだ違ってるじゃないか、と言われないためであり、大胆な予測で大向こうをうならせるものではない。
だから殿戦なのだ。ミスリードしなくてあたりまえ。それがどれだけ身を削るような読みであっても、誰もほめてくれない。朝刊、夕刊のある新聞ならみなやっていることなのだが、これはなかなかつらい。煽るだけ煽って、あとは頬っかむりするメディアになるまいとする意地である。ま、結果は何とか合格点だったと思う。
土壇場での中国とロシアの注文で、安倍新政権が当初望んだような国連憲章第7章42条(軍事制裁)ではなくなり、41条(非軍事制裁)にとどまったものの、7月のミサイル発射時に比べれば、7条に基づく決議だから大きな一歩である。
そこまでは読めた。自慢するほどのことではないが、内心はほっとしている。どれだけ苦心したかは、誌面を見て読者の想像に任せるほかない。問題はここから先である。先月報じた「予告スクープもう一丁!」の日中首脳会談問題にもかかわるので、次回に稿を改めよう。
ちょっと黒板協定破り
急に張り切って、と言われそうだが、きょうは2度目のブログを送る。
ちょっと「黒板協定」破りをやってみたいからだ。「黒板協定」とは、記者クラブの悪癖のひとつで、クラブの黒板に会見予定を書き込まれたら、報道協定を結んだも同然とみなし、加盟社は抜け駆け的な記事を書けなくなる。俗に言う「シバリ」である。このためにどれほどくだらない駆け引きが行われ、働きたくない社、または記者が抜け駆け封じに、黒板協定に持ち込んでいることか。新聞がスクープを抜けないのはこういう自縄自縛のシステムを抱えているからである。
本日標的にするのは司法記者会である。6月にニッポン放送株のインサイダー取引容疑で逮捕された村上ファンドの村上世彰被告の公判前整理手続きがきょう午後行われる。ライブドアの堀江貴文被告と同じく、裁判迅速化のために公判前に双方証拠を提示し(つまり持ち札を見せ合って)短期決戦の裁判を行う段取りだ。午後6時過ぎから村上弁護団の記者会見が行われるが、これが先週末、黒板協定となってしまった。
村上被告は起訴事実を認めて拘留22日間で釈放されたが、その後は否認に転じて、東京地検と全面的に争う構えである。村上被告側が何をもって180度姿勢を翻したのか、ぜひとも知りたいところだが、司法記者会の横着な黒板協定でそれが封じられた。「FACTA」は司法記者会に入会していないし、“登院”停止など制裁を受けるような人質はいない。だから、黒板協定を無視して、弁護側が検察に挑戦する争点を先に報じよう。予告スクープというほどではないが、あすの朝刊を先取りする。
・機関決定
昨年1月時点で村上ファンドがニッポン放送株を買い増しした時点で、ライブドア(LD)内でニッポン放送株買収の機関決定はできていなかった。当時の宮内取締役らが「買いたい」と言っているだけで、機関決定していないということは、インサイダー取引の構成要因である「重要事実」が存在しないことになる。
・ファイナンス
同時点でLD側はニッポン放送株買収の資金調達(ファイナンス)のメドは立っていなかった。一時は日興シティに持ちかけたが、蹴られている。結局、リーマンが2月にMSCB(行使価格修正条項付転換社債)で800億円調達するが、直前まで危ぶまれていたのである。
とにかく、大鶴特捜部の証拠がメールばかりで、供述が取れていないことが明らかになっている。逮捕直前、特捜部が他の村上ファンド幹部を逮捕すると“脅し”て強引に司法取引に持って行ったことは知る人ぞ知るなのだ。女性スキャンダルで失脚した元東京高検検事長、則定衛弁護士との取引を暴露するかたちで、弁護側は「特捜部のフレームアップ」を立証する作戦と見られる。
恐らく、堀江裁判以上に東京地検にとって難物となりそうな雲行きだ。やはり公判前整理手続きは、薄手の捜査能力を力ずくで押し切ってきた特捜部にとって、メッキがはげるきっかけになりそうだ。大鶴特捜部が崖っぷちに立たされる可能性もなくはない。
てなことを、検察に飼いならされた“子羊”の司法記者会は書けないだろうなあ。だから、黒板協定のぬるま湯で、みんなで仲良くなるのか。滑稽と思いませんか。
あなたがたの苦虫を噛みつぶしたような顔が目に浮かぶ。好きなだけ、知らん顔をするがいい。
10月20日新サービス第2弾――「日曜日はダメよ」
国連安保理で北朝鮮制裁決議案が採択された。それを期してブログを再開しよう。
むかし「日曜日はダメよ」(Pott Tin Kyriaka、1960年)というしゃれたタイトルのコメディ映画があった。メリナ・メルクーリという目鼻と口の大きいギリシャ人女優(のちにこのジュールス・ダッシン監督と組んで「トプカピ」なども主演。ギリシャの国会議員にもなった姐御肌)が娼婦役をやっていて、日曜は客を取らずに酒場で騒ぐのよ、という意味である。メルクーリが歌った「Nevetr on Sunday」は確かアカデミー音楽賞をとっていて、そのメロディーは小生いまだに口ずさむ。あれをまた見たいな。
と、そんな連想が働いたのは、もう10年以上も定期購読を続けているThe Economist誌が、このところ土曜に届かなくなったからだ。理由は承知している。9月下旬にアジア・太平洋地域の発行人ティム・ピネガー名義で「配達日変更」のお知らせが届いたからだ。
「日本における配布業者の送付手続きの変更のため」、10月1日から日曜日が到着日になるという。週刊誌である同誌は、たぶん税務対策上からも香港で印刷、発行しており、水曜が最終締め切りのはずだが、木曜のニュースでも突っ込むことがある。印刷、空輸、配達を考えると、毎週土曜に東京の読者に届けるのは驚異的なスケジュール(大部数の恩恵もあるだろうが)である。それが維持できなくなったというのだ。
一読者にとってこれは痛い。あの難しい英語、このボリュームは、土日で読めるから何とかついていけるので、いくら同業でも1日でThe Economistは読みきれない。駄洒落ではないが、「日曜日だけではダメよ」と言いたくなる。
しかし、同業の雑誌発行人としては、同じ悩みを抱えていますと言うしかない。この「配布業者の送付手続き変更」というのは、The EconomistもFACTAも発送を依存しているヤマト運輸のメール便が、事実上パンク状態になったらしいことに起因している。メール便は輸送量の増加にヤマトのキャパシティーがついていけなくなったのだ。
さもありなん。景気回復で物流のトラフィックが膨張しているだけでなく、恐らく末端の配達部門で重労働に耐え、かつ地理をよく知る人材が集まりにくくなっているのだろう。物流は限界的な業種だから、ボトルネック現象を起こし始めたのだ。
The Economistと同じく、FACTAもヤマト運輸から「配達に1日多くかかる」という通告を受けた。1日の差はサービス低下を意味する。では、締め切りを1日繰り上げるかというと、これは記事内容の低下を招く。あちら立てればこちら立たず、と悩ましい。
たまたまなのだが、10月20日号からFACTAオンラインは、ウェブ・サービス拡充の第二弾を実施する。IDとパスワードを持つ年間予約購読者(会員登録はこちらから)に対して、20日午前零時から最新号が閲覧できるようになるのだ。「プリント+ウェブ」の特性を生かして、紙の到着が1日遅れる分をウェブでカバーするものだ。お急ぎの方、気になる方はまずウェブをご覧ください、というわけである。
これで編集長は、遅配の責任をとって丸坊主になる心配から少し解放される。もちろん、紙の雑誌しかとっていない読者にはご迷惑がかかるが、これはThe Economistと同じく手がない。申し訳ない、と頭を下げるしかありません。
また、新サービス第二弾には応分のリスクがある。つきものの無断コピーである。閲覧したものをコピーして配布すれば、ただ売りになる。しかし、IDとパスワード登録時に無断複製をしない旨にOKをいただくことにして、そのうえで無断コピーが発生したら跡をたどる措置を講じることにした。悪質なら賠償を求めるなどの措置を取らざるを得ないので、そういう悲しい事態にならないことを祈ります。
もちろん、ご愛読いただいているFACTAの読者を猜疑する気はない。使いやすく快適なウェブ環境を守ることは、読者全員の利益になると思いますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
さて、国連決議。その評価は明日書こう。
不思議の国のウサギ4――エクスキューズ
お叱りをいただいた。なぜブログが1週間も沈黙しているのか、と。
ごもっとも。日中首脳会談をスクープしておきながら、それが行われた肝心のタイミングで何もコメントしないのはいかがなものか、と言われてもしかたがない。しかも、北朝鮮の核実験まで起きているのに。
いやはや、と頭をかくしかない。雑誌の編集締め切りピークと重なって、にっちもさっちもいかなかった。物理的な時間と、体力的な限界で、書けませんでした、とお詫びするしかないです。
やっぱり中国に行ったのが大きかった。木曜から月曜まで週末をつぶした出張で、そのまま編集に突入したので、まあ、30日間ぶっ通しという殺人的なスケジュールだったのです。
すこしへばりました。もともと不眠症だから、疲労すると頭の中をいくつもアイデアが堂々めぐりして、言葉にならない。そういう状態でブログを書くと、支離滅裂になります。
いくら覚悟していたとはいえ、核実験は編集上は大わらわ。ハンドルを切るのに精一杯で、脱輪しないよう必死。アゴを出しかけました。
ま、中国では旬の上海蟹という「楽」、スリの災難にあうという「苦」の両方の目にあったから、自業自得でもあります。編集もやっと最終局面。そろそろ再開するから、ちょっと待っててください。
不思議の国のウサギ3――中国公安局のコオロギ
中国から無事帰ってきました。と、言いたいところだが、無事ではなかった。上海でやられたのである。スリに財布を取られた。現金はしようがないとしても、クレジットカードを5枚失った。
週末の上海は国慶節の人ごみに加えて、F1の観客が押し寄せて、人民広場や外灘などは、芋の子を洗うような人また人の海。ラッシュが苦手なだけに恐怖すら覚えた。
日曜夕、ホテル近くの百楽門酒店で乾物でも買おうとしたが、タクシーから降りた際に財布を胸ポケットに入れたのを誰かに見られたのだろう。1階の人ごみで誰かの肩に突き当たる。はっとした瞬間、胸ポケットが急に軽くなり、あわてて探したが、財布がない。
やられた!振り返ったときにはもう誰が突き当たったのかわからない。たぶん複数犯に囲まれていたのだろう。心覚えのある人影はない。途方に暮れて立ちつくすだけだった。
ホテルに戻って、クレジットカードの使用停止の電話をかけるのに1時間余を費やした。それから警察に出頭しようと思ったが、中国の警察は英語が通じない。どうせ財布は戻ってこないし、日本人の多くは泣き寝入りだという。
が、ホテルが親切にも通訳の男女二人の社員を付き添いにつけてくれた。上海市公安局窓口「治安受理」なるところに連れていかれる。おやおや、これが音に聞く中国の公安か。
ガラス窓の向こうに座った警官は、意外なほど気さくだった。被害状況などを聞き取り、それを調書にしていく手順は、私も日本で経験があるが、万国共通なのだろうか。
署名する段になって気がついた。警官はえらい達筆なのだ。ううむ、漢字発祥の国だけに、負けた、という気がしてくる。自分のへたくそな署名がよけいいじけてしまった。
さて、隣の警官がその調書をもとに、PCのキーボードをたたく。MIZUHOがMIXUHOになっていた。打ち込む間、調書をとった警官が、通訳してくれた女性に何かを見せた。
布袋入りの小さな箱。何だろう?女性がそっと袋から箱を取り出してあけると、そこにコオロギがいた。さっき屋台で売っているのを見たから、中国人にコオロギを飼う趣味があるのは知っていたが、この警官までそんな風流人とは知らなかった。
この殺伐たる警察で耳を澄ませば、リーリーと鳴くのが聞こえたのだろうか。スリに狙われた屈辱と自己嫌悪が、すこし癒された。
オンライン版新装と再び勝利宣言――予告スクープを掲載
本日よりFACTAオンライン版が新しくなりました。目玉は“本誌記事アーカイブ"です。ご購読者は、最新号を発行日にあたる20日零時よりオンラインでお読みいただけます。これで、配送状況に関わらず、すべての地域のご購読者へ同時に記事をお届けすることが可能になりました。
さらに、すべての過去記事をオンラインで閲覧できるようになり、大幅に掲載コンテンツも増えました。サービスをご利用いただくには新たにオンライン会員登録(無料)が必要です。詳しくは「会員サービスについて」をご覧ください。
さて、オンライン版のもう一つの目玉として、9月13日に配信したスクープメールの後追い記事が、ようやく29日の各紙夕刊一面に掲載された。ご購読者限定で流したのは「安倍氏が10月にも日中首脳会談代償には『台湾切り捨て』カードか」で、本誌10月号(9月20日刊行)に掲載されている記事の要約版である。これで、やっとあの予告スクープがいかに早かったかを証明できた。前回と同様に、スクープが新聞やテレビ等で後追いされたので、約束どおりこのブログでも全文公開します。
*****
安倍氏が10月にも日中首脳会談代償には「台湾切り捨て」カードか
政権発足後も、中国に対して強硬外交を展開すると見られてきた安倍晋三新首相が「サプライズ外交」に踏み切ろうとしている。就任早々の10月にも北京を訪れて胡錦涛国家主席と首脳会談を行い、その途上でソウルに立ち寄って盧武鉉韓国大統領とも会談する構想で、水面下では日中韓の複雑な駆け引きが始まっている。
小泉首相の靖国参拝で冷え切っている日中関係を劇的に改善させるには、日中双方が国内を納得させるに足る大義名分が必要となる。安倍氏は靖国問題を曖昧にする代償に、台湾問題でカードを切る用意があるようだ。
日程については、11月18、19日にベトナムの首都ハノイで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の際、あわせて日米首脳会談と日中首脳会談を行うのでは「サプライズがない。埋没してしまう」としている。
現に安倍氏は自民党総裁選告示の9月8日夜、テレビ報道番組で「すでに設定されているマルチ(多国間)の会議の中で、バイ(2国間)の会談を行うことは決まっているが、それとは別にアジア外交重視を示すためにもアジアの国と首脳会談をやりたい」と述べた。これはハノイとは別の早い時期に訪中して首脳会談を行う意欲を示したものと見られる。
この大胆な外交構想の狙いは3つ。第1は自民総裁選で対立軸となったアジア外交で先手を取ることだろう。麻生、谷垣2候補はもとより、出馬を断念した福田康夫氏、反安倍色を強める加藤紘一元幹事長、山崎拓前副総裁、野党民主党の小沢一郎代表もアジア外交を批判の要としていただけに、逆手をとれば党内外を押さえ込めるとの計算だ。
第2の狙いは、本音では日中関係の悪化を危惧している米ブッシュ政権の不安を払拭できること。第3の狙いは、来夏の参議院選挙をにらんで、このサプライズ外交を攻勢の目玉にすることだ。
この安倍・胡会談実現に向けて日中は早くから動いてきた。なかでも5月にカタールの首都ドーハで麻生太郎・李肇星の日中外相会談が行われ、麻生外相が靖国神社の非政治化と非宗教法人化を骨子とする私案を提示したことが突破口となった。李外相もこれ以上の日中関係悪化は望まないとする発言があり、8月15日に小泉首相が靖国参拝しても中国は比較的冷静だった。
そして8月22日、李登輝前台湾総統の来日延期が報じられた。 9月12日から17日まで訪日すると発表して3日後、体調を理由に突如、延期を決めたのだ。
実は安倍氏が「新政権発足前なら」と李氏と日本で会談することを内諾していたが、突然キャンセルしたのだ。意味は大きい。安倍氏は日中首脳会談を実現するために、李登輝氏のみならず、台湾そのものを切り捨てたことになるからだ。祖父、岸信介元首相以来、福田赳夫、安倍晋太郎と脈々と続いてきた森派の「親台湾」は、安倍氏の手で果断に幕が引かれようとしている。
中国外務省は安倍氏の「君子豹変」を基本的に歓迎している。「靖国」と「台湾」では中国の政局のうえでも重みが決定的に違い、首脳会談受け入れへ国内説得の大義名分がつくことになるからだ。
しかし、韓国がこの動きをいち早く察知した。潘基文外交通商部長官(外相)がこのままでは日中韓3国のなかで韓国の盧武鉉政権だけ取り残されてしまうと危機感を抱き、 9月6日に訪韓した谷内正太郎外務次官に日韓首脳会談を提案した。韓国の面子を守るため、北京への途上、ソウルに先に立ち寄る歴訪案を日本側は提案している模様だ。
11日に日本記者クラブで行われた自民総裁選3候補の公開討論会では、安倍氏が「(首脳会談については)この場でつまびらかにできない」と述べたものの、麻生氏が「いろいろな形の努力が行われているのは確か」と水面下の調整の存在をほのめかしている。
ただ、ハードルがなくなったわけではない。靖国参拝自粛問題である。「参拝するかどうかは申し上げない」とする「曖昧戦略」の安倍首相がその約束を言明できないのなら、「せめて首相の名代となりうる人物からその保証を取り付けたい」というのが中国の条件だと言われている。しかし、周辺からは「靖国参拝への安倍さんの思いはまだ“成仏”していない」という声が聞こえる。
このFACTA報道で「台湾切り捨て」カードが問題視されれば、安倍氏を非難する声も出るとみられ、劇的な豹変を国内外に説明する言葉遣いは「極めて微妙でファジーにならざるをえない」。このため直前に折り合えなくなる可能性もまだ残っている。
※本誌10月号に掲載の全文はこちら(お読みいただくにはオンライン会員登録が必要です)。
不思議の国のウサギ2――有らざらん
あすは久しぶりに中国に行く。帰路、寧波に寄って、余秋雨が書いた魚背嶺に立寄るのでちょっと無理をする。そこで念のためクリニックに行った。4年前、強行軍でモスクワを往復したら、胸の重苦しさがとれなくなり、榊原記念病院で入院検査する始末になったからだ。
まあ、若くはないので、あまり無理をしないように、と言われた。ごもっとも。すでにタバコはやめているので、お酒は自重していいきましょう。
さて、デジタルメディア研究所から再三要請があり、ちょっと気が引けるが、自分の本のことを書こう。デメ研の橘川氏が始めた「オンブック」に肩入れして、この秋に彼のところから3年ぶりに本をだします。タイトルは「有らざらん」。
和泉式部の和歌(後拾遺集)、というより百人一首のひとつとして有名な「あらざらんこの世のほかのおもひでにいまひとたびの逢ふこともがな」からタイトルをとっていますが、小説ではない。ノンフィクションです。
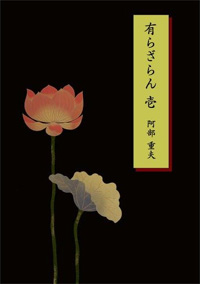 テーマはレイシズム(人種差別)。いまどきどうして?と聞くなかれ。中公新書で出した「イラク建国」のあとは、ムスリムへの逆差別が火を噴くと見越してのこと。でも、今度の主題はイスラームではない。オーストリアとハンガリーの境界にある城から始まるエピソードで、東西の衝突を追いかけた。しかし予感としては全体が「戦争と平和」くらいの長さになりそうなので、とりあえず第1巻を出すことにしたのである。
テーマはレイシズム(人種差別)。いまどきどうして?と聞くなかれ。中公新書で出した「イラク建国」のあとは、ムスリムへの逆差別が火を噴くと見越してのこと。でも、今度の主題はイスラームではない。オーストリアとハンガリーの境界にある城から始まるエピソードで、東西の衝突を追いかけた。しかし予感としては全体が「戦争と平和」くらいの長さになりそうなので、とりあえず第1巻を出すことにしたのである。
詳しくはオンブックのサイト、および早々とアマゾンで予約を始めたので、そちらをご覧ください。今度はハードカバー。表紙は知人に頼んで、漆の蓮のデザインにしていただいた。英国の劇作家サー・アーノルド・ウエスカー夫妻に叙爵記念で贈ったプレゼントと同じで、実は気に入っている。
単価は1800円くらいの予定。発売日が決まったら、また先着様何名かに無料配布もしくは割引配布しようかと思いますが、まだ詳細は未定です。ご興味のある方は予約をしてください。マスの出版ではないが、売れ残ってオンブックに迷惑はかけられないので、よろしくお願いします。
さて、編集長をやりながら本を書くなんて酔狂な、と言われそうですが、実は「イラク建国」を出した3年前の夏、500枚ほどの原型をえいやっと書きあげた。だが、どうしても納得がいかず、約束していた出版社にも迷惑をかけた。書けば書くほど自分の知識の拙さがあらわになって、とうとう筆を投げたのである。
でも、会社をつくり、雑誌を創刊することを優先させながらも、少しずつ改稿していった。ところが、すでに当初の3倍近い分量に達して、放っとけば果てしなく膨張していくような気がしてきた。
この作品をどう終わらせるのか、正直怖くなった。「交響曲10番」を恐れるマーラー(交響曲9番を超えて書いたら、命取りという迷信にとりつかれ、案の定「10番」を未完成のまま死んだ)みたいなものである。
想を練るほど、遺書を書いているような気がしてくるから不思議だ。タイトルも、ハイデッガー風に言えば、zu-Ende-Sein(終わりへ=向かって=存在すること)という不吉さがある。
手元にある桑木務訳のハイデッガー「存在と時間」は昭和44年版だから、安田講堂のあとに読んだのだろう。あの奇怪なデスマス調が、今も記憶の底から顔をのぞかせる。zu-Ende-Seinはこう説明されていた。
「こうして死は、最も自己的な、他と無関係な、追い越しえない可能性として露れます。このような可能性として、死は、ひとつの優れた差し迫りなのです。(中略)この可能性を、現存在は、その存在の経過のうちに、後から時折手に入れるのではありません。そうではなくて、現存在が実在しているときに、かれはまたすでにこの可能性へと投げ込まれているのです」
こういう文章は、あの時代、電撃のようだった。鎖状の造語に目を回しながらも「他と無関係な、追い越しえない可能性」の不安、「終わりへの投げられた存在としての実存」は、眼前にあった気がする。
今はそういう本に胸を高鳴らせる人などいないのだろうか。「有らざらん」はしかし、「他と無関係な、追い越しえない可能性」にレイシズムの起源を見ている。それを実証したいのだ。
進化論の現在をフィクショナルな対話にする以外は、全編を実名、実際の年月日、実在の場所で埋めた。さて、無事に終点までたどりつけるか。鳥居民の「昭和二十年」くらいの気長さでやるほかない……。
不思議の国のウサギ1
「たいへんだ、たいへんだ、もうきっと間に合わないぞ」。とチョッキから懐中時計を出し、ちらっと見て走り去っていく「不思議の国のアリス」のウサギに、いつも自分をたとえたくなる。
あたふたしているうちに1週間アップしないままであった。「そろそろブログを書かないと」と言われて、あ、もうそんなに、と思った。時間に錯覚が生じたのは、「予告スクープ、もう一丁!」の記事をいつこのサイトに掲載するかで、タイミングを見計らっていたからだ。
予想通り、政府および安倍周辺から番記者には口止めがかかって(「交渉中なのでコメントできない」)、東証のようなきれいな追っかけ記事が出てこない。でも、なし崩しに日中が交渉中であることは公然の秘密になってしまった。23、24日の日中外務次官協議もそれが主議題であることは明らかだが、さすがに内容は洩れてこない。
そんなわけで、雑誌は読者のもとに届き、あの予告スクープがいかに早かったかを証明するだけになった。残念だけど、ま、それもやむをえない。正式に確定したら、やはり公開するつもりである。
月末に久しぶりに中国に行く。その取材ではない。別用があってのこと。しかし中国でこのサイトにアクセスしてみようかしらん。まったく制限がないのかどうか、自分の雑誌の受け止め方に興味がある。簡体字の中国語版を出しているわけではないから、あくまでも外国の雑誌だろうが、当局は見ているだろうから。
そんなわけで次の週末はブログがお休みになるので、今週は少し書いておこう。「編集長のブログ」は長続きしないというのが世間の言われかたで、当ブログはその例外だそうだから、しばらく孤塁を守りましょう。
インタビュー:渡辺聡氏「メディアはどう変わるか(5)――メディアの適正規模とは」
メディア通信情報コンサルタントの渡辺聡氏との対談の最終回。FACTAはミニ出版企業だが、インターネットでそのハンディをカバーしようとしている。しかしSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の中には巨大化して上場するものも現れた。その維持に資本力が必要になってきたのである。同好会の延長線上にあるがゆえに心地よかったのに、資本の論理が入ると変質してこないのだろうか。ネットでもメディアには適正規模があるのかどうかを最後に論じた。
阿部我々の雑誌にも関わることですが、メディアの規模をどう考えればいいのかという疑問があります。例えば、上場予定のmixiを考えた場合、あそこまで規模が大きくなると、サーバーやシステムを維持するには、かなりの資金調達力が必要になるでしょうから、上場する意味はあるとは思います。けれども、資本市場外だったサービスが、次第に資本の傘下に入って行くことで、巨大化戦争に入らざるを得なくなります。そう考えると、規模の論理とその中身の質とを整理して考える必要がありそうですが、巨大化すべきものと、そうでないものを分ける目安みたいなものはありますか。
渡辺SNSは全体としては大きいですけれども、個々のユーザは分散しているので、1つのコンテンツが流通している訳ではありません。全員が同じものを見ているのではなく、少数の集まりが沢山あって、たまたま同じ皿の上に載っている。ローカル・メディアがたくさん集まっているような状態です。ユーザーの操作感は同じですが、コンテンツとしての繋がりはありません。全体として緩いネットワークはあるにしても、500万人いるメディアかと言われたら違う面があります。やはりサービスとして見るべきでしょう。
ヤフーの場合は、基本的にはみんなが同じコンテンツを見るので、オールド・メディア的な発想に近いわけですが、オークションサービスのようにモノのやり取りなども行われているのでパーソナルの積み重ねとも言えます。総体としての数と中で機能しているサイズは違うので、一番大きいサイズだけで比べて議論するのは違うのかなという感じがします。サービスによって内部構造が違うところが肝ですから。
阿部SNSを広告媒体として売っていかなければいけない運営会社の立場だと、かつて新聞が販売部数競争をやったように、加入者を獲得しないといけないわけですよね。
渡辺そうですね。当然、事業としては利用者を増やさなければいけないので。
阿部そうなるとやはり規模の論理を追い続けなければいけなくなってしまうのかな、と思うのですが。そうでもないのですか。
渡辺そこは当然出てきます。総体としてのサイズは力になるので、人が集まることは媒体としての価値になります。問題は集まっていることと、その効果がいかほどかということです。数が集まっても効果が変わらないのであれば、媒体としての価値は高まりません。あとは効果を上げて行くための施策をどう打っていくかということが課題になります。
阿部mixiの場合、それだけの利用者を支えるビジネスモデルは成り立っているのでしょうか?
渡辺利用者が数十万人位までは赤字でしたが、今は完全に黒字化して収益率が上がっています。あとは壊れないようにバランスを取って行くということですが、そこは概ね為されているところなので、だいぶ事業体としては安定しつつあるところです。まったく違うモデルが出て来て、利用者が全員そっちに乗り換えない限りは、かなり安泰な次元に入ろうとしています。
阿部動画を扱うYouTubeの場合、mixiよりさらに設備投資負担が重いわけですが、ビジネスモデルとして黒字化できるのでしょうか?
渡辺データは公開されてませんが、月に億単位のシステムコストが飛んでいるという話は出ています。ただ、使われ方を見るとテレビとは全然質が違っていて、まったく新しいメディアが出て来たということは確認できました。あとは、いかにして世の中に伝えて、理解してもらえるかがクリアできれば、個人的には全然大丈夫なのだろうと考えています。
確かにすごい勢いでお金が出ていっているようですが、それ以上にメディアとしてのプレゼンスがかなりのところまで来ているので、ボタンを1個、2 個つなげると、あとはぽんと黒字化するのではないでしょうか。あとは法的なところなど、残った問題が大きな火種にならないかです。
阿部分散型メディアではスパムが問題視されています。スパムの洪水でメディアとしてだめになってしまうという悲観的な見方もあります。SNSでも規模が大きくなるとスパムは生じる訳ですよね。
渡辺あまり表には出てませんが、たくさん起きてますね。ただ、そこで起こっていることは現実社会と変わりありません。利用者が増えれば増えるほど日常生活と近くなるので、現実社会で起きていることは当然ネットでも起きる。DMや怪文書がばらまかれたり、犯罪も起きるだろうし、嫌な気分にもなることもあるでしょう。ネットだからという意識で問題を必要以上に大きく取り上げるのは、そろそろやめたほうがいいと思います。
阿部スパムやウィルス、スパイウェア対策に、利用者はある程度コストをかけなければいけないということでしょうか。
渡辺いけなくなるでしょう。マンションや個人宅でセキュリティに入る感覚に近いですね。生活がインターネットに依存していない人は別ですが、ネットバンキングをはじめさまざまな情報のやり取りをする場合、PCには重要な情報が保存されているわけですから、当然守らなければいけない。家に大金を置くときは金庫を買ったほうがいいのと同じ議論です。
阿部そういったセキュリティ・コストがインターネットの“チープ”にビジネスを起こせるメリットを阻害するところまで行かないでしょうか。
渡辺一部で阻害しているところはあります。例えば、ユーザーが参加することによってコンテンツが作られていくソーシャル系サービスでは、規模が大きくなると利用者の価値観も多様になり、小規模の時にはなかったトラブルやスパムの増加によって品質のばらけが起きてきます。すると、何か最近使えないよね、と言われて急に廃れてしまう。そこには常にコストと規模の問題があります。
阿部オールド・メディアのネット戦略も、いずれ同じ問題に直面することになるかもしれません。
(5/5)
インタビュー:渡辺聡氏「メディアはどう変わるか(4)――コンテンツ設計のズレ」
メディア通信情報コンサルタントの渡辺聡氏との対談の続き。今度はメディアの「かたち」ではなくて「中身」。新聞も雑誌もパッケージにしたコンテンツを売っているのだが、読者に一方通行で発信しているから時代とズレ始めてきたという議論がある。私もそう考えていた一人だが、渡辺氏は違うことを言う。それは効率重視の富国強兵的なロジックを土台としてきたからで、今やそうした政治主導や経済主導のコンテンツは求められなくなっているという。これはショッキングな指摘だ。「空間的に自分の活動圏と地続き」というニーズは何なのか。
阿部紙メディアは読者をセグメントすれば生き残れるという話は分かりますが、規模の大きい新聞社や出版社は雇用を維持しなくてはなりません。その場合、本業が細って営業収入が減った分、まったく別のビジネスを始めることによって補う必要がある。
The Economistの記事には北欧の新聞がインターネットへの変換で成功しましたと書いてありますが、本業の収益低下をインターネットを使った料理教室やダイエット教室で補っているのです。しかし、それではメディアとしてインターネットに適応したとは必ずしも言えないと思います。
テレビから紙、インターネットまで手がける複合メディアの企業戦略の問題と、メディアとしてどう生きるべきかという話は違います。個々で見た場合、分散型メディアから凝縮したパッケージで売るメディアまで、どう戦略を立てるのが理想的でしょうか。

渡辺多様すぎて、一つの公式でははまりませんが、まずは世の中の変化をきちんと受け入れているかどうかだと思います。それが実際の企業行動にどう出ているかですね。
阿部私を含めて、オールド・メディアは発想がブロードキャストで、ある一点からかくあるべしとピラミッド状に情報を散布しようとしがちです。情報がどう着地したかやリアクションはあまり気にしていない。
ただ、アウトプットのプロセスはそうですが、インプットのプロセスでは、取材先に行って対話をし、いろいろな人の意見を聞いている。取材先とはコミュニケーションを取りながらも、受取手に対しては常にブロードキャスト発想で、跳ね返ってくるものに耳を傾けられない。はっきり言えば、新聞・テレビ・雑誌にとって恐いのは、取材先からの訴訟であって、受取手からの反応ではないのです。だからメディア戦略を作る時も独りよがりになりやすい。それが習い性になっていますから、そこを変えるにはコペルニクス的転換をやらないといけない。
メディアに対する世間のイメージと中にいる人間の感覚がまったく違っていて、時代の流れからだんだん乖離しているような気がします。
渡辺世の中が経済主導ではなくなってきていることも一因でしょう。経済主導でない時代に必要とされているメディアの一つがネットなのかもしれません。これは紙とネットという媒体の違いではなくて、コンテンツがニーズに関してフィットしているかどうかの問題です。あくまで感覚的な意見ですが。
阿部感覚として、経済以外にどういうニーズがありますか。
渡辺経済活動が世の中からなくなることはありませんが、日本においては戦後のような経済成長はもうないでしょう。物質的に豊かになって、これ以上物は必要ないという時に、ブロードキャスト的に生産効率とか強く大きくというロジックだけで組まれているコンテンツがどれだけ必要とされるかという疑問があります。十把一絡げでエンターテインメントというと表現が広いですが、娯楽、遊びだけではなく、カルチャーなども含めたコンテンツが生活の豊かさに繋がりやすくなっている。
政治が偉かった時代がありました。政治は今でも大事ですけれども。経済が偉かったのは、国がどんどん伸びて強くなって行くことが主題だったからです。でも、それもどこか一段落して、数パーセントの成長で、ゆったりとした流れを望む人が増え、コンテンツにも変化が出ている。
紙とネットの議論が盛んですが、コンテンツの問題が見過ごされているとしたら、戦略を組むときにもなにかのズレが出てしまう可能性は高まるでしょう。根本的な問題の所在があまり取り上げられてないように思います。
阿部政治の時代、経済の時代が終わって、次はもっと自分の生活に近い情報が求められているとすると、渡辺さん個人はどういう情報が一番欲しいですか。
渡辺何の情報が欲しいかというよりは、情報の提示のされ方として、こちらが上でほかは下というコンテンツ設計ではなく、それぞれの情報が空間的に自分の活動圏のちょっと先に繋がっているような受け取り方ができればなと思います。検索サービスの作り方はこの感じに近いです。
その方が、世の中で何か起きていて、もしかしたら自分に影響するかもしれないということが分かり易いしフィットする。どこに真実があるかとか、偉い人が何かを言っているということへの感覚が薄れているように感じます。そういった時代においては、ライフスタイルと遠い話をうまく橋渡ししてくれて、受け止め易い翻訳をしてくれるものが必要とされるのだろうと思います。
阿部例えば世の中のことをユダヤ人の陰謀だと何となしに関係付けてしまう、コンスピラシー・セオリーという一番やっかいな考え方があります。ネットの世界では嫌中や嫌韓を言う人たちが目立ちますが、そこで使われているのは、まさに遠い世界の話を身近なところに引き付けるロジックで、すぐに「すべては陰謀だ」という話になってしまいます。ジョークやフラストレーションの発散でやっている人も多いのでしょうが、これだけ横行すると、憂える人にとってはやばいなと思える状況です。やはりライフスタイルの遠近感、距離感が昔と全然違ってきていて、そこを埋めるメディアがないことによるのでしょう。
渡辺そうですね、説明の仕方がないのでしょう。象牙の塔だったものを落として行く形ではなくて、逆転させた上で言葉にするようなものがそんなにない。情報が欲しいと思っている人は沢山いて、知りたいと思っている人は何を見ればいいか分からないと言う。その答えとしてウェブやブログをただ持ち出して終わりとするのはまだ弱いところがある。今のところ、上手くガイドするものがないのだなと思います。
それが出来ればすごく受け入れられるはずですが、それが紙なのかネットなのか別の媒体なのかはまだ分かりません。
(4/5・つづく)
ときどき代行5――「いちばん早い書評コラム」を始めます
編集長ブログ「ときどき代行」の和田紀央です。FACTAは創刊から半年経ちましたが、11月号(10月20日刊行)から書評欄を載せようと現在準備中です。
ありきたりではつまらないし、小説やミステリー、あるいは政治家やタレントの宣伝本、さらに学術専門書や研究文献の書評を載せても、FACTAのめざすものから外れてしまいそうです。そこで、ノンフィクション、またはそれに準ずる伝記、歴史、ルポルタージュ、紀行、サイエンスなどFACTSに関わるジャンルに絞った書評を考えています。
FACTAの原点はそこにあると思うので、ノンフィクション・ライターへの激励もこめてそれに傾斜した書評にしたいと思います。ノンフィクションは日本の出版界では比較的不遇で、取材の労多くして実入りが少ないジャンルです。しかし、英国の書店で人気のあるコーナーは「Biography」と「Travel」です。その内実は「ある人生」をとことん追跡するノンフィクション、辺境や未知の地域を見て歩く紀行ノンフィクションで、これは希望の光と思えます。
編集者の方々も苦労されていると思いますが、英国の伝記や紀行の隆盛はそこにライターの努力を刺激するクライテリア(評価基準)が確立し、市場を成り立たせてこそだと思います。出版社の方々はこの書評欄の趣旨をご理解いただき、これぞと思う本をご紹介ください。
ひとつ条件があります。ノンフィクションの本は店頭に並べられる期間が大変短い。新刊本をお送りいただいてから、読んで書評すると早くても1カ月、遅ければ数カ月かかって、せっかく紹介しても店頭から消えていて、アマゾンからお取り寄せになってしまいます。
そこで出版前のゲラ(またはバウンド・プルーフ)をお送りいただき、刊行日にあわせて事前もしくは新刊早々に書評を載せる方式をとりたいのです。そうすれば、書評を読んだ人が店頭でめざす本に出会えることになります。出版取次の容赦ない効率陳列を出し抜いて「日本でいちばん早い書評コラム」をめざすというのはどうでしょう。
赤字が入っているゲラでも構いません。筆者の了解をえて、責了前のゲラをお送りいただければ、書評の対象として検討いたします。サンプル例をお見せしましょう。本誌編集長が親しい編集者たちにご協力をお願いして、お送りいただいたゲラのうち、9月15日発売予定で、書評コラムのスタートが間に合わない本を、このブログでとりあえず私が取材して書評してみました。
『累犯障害者獄の中の不条理』(山本譲司著、新潮社、1470円)
 著者のお名前に見覚えがある方もいるかもしれません。政策秘書給与の流用事件で01年2月に実刑判決を受けた元衆議院議員(菅直人氏の元公設秘書)です。獄中での生活を『獄窓記』(ポプラ社)として著し、04年に「新潮ドキュメント賞」を受賞していますが、今回は第2作目となります。
著者のお名前に見覚えがある方もいるかもしれません。政策秘書給与の流用事件で01年2月に実刑判決を受けた元衆議院議員(菅直人氏の元公設秘書)です。獄中での生活を『獄窓記』(ポプラ社)として著し、04年に「新潮ドキュメント賞」を受賞していますが、今回は第2作目となります。01年、刑務所に入所した山本氏を待っていたのは「塀の中の掃き溜め」と呼ばれる隔離工場での懲役作業でした。そこで、精神・知的・聴覚・視覚などに障害を抱えた受刑者たちの世話係として、433日間の獄中生活を送ります。出所後、同氏はそこで知り合った元受刑者たちの消息を追い始めますが、本書はその記録をまとめたものです。一部は「新朝45」に掲載されましたが、加筆や増補してこの本ができあがりました。
かつての受刑者仲間たちは、ある者は路上生活者となり、ある者はヤクザの一員となり、もがき苦しんでいました。そして何名かは変死や自殺によってこの世を去っていました。さらに取材を重ねた結果、著者が目にしたのは、この世のどん底ともいえる地獄絵でした。
暴力団員と養子縁組させられて一生食い物にされる人々、売春を生きがいにする知的障害女性たち、必要もないのに精神病院の閉鎖病棟に収容されている重度知的障害者たち……。一事、メディアを賑わせたあのレッサーパンダ事件の犯人とその家族にも迫ります。そこには高校にも行けず、癌に侵されながら兄(犯人)と同じく知的障害を持つ父の面倒を見続けた若き妹の存在がありました。
その衝撃的な内容に心を奪われ、一気にゲラを読んだ私は、山本氏に電話でこの作品を書くにいたった事情などのお話をうかがいました。
――執筆にはどれくらいかかりましたか。
山本02年8月13日に出所して4年かけたことになります。障害者施設の支援スタッフをやりながら執筆を続けました。
――この本を書くにいたった心境は?
山本服役するまでの私は、刑務所に重度知的障害者などいるわけがないと思っていました。彼らは福祉からも教育からも親族からも見放され、司法の網にようやく引っかかってきた人たちです。私も議員時代に「セーフティーネットの構築で安心できる社会を」などともっともらしく語っていましたが、日本の福祉のセーフティーネットはあまりにも脆弱でした。触法知的障害者にとっての安住の地は刑務所なのです。その現実を知って愕然とし、忸怩たる思いをしたことが、出所後の障害者支援活動や執筆の原動力に繋がりました。
――タイトルが刺激的ですが?
山本覚悟と期待をこめています。「知的障害者は犯罪を犯しやすい」と言っているかのように誤解されかねず、障害者本人及び福祉関係者からクレームが来るかもしれません。でも、この本は“なんとなく癒し癒される美しい関係”に満足している日本の福祉に対する挑戦ですから、感動的に美談調で取り上げることはしたくありませんでした。どう読んでもらえるか、楽しみにしています。
――日本のメディアでは悲劇的な事件も「頭のおかしな人が犯した犯罪」として片付けられていることが多いように感じます。しかしそれでは解決できるものもできません。
山本そうなんです。知的障害者が犯す犯罪には、誰も目を向けようとしない社会の闇が大きく関係していると私は考えています。しかし、マスコミはタブーに触れようとせず、事件の猟奇性にばかりクローズアップします。日本の福祉の現場も同じで、前科が加わった障害者に対して概して冷淡です。知的障害者の罪を対岸の火事として見て、司法に投げてしまいます。
私も一時期は『新潮45』や週刊新潮の「黒い報告書」にはまっていたことがあります。「読み応えあり」と自信を持っておススメしたいと思います。ただし、読み応えがあり過ぎて、心にズシリと来てしまうかもしれません。
インタビュー:渡辺聡氏「メディアはどう変わるか(3)――大衆化とSNS」
メディア情報通信コンサルタント、渡辺聡氏との対談の続きです。第1回は「Web2.0」とな何か、第2回はヤフー・ニュースのような人手と自動が渾然一体となっているもの。今回はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)について語りあいました。もちろん、私は同好会的なSNSとは対極的な月刊誌を編集し発行している立場で、冷静にメディア間の違いを眺めることのできる渡辺氏と違い、つい熱くなってしまいました。近視眼的かもしれません。
阿部このブログでも書いたのですが、「The Economist」の"Who kills the Newspaper?"という新聞論は、実際はインターネット対新聞論になってます。内容は目新しくはありませんが、非常にイラストレーターが上手で、崖っぷちに新聞を持つ人が立っていて、その新聞の紙飛行機に乗ってディスプレーの中に消えて行く。うまいなあ。まさに、メディアの現状を表しています。
私のような元新聞記者にとって、エポックメイキングだったと思うのは、ニューズ・コーポレーションがアメリカのSNS最大手、MySpaceを買ったことです。ニューズ・コーポレーションのルパート・マードック氏は新聞業界の中では伝説的な人物で、彼こそ新聞王と言っていいかもしれない。しかし、新聞買収に非常に執着を持っていましたが、彼の買収によって新聞が良くなったかどうかというと、それは別問題です。
「The Times」という有名な英国のクオリティペーパーがニューズ・コーポレーション傘下に入ったのですが、質はどんどん低下した。今はタブロイドになっていて、中身は硬い内容が書いてありますが、全体として何をやっているのか分からなくなってしまった。昔は硬くて地味だけれども、英国の保守党エスタブリッシュメント層の内輪話が沢山載っていて、それが英国政界を読む時などには非常に役立ったのです。今は、そういう部分はまったく無くなった。はっきり言えば大衆化したのです。
マードック氏はThe Timesを持ち、20世紀フォックスを買ってフォックステレビをやり、どんどん資本の論理で回転して行った果てに、MySpaceを買って大成功した。それが彼がやった成功物語です。
これを大きな流れとして見ると、商業メディアに求められているのはローカルニュース、天気情報、交通情報、エンターテインメントです。読者は身近な話を求めていて、政治や外交などの大言壮語するような情報は二の次、三の次でよろしいというのが典型的な動きです。それは新聞記者魂を滅ぼすものだと言って嘆いた人は、あの時代のThe Timesの編集部にも沢山いました。
しかしここまで来ると、その流れを否定できない。先ほど渡辺さんがおっしゃった折り合う地点というか、メディアとしての住み分けを考えざるを得ないのかなと思います。果たしてそれが可能なのかどうか、どういうふうにお考えでしょうか。
渡辺例えば、英国の通信社ロイターが消えるかと言ったら、恐らく消えないですよね。そのビジネスの中心は、新聞への配信から金融市場向けのロイター・モニターに移っている。金融取り引きをする時に、その基盤になる情報を提供するロイター的な組織体は絶対なくならない。ある産業にとって必要な情報を提供するエージェント的なものは絶対に残るだろうと思います。
また、リクルートのフリーマガジン「R25」のように小さくて軽いながらも、コンテンツ自体はしっかりとしているパッケージがある時に、総合誌とか新聞とかをどんと出されると、ちょっと重いなという感じもあります。消費者が使い勝手のいいサイズが欲しいと言っている時に、いくらクオリティが高くても重いコンテンツを出してはしょうがないわけです。
The Timesの話で、エスタブリッシュメント層の内輪話という話がありましたが、それは、The Timesがその層の情報交換を代理していたということでしょう。あるコミュニティというか文化圏があって、その範囲の中で必要とされるものをカスタマイズしてフィットするように出して行くのは、メディアのひとつの基本形です。国のサイズになると全国紙だし、30代女性というと女性誌とかになる。ターゲットにフィットする切り出しが出来て、その人たちがオーケーだと言えばメディアは成り立つわけです。あとはコストの問題、組織体の問題です。
ただ、今は利用者(読者)数が増えれば破綻するロジックが強固に働いているので、下手に増やさずに、小さくきれいにまとめるほうが安定化しやすい傾向はあると思います。
(3/5:「コンテンツ設計のズレ」へつづく)
予告スクープ――もう一丁!
FACTAは9月13日午前6時を期して、またスクープを報道します。今度のインパクトはたぶんもっと大きい。海外紙にも追っかけさせたいな。
前回は期待以上の成果でした。8月22日発信の「東証にみずほ証券が400億円請求」の特報は、新聞全国紙の全紙が第1面で追っかけたからです。ある出版社の知人は「バットで外野をさして予告ホームランするみたい」と悔しがった。
今度はそこまで完勝は期待しない。ちょっと漏れかかっているので、9月20日の10月号刊行日まで待っていては、スクープがもたないと判断した。しかし、取材はずっと先行していたはずで、ウラも取れているから、中身の濃さには自信がある。
前回の「東証」は本誌に載っていない独自ニュースだが、今回は本誌10月号(9月20日刊行)に掲載される記事の要約版である。詳細な全文をお読みになりたい方は本誌が届くまでお待ちください。関連記事もいろいろありますから、タイミングはネットより遅れても、けっして損はさせませんから。
ところで、東証400億円スクープの第一報が実はFACTAのメールマガジンだったことをご存じない方もいらっしゃるかもしれない。改めてわがメルマガ臨時版をご紹介しましょう。
FACTAは紙の雑誌とインターネットの二刀流です。このウェブサイトに載っている編集長ブログや記事の無料公開(フリーコンテンツ)は不特定多数の方々からのアクセスを待つ受身形ですが、FACTAから能動的に発信しようとメルマガ「FACTAオンライン」をスタートさせたのです。
8月から最新号の紹介版として登場し、東証400億円のニュースはその臨時版として、本誌ご購読者に限定して送ってみたものです。いわば、FACTAオンラインの号外版ですが、幸いご好評を得たので、これからは本誌締め切りのタイミングに合わないスクープを随時発信していくことにしました。
発信させていただくのは、本誌の年間予約購読者で、かつメールアドレスをご登録いただいている方です。まだご登録していないかたは、このスクープをお見逃しなきよう、support@facta.co.jpまで愛読者番号(本誌包装袋のラベルに記入されていますが、ご不明の場合は上記アドレスかサポートセンターまでお問い合わせを)を記入のうえお知らせください(13日午前6時配信の受付は本日20時までとさせて頂きます)。
メルマガFACTAの臨時版はご購読者に一足先にサービスしようというものですが、ご購読者以外の方々を締め出すわけではありません。前回と同じく、このスクープが新聞やテレビ等で後追いされましたら、このブログでも無料公開します。
号外でない通常のメルマガ「FACTAオンライン」は本誌最新号の目次や読みどころなどの内容紹介として、7月20日の8月号発刊時から開始しました。10月号については刊行日の9月20日に発信しますので、ぜひご覧ください。
さて、なんだか、長年「種の起源」を書きためてきたダーウィンが、まったく別に進化論の着想に到達していたウォーレスが発表しようとするのを聞いて、急ぎ自分も同時発表にしたのと似た気持ちです。刊行日に間にあわないのは悔しいが、ご購読者に一日でも早くスクープをお届けするためです。乞うご期待!
インタビュー:渡辺聡氏「メディアはどう変わるか(2)――ヤフー・ニュースの新と旧」
メディア情報通信コンサルタントの渡辺聡さんとの対談の続きです。Web2.0のテーマから一歩踏み込んで、ヤフーのニュース論に進んだ。選別や見出しなどの作業が実は人手というあたり、E・A・ポーの「メルツェルの将棋指し」を思わせて面白かった。確かにヤフーには微かに人肌の温もりがあるが、グーグルにはない。
阿部渡辺さんが書いた「信頼性とメディア設計」の中でアウトライン整理としてメディアのタイプを「新聞、雑誌」「ディレクトリサービス」「サーチエンジン」「ソーシャル系サービス」と4段階のカテゴリーに分けてられてますね。新聞、雑誌は分かりますが、第2番目のディレクトリサービスとはヤフーなどのことでしょうか。
渡辺そうですね、各社いろいろありますが、ユーザーの現実としてイコールでヤフーと言ってしまったほうがいいかもしれません。
阿部それぞれのサービスの中身はどう違っているのでしょうか。
渡辺紙だと発刊サイクルがありますよね。ソフトウェアもそうですが、箱に入れて流すと、物理的なタイミングや制約によってリリースのサイクルが決まってしまいます。しかし、インターネットによって決まったサイクルでしかコンテンツを出せないことから解放されました。毎週でも、毎日でも、毎時間でも、好きなタイミングで更新出来るようになったというのがポイントです。だからヤフーのニュースは、そういう時間単位でぐるぐる変わって、見られなかったらぽんと打ち切ったりと、常に動いています。紙などに比べてパッケージングが非常に柔らかくなったのです。
つまり、最新号という概念がない。何号というパッケージがないのです。行けばその時点で最新のコンテンツが見られる。その時々に必要なものが出て、ずっと更新され続けています。しかし、裏では人がやっている訳です。だから、この記事がいいとか、タイトルを好みで付けたりという点では、ある意味、昔のメディアとそんなに変わらない。
阿部新聞でいう整理部をやっている。
渡辺ええ。新聞の見出し付けと、あまり変わらないところです。ヤフーが出てきた時代というのは、どこかの紙の記事、ちゃんと書かれた記事を引っ張って来て、そのままオンラインに出しておく形です。そういう意味では、以前とそんなに変わらないとも言えます。ただ、素人の入る余地はない。
ところが、だんだんネットにコンテンツが増えて来て、サーチエンジンで検索したものが自分にすごいフィットするようになると、どこかでお墨付きを受けたものでなくても、出たものを自分が納得できればよくなってきた。パソコンの前でかちゃかちゃやると、自分にフィットしたものが出て来る。こうなった瞬間にパッケージングがメディアの商売だとすると、メディアの形というものがなくなってしまう訳です。パッケージングはもうプログラムに置き換わってしまっていて、ひと目見てもよく分からないブラックボックスになってしまっています。ある記事が他の記事より重要だというランキングの結果が出てもそれは数学的にしか説明出来ない。
サーチエンジンによって、人が何か情報を欲しいと思った時に、これだと思えるものがぽんと答えのごとく出て来るようになった。魔法の小箱のような感じです。これは当然、ニュースにも利用できるだろうということで、グーグル・ニュースのように、いろいろな媒体のニュースを集めて来て独自の見せ方をするアグリゲーター・サービスが沢山出てきています。
昔は人が考えてやっていた順序付けとか誌面配分をプログラムが行うことによって、編集者ではなくてエンジニアが誌面を作っているような形になった、というのがサーチエンジンによる自動化の流れです。この時、コンテンツはどこからでも引っ張ってこれるので、プロが作ったかどうかではなく、いかにしてフィットを保証するかが重要になったのです。
次に、サービス利用者が多くなると、利用者みんなで情報に重み付けするのもいいよねという話が出てきた。
この記事は面白いよ、という話をみんなから集めるうちに、だんだんと重要なニュースが浮かび上がって来る。読みたい人が読みたいものを、読みたいように読めるようになってきて、誰かがこれは大事だと決めたものを受け取るのではなくて、自分たちで重み付けを行うのが、最近出て来ているソーシャル・ブックマーク・サービス(SBS)のようなものです。米国の「digg」や「del.icio.us」、日本では「はてなブックマーク」などが有名ですね。
SBSはメディアかと言うと違うかもしれませんが、ある情報をランキングして、大事なものを引っ張り出して、これだけ読めばだいたい今の世の中の動きが分かるよ、というメディア的なパッケージングをしてくれるサービスがいろいろ出てきた、というのが今までの流れです。
これが絶対的な進化ではないですが、メディアと呼ばれる組織がやることは非常に小さくなっていて、もしかすると情報が流れる仕組みさえ作って面倒を見ていれば、あとは全部できてしまうかもしれない。片方ではそういう流れになって来ています。でも反対側では、取材しなければいけない記事というのは絶対にあるので、すごい軽い世界と絶対にやらなければいけない世界が今は同時にあって、この2つのバランスが全然取れていない。だから、右を見ても左を見ても気持ち悪い感じがするのでしょう。今はこのバランスを取って行くために、いろいろな議論やステップが踏まれている時期だろうというのが、私の見方です。
もしかしたら、今は過渡期の中でも一番ややこしい時期かもしれませんね。片方はもう間違いなく伸びると言われているが、もう一方がだめな訳でもないし、絶対に必要な部分もある。でもしっくりした接点がない。だからすごく議論がある。
阿部おっしゃるとおりです。私がやっている雑誌はまさにプロフェッショナルな世界で、分散していないというか、代替不能の取材そのものの世界です。小さいところに凝縮したパッケージを、編集部数人で月ごとの切り口にして売るわけです。それが薄く広く浅く、かつ身近な話を膨大に時々刻々並べたサイトに情報のニーズが移って行って、全部そちらへ行ってしまうのですかという疑問が起きます。つまり、プロフェッショナルなパッケージは生き残れないのかという疑問です。ただ、何の理論的根拠もないけれど、直観的にプロフェッショナルのある一定の枠を持ったメディアは消えることはないと確信がある。だからやっているわけです。
(2/5:「大衆化とSNS」へつづく)
インタビュー:渡辺聡氏「メディアはどう変わるか(1)――web2.0の実体」
前回の鳥越俊太郎・オーマイニュース編集長につづき「メディア論」をテーマしたインタビューを連載します。今回登場していただくのは、メディア情報通信を専門としたコンサルタントの渡辺聡氏(渡辺聡事務所)です。渡辺氏は2004年4月よりテクノロジー系メディアのCNETJapanで「情報化社会の航海図」と題したブログを連載しており、テクノロジーの視点からメディアについてたびたび取り上げられています。
渡辺氏はCNET Japan ブログの「信頼性とメディア設計」(2006年6月7日)という記事の中で、インターネット時代におけるメディアのタイプを「新聞、雑誌」「ディレクトリサービス」「サーチエンジン」「ソーシャル系サービス」の4つに分類し、それぞれの特徴について論じています。今回は、その辺りの話を中心に、テクノロジーの変化によって今後メディアがどう変わっていくかについて聞きました。
阿部私はどちらかというと、渡辺さんがジャンル分けしている中ではかなりオールド・メディアに所属する人間で、ニュースアグリゲーターや検索エンジンも人並みに使っていて、自分の出しているプリントメディアとの落差というか違いを意識しなければいけないと思っている人間の一人です。世の中ではよく Web2.0と言われていますが、私自身も含めて今一つ、はっきり良く分からない。私の理解ではWeb2.0というのは、ユーザーがある程度参加するもので、かつ非常にサーバーが廉価になったので、その安さを自分たちのビジネスを形成していく上で取り込もうとしているものと漠然とイメージしていますが、渡辺さんはまずWeb2.0についてどうみていますか。
 渡辺なければならない論のような決まった考えというのはないです。2.0というまとまりで物事を考えたら正解かと言うと、あまりそう思っていないところがまずあります。お客さんのビジネスにしても何か新しい事業モデルが出てきたときでも、「これは2.0かどうか?」などとは全然考えません。クライアントに対して何かメリットを提供して機能するかどうか、ユーザーにしても事業者にしても、新しさなりインパクトがあるかということを考えるので、中身がアナログであろうとあまり関係なく見てます。ただ、こういうトレンドというか、言葉が出てきたなとは認識しまていますし、まとまった言葉として出て来て世の中に受け入れられつつある、表れつつあるということが大事なのだと思います。言われていることが正解かどうかというのは、もう少し歴史的に待って判断した方が良いと考えています。
渡辺なければならない論のような決まった考えというのはないです。2.0というまとまりで物事を考えたら正解かと言うと、あまりそう思っていないところがまずあります。お客さんのビジネスにしても何か新しい事業モデルが出てきたときでも、「これは2.0かどうか?」などとは全然考えません。クライアントに対して何かメリットを提供して機能するかどうか、ユーザーにしても事業者にしても、新しさなりインパクトがあるかということを考えるので、中身がアナログであろうとあまり関係なく見てます。ただ、こういうトレンドというか、言葉が出てきたなとは認識しまていますし、まとまった言葉として出て来て世の中に受け入れられつつある、表れつつあるということが大事なのだと思います。言われていることが正解かどうかというのは、もう少し歴史的に待って判断した方が良いと考えています。阿部「まとまり」とおっしゃいましたけれども、それは具体的にどういうイメージですか。
渡辺ネットが進化しつつあるようなイメージと、進化したイメージの中に具体事例っぽいものがいっぱいあるということの2つです。mixiがすごく伸びていますとか、ブログがたくさん使われ始めましたとか、ああいう新しいビジネスモデルを何とかものにしたいという人たちがいっぱい出て来て、何だか最近、騒がしい。このざわついている感じと、ざわついている感じをぐるっと囲って、web2.0というシンボリックな言葉がある。よく分からないけれども世の中何か起きているらしい。そこがまず基本だと思います。オライリーの論文にしても、その他の様々な議論も見るところは見ていますが、公式として機能しているものでもないですし、どれかが決定版というものでもない。でも、なんとなく共有しているイメージとドライブ感は業界に感じられます。
最終的な消費者というか利用者として見た場合、使っているサービスが便利かどうかだけがポイントなので、何に分類されるかはあまり関係ありません。投資家とか会社を作りたい人たちが共通言語として使うかどうかであり、ユーザー側はサービスされるときに、ビジネスメリットなり以前に無い便利さがあると判断して取り込めば良いと考えてます。
阿部梅田望夫さんの『ウェブ進化論』が一番代表的だと思うのですが、オールド・ウェブと2.0をはっきり分けて、要するに明暗をはっきり対照させているところが分かりやすいのでしょう。だから、ベストセラーになったのだと思います。正直に言うと、あの分け方は若干人工的で、それを分けることによって何か新しいことが出来る、そういうふうなイリュージョンも含めて作ったのではないかと思います。分かりにくいのは、いったいそこで本当に、本質的に新しいものは何かという点です。
前回インタビューしたオーマイニュース編集長の鳥越さんは私と同じオールド・メディア出身ですけれども、今一つそこのイメージがはっきりしない。 Web2.0がキャッチフレーズだとするならば、一種の玉石混淆の中で玉に当たるものはいったい何になるのでしょうか。何のニーズに合致した時に、それが今までにないものだと認められるのか、その辺りの目安を教えていただきたいのです。
渡辺何か方程式やチェックリストがあって、クリア出来れば正解というのではないと思います。最近、非常に使われ始めていて、恐らくこれは何かに化けるだろうと言われている、米国のYouTubeとかMySpace、日本のmixiなどがどういうふうな動きをしているかというところをひとつ判断ポイントとしてみています。あとは、カレンダにしてもコミュニケーションにしても面白いものは出つつあるのでどう受け入れられ定着していくのか。ケーススタディを地道に積み重ねています。
あとは当たり前ですが、ヤフーとかを改めて何かと考えるのが大事だと思います。ヤフーは日本のニュース・サービスでもおそらくトップクラスのユーザー数を抱えていますが、ヤフーがメディアと言われたら、そうは思わない人もいるのではないでしょうか。でも、ニュースはおそらく一番多く読まれていますよね。あれはまず何なのだろうというところが、私はメディアを議論する時に大事なポイントだと思っていて、新聞社のサイトがいろいろあるにしても、それとは別に非常に使われているものがあるという現実をまずは見据えたいです。
それから、いわゆるニュースを載せる媒体ではないですが、ユーザーが集まっている場所でミュージシャンがプロモーションしましょう、新しく出たものをアピールしてみましょうという話が成立しているところがあります。タワーレコードが潰れている反面で、MySpaceにMTVもミュージッククリップのコンテンツを出しますと言って、恐ろしい勢いで伸びている。ユーザーは「そういうものがいい」、「私としてはこういうサービスを受けたい」ということを明確に言い始めている。
ここで起きているユーザーの動き、お金の流れ方はどうなっているのだろうということを、まず一番に考えるべきでしょう。その前例として、ヤフーはどうなのか、検索サービスとは何なのかという話があって、これから出つつある、多分メジャーになるだろうモデルというののキーは何かを考えるのが重要です。これは別に、イコールWeb2.0ではないと思います。「Web2.0の7カ条」みたいな本を暗記したところで、それは答ではない。
でも、こういう説明の仕方はあるよね、確かに今伸びて来ているモデルと何か似ているとこがあるからこれは何かトレンドを1つ捉えているよね、言っていること分かるよね、という感じなのです。たとえ後付けになっても、うまくいったものはうまくいったとしか説明の出来ない部分というものがあるじゃないですか。わりと今起きてることはこの言葉に近いと思っているので、うまくいっているキーポイントは何かと言った時に、誰かの作った理屈をこねくり回して良い悪いよりも、真面目にケースをちゃんと見ることのほうが、多分先でしょう。
(1/5:「ヤフー・ニュースの新と旧」へつづく)
渡辺聡(ワタナベ サトシ)氏プロフィール
渡辺聡事務所/CNET Japan Blogger。神戸大学法学部(政治経済、法社会学)卒。NECソフト、インターネット企業を経て、メディア情報通信周辺を専門としたコンサルタントとして独立。大手企業から大学、スタートアップ、インターネット企業、ハイテクベンダーまで幅広く支援している。戦略立案の支援から、実際の開発インプリテーションまでステージを問わずサービス提供中。2004年4月よりテクノロジーメディアCNETJapanの「情報化社会の航海図」連載を開始。各誌への執筆、カンファレンスの支援を含めてビジネスの現場とメディアの接点作りをサポート。プライベートで技術トレンドの研究会、EmergingTechnology研究会を主催している。
誰が新聞を殺したか3――ベンヤミンの光学
ケンブリッジ大学ウォルフソン・カレッジの日本人卒業生の会に出席した。
仕事が長引いてだいぶ出遅れたが、帝国ホテル地下の三田クラブにかろうじてすべりこんだのは、もう7時近かったと思う。私と同時期に研究員として在籍した大蔵省の寺村信行元銀行局長に会えなかったのが残念だった。会場を見渡すと、さすがに大学在籍の方が多く、ジャーナリストなんて人種は見えなかった。誰かから「編集長はどんな本を読んでおられるのですか」と聞かれて、へへへ、と恥じ入った。
本をどう読んでいるか、という質問をよくされる。雑誌編集長は物知りだという先入観があるからだろう。大したことはない。雑誌づくりが商売だと、日本語の本を読むのはすべて仕事用になってしまう。私的に楽しんでは申し訳ないと思っているから、もう何年もミステリーもSFも小説も読んでいない。内情はかなり貧しいのだ。
自分流を少し打ち明けよう。濫読である。同時並行で何冊も読み飛ばしながら、頭の中でジャムしつつ、心に残るフレーズに、連想のタグをひょいひょい付けて、記憶の引き出し(かなり乱雑)に放りこんでおく。不眠症だから、こうして眠れない夜の衰えた持続力をつなぐしかすべがないのだ。
気恥ずかしいが、いま同時並行で読んでいるのは、Walter BenjaminのSuhrkamp版である。年代順に読んでいるのだが、ちょうどMoskauer Tagebuch(モスクワ日記)にさしかかったあたり。ほかに関連でGershom Sholem編の書簡集、Sholemの回顧録、T.W.Adornoの回顧録、Antony BeevorのThe Mystery of Olga Chekhova、それにClaude Levi-StraussのLe Cru et le Cuitなどなどである。
考えてみれば、なぜかみなユダヤ人の本ばかり。不思議なものである。学生時代に所在なく全集本を隅から隅まで読む癖がついたせいだ。ただ、柳田國男が蔵書のアナトール・フランスを盗み読んだ書生に「小説なんか読んで、どれだけ私は時間を無駄にしたか」と叱った話を知って、フィクションはできるだけ避けることにした。
いまでも本は娯楽として消費する気はない。
さて、どういう言葉を記憶するのかというと、Moskauer Tagebuchを例にあげよう。この日記を推敲した文章をマルティン・ブーバーの雑誌に寄稿したベンヤミンが、自らの文体について語る言葉が忘れられなかった。
私の表現は理論というものを全く欠いたものになるでしょう。これまで私はこういう流儀で、完膚なきまでに変貌を遂げた環境の騒々しい仮面を通じて、轟々と鳴り響くこの極めて新しく混乱した言語を把握し、翻訳することに成功してきました。それと同じように生動するものそれ自体に語らせることに成功したいのです。私は「全事実性がすでに理論」という形で、現時点のモスクワの描写を書きおろしたい。それによって、一切の演繹的抽象を断ち切り、一切の予言を、ある限度内では一切の価値判断を遮断するのです――それら全ては、この場合、精神的「データ」の土台の上では公式化されえない、と私は確信しています。ロシアでさえも、十分に広く熟知している人などほとんどいない経済的ファクツの土台の上にのみ、それは公式化されるのです。
彼一流の屈折した晦渋な表現だが、1927年のモスクワを見る視線として、理論という予断を遮断し「全事実性がすでに理論」という光学を宣言しているのだ。その結果は、書かれたモスクワ日記、そしてその推敲である「モスクワ」を見ればいい。路地の細部を凝視して、なにも見逃すまいとする視線。淡々としてイデオロギーに染まっていないが、そこに潜むカタストロフィーをくっきりと捕らえている。これは「予言しない予言」なのだ。
今の新聞ジャーナリズムにはこれができない。カール・クラウスが言うように、いっさいを常套句の鋳型にはめこむだけなのだ。新聞が滅びようとしているのは、その光学が曇っているからである。
4日夜はテレビに出てくれと言われている。筑紫哲也氏の「ニュース23」だが、知人のプロデューサーに頼まれてはいやとはいえない。本来、おしゃべり人間ではないので、ベンヤミンのいうように「生動するものそれ自体に語らせること」を心がけよう。
誰が新聞を殺したか2――New Assignment.Net
今週はじめから最新号の一部記事の無料公開が始まっています。すでに月曜に「イオンがローソンを買収か」という記事、火曜に「産経がセレブな紙媒体創刊へ」という記事を公開したが、本日(水曜)は「ケータイクレジットに致命的な欠陥」の長尺記事です。
これは業界内外で「やっぱり」「よくぞ指摘してくれました」と好評だった記事で、便利さの裏に潜む問題をえぐっていますので必見のお勧め記事です。
さて、宣伝はここまで。先日ご紹介したThe Economist 最新号の特集「誰が新聞を殺したか」で、ひとつだけ、おや、と思ったくだりがあった。こうである。
硬派ニュースの報道にとって、インターネット・ジャーナリズムの結果は、(百花斉放の)コメントとは逆に、誰もが認めるように限界があった。大半のブロガーは安楽椅子に座っていて最前線にはいない。(オーマイニュースが集めるような)市民ジャーナリストもローカルな話題をなかなか出られない。しかし、即断するのはまだ早い。紙媒体が後退するにつれて、新しいオンラインのモデルが生まれるだろう。非営利団体のNew Assignment.Netは、インターネットに調査報道の記事をつくりだそうと、素人とプロの仕事を結合させることを計画している。うまい具合に、無料クラシファイド広告のサイト、クレイグリストのクレイグ・ニューマートが、そうした計画に1万ドルを寄贈した。
これは朗報というべきか。ジェイ・ローゼンのブログ・サイト「PressThink」がそれを詳細に論じている。実はまだNew Assignment.Netというサイトは存在していない。しかし面白いアイデアである。いわば、調査報道請け負いサイトである。
世の中には新聞その他の既成メディアにあきたらないリッチ層はいくらでもいる。その人たちがこういう非営利サイト(もちろん持ち逃げするようなところは論外で信用力がなければならない)に寄付するお金によって、リスク(訴訟リスクも含む)をとって調査報道(時間、記者などコストがかかる)をさせるというビジネスモデルである。
利益ではない。しかし真に取材力のあるライターに、やりがいのある仕事をさせるには、いいモデルかもしれない。もし日本でもそういうモデルにチャレンジする非営利団体ができたら、FACTAも当然ながら請け負ってみたい。市民記者の「オーマイニュース」モデルより、もしかすると有効かもしれないと思いませんか。
それが成立したら、商業メディアとして利害が絡みあって抜き差しならなくなっている新聞・テレビ・雑誌メディアに対する大きな風穴になると思う。ただ、その風穴があいた瞬間、既存メディアは即死するだろう。広告スポンサーに気兼ねしているメディアを誰も信用できなくなるからだ。
どうでしょう。このアイデアは。
31日に開催されるRTCカンファレンスというイベントでゲスト講演することになりました。テーマは「総裁選とアジア外交」です。ご興味のある方はこちらのサイトをご覧ください。
誰が駒鳥を殺した?――新聞没落論
最新号のThe Economistのカバーストーリーが「誰が新聞を殺したか」(Who killed the Newspaper?)。マザーグースを知る人ならぴんとくる「誰が駒鳥を殺したか」(Who killed cock robin?)のもじりである。
Who killed Cock Robin?(誰が駒鳥殺したの?)
I, said the Sparrow, (それは私、と雀がいった)
With my bow and arrow,(私の弓と矢で)
I killed Cock Robin. (私が駒鳥を殺した)
葬送行進曲 を思わせてちょっと不気味だから、Ten Little Niggersなどマザーグースをタイトルにしたアガサ・クリスティーあたり、どこかで使ったような気がするが、今は思い出せない。しかし少女漫画好きの人なら、懐かしい「パタリロ!」(80年代からまだ続いている漫画界の「寅さん」)を思い出せばいい。「クックロビン音頭」ってあったでしょ。あのギャグ、実はThe Economist級のエスプリだったと思いますね。
さて、エコノミスト誌のカバーストーリーは、インターネットに客を奪われていよいよ構造不況業種入りしようとしている「新聞の死」の現状報告である。早々と飛び出してしまった私のような元記者からすれば、さほど目新しい事実が報告してあるわけではないが、その副題が「More media, less news」であり、崖っぷちで新聞を開いている人が、新聞を折った紙飛行機に乗って、パソコンのディスプレーに吸い込まれていく挿絵などを見ると、ああ、やっぱりという感慨ひとしおである。
何より罪悪感が心をかすめる。「誰が新聞を殺したか」――自分も「それは私」と答えなければならない雀の一羽かもしれないと思ってしまうのだ。先週、メルマガ臨時版を発信し、本誌読者限定で届けた予告スクープなどは、新聞がすでに「less news」のメディアに落ちぶれ、その死が近いことを証明したのかもしれない。だが、それは自慢でも何でもなく、新聞が前提としている「良識ある固定購読者」という基盤を突き崩すことかもしれないのだ。エコノミスト誌はこう書く。
メーンストリームの新聞の読者の嗜好調査が長く示してきた結果は、短編のストーリーやそれに関連したニュースが人々に好まれているというものだった。地方記事、スポーツ、娯楽、天気、そして交通情報である。「インターネットでは特に」とChisholm氏は言う。「人々は暮らしを補強するために眺めている」。国際報道の長文記事などは、読者の優先度が低いのだ――インターネットのおかげで、国際ニュースの見出しがほんの数瞬で一瞥できるようになったからなおさらである。
これは「グーグル・ニュース」のようなNews Aggregator(新聞のサイトを常時さらって最新ニュースを集めてくる検索ロボットのサイト)の隆盛で、外信の後光がすっかり薄れたことを示している。ヒズボラや地震など遠い海外のニュースは、ただのテレビかNews Aggregatorでちらっと一瞥するだけとなれば、新聞も手を抜く。カネもかかりリスクもある特派員の派遣より、ロイターなど通信社の配信でお茶を濁すのだ。なるほど低コスト化は実現できるだろうが、どの新聞も差がなくなり、News Aggregatorでは大同小異、ますます読者離れを招くという悪循環である。
しかも足元では、購読料に依存せず広告だけでコストを賄う「R25」のようなフリーペーパー(無料紙)に脅かされている。記者のプロに言わせれば「あんなものは記事ではない」が、世の読者は浅く、広く、身近で、タダ……を求めているのだ。それがネット時代に求められる新聞経営の要諦だとすれば、まったく夢がない。
「なあ、阿部クン、君ならどうすればいいと思う?」。さる新聞社の社長にそう聞かれた。心ある新聞の首脳はみな胸を痛めている。しかし、FACTAは新聞メディアを救済する「解」ではない。それにこんなちっぽけなブティック型のメディアでは、デパートのような巨大な新聞コングロマリットの経営と同断に論じられないこともある。
ただ、数百万から1千万部の総合紙型ビジネスモデルに明日はない。ブティック化と高級化への流れがいずれ強まると予想して、FACTAでそれを試みていると言える。エコノミスト誌も自らの経営が揺らぐとは考えていないせいか、リードに「(新聞の凋落は)懸念の理由にはなるが、パニックの理由にはならない」としている。
マザーグースの「誰が駒鳥を殺したか」は、初聯のあと葬列が延々と続く。「死ぬのを目撃した」のがハエ、「血を受けた」のが魚、「経帷子を縫う」のがカブトムシ、「墓穴を掘る」のがフクロウ、「牧師」がカラス、「付き人」がヒバリ、「松明役」がベニスズメ、「喪主」がハト、「柩かつぎ」がトビ、「棺おおいを捧げ持つ役」がミソサザイのつがい、「賛美歌を歌う」のがツグミ、「鐘を鳴らす」のが牛。そして、最後はこうだ。
All the birds of the air (空行くすべての鳥たちは)
Fell a-sighing and a-sobbing, (ため息ついて啜り泣く)
When they heard the bell toll (鐘の音高く響き渡り)
For poor Cock Robin. (哀れな駒鳥を弔って)
poor Newspaperも、すすり泣くだけではあまりに能がない。