EDITOR BLOG

ATMも「対朝包囲網」の戦場――シンジケート・コラム第一弾
昨日、6紙に掲載されたシンジケート・コラム「時代を読む」の原稿をここに再録する。
こちらがつけた仮タイトルは
ATMも「対朝包囲網」の戦場
だが、各紙でそういう見出しを採用したかどうかは分からない。
*****
一斑を見て全豹を卜す。
唐代に房玄齢らが編んだ史書「晋書」にある言葉である。豹の皮の斑紋の一つを見て、あ、これは豹だなと分かるという意味で、ちいさな一端から全体を見渡す眼力をさす。
まず「一斑」を示そう。この1月から全国の金融機関のATM(現金自動預け払い機)で、現金振り込みの上限が1回10万円まで引き下げられた。それまでの200万円から一挙に20分の1である。一見、振り込め詐欺などの被害防止が狙いかに見えるが、実は「全豹」は日本海沿岸地域の最大の脅威――北朝鮮の核兵器問題にある。
ATM現金振り込みの上限とは、裏返せば本人確認が求められない送金額ということ。要するに、全国津々浦々の金融機関窓口では、10万円を超す送金はすべて本人確認が必要になったのだ。北朝鮮工作員の身になってみれば、この締め付けがよく理解できる。マネーロンダリング(資金洗浄)も第三国経由の送金も、邦銀の決済システムを通せばたちまち捕捉される恐れが出てくるのだ。
この締め付けは海外送金並みと言っていい。外国為替及び外国貿易法では、100万円超の現金海外持ち出しは税関に届出義務があるし、500万円超の海外送金・受け取りは銀行に報告提出の義務があるが、9・11同時多発テロ後の改正で為替取引の本人確認が義務づけられた。ATMの上限引き下げは、それに匹敵する「国内」のハードルなのだ。
そうした目で北朝鮮の核兵器問題をめぐる6カ国協議を眺めると、風景が一変する。協議は二月にも再開される見通しだが、舞台裏の動きがあわただしい。1月半ば、ベルリンで北朝鮮の金桂官(金桂寛)外務次官と接触したヒル米国務次官補は、米朝間で歩み寄りの可能性を示唆し、22日には韓国の聨合ニュースがその中身の輪郭を報じた。
北朝鮮が核兵器放棄へ初期段階の措置をとれば、マカオのバンコ・デルタ・アジア(BDA)で凍結されている北朝鮮関連口座(約50口座、総額2400万ドル)のうち、5~7口座の凍結解除を検討する――というもの。初期段階の措置とは、寧辺の実験用原子炉の稼動凍結と国際原子力機関(IAEA)による査察の受け入れだという。
歩み寄りがこの程度なら、双方にとってまだ本格的な妥協を意味するものではない。北朝鮮は例によって時間稼ぎが狙いだろうし、米国も対朝「金融制裁」包囲網のごく一部に窓を開けるにすぎないからだ。
この包囲網には20年近い歴史がある。マネロン対策や国際組織犯罪対策のために1988年にOECD加盟国を中心に結成された「金融活動作業部会」(FATF)を皮切りに、98年の「金融情報ユニット」(FIU)設置合意など、米国が着々と築いてきたものだ。9・11テロ後は、大量破壊兵器の移転・輸送阻止のために、米国主導で始まった国際的な枠組み「安全保障イニシアティブ」(PSI)と両輪を形成するようになった。
それと歩調を合わせて、日本国内でも北朝鮮への資金ルート遮断が進められてきた。99~03年に朝鮮総連系の16信用組合が経営破綻し、1兆3000億円余の国費を投じて処理する一方、破綻信組の受け皿機関の四信組や生き残り信組に厳格な検査を実施して、不法送金の痕跡を洗い直したのだ。
総連系信組の海外送金窓口となっていた栃木の地方銀行である足利銀行も、02年に北朝鮮とのコルレス契約を解消、全信組連も総連系信組の海外送金取り次ぎをやめている。足利銀行は経営破綻し、現在は財務省次官OBが天下る横浜銀行を中心とした地銀連合か、みずほグループの傘下入りが取りざたされている。二度と「足利ルート」が開かれないよう、厳重な監視下に置くということだろう。
1月24日、米連邦準備理事会(FRB)などの金融監督当局が、三井住友銀行ニューヨーク支店が行っている送金業務などで、マネーロンダリング(資金洗浄)監視に不備があるとして東京の同行本店も含めて業務改善命令を下した。昨年12月19日に同じ理由で三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)が行政処分を受けたばかりである。日本の金融庁も両行への処分を検討し始めた。メガバンクといえどもお目こぼしはないのだ。
米国のグリップがいかに強まっているかの証左である。米国持ち株会社設立に日本のメガバンクでは唯一認可を得たみずほフィナンシャルグループが、足利の受け皿候補にあがるのも、米金融当局が課したマネロンのハードルを越えられたからと見てもおかしくない。
これら一つ一つの布石全体が対朝金融包囲網を形成しており、BDA口座の一部を凍結解除しただけでは、「マネーの蛇口」を絞られる北朝鮮の逼塞感は解消しないだろう。2月の6カ国協議で米朝が歩み寄ったとしても、その後は楽観できない。
ATMの前に立つとき、すでに「金融の戦場」が眼前にあることを、誰もが実感すべきである。
*****
シンジケート用の原稿を書いたあと、もう1コマ入れるべきだと思ったが、締め切りと行数の関係があって無理はしなかった。でも、これはブログだから、それを付け加えた。太字部分がそれである。
シンジケート・コラムの試み
1月27日(土)から新しい試みとして「シンジケート・コラム」を始める。「シンジケート・コラム」というと戸惑うかもしれないが、複数の新聞に共同配信するコラムのことである。既存の通信社を使わず、外交ジャーナリストの手嶋龍一氏、建築家の隅研吾氏と3人でローテーションを組み、地方紙7紙に大型のコラム「時代を読む」を月1回、一斉掲載することになった。本日がその第一弾である。
日本では「コラムニスト」という名称がインフレ気味である。雑誌や新聞で著者名入りの企画記事を載せることができる身分になるだけで、たちまちコラムニストを名乗る。確かに海外ではコラムニストというと、並みの切った張ったの記者よりは格上の感があるが、なんでもかんでもコラムニストというのはいかがなものかと思っていた。
しかし、全国紙のないアメリカでは、複数の地方紙に配信されるシンジケート・コラムがあって、全国的に名の通った書き手でなければ登場しない。あのシンジケート・コラムニストこそ真のコラムニストだろう。NYタイムズの辛口コラムニスト、ウィリアム・サファイア、ワシントン・ポストの政治風刺コラムニスト、アート・バックウォルド氏らがそれにあたる。読売新聞が翻訳掲載した元国務長官ヘンリー・キッシンジャー氏のコラムも、このシンジケート・コラムとして配信されたもので、日本での独占掲載権を読売が得ただけで、キッシンジャー氏が読売向けにコラムを書いていたわけではない。
全国紙が強い日本でも、ああいうシンジケートの試みができないかとかねがね思っていた。1社終身雇用で記者をしだいに管理職に絞りこんでいく現行の閉鎖的システムに風穴をあけたかったからだ。私が英国、手嶋氏がアメリカにいた時代にそんな話をしていたから、構想は10年近い歴史がある。ようやく、各方面のご協力を得てその小さな一歩が実現することになる。
その7紙とは
・東奥日報(青森、26万部)
・秋田魁(秋田、26万部)
・新潟日報(新潟、50万部)
・北日本新聞(富山、25万部)
・福井新聞(福井、21万部)
・神戸新聞(兵庫、56万部)
・山陰中央新報(島根・鳥取、20万部)
である。掲載参加紙のうち神戸新聞と秋田魁新報の2紙は4月からの加入になる。7社の朝刊発行部数を総計すると200万部を超えるから、ちょっとしたインパクトが持てる。
実は私自身、昨年は地方紙2紙に定期コラムを持たせていただいた。熊本日日新聞と新潟日報である。まだ月刊誌FACTAが創刊していなかった05年12月、このサイトを立ち上げたときにブログでソニーBMGのスパイウエアCDのことを熊本日日に載せたと書いたが、あれがそのコラムである。その縁で、新潟日報がいわば幹事社になり、環日本海地域を中心とした地方紙連合に配信するコラムを実現できた。世話役の同紙編集委員、望月迪洋氏に感謝申し上げます。
一番バッターは不肖、私が書くことになった。担当分野は経済。もちろん、FACTAの編集雑記を書くわけではない。といって雑誌の中身と重複させるわけにもいかない。かといって、単なるオピニオンを書くわけでもない。地方紙の読者の方々に、身近の現実からグローバルな視野が開けるようなものを書きたい。だから、最初に自分に課したテーマは――「一斑を見て全豹を卜す」。
もし上記7紙(とりあえずは5紙)の読者がおられましたら、ご一読いただいてシンジケート・コラムが日本で成立するかどうか、ご意見をお寄せください。新聞掲載を待って後日、このブログで私の原稿を公開します。なお二番バッターは手嶋氏で2月24日(土)掲載、三番バッターは隅氏で3月31日(土)掲載の予定です。お楽しみに。
琴欧州後援会
法務問題などでFACTAがいろいろお世話になっている山王法律事務所の金森仁弁護士が、なぜか本物のタニマチをめざしていて、とうとう大関琴欧州の後援会会長になってしまった。
25日は後援会の第一回会合だとのことで、たってのお誘いを断りきれず、どうにか芝浦の料亭「牡丹」に駆けつけた。ブルガリア大使も来て挨拶をしていたが、お酌に来た大関を間近に見ると、やはり2メートル余の堂々たる偉丈夫である。3年で大関というスピード出世だったため、彼の後援会ほこれが初めてと聞いて驚いた。
席には見知った方々も何人かいて久闊を叙した。あいにく所用あって途中退席せざるをえなかったのが残念。
それにしても、つい先日はかつての安芸乃島関(千田川親方)の励ます会に呼ばれたばかりである。こちらもロンドンでお世話になった三菱商事元常務の増田徹郎氏のご縁だった。
まあ、こちらはタニマチになれるようなお金持ちではないから、あちこち渡り歩く余裕はないが、美男の佐渡ケ嶽親方(元琴の若)はわが義父がファンだったから、応援しても大目に見ていただこう。
ただ、世にタニマチ候補の旦那衆が減っていることは事実。これから琴欧州後援会のご発展を祈るほかない。
捲土重来――予告スクープ
メルマガ版の予告スクープは、先日の利上げ報道で失敗したので、3勝1敗である。そこで捲土重来を期して、今週もメルマガ版予告スクープを打とうと思う。
今度は外さないぞ、と決意表明。勝率を上げます。
第2スクープも裏づけ――中国とバチカン「和解」
FACTAの愛読者の方は、あっと思ったかもしれない。1月20日、ローマ法王庁(バチカン)が中国政府と関係正常化をめざす声明を発表、法王ベネディクト16世が近く中国の全カトリック信者に書簡を送るというニュースである。
記憶のいい方は忘れておられないでしょう。FACTA10月号(06年9月20日刊行)といえば、安倍首相の10月訪中を的中させたスクープを掲載した号ですが、同じ号で「中国がバチカンと『和解』」という第2のスクープも掲載しています。こちらも必ず確報が出ると確信していましたが、1月になって法王庁自ら発表してくれました。
無神論=唯物史観を国是とする中国では、信者の多くが帰依する地下教会への弾圧と、共産党傀儡(かいらい)の公認教会と法王庁の対立が長く続いてきたことは、本誌記事が詳述している通り。それを読まなければ、中国とバチカンの歴史的和解の意味が理解できないと思います。
中国カトリック教徒弾圧と傀儡教会のジレンマを追っていたのが、バチカン筋に近いといわれる「AsiaNews.it」。そうした報道の一例が昨年5月15日の報道」でしょう。しかし、バチカンの特使が中国入りした昨年夏以降は、香港筋でも和解観測が流れており、大陸の姿勢変化にいちはやく反応したものと思われます。
そうした情報を詳しいバックグラウンドまで含めてFACTAが日本のどのメディアよりも早く報道できたのは、横縦翻訳だけの中国情報の後追いに頼らないからだと思います。
今後、上記のようなFACTAの報道に関連する記事やサイトを見つけた場合、新しく始めました「FACTAブックマーク」にどんどん保存していきます。定期購読者の方は是非ご登録のうえ、ご覧になってください。
法事ダブルヘッダー――月曜から平常復帰
私事ながら、義母の通夜と葬儀を19、20日に終えました。
過分なご厚志、ご弔電を賜り、ひとまずこのブログの場を借りまして心より御礼申し上げます。
20日夜には東京へ飛んで帰って、21日に父の37回忌の法事を済ませました。菩提寺は麻布なのですが、21日の東京の空は寒々と曇っていて、墓地も森閑としていました。
父は癌で早くに亡くしたのですが、住職さんに言われたのは「37回忌のあとは本来もう法事がない」とのこと。寿命の短かった昔は、そうした長年月の法事を想定していなかったのでしょう。故人を知る先輩、友人、同僚はもとより、家族ですら代替わりで「ご先祖」の一員になってしまうということです。
なんだか、何度目かの厄年を通り越して、もう「厄年はない」と言われたような気分です。おお、もう人生は余禄と考えなければいけないのか。
それでも、しいて法事を開くなら43回忌、47回忌を飛ばして50回忌とか。どこかの偉い上人様じゃないので、そこまでやるべきかどうか迷います。ま、あと13年後、私のほうがどうなっているか分かりませんが。
とにかく22日月曜から平常に復します。
「ニュース脳」のつくり方――FACTAブックマーク
新しい試み「FACTAブックマーク」を始めます。ひとことで言えば、「第一級のニュース感度のアタマ」のつくりかたをお教えするというものです。チャレンジしてみませんか。
原理はカンタン。ネットで「これは」と思ったサイトの記事をブックマークし、それをFACTAの他の購読者とオンラインで共有するという試みです。FACTAを土俵として、筆者と読者とが「イチオシのネット情報」を交換するというイメージです。
ちょっとSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に似ています。でも、mixiなどは同好の士の百貨店のようなもので、大きなサーバーと広告モデルが必要になります。もっと小振りの専門SNSはできないか、たとえばFACTAの目指す調査報道の基盤になるSNSを独自にできないかと考えて、たどりついたのが「FACTAブックマーク」です。雑誌としてはたぶん初めての試みでしょう。
ときどき聞かれます。「FACTAの情報力はどこから来るのか」と。もちろん編集者やライターの人脈、経験、知識が総合したものとしか答えられないのですが、それだけではありません。「これが知りたい」という強烈な好奇心、「これが時代の水脈だ」という確信が基盤になっています。取材源は公開できませんが、そのインフラは共有が可能だと考えました。
編集長も参加しますので、これにより何に刺激され、何に好奇心を抱いているのか、というカタログとして、FACTA編集者のアタマの中を知ることができます。また、FACTAの読者が何を探し、何をみつけたかも察知でき、編集・読者双方にとって水先案内のヒントになります。ひとりで茫洋たるネット空間をさまようよりは、大幅な時間節約になるでしょう。
よく言われました。軽々に他人(恋人であっても!)に自分の本棚を見せてはいけない、と。人間の生きざまと教養が透けて見えてしまうから、というのです。でも、そういう時代ではなくなりました。本は消耗品となり、知識は衒学ではでなく、日用品のツールです。知識は独占して秘めておくべきものではなく、共有して「教養のインフラ」にすべきではないでしょうか。
とりあえずは購読者限定のサービスですので、オンライン会員登録をしていただいたうえで「FACTAブックマーク」へどうぞ。FACTAブックマークのお仲間になっていただくとともに、お気に入り情報をマークしていただくようご協力をお願いしたいのです。編集長以外にも、経営者、ジャーナリスト、専門家の方々が参加します。
FACTAブックマークによって「ニュース脳」の持ち主になった方は、第一級の情報網を抱えているにひとしく、メディアが次にどこを狙うかを予測できるようになります。テレビや新聞の聞きかじりで満足できない高感度人間はぜひご参加ください。
FACTAブックマーク
しばらく喪中
家人の母が逝ったので喪に服します。
ブログが滞っていたのもそれが理由でした。恐縮ですが、ご理解のほどを。
利上げ見送り
18日の政策決定会合では6対3の多数決で金利据え置きが決定。前代未聞のどんでん返しで、日銀は深手を負いました。残念ながら、メルマガの報道は覆されたようです。
時間的には最新号に間に合わないエアポケットの時期だったのですが、改めて報じるタイミングを考えさせられました。今回は失敗を素直に認めることにします。
ただ、日銀がなぜ根回しに失敗したか、その理由は深く追求するにたるテーマです。安倍政権下の福井日銀とは何か、は改めて誌面で論じましょう。
ブログ再開します
ちょっと日があきました。8日成人の日のあおりで、今週は編集で目いっぱい。午前様が続いて、ブログを書けませんでした。でも、ようやく編集作業が終わりましたので、あすからブログを再開します。
村山治「特捜検察vs.金融権力」――破られた沈黙

この連休から編集作業が始まっているので、ちょっとブログを書く時間がない。「成人の日」をけなすつもりはないが、昔の1月15日と違って、変則で週初にくっつくから、締め切りのある雑誌屋さんは、結局、連休返上で働かざるをえない。まだ人けの少ない神保町をせっせとご出勤である。
さて、暮れに朝日新聞の村山治編集委員から新著を送っていただいた。刊行日は1月30日だが、店頭にはもっと早く並ぶのだろう。FACTAの書評欄で書評してさしあげたいが、正月を挟んで書評子に無理強いはできないので、このブログで紹介させていただこう。
新著は「特捜検察vs.金融権力」(朝日新聞社1400円+税)である。村山さんはなかなか書かない記者である。80年代末のバブルからその崩壊、そして「失われた10年」で変わっていった永田町と霞ヶ関の権力構造をずっと追い続けた。その執拗な取材は脱帽せざるをえないが、膨大なメモと知識は水面下の氷山のように沈んだまま。書いた事件より書かなかった事件の卵のほうが多いだろう。
記者には書くタイプと書かないタイプがあるが、彼は典型的な後者だった。「今のうち書かないと、歴史の闇に埋もれちまいますよ」と何度か促したが、笑顔が返ってくるだけだった。それがとうとう書く決断をしたらしい、と昨年伝え聞いた。朝日新聞夕刊の「人脈記」の連載で法曹界シリーズを担当したのが、沈黙を破るきっかけになったのだろうか。
ぜひ店頭に出る前に読ませてほしい、と頼んだら、約束を守ってくれたのだ。破られた沈黙とは何ぞや、と正月休みに読み始めた。面白い。はじめは寝そべって読み、それから座り直した。最後は正座していた。自分も取材した事件が出てくるし、大蔵省護送船団の崩壊と特捜検察の限界が書いてある。彼の取材と自分の取材をつきあわせる心のなかの真剣勝負になった。
ああ、なるほど、と目からウロコの部分がある。やっぱり自分の取材は正しかった、と安堵する部分もある。いや、これは違うと首を傾げる部分もある。何度も彼の口から聞いたことも書いてあった。
「本来、国策とは国の政策をいう。検察は国の行政機関である。その検察が国の政策に沿って権限を行使するのは当然のことである」
「国策捜査イコール『悪』ではない。民間企業である住専や銀行の破綻の穴埋めに税金を投入するからにはそれらの経営者の責任追及は必要であり、本来検察が積極的に取り組むべき仕事である。国民もそれを望んでいた」
私事ながら、私も当時、日本経済新聞の社説で同じ趣旨のことを書いた。しかし、私にはここでいわれている「国」は純粋な統治装置ではなく、恣意の塊だったとしか思えない。「国民も望んでいた」という「国民」に実体がないのと同じである。これは紛れもない検察の論理だと思う。
ライブドアに強制捜査が入り、堀江貴文社長が逮捕されたとき、このブログで「国策捜査」と書いたら、真っ先に電話してきたのは村山さんだった。日比谷で会って彼の統治論を聞いたことがある。検察―大蔵(国税)という霞ヶ関権力の頂点が分裂して、国家の態をなさなくなったという認識までは一緒だった。しかし、その先は微妙に違った。
この本は松尾邦弘・検事総長が金融庁の五味広文長官に退任あいさつに訪れる場面に始まり、検察―大蔵の蜜月と亀裂、そして関係修復を経てまた冒頭の松尾退任で終わる構成だ。それはあたかも霞ヶ関が形状記憶合金のように、裂けた傷をふさいで再び統治の体制を立て直したかに見える。
めでたしめでたしの大団円?それがこの本の眼目なのだろうか。国家の統治は、畢竟するに検察と租税の両輪ということだとすれば、依然としてこの両者にとって市場はアナーキーな「外」なのか。
「集団知」の象徴である市場とそこから輩出する“悪玉”に、正義(検察)と公正(国税)を掲げる統治装置が知的にもついていけなくなったことが原点だったはずだ。強引で乱暴な強制捜査や税務調査で生贄をあげて、それで統治が回復したとことほぐ気に私はなれない。
終わりでなく始まり……そんなことを考えていたら、正月が過ぎてしまった。編集が終わったら、ぜひまた問い質してみよう。
本誌記事に訂正があります
FACTA最新号の1月号(12月20日刊行)に掲載した「『木村銀行』買収に韓国から食指」の記事について、読者からご指摘がありました。36ページ2段目、左から3行目に大阪興銀(関西興銀の前身)を設立した李熙健(イ・ゴンヒ)理事長についてです。ご指摘は以下の通り。
「李・元関西興銀理事長が故人となっておりましたが、ご健在です。新韓銀行名誉会長で昨年11月に行われた四天王寺ワッソでは、NPO法人大阪ワッソ文化交流協会の顧問として挨拶されていました」
確認いたしましたところ、ご指摘の通り李元理事長はご健在です。ご本人、ならびに関係者の方々にご迷惑をおかけしました。訂正して、お詫び申し上げます。
なお、37ページの写真説明で「日本振興銀行、木村社長」とあるのは、本文にある通り「木村会長」の誤りです。チェックで見落としました。これも訂正します。
次号以降、ケアレスミスにより一層注意します。
仕事はじめ
いかがでしたか、皆さんのお正月は。
頭を休めないと擦り切れてしまうので、当方はほとんど寝正月。どこにも遠出せず、おせち料理三昧でした。駅伝を見ながら、お餅食いすぎで、ちょっと肥ったか。
でも、4日は出社。まだ世間はお屠蘇気分らしく、通り道の神保町を歩いても、古本屋街はほとんど開いていない。開いているのは大型書店くらいだが、ビクトリアなどのスポーツ用品店をめざす人が結構出てきていらっしゃる。
さて、頭が痛いのは年賀状。リストに漏れて送っていない人から年賀状をいただいて、しまったと思うのが4日である。そのリカバリーに半日を費やした。遅れた人はごめんなさい。しかし今年の年賀状は「ブログ見てます」と添え書きが多い。いよいよ恐縮する。改めて御礼申し上げます。
来週からいきなり編集である。休んだ分だけ、時間が詰まってきつくなる。もう、浮かれていられない。
賀春 ことしも「FACTA」をよろしく
旧年中はご愛読ありがとうございました。「プリント+ウェブ」というFACTAの実験が、初年度を無事乗り切れましたのも、 みなさまのご声援のおかげです。新年のご挨拶とともに、今年もよろしくお願い申し上げます。
FACTAを06年4月20日に創刊して9カ月余、インターネットに浸食される紙のメディアという逆風に敢えて挑み、ひとまず地歩を築くことができました。月1回しか出せない月刊誌のハンディキャップを、随時送信できるメルマガ「FACTA online」でカバーする手法を確立。ベストタイミングでスクープを連発して、新聞など既存の商業メディアを震撼させることができました。
ご承知の通り、メルマガでFACTAが独走したスクープは
・東京証券取引所にみずほ証券が400億円賠償請求(8月)
・日中首脳、10月にも会談(9月)
・トヨタが「フォード支援」提案(11月)
いずれも新聞があとで追いかけ、FACTAの信憑性を実証してくれました。
今年もスクープを狙って、FACTAの突進は続きます。FACTAのメルマガはまた、スクープ以外にも「深掘りシリーズ」など多彩な展開を考えています。またポータルサイトとの協力で、より社会へのインパクトを大きくすることも考えています。ご期待に違わぬよう、これぞ報道という世界を切り開いていきます。
2007年元旦
新刊本プレゼントのお知らせ
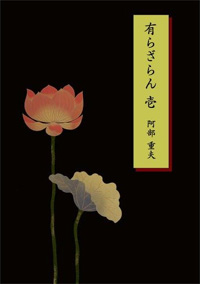
2007年1月1日から31日に月刊FACTAの年間予約購読をお申し込みいただいた方と、2006年12月31日までにお申し込みいただいた方で、1月31日までにオンライン会員にご登録の方に、編集長・阿部重夫の新刊本『有らざらん壱』を抽選でプレゼントします。
ご希望の方は、オンライン会員にご登録のメールアドレスから件名に「新刊本プレゼント希望」を、本文にお名前をご入力のうえ、present@facta.co.jpまでお送りください。オンライン会員に未登録の方は、「購読者限定オンラインサービスのご案内」をご覧のうえご登録ください。
応募締め切り2007年1月31日
※結果は発送をもって返させていただきます。発送は2月中旬の予定です。
アッラー・アクバルと「凡庸なる善」
サッダーム・フセインが処刑された。あの暗い冬のバグダードに取材で行ってから10年、何がしかの感慨はある。しかし処刑直前のサッダームを撮った映像には吐き気を催した。
髭の白いサッダームは、黒いバラックラーバ帽で顔を隠した看守たちに囲まれていた。刑執行後の報復を恐れてだろう。白と黒の対照。サッダームは毅然としていた。それだけでも「殉教」に見えてしまうのに、カメラは何も気づかない。しかも奇妙なことに、この光景にデジャヴ(既視)を感じた。
「イラク聖戦アル・カイダ組織」が流した人質の外国人を囲む覆面姿のテロリストたちの映像とそっくりではないか。06年6月に米軍機の爆撃で死亡したヨルダン人テロリスト、アブ・ムサブ・ザルカウィが率いていたこのテロリスト・グループは、日本人青年が斬首されたからその映像はまだ記憶に新しい。
処刑前に撮った光景がこれほど似ているということは、イラクの内戦が「目には目を」の報復の無限連鎖であることを何よりも雄弁に物語っている。もはや政権とテロリストの境界はない。狩る側と狩られる側がスクランブルして、相似形になっていく恐怖がそこにある。
サッダームの肩を持つのではない。でも、かつての独裁者とスンニー派復活を恐れる臆病なマラキ政権には、報復以外のレジティマシーがないことを、世界に知らしめたと思う。
サッダーム最後の言葉は「アッラー・アクバル」。神は偉大なり、という意味で、バグダードのみならず、世界のイスラム圏のミナレットから毎日朗誦される礼拝の言葉である。ありきたりだが、日常のメッカ礼拝から、自爆や吶喊にいたるまで、あらゆる多義を呑みこむブラックホールかもしれない。
それをサッダームに叫ばせることによって、マラキ政権は「殉教の冠」を授けたかもしれない。マラキ政権、およびそれを後押しするブッシュ政権のどちらにも、この処刑を正当化する堂々たる大義がないからである。ホワイトハウスのそっけないコメントは、他の中東諸国も含めいたずらに刺激すまいとの配慮だろうが、サッダーム滅亡を果たした今、無言自体が敗北の象徴である。
アメリカもまた、この戦争のレジティマシーを主張できていない。サッダーム処刑の寥々たる光景は、ただ一人のハンナ・アーレントも現れなかったことに起因するのではないか。
この女性政治学者は1961年のアイヒマン裁判を傍聴、「ニューヨーカー」誌に優れたルポルタージュを書いた。彼女自身がケーニヒスベルク生まれの東方ユダヤ人(アシュケナージ)で、ナチスに追われてアメリカに亡命した身だが、イスラエルのベングリオン政権の芝居がかったプロパガンダ裁判を糾弾、ユダヤ人自身が強制収容に手を貸したことを暴き、返す刀でアイヒマンが誰もが期待する極悪人ではなく、「凡庸なる悪」であるがゆえに救い難いと訴えた。
「アイヒマンという人物の厄介なところはまさに、実に多くの人々が彼に似ていたし、しかもその多くが倒錯してもいずサディストでもなく、恐ろしいほどノーマルだったし、今でもノーマルであるということなのだ。(中略)この正常性はすべての残虐行為を一緒にしたよりもわれわれをはるかに慄然とさせる」
この記事はユダヤ人社会からは轟々たる非難を浴びたが、処刑されたアイヒマンが殉教者に祀りあげられなかったのは、エルサレム法廷の報復の論理を批判した彼女の勇敢な筆鋒があったからと思える。それでも彼女は、『エルサレムのアイヒマン』の末尾で、自分なりに死刑宣告を下す。
「あたかも君と君の上官がこの世界に誰が住み誰が住んではならないかを決定する権利を持っているかのように――ユダヤ民族および他のいくつかの国の国民たちとともにこの地球上に生きることを拒む政治を君が支持し実行したからこそ、何人からも、すなわち人類に属する何ものからも、君とともにこ地球上に生きたいと願うことは期待しえないとわれわれは思う。これが君が絞首されねばならぬ理由、しかも唯一の理由である」
ブッシュおよびマラキ政権は、死せるサッダームに堂々とこう言い放てるか。こそこそしていれば、この判決と処刑が、かつてのサッダーム政治と同じく勝者の恣意に過ぎないことの証明になる。つくづく情けない権力者たちだ。慄然とすべきはこの「凡庸なる善」ではないか。
藤原伊織の「ダナエ」――何物をも喪失せず

本が家に届いた。1月に店頭に並ぶという彼の最新作品集「ダナエ」(文藝春秋刊、1238円+税)である。彼に約束した書評をここで書こう。
目を皿にして読んだ。一言で評するとしたら、何と呼ぶべきか。
今生の。
あとの言葉がみつからない。淀みなく流れるストーリーの語り口はいつものように巧みで、ああ、プロなのだなあと感心するばかりだ。でも、措辞のひとつひとつ、レトリックや描写、その裏に透けて見える作者の心の襞を追っていくうちに、繊細に組み立てられた「謎解き」の裏にあるものを思わずにはいられない。
「ダナエ」には未完の透明感がある。小説の結構に難があるというのではない。もっと長編の一部になってもおかしくない筋立てなのだが、複雑なミステリーになる一歩手前でふっと宙に消えてしまう。どこかで作者は謎解きへの執着を捨てたかに見えてならない。
唐突に現れる朔太郎の詩句。
わが思惟するものは何ぞや。
すでに人生の虚妄に疲れて
今も尚家畜の如く飢ゑたるかな。
我れは何物をも喪失せず
また一切を失ひ尽せり。
そしてガーシュインの「サマータイム」とともにあふれてくる涙。
Summertime,
And the livin' is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high
作者は誰の声を思い浮かべているのだろう。ジャニス・ジョプリン、エラ・フィッツジェラルド、いや、淺川マキ……?知らず、子規の「病床六尺」のような息遣いが聞こえる。
私はもともと小説の楽しみ方を知らない。コトバは非情な武器であり、非情な文章しか書いてこなかった。中篇の「ダナエ」が上質のエンタテインメントだとしても、私には悲痛なノスタルジアとしか読めない。
短編の「水母」のほうがパセチックに思えた。表参道のカフェに座って、5杯のウオッカソーダで気が遠くなるシーンがある。
「世界のすべてが遠ざかっていくような感覚にとらわれた。表参道のざわめきが、潮騒のように高くなり低くなり、耳にとどいてくる。うすぼんやりしたそのあいまいな世界で麻生はじっと息をひそめていた。そのうち、べつのかすかな音が聞こえ、ついで何かの感触が手にふれてきた」
作者は別れを告げようとしている。本の帯に書いてある通りだ。黙って泣こう。
もういちど「ソニー病」5――フェリカと紀香
「夕刊フジ」の編集者は不思議な感覚を持っているらしい。「フェリカ」と「紀香」という奇妙な韻(駄洒落?)を踏んだ紙面には仰天した。
12月27日(木)発売の同紙AB統合版のアタマでは、黒べた白ぬきの「電子マネー極秘情報流出」という大きな見出しが躍っている。この「電子マネー」とは、FACTA最新号が「暗号が破られた」と報じた非接触型IC技術「フェリカ」のことである。書いてあることの大筋は、弊誌の記事とこのブログの後追いと思える。
目鯨をたててもしようがないが、このフェリカのニュースとからみあうように、前夜婚約会見をした藤原紀香の大きく胸のあいたドレス姿の写真が載っているのはなぜか。アイキャッチにしても「東スポ」的なシュールな組み合わせである。思わず笑ってしまった。立場は違うが、ソニーの方々もさぞかしぎょっとしたろう。
しばらく脳内で連想ゲームをしてみた。この二つのニュースの共通点は何か。
「漏洩」だろう。一世を風靡したこの「K1の愛人」も、プロダクションの演出で“婚約”情報をリークしてもらい、最終的に笑顔で認めたという。この芸能やらせニュースにどういう裏事情があるかは知らないが、フェリカも「漏洩」でお騒がせしている。
フェリカの暗号が破られたというFACTA最新号の報道に続いて、ソニーの子会社フェリカネットワークスで働いていた元派遣社員のPCから、フェリカの導入先企業の情報がネットに漏洩したことも明るみにでた。そのことは12月22日にこの編集長ブログ「もういちど『ソニー病』4――屁のつっぱり」で既報済みである。
弊誌報道をソニーがあまりに頑なに否定しつづけるから、ブログで揶揄してみたのだ。ソニーが言うほどフェリカはご立派な情報管理でしょうか。自らの足元で起きた情報漏洩を隠し続けるアンフェアな態度では、全面否定も説得力がない。いったい、いつ発表するのだろう、とボールを投げたのである。
それをむざむざ、夕刊フジに拾われてしまったというわけだ。同紙は2面でも続きの記事を書いていて、そこではFACTAの記事を引用して、そのセキュリティの脆弱性をめぐる問題を指摘している。目新しい情報はないが、フェリカへの危惧を世に知らせるうえでそのパワーは侮れない。
問題はこれからだ。藤原紀香も婚約を否定しつづけて、最後に肯定会見となったから、ソニーもフェリカでは否定し続けて、最後に白旗を掲げるのだろうか。とすれば、ソニー広報は惨敗を予告されたようなものではないか。傷は深くなるばかり。広報室、沈黙す――の日はいつ来るのだろう。
FACTAは夕刊紙にお騒がせネタを提供するのが目的ではないから、フェリカと紀香をカップリングさせるような無茶はしない。傷ついたエクセレント・カンパニーをこれ以上深追いするのも望むところではない。でも、ネット上では侃々諤々の議論である。電子マネーをめぐるもっと本気の議論がしたいのだが……。
「トヨタ・フォード」スクープが実証されました
本日(27日)の日本経済新聞朝刊は、トヨタとフォードのトップが「提携を模索するため」会談したと報じた。トップとはトヨタの張富士夫会長と、フォードのアラン・ムラーリー社長である。先週、都内で会談し、かつてフォード傘下のマツダ社長をつとめたフォードのマーク・フィールズ副社長も同席したという。
この報道に対し、トヨタ広報は書面のニュースリリースは出していないが、問い合わせに対し以下のように口頭で説明している。
「トヨタは日ごろから他社のトップとはお会いしている。張とフォードのムラーリーCEOが会って、ご挨拶したことは事実。いつ、どこで会い、誰が同席したのか、どのような内容だったか等の詳細は答えられない」
FACTAの愛読者はお忘れではないでしょう。「トヨタが『フォード支援』提案」というスクープは、11月17日にFACTAオンラインのメルマガ読者に要点を特報し、その本文は本誌12月号(11月20日発売)に掲載しました。あまりに突出したスクープだったため、当時はどこも追いかけませんでしたが、ようやく日経が追いついてくれました。トヨタおよび日経からの「お歳暮」として有り難く頂戴し、お礼申し上げます。
世界一の座につくことが確実なトヨタと、第3位に落ちたフォードの提携の可能性というニュースは、第一報なら日経も二段ぶち抜きのアタマにしたかもしれません。少し抑え目なのはこれが後追いであることを意識したのでしょうか。ま、当方は慶賀にたえません。
他メディアが追いかけた場合は、メルマガ読者および本誌定期購読者に限らず、広く一般公開するとの公約に従い、12月号に載せた本文記事を無料公開します。27日付の日経朝刊と読み比べてください。事前にどういう動きがあって、FACTAがいち早く報道できたかが追跡できると思います。
さて、8月から始めたメルマガによる予告スクープ。これで3発とも的中し、すべて新聞など他メディアに追いかけてもらいました。FACTA報道のタイミングと信憑性の実証になります。ちなみにそのスクープは、以下の3本です。
1)東証にみずほが400億円賠償請求(8月)
2)日中首脳会談、10月にも開催(9月)
3)トヨタが「フォード支援」提案(11月)
新参の月刊誌としては誇るにたる成果でした。でも、メルマガで報じていないスクープも本誌にはたくさん掲載してあります。たとえば、最新号では「『木村銀行』に韓国から食指」の記事も、ある関係者から「どこで知ったの?あれは本当なんです」とすぐ電話がありました。もちろん、ソースは明かせませんが、雑誌冥利に尽きます。いずれどこかの新聞か雑誌が追いかけてくれるでしょう。
すこし自慢話になりました。来年もスクープを追いかけますので、ご声援のほどを。
暗闇のスキャナーと犬死
P・K・ディックがまた映画化された。「スキャナー・ダークリー」(厳密に訳すと「朧なスキャナー」。最初の邦訳であるサンリオ版が「暗闇のスキャナー」と題したのでそれを踏襲する)である。「ブレードランナー」から「マイノリティー・レポート」まで、ディックの映画化はことごとく原作の冒瀆ないしは改悪だったけれど、この映画化はこれまでになく原作に忠実だった。
ということは、70年代の饒舌と退屈、難解と通俗、悲痛と滑稽が入り混じっているということだ。あの時代を知らない世代に、この苛烈なユーモアはまず伝わらない。キアヌ・リーブスの名に釣られてきた女の子の観客が、「ぜーんぜん分かんない」とロビーでつぶやいていた。
彼らがいま原作を読めば驚くだろう。イトーヨーカ堂に買収される前の「セブン・イレブン」が冒頭で出てくる。ジャンキーが油虫にたかられる強迫観念にとり憑かれ、殺虫スプレー缶を買いに駆け込むのがセブン・イレブンなのだ。この妙な生々しさが、ディックの身上だと言える。
脚本・監督のリチャード・リンクレイターはよほどディックに入れ込んだ人らしい。メジャーな俳優を登場させながら、ほとんど娯楽を放棄した作品になっている。キアヌはおろか、万引きでハリウッド・スターから転落したウィノナ・ライダーも、アニメのキャラクターにさせられ、俳優めあての観客は肩透かしを食ったような気分になるだろう。その代わり、ディックのファンは満足する映画である。
「暗闇のスキャナー」の映画化が困難とされたのは、ドラッグの幻覚(その快楽より無限の退屈と悲惨)がリアルに描かれているだけでなく、SFの小道具である「スクラン・ブルスーツ」が難題だったからだ。
多面体の水晶レンズをはりつけた薄い屍衣のようなスーツで、これを着用すると、コンピュータに記憶されたありとあらゆる目の色、頭髪の色、鼻や頬の輪郭、歯並びなどの人体特徴が、眼内閃光のように水晶レンズに投影されて、誰の記憶にもイメージが結実しないという。聖書の「鏡の中にあるごとく」、人は朦朧として変幻極まりない存在となる。精神脱抑止剤の静脈注射で見た幻覚から着想したらしいが、SFのアイデアとしては見事というほかない。
麻薬捜査官である主人公ボブ・アークター(キアヌ)がこのスーツをまとって潜行捜査を行うのだが、なまじのCGでこのアイデアを映像化するのは難しい。監督のリンクレイターはこの難題を克服するのに、実写映像にアニメを重ねる「ロトスコープ」という手法を採用した。なるほど、コロンブスの卵である。
実写にアニメを重ねるから、映画自体がスクランブル・スーツになるのだ。アニメのキアヌの向こうに、常に実写のキアヌを想定させられる。だが、どちらが本物かわからない仕掛けになっている。
それがこの映画の秘訣だろう。キアヌやウィノナが出演したのは、きっとその意図を理解したからだ。俳優のイメージを売るハリウッドの常識に反する「ロトスコープ」に出演したのは、彼らもディックの暗澹たる原作を好み、出口のない迷宮を偏愛しているからだろうか。美男系のキアヌが、「マトリクス」トリロジーの暗い近未来映画に出演しつづける理由がわかったような気がする。
「暗闇のスキャナー」が、SF小説としてもドラッグ小説としても傑作とされたのは、カリフォルニアの乾いた風景の上で繰り広げられる沈痛な絶望的コミックが、自己喪失の時代を過たずとらえていたからだ。スクランブル・スーツを着た主人公が、ドラッグのバイヤーを偽装しているうちに、自分を監視する奇怪な任務を課せられ、重度のドラッグ中毒になって廃人と化していく過程と重ねられている。
自我の崩壊とその先の犬死。作品の最後が近づくと、ほんとうのテーマが犬死であることがわかってくる。「スキャナー・ダークリー」はドラッグに斃れた人びとへの鎮魂歌なのだ。
結末はグノーシス的だ。価値顛倒と陰謀史観の合体。脳を冒された主人公はそこに涅槃を見る。その彼が「フィールド・オブ・ドリームス」のようなトウモロコシ畑で発見するのが、麻薬物質Dのもとである青い花だ。ああ、ノヴァーリス。ドイツ・ローマン派がこのイメージの下敷きになっているのだろう。
ディックの作品2作を翻訳したから、この映画に一つだけ注文をつけたい。青い花のラストシーンだけは実写にすべきだった。そのほうがディックらしい結末となったろう。エンディング・ロールでは、ディックが悼んだ友人のジャンキーたちの墓碑銘まで再現しているのだから。