EDITOR BLOG

谷脇康彦著「世界一不思議な日本のケータイ」のススメ
MVNOだの、MNOだの耳慣れない略号が最近、氾濫している。訳語がまた難解だ。「仮想移動体通信サービス事業者」と「移動体通信事業者」。VはバーチャルのVなのだが、まず庶民には何のことやら分からない。いかにもお役所的な、こなれない訳語である。

この本「世界一不思議な日本のケータイ」(インプレスR&D、税込み1890円)の筆者は、総務省総合通信基盤局でMVNOの旗振り役として奮戦する現職の事業政策課長だけに、この難解な訳語を世に広めた張本人のひとりかもしれない。
2002年から3年間、ワシントンの日本大使館で参事官をつとめ、米国の情報通信のコンセプトをたっぷり身につけてきたから、無理ないことなのかもしれないが、それにしてもMVNOが体現する携帯(モバイル)ビジネスのオープン化が今ひとつ理解されないのは、この略号を放置しているからではないのか。
現にNTTドコモの薬罐アタマ経営陣は、この略号を聞くだにひきつけを起こす案配だ。そこでひとつ、提案したい。
MVNOをぐっとくだけて「アンテナ借り業者」、MNOを「アンテナ貸し業者」と言いかえたらどうか。
固定電話には回線貸しの制度がある。NTT東西のように全国に回線網を持つ業者が、そうした設備を持たない業者に回線をリースすることが定着した。MVNOはその携帯版である。MVNOを「携帯版回線借り業者」、MNOを「携帯版回線貸し業者」としてもいいが、どうもまわりくどい。
実際にはアンテナだけでなく、その背後にあるネットワークも含めて貸し借りするのだが、アンテナ貸しだと無線のニュアンスが残るのがいい。そうすれば、MVNOがMNOのフンドシを借りて携帯電話のサービスをするイメージが、脳裏に描けそうな気がする。
本の紹介からつい話が脱線した。谷脇課長は結構、筆まめな官僚で、これまでも「インターネットは誰のものか 崩れ始めたネット社会の秩序」(日経BP、税込み1890円)や「融合するネットワーク」(かんき出版、税込み1890円)を世に問うている。なぜか、どれも値段が同じなのは、ケータイ本のお値ごろ価格がこのあたりにあるということだろうか。
それにしてもバリバリの現役官僚、それも総務省でモバイルビジネス研究会の事務方をつとめる課長の本である。研究会の報告のような官製の文体かと思いきや、文章に硬さはない。むしろ研究会で何を議論してきたかがすっと頭に入る内容で、専門家と称する人々の下手な解説書よりよほど読みやすい。
「世界一不思議」という意味は、なぜ携帯の料金プランはあんなに複雑なのか、なぜ端末とサービスが別々でないのか、なぜすべての端末が高機能なのか、なぜ携帯会社の数は5社なのか、なぜ携帯インターネットは携帯会社が提供しているのか……という5つの素朴な疑問にある。
それがすべて携帯各社の囲い込み――垂直統合型ビジネスモデルに起因していること、成熟期に入った携帯ビジネスの第二の飛躍(モバイルビジネス2.0)を促すため、総務省は水平分業型モデルへの移行をめざしているという議論の組み立てである。なるほど。
だが、たったこれだけのことでも抵抗は強い。FACTA最新号が報じた「ドコモに行政指導」の記事でも明らかなように、既得権に固執するNTTグループは徹底抗戦。
しかし日本の携帯端末は、世界で通用しない「ガラパゴス」なのだ。デザインも機能も袋小路に陥り、iフォンやgフォンが上陸すれば、たちまち席巻されそうなほど危うい状態だ。
既得権の囲い込みは、進化を阻害する。前例踏襲、リスク回避は「サラリーマン」の悪癖だ。そういう危機感が、谷脇氏を執筆に駆り立てたのだろう。役人ですらもう既得権では立ちゆかないことを知っている。携帯の業界人も少しは見習ったほうがいい。
その意味では、一般の読者よりもむしろ業界人がこの本を読んで、新しいビジネスモデルに挑む勇気を奮い立たせてほしいと思う。
6月号の編集後記
FACTA最新号(6月号、5月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
あれは褒め殺しなのか、殺し褒めなのか。本誌にコラムを寄稿している手嶋龍一氏が、誰かに私を紹介する時、ふと悪戯っぽい目になることがある。北野武(ビートたけし)のバイオレンス映画をもじってこう言うのだ。「この男、凶暴につき」。まさか、とこちらは苦笑するほかない。
▼世の中にはスクープを「凶暴」と感じる人がいる。乱倫破戒を是とする気はないが、スクープは何かを踏み越えるものだ。それを「凶暴」と言われるのならしかたがない。少しだけ手前ミソを言えば、今号などはその典型かもしれない。朝日新聞株しかり、JFEしかり、ムグニエしかり、ドコモしかり……こんなにサービスしていいのかしら、と思うくらい特報記事を詰めこんだ。
▼誰も追えないスクープは、もちろん電通だろう。2年前の本誌創刊から連打して以来の追撃再開だが、「またやろうかな」と同業者に事前に漏らしても、「はあ、ぜひ読ましてもらいます」と危うきに近寄らずの風だった。お手並み拝見か。どの媒体も広告の蛇口を絞られたくないから、この記事は黙殺されるかもしれない。
▼だが、わが手元にはタンダ記者から送られてきたA4で228ページの起訴状がある。ドイツ語なので、サッカーファンの友人に翻読してもらったが、興奮してほとんど2日間寝ずに読んだという。ネタの宝庫だ。これが日本で報じられないのが不思議なほど、とつぶやいたが、電通ですらノーガードだったらしい。
▼FIFAの黒い噂と激しい内部抗争は、欧州の調査報道の主戦場なのだ。日本では断片的に報じられたにとどまる。この奇妙な沈黙を破って99年に翻訳出版されたヤロップの『盗まれたワールドカップ』で、監修者の二宮清純氏が「権力者を追い詰めることは不得手で、もっと言えばその方法すら知らない日本人」の沈黙を難じている。その挑戦、「凶暴」な本誌が引き受けよう。
まぶしのマジック
恥ずかしい話だが、名古屋名物の「ひつまぶし」を、大人になるまでずっと「ひまつぶし」と読んでいて、その正体をずっと知らなかった。うなぎをご飯にまぶし、最後はお茶漬けにしてさらさらと食べるものと知ったのは、かなり後になってからだと思う。だから「まぶす」という言葉を聞くと、パブロフの犬ではないが、何となく悔しさを感じる。
さて、最新号の目次が本日正午にサイトに掲載されるが、この「まぶし」によってスクープを一本損した気がする。5月17日の日本経済新聞朝刊1面脇のニュースで、「総務省が週明け(19日)、携帯各社に対し回線貸出料について行政指導する」と報じているからだ。
してやられた、と思った。日経にではない。総務省にである。
FACTAは19日正午にサイトで新刊号(6月号、5月20日発行)の目次を公開、購読者の会員にはオンラインで記事が読めるようになる。そこで報じる一本のスクープ――「『大臣裁定無視』ドコモに行政指導」が、日経報道で出遅れた形になるからだ。FACTAは先週初にすでにそれをつかんでいて、誌面に突っ込んだのだが、月刊誌の悲しさ、印刷中に日刊紙に報じられてしまったことになる。ま、しようがない。ほかにもスクープはあるから、そう目くじらは立てないことにしよう。
ただ、総務省もさるもの、この行政指導を上手に「まぶし」ている。行政指導は本来、大臣裁定に従わず、フテ寝を続けるドコモが対象だった。KDDIやソフトバンクモバイルなど携帯全社に指導する形をとるのは、ドコモ一社を目立たせないための「まぶし」なのだ。
それが証拠に、19日の指導に先立って5月13日、総務省はNTT持ち株会社の三浦惺社長を呼び、MVNO(仮想移動体通信事業者)に対し回線貸しの交渉を長引かせるドコモの抵抗を排除するよう要請、三浦社長も「善処」を約束した事実がある。日経報道ではその裏側がまったくわからない。たぶん記者も分かっていないのではないか。
総務省とドコモの間に何があったのか、本当のことをご存じになりたいなら――つまり「まぶし」なしのファクツをご覧になりたいなら、弊誌記事をご覧ください。読めば、まぶしに混じった山椒の辛さがちょっとはお分かりいただけると思う。
ジェラルド・カーティス×手嶋龍一×阿部重夫トークイベント「オバマと秋刀魚――日米政治の分かれ目」開催
5月26日(月)の19時より東京・秋葉原で、日本政治研究の第一人者であるジェラルド・カーティス氏と外交ジャーナリストの手嶋龍一氏をお招きして、日米政治の分かれ目を論じるトークイベントを開催します。今回のイベントでは、二人の出版を記念したサイン会も開催します。詳しくはFACTAフォーラムの告知ページをご覧ください。
吉野直行・慶大教授を批判する
久しぶりにひどい文章を読んだ。6日付の日本経済新聞朝刊の「経済教室」である。臆面もない御用学者ぶりには恐れ入った。日経を読まない人のために、まず見出しだけ紹介しよう。
特別会計と財政再建「埋蔵金」頼みには限界
「焼け石に水」の規模
健全化の議論こそ本筋
これだけで、金融・財政政策を専攻する学者にありがちな「財務省の腹話術」が感得できる。要旨をまとめた「ポイント」を見れば、それはいよいよ明らかだ。
・財政融資資金特会の準備金は依然必要
・「埋蔵金」を取り崩す効果はわずか
・国債円滑化の方策に関する議論尽くせ
ああ、おぞましいまでに財務省の理屈のおうむ返しである。正直言って、これで「埋蔵金」論者とされている高橋洋一・東洋大教授を論破できるとは思えない。反論は本人にしてもらうのがいちばんだが、こんなアホらしい議論につきあえないと言うかもしれない。素人でもわかる部分はここで指摘しよう。
歳入の30%を国債に依存し、国債を年々大量発行しているにもかかわらず、「これまで、日本の国債は非常にうまく消化されてきた」と吉野教授は言う。うまく消化?馬脚が現れる。視点は財務省理財局の国債管理政策にあり、消化難に陥らなかった「うまさ」を自賛する政府に丸のっかりしている。
吉野氏が持ち出すのは部門別の資金過不足(日銀の「資金循環」参照)である。90年代を境に企業部門が赤字から黒字に転じたことが、国債の消化難回避に寄与したという。
日本企業は、国内の投資需要がなく将来的にも成長があまり望めなかったため、銀行から借り入れていた資金を返済し、企業の内部留保である企業貯蓄を増大させ、企業部門は赤字主体から黒字主体へと変化していった。
他方、量的緩和、ゼロ金利政策といった金融政策で、資金は潤沢に供給されてきた。金融機関は、順調に拡大した預貯金を、企業向けの貸し出しではなく、国債の購入に向けた。
仰るとおりだが、それは失政だったのではないのか。企業が家計部門から奪った資金余剰を投資に向けず貯蓄に回し、それを政府が吸い上げて生産性の上がらないハコモノに投じたあげく、経済が行き詰った現状を、この慶大教授は何も考えていない。
「今後民間企業の資金需要が増大し、再び黒字から赤字部門へと変化すれば、低下する家計の貯蓄では、膨大な政府の赤字(大量の国債発行)と企業の投資需要を賄えなくなってしまう」というまるで他人事のような物言いに、この御用学者の本領が発揮される。
民間企業の資金需要をどうやって増加させるのか。自然に投資に向かうとでも思っているのか。彼が恐れているのは政府の帳尻があわなくなることだけであり、需要を喚起する政策誘導などはどうでもいいのだ。経済学者としては三流というほかない。
だいたい、吉野教授が仮想敵にしている高橋氏自身、かつて理財局に在籍して国債管理政策の舞台裏に通暁している。財投改革で郵貯・年金の預託を廃止し、財投債の発行によって民間金融機関並みのALM(資産負債管理)を財投に持ち込んだアイデアの張本人だった。それを知らないのか。
金利リスクを度外視してきた財投に市場原理を導入する意味を、主計局の主流派が理解できなかったことが今日の財務省凋落の原因である。それは郵貯民営化を必然的に導きだすトロイの木馬だった。高橋氏の『財投改革の経済学』をよく読めばすぐ分かる。吉野教授は財務省からもらった資料に洗脳されていて、実は不勉強なのではないか。
日経に寄稿したこの文章は「釈迦に説法」の典型だろう。財投の貸付が元金均等型の償還で、財投債には償還年限が2年、5年、10年、20年、30年物があるからミスマッチのギャップが残ると論じるが、刻みが異なっているから「金利リスクがゼロにはならず、一定程度残る」程度でしかない。『財政改革の経済学』ではリスクフリーとは書いてないし、日経経済教室に寄稿した高橋論文でも準備金の積み立て過剰を指摘しても、積み立て不要論は主張していなかった。
経済学者の本来の役目は、現行制度下では適正な準備金積み立てがいくらか、という実務的な試算だろう。吉野教授がそれをはじき出したという話は寡聞にして聞かない。資産残高の千分の100から千分の5への引き下げも、「埋蔵金」の吐き出しも、吉野教授は財務省が行った良心的是正のように書いている。冗談じゃない。与謝野馨・前官房長官に入れ知恵して「埋蔵金」否定キャンペーンの論陣を張ったのはどこの官庁なのか。
あげくに追い詰められ、いやいや隠しポケットから出してきた。経済財政諮問会議などの場で「埋蔵金」を指摘され、追い詰められなければ、財務省は知らぬ顔の半兵衛、隠し通したろう。そうでしょ。丹呉(泰健・官房長)さん。財務省はホゾを噛んだに違いないのだ。
吉野教授は問題設定自体が間違っている。特会の準備金など(いわゆる埋蔵金)を取り崩すことで、国債残高の減少につなげることができるか――。これが「焼け石に水」なのは当たり前だ。GDP比120%に達する国の債務をゼロにすることなどできやしない。しかし、では、財政再建のための増税でそれは可能か。消費税を1%増税しても増収は2兆5000億円。これまた「焼け石に水」なのだ。
財務省やその代弁者である御用学者の議論は、木を見て森を見ず、国債管理政策だけ見て、経済のアンバランスを見ていない。
それが、外国為替等審議会の外資特別部会でも露呈した。同特別部会が4月15日にまとめた意見書では、英国の投資ファンド、TCI(ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド)が、東証1部上場の電源開発(Jパワー)株を9・9%から20%まで買い増す計画を立てていることに対し、「公の秩序の維持が妨げられる恐れがある」ことを理由に中止を勧告する内容である。誰が見ても、20%の株取得が安全保障の根幹(Jパワーは大間に原発建設を計画)に抵触するとの証明は不十分である。
この部会長は吉野教授その人だ。さもありなん。政府の「いいなり」の人、適材適所である。
プレミアム・サービス「FACTA Associa」について
3月号で告知したアソシエイト会員限定のプレミアム・サービスの開始ですが、予定より準備に時間が掛かっており、資料請求の受付を少し延期させていただきたいと思います。
すでに、多くの方からお問い合わせをいただいており、お待たせして大変申し訳なく思っています。編集部としても、かなり踏み込んだサービスをご提供できるよう、万全の体制を整えたいと思っておりますので何卒ご容赦ください。
準備が整いましたら、改めてお知らせしますので、もう少しお持ちいただけると幸いです。
コラム「時代を読む」への寄稿
4月27日付で新潟日報など環日本海10紙のリレーコラム「時代を読む」に寄稿しました。たまたま、青森に取材に行っていた知人が東奥日報でコラムを見たとメールをしてくれました。通信社を介した配信ではありません。手嶋龍一氏らとローテーションを組み、日本でもシンジケートコラムができないかと始めた試みです。10紙の購読者を合算すると200万人になるそうですから全国紙規模ですが、都市部に偏ることなく地方にもメッセージを届けられるというメリットがあります。FACTAの知名度をあげる狙いもあります。
*****
<時代を読む>農のマエストロよ、いずこ
前FRB(米連邦準備理事会)議長、グリーンスパンのインタビューをCATVで見る機会があった。市場を巧みに操り「マエストロ」と呼ばれた1990年代アメリカ経済の救世主が、議長在職中に端を発するサブプライムローン(信用度の低い個人向け住宅ローン)問題で被告台に立たされていた。
化粧品のモデルのような美人キャスターが、機関銃のように質問を浴びせる。マエストロは懸命に「バブルの予見は不可能だった」と縷々説明していたが、男のキャスターが割って入り「博士、お言葉ですが」と遮って容赦ない責任追及を始めた。
一瞬、前議長の目が泳いだ。あの受け口の唇がめくれる。ぶざまな絶句。だが、それから何を言っても弁解にしか聞こえない。
どこかで見た表情だった。「新しい天使」(Angelus Novus)。スイス人画家クレーが描いた銅版画に似ている。ライオンのようなたてがみの天使が、大きく目を見開き、強風に吹き飛ばされるように、翼を広げて驚愕の表情を見せていた。
「かれは顔を過去に向けている。僕らなら事件の連鎖を眺めるところに、かれはただカタストローフのみを見る。(中略)かれの眼前の廃墟の山が、天に届くばかりに高くなる。ぼくらが進歩と呼ぶものはこの強風なのだ」
この絵を買って自室の壁に飾っていた批評家ベンヤミンの言葉である。そう、慣性の法則は物理だけではない。グリーンスパンも言いたかったに違いない。「エコノミストは過去しか語れない。未来予測はできない」と。
タイムラグの大小はあれ、エコノミクスも残像の呪縛から逃れられない。いま、日本のエコノミストの多くはデフレの残像にとらわれている。
原油や鉄鉱石、燃料炭や非鉄金属から小麦まで国際商品市況の高騰が国内に波及、いよいよ消費価格転嫁が始まった。でも、個人消費は依然慎重で、インフレの恐れは小さいとのご託宣が下されている。サブプライム禍による金融不振の余波で、投機資金が商品市場に流れこんだ一過性の現象だという。
そうだろうか。
最近、コートジボアール、カメルーン、ハイチ、フィリピンなど赤道を囲む貧困国で、食糧暴動が同時多発している。なぜか。飢餓はかつて戦争や政策的失敗などローカルな現象だったが、今の食料危機はグローバルなのだ。
その一端がコメの国際価格高騰だろう。世界のコメの生産量4億2千万トンのうち輸出されるのは7%程度にすぎないが、主要輸出国タイのコメ価格が急騰、輸入国のインドネシアやフィリピンなどを直撃しているのだ。
理由は明らかだ。30億人弱の人口を抱える中国とインドが、急激な経済成長とともに世界のエネルギーと食料の需給を逼迫させ、穀物などの価格急騰で「弱い環」の最貧国を追い詰めているのだ。アメリカがエタノール燃料の旗を振ったことも穀物価格上昇をあおり、はしなくも「鉱」と「農」がそこでリンクした。
金融は所詮ゼロサムだが、「鉱」と「農」の一次産業は付加価値が大きい。デフレは「余剰のグローバリゼーション」の産物だが、これらの現象は「不足のグローバリゼーション」が始まったことを示している。
もう従来の農業政策は意味をなさない。保護によって余剰(価格下落)から生産農家を守ろうと補助金漬けにしてきただけに、不足を埋めるための増産をしようにも高齢化し兼業化した農家は対応できないからだ。
しかし不足のグローバリゼーションは、いくら札びらを切っても海外で食料を調達できない「買い負け」時代の到来を意味する。エネルギー政策と農業政策は戦後日本の政治がなおざりにしてきた最大の失策だが、鉱・農軽視のツケを支払う時期が来た。
人は後悔する動物である。だが、困難そのものの反復による困難の克服――に「新しい天使」は宿る。進歩と呼べるのは過去から吹きつける強風なのだ。
形を変えた失業対策費でしかない道路財源にこだわるなかれ。これから「農」は売れる。土木から労働人口を呼びもどそう。市場に背を向けた保護策を捨て、甘えで傷んだ「農」を再建するには、新しい革袋が必要である。
いでよ、農のマエストロ!
ゴードン・トーマス氏に感謝します
本誌4月号(3月20日刊)に「『北朝鮮の核密輸』をモサド暴露」を寄稿してくれた英国のジャーナリスト、ゴードン・トーマス氏に改めて感謝申し上げたい。
4月24日にホワイトハウスが米議会の非公開説明会で報告、その後にシリア奥地に建設中だった原子炉施設の映像まで公開したものだから、モサドに強いトーマス氏が本誌で特報してくれたこの施設へのイスラエルの空爆作戦の詳細は、世界の耳目を集めるにふさわしいスクープだったことが裏づけられたと思う。
この貴重な記事はフリーコンテンツ(無料公開)にしていなかったので、FACTAの定期購読者にしか読めなかったが、その意義を考えて公開するとともに、ポータルサイトのYahoo!とgooにも配信することにした。初めて読まれる読者は、トーマス氏の奮闘に拍手を送ってくれるだろう。
彼がこの記事をFACTAにexcluiveで寄稿してくれたのは、何よりも北朝鮮の核の脅威に日本がさらされていることをよく理解していたからだろう。さらには、オルメルト訪日を控えて日本の世論を喚起し、米国の宥和派にブレーキをかけようとするイスラエル、そしてモサドの意思も裏側にはあったろう。
トーマス氏のインテリジェンスに疑義を呈していたサイトにも心から感謝したい。おかげでトーマス氏の名は日本でも一段と知られるようになった。これからも思い切り薀蓄を傾けて論評してくれることを願う。きっと弊誌にとってもも何がしかのいい影響があるだろう。多謝!
ジェラルド・カーティス「政治と秋刀魚――日本と暮らして45年」のススメ
 アメリカから日本の政治を研究しにやってきた青年が、1967年の衆院選挙で大分二区に立候補した佐藤文生氏(中曽根派)の事務所に飛び込み、舞台裏を活写した『代議士の誕生――日本保守党の選挙運動』(1971年)以来、ジェラルド・カーティスの名はいわば「密着取材」の先駆者の代名詞だった。
アメリカから日本の政治を研究しにやってきた青年が、1967年の衆院選挙で大分二区に立候補した佐藤文生氏(中曽根派)の事務所に飛び込み、舞台裏を活写した『代議士の誕生――日本保守党の選挙運動』(1971年)以来、ジェラルド・カーティスの名はいわば「密着取材」の先駆者の代名詞だった。
この処女作のことはよく覚えている。まだ私は新聞記者ではなかったが、やられたという悔しさより、その密着手法がえらく新鮮に思えた。ライシャワーはじめアメリカの日本通はどこか雲の上の存在であり、日本の政治のような下々の泥臭い世界には下りてこないものと決めてかかっていたが、カーティス氏の手法は大所高所ではなかった。ブルックリンのリアリズムを体現したかのような「あたって砕けろ」式の現場主義は、自分にもできるのではないか、と私には思えた。
氏が日本の市井で暮らし始めたのは1964年というから、もう44年である。来し方を振り返って書いたこの『政治と秋刀魚――日本と暮らして45年』(日経BP社、1600円+税)は、単なる政治学者の回顧録とは違う。混迷の度を深めるばかりの日本の政治に、カーティス氏なりの助言を試みたものだ。
その助言は温かい。日本の死角をさらりと指摘してくれる。米欧から輸入した概念が必ずしも日本の現実にはそぐわないことを教えてくれるのだ。たとえば「小さな政府」というが、日本の公務員の数は欧米に比べて格段に少ないという。
「問題は人数ではなく、官僚の権限である。規制緩和など政府の権限を縮小することと公務員数を削減することとは別の問題である。マナーからルールへと社会構造が変わっていくことによって、逆に公務員の数を増やさなければならない分野はたくさんある」
また、政策新人類といわれる若手政治家にもやんわりと苦言を呈している。
「日本では『地元への利益誘導』は響きが良くない。だが、代議士が自分の選挙区である地元の利益を考えなければ、選挙民は何のためにその人を国会に送るのだろうか。……今の小選挙区制だと、親の強い地盤を受け継いでいる二世議員は、自分は『政策通』だと自慢してテクノクラートのような態度を取る。まさに政治家の官僚化現象である。今、必要なのは、政策通よりも『政治通』である」
二大政党制を美化し、アメリカの大統領制を真似ようとすることのむなしさ。安倍政権が熱心だった政治任用制度についても、イラク侵攻で失敗したブッシュ政権を例に挙げ、「トップにある政治リーダーを下部にいる専門家のアドバイスから遮断する」システムと批判したドビンズ元国務次官補の発言を紹介する。
「現在のイラクにおける混乱を招いた責任は、政治任用された新保守主義者にかなりの部分がある。政治任用された人が問題を起こすことは新しい現象ではないし、政治的に『右』の人間だから起きた問題でもない、ディビッド・ハルバースタムが『ベスト&ブライテスト』で描いたように、ベトナム戦争の愚行は政治任用されたリベラルの人たちによって引き起こされたものだ」
カーティス氏は自らを知日派第三世代と定義している。彼が45年前に見た日本の政治は「機能している」(The system works)ものだった。その機能の秘密を知ろうと彼は現場に飛び込んだのだ。その彼とて1990年代には日本の政治が「後れている」ことを認めざるをえなくなった。欧米に対する後進性という意味ではない。内外の環境変化に対応できていないという意味で「後れている」というのだ。
このいわば常識、語の本来的な意味でいうコモンセンスがカーティス氏の持ち味だろう。それがどう形成されたかは、この本の前半に詳しい。東京の山の手、西荻の下宿で、銭湯に通い、秋刀魚に舌鼓を打つといったディテールは、ほとんど「三丁目の夕日」を思わせるほど懐かしい。それは奇跡のように日本に適応した「ガイジン」さんの苦労話というより、庶民の暮らしに密着した人のみがもつぬくもり、ほのぼのとしたコモンセンスの所在が感じられるのだ。こういう「常識」をわれわれはいつから失ったのだろう。
文章も驚くほど平明だし、音楽的である。カーティス氏ははじめジャズピアニストを志してニューヨーク州立大学に進んだというから、きっと耳がいいに違いない。日本語がけっして上手でなかったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)があれだけ溶け込めたのも、その耳のよさのおかげだと思う。
八雲の耳にはヤマバトの鳴く声が「テテ ポッポー カカ ポッポー」と聞こえた。カーティス氏の耳に永田町スズメはどう聞こえているのだろうか。
畔蒜泰助「『今のロシア』がわかる本」のススメ
ロシアの魂とは何かについて、私には何もわからない……
佐藤優との対談を新書にした「ロシア闇と魂の国家」で亀山郁夫が何度もそう呟いている。私にもこの北のラビリンスはさっぱり分からない。ツルゲーネフ、トルストイ、ドストエフスキー、チェホフ、ブルガーコフ……と人並みに訳書は読んでみたが、ロシア語を学んだこともない身では謎だらけの国である。
が、世の中には日々研鑽を積んでいる人々がいて、そのサイトのひとつ「週刊オブイェクト」で弊誌のロシアの兵器に関する記事が批判されているらしい。このサイト、兵器愛好家の筆になるものらしく、どこにでも目利きは存在するのだと感心した。FACTAとしては、誤報というご指摘は歓迎する。
編集長が全知全能ではないように、弊誌もまた全能ではない。どこかに誤報がまじる可能性は常に意識している。メディアは情報の非対称性に派生する。それゆえ誤報は正確な情報のシーズになる。だから、誤報とのご指摘には、根拠とその情報源をご教示いただくようお願い申し上げます。
すでにこのサイトの筆者にお会いする機会を与えていただくよう申し入れているところです。もし、ご快諾いただけるようなら、このサイトでインタビューを収録したいと思います。
 さて、ロシアが分からないといっても、関心の外にあるわけではない。畔蒜君が書いた「『今のロシア』がわかる本――日本人が知っておきたいロシア経済とその世界戦略」(三笠書房知的生きかた文庫、533円+税)は、私にとっては貴重な本である。
さて、ロシアが分からないといっても、関心の外にあるわけではない。畔蒜君が書いた「『今のロシア』がわかる本――日本人が知っておきたいロシア経済とその世界戦略」(三笠書房知的生きかた文庫、533円+税)は、私にとっては貴重な本である。
保険会社を辞めて自費でモスクワに留学し、政治学を学んだ彼のロシア観の根幹には、ジオポリティクスがある。本書もそれは貫かれていて、凡百のロシア本とは質を異にする。
ユコス解体から、独ロのバルト海パイプライン、ウクライナのオレンジ革命、米ロの核燃料合弁会社構想を結ぶ赤い糸を手繰る鳥瞰図は、ロシアの地政学的戦略をよく捕らえていて圧巻と言えよう。
私の机の上には、彼に教えてもらったWSJ(ウォールストリート・ジャーナル)05年2月23日の1面記事のコピーがまだある。ドレスナー銀行ロシア現地法人の社長で、独ロ間に建設する北海パイプライン会社の社長(会長はシュレーダー前首相)に就任したマティアス・ヴァーニッヒの記事だ。
かつて彼は東ドイツの諜報機関シュタージの一員で、当時東独にKGB部員として赴任していたプーチンと親しくなったことが暴露されていた。それはシュレーダー、メルケル両政権が追求した「東方政策」が、いかなる人脈によって担われてきたかを示す。それをWSJに暴露した米保守派の歯ぎしりまで伝わってくる。この記事の所在を教えてくれて、わが蒙をひらいたのも畔蒜君である。
瑣事に見えても、一瞬にして全豹が見えるツボがある。本書はそういう本だ(兵器オタクより戦略オタク向きかも)。陰謀史観に堕すこともなく、ありきたりの冷戦思考でもない。外務省に使い古された袴田茂樹教授とはひと味も二味も違うロシア専門家の登場は心強い。
それにしては、シリーズものとはいえ、この本のタイトル、いささか単刀直入すぎないか。もったいない。ケニアの副環境相マータイさん(ノーベル平和賞)ではないが、ちょっとそう言いたくなる。
5月号の編集後記
FACTA最新号(5月号、4月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は28日からです。
*****
ものみな、ういういしい春。わがFACTAも今号から3年目。終始温かい支援を惜しまなかった愛読者の方々や、鋭い切り口の記事を数々寄稿してくれた記者の方々、そしてこの雑誌の刊行を有形無形に支えていただいた関係者に、心からお礼申し上げます。思えば恵まれていました。調査報道を旗印にクオリティーマガジンをめざすといっても、時代を切り開く幾多のスクープを連打できなかったら、世の読者にこれほど認知してもらえなかったろう。
▼幸い、発行部数も着実に伸び、今号から念願の輪転機印刷になった。これで印刷工程を短縮し、デッドラインを繰り下げられる。月刊誌編集者にとって、最大の恐怖は下版から読者のお手元に届くまでのタイムラグ。この空白に何が起きても、変更できない誌面は後の祭りとなる。1日で潮の流れが一変する政局や市場の記事は、よく外れて週刊誌や日刊紙も泣かされる。月刊誌でも彼らに競り勝ちたい意地っ張りのFACTAは、何度歯軋りさせられたことか。
▼その不利を輪転機印刷で多少埋められれば、記事の射程は中距離砲から短距離砲に変わる。読者にとっては、よりアップデートな情報を入手できることになる。もっともこの時間の不利あればこそ、わが誌は何とか「三歩先を読む」勘を磨いて、待ち伏せを仕掛けてきた。その猟人本能を失っては元も子もない。雑誌は狙撃手。物陰に身を潜め、息を殺して獲物を仕留めよう。
▼短期連載の「凍河越境千里行」は今号で完。脱北者にここまで密着したライターの労を多としたい。また新たに「ポリシーの極意」と「インダストリーの極意」の1ページコラム連載を始めた。これまた、余人の知らぬ奥深い秘境である。3年目のFACTAは、これまでにも増して斬新な企画やスクープに挑み、世を震撼せしめたい。今後もどうか変わらぬご愛顧を。
日銀新総裁・白川方明氏の新著を真剣に書評する
 タイミングが良すぎたというか、してやったりとういうか――空席だった日銀総裁に、先に副総裁に就任していた白川方明氏がきょう(4月9日)昇格するが、4月6日付の熊本日日新聞で、白川氏が先月出版した大著の書評を掲載したので、ここに再録する。
タイミングが良すぎたというか、してやったりとういうか――空席だった日銀総裁に、先に副総裁に就任していた白川方明氏がきょう(4月9日)昇格するが、4月6日付の熊本日日新聞で、白川氏が先月出版した大著の書評を掲載したので、ここに再録する。
書評にもあるように、彼とは年齢も近く、日銀取材を通じて知己となった。個人的には「大変な重責ですが、おめでとう」とお祝い申し上げたい。しかし知己であるがゆえに、書評で変にじゃれたくはない。
同じ6日付の日本経済新聞で、ロンドン特派員の女性記者が「独立性揺るがぬ英中銀」と題してコラムを書いていたが、その不勉強にちょっとあきれた。97年にブレア政権発足後すぐ、ブラウン蔵相(現首相)が行なったイングランド銀行改革をとり違えている。あれは独立性をイングランド銀行に与えたのではない。剥奪したのだ。当時、私はロンドンに駐在していたが、銀行監督部門を切り離してFSAを創設することによって、中央銀行の権限を限定し、金融政策専従にしたのだ。
表向き金融政策運営に独立性を与えるという見かけをとっているが、イングランド銀行は金融街シティに君臨する法王の座から蹴落とされたのだ。ブラウンの剛腕をかいまみた。当時の総裁、エディ・ジョージの複雑な表情が忘れられない。
「スレッドニードル街の老女」とあだ名されたイングランド銀行が、かつて秘密めいた支配力を握って放さなかったことは、大蔵省出身の経済学者ケインズと、ドイツ賠償問題や金本位復帰などで対立した伝説のノーマン総裁を見ればよくわかる。ケインズが「野に叫ぶ預言者」だった不遇の時代、誰が沈黙して英国の金融を牛耳っていたのか。ブラウンは過たず独立性の牙城を骨抜きにし、英国経済を思うままに好調軌道に乗せ、ブレア長期政権を担保したのである。
そういう隠微な歴史をろくに知らない記者が中央銀行論を書く時代だ。9日の場況記事では白川氏の新著――「現代の金融政策―理論と実際」(日本経済新聞出版社 6000円+税)に触れたくだりが出てくるが、時間軸効果だけとは寂しい。タカだのハトだのでなく、もっと本質を論じるべきだろう。
それにしても、白川氏本人も金融政策の理論家として本書を執筆したときは、まさか総裁として日銀に舞い戻ろうとは考えていなかったろう。論が慎重すぎるのでは、と素直にジャーナリストの視点から苦言を呈する書評になったが、ときにないものねだりだったかもしれない。白川総裁には寛恕を願うばかりだ。
*****
熊本日日新聞書評
「現代の金融政策―理論と実際」 白川方明著
論戦の自律こそ「日銀の独立」
◇
主なき日銀という異常事態のなかで、総裁代行から総裁に昇格した“渦中の人”白川方明氏の新著が、まるで見計らったかのようにほぼ同時に出版された。もちろん偶然だろうが、四百二十ページもあるこの力作の学術書のどこかに、「趣味は金融政策」という彼の本音がうかがえないかと、読者は目を凝らすに違いない。
実を言うと、評者は1990年代前半の信用機構局時代から白川氏を知っている。国際決済銀行(BIS)の委員会出席のため欧州出張した彼が、ロンドン駐在中の評者を訪ねてきて、金融危機論に花を咲かせたこともある。それゆえ、この「金融政策大全」は、真剣勝負で(つまり容赦なく)書評したい。
本書はポレミーク(論戦)の書ではない。前書きにあるように、特定の政策に対する批判や弁明と受けとめられるのを避けている。金融政策の運営で「直面する問題を過不足な説明」し、セントラルバンカーの「悩みを率直に説明」しようとしたのだ。
記述の誠実は疑えないが、総裁空席に直面した日銀の「独立性」とは何かが問われているさなかだ。総裁副総裁人事が政争に左右されること自体が「独立性の不全の証明」とも言えるが、白川氏自身も執筆時点でまさか自分が巻き込まれるとは想定していなかったろう。
が、独立性を論じるために割いた一章「誰が金融政策を決定するか」は、中川秀直・元自民党幹事長ら「上げ潮派」との論戦に深く踏み込まず、各国制度の比較にとどめている。インフレ・ターゲット論者の伊藤隆敏・東大教授が参院不同意で副総裁の座を棒に振ったことを思えば、白川氏のこの沈黙は正直物足りない。
賛否は明示せずとも、福井日銀が受け入れなかったターゲット論自体には微妙な口調になる。「独立性を議論する際には、目的(ゴール)、具体的目標(ターゲット)、手段(インストゥルメント)に明確に分けることが必要である」
誰しも異論がないだろう。だが、その裏には「物価安定」という広義の目的は受け入れても、「政府に具体的な物価目標を決められ、自由度を奪われるのはご免」という日銀の思いがにじみ出ている。
本書の白眉は、第Ⅵ部の「近年の金融政策運営をめぐる論点」だろう。ゼロ金利、量的緩和の当事者による評価は読者も読みたいし、筆者も悩みつつ苦心したところだろう。「サブプライム禍」に直面した米連邦準備理事会(FRB)が、実質ゼロ金利に踏み切り、市場に大量資金供給を行うばかりか、全米第5位の証券ベアー・スターンズ救済に“特別融資”に踏み切った今、先にバブル崩壊の崖っぷちに立って日銀が得た教訓を誰もが知りたい。
が、ゼロ金利をいったん解除して再導入、量的緩和に踏み切るまでの逡巡、そのジグザグの分析は、腫れ物に触るように扱っている。金利の“神器”を失ったトラウマから、福井日銀がめざして志半ばで終わった「金利の正常化」を、新総裁を迎える日銀は継承するのか否か。
量的緩和が奏功して「デフレ・スパイラルは生じなかった」という結論は是としても、では、デフレから日本は脱却できていたのか、という本質的かつ喫緊の問いに本書は解を与えていない。上方バイアスなど「デフレの糊代」を否定し、物価上昇率0~2%の下限を目標としたかに見える福井日銀のレールを、白川氏も踏襲するのだろうか。
答えは本文でなく、巻末の引用文献にある。伊藤教授ら日本のターゲット論者の主要論文はほとんど挙げられていない。海外の文献はバーナンキFRB議長やウッドフォードらターゲット論者のものまで満遍なく網羅されているが、辛らつに日銀を批判したプリンストン大学のラース・スヴェンソン教授の「フールプルーフ(阿呆でも分かる)論文」(正式題名は「金融政策と日本の流動性の罠」)がなぜかない。
不在の影によって輪郭が浮かびあがるようでは、本書は「日銀のための日銀による日銀の教科書」と思われてしまう。「通貨の番人」の城砦に籠らず、ポレミークの野戦に打って出る自律性あればこそ、真に独立した中央銀行ではないか。
高橋洋一「さらば財務省!」のススメ
 この本が出来上がったばかりの3月下旬、彼をゲストに呼ぶBSデジタル放送の番組で司会をつとめた。彼がこの本を持参したので、番組の中で紹介し、ブログで紹介することを約した。その約束をここで果たそう。
この本が出来上がったばかりの3月下旬、彼をゲストに呼ぶBSデジタル放送の番組で司会をつとめた。彼がこの本を持参したので、番組の中で紹介し、ブログで紹介することを約した。その約束をここで果たそう。
佐藤優「国家の罠」を連想させるタイトルだが、これは講談社の編集者がつけたもので、売らんかなの思惑が見え隠れするのは、高橋氏の本意でも希望でもない。
霞が関官僚で彼を毛嫌いする人は多い。彼の名誉のために言っておくが、恨み節や暴露本を書こうとしたのではない。彼の前著「財投改革の経済学」をやさしく噛み砕き、彼自分が左遷されるなどの個人的な体験もまじえた読み物に仕立てた本である。前著と共通しているのは、霞が関の通念と化した不条理を切り捨てて、合理性を回復させようとする情熱であって、それ以上でも以下でもない。
前著が週刊東洋経済の年間経済・経営書ベストワンに選ばれたのは、与謝野馨・元官房長官と中川秀直・元自民党幹事長の論戦になった財務省の「埋蔵金」問題で、埋蔵金ありとする根拠が本の中に明示されていたからだ。財務省のからくりを知るインサイダーが「ある」と主張したのだから、論戦は勝負あった。財務省も渋々埋蔵金の一部を差し出して消費税増税論を引っ込めたのである。
そうしたエピソードがテンコ盛りで、安倍前総理の辞任の引き金の一つになったと書かれた昨年9月の彼の人事も、当事者としてリアルに書いてある。小泉・安倍内閣の舞台裏で政策を立案した彼の考えを集大成した学術論文集である前著よりも、素人にはずっと面白い。前著にはちょっと歯が立たない人でも、エリート中のエリートと言われた財務官僚が実は世間の常識に疎い阿呆だとここまでとっちめられると、溜飲が下がる思いをするだろう。
前にこのブログでも書いたが、高橋氏は東大数学科の出身。同じ東大でも法学部出身の財務省主流は、彼の数式と論理に対抗できない。ドンブリ勘定の財政投融資を合理化しようと、彼が理財局時代に孤軍奮闘してつくりあげた財政のALM(資産・負債総合管理)も――私はそのころ取材していたが、なかなか理解されず、その後は宝の持ち腐れになったという。既得権擁護に汲々とする霞が関の世界に、こういう存在がまじれば、泥田の鶴となるのは明らか。彼は傍流を歩き続けることになる。
3年間在籍したプリンストン大学ではバーナンキ教授(現FRB理事長)と親しくなったのに、そのコネを財務省が上手に使った形跡はない。国土交通省出向から関東財務局へと転々とする彼を、もったいないなあと思っていたら、かつて研究所で一緒だった竹中平蔵氏が入閣時にピックアップした。当然ながら、竹中氏とのエピソードはこの商売上手のエコノミストに高い評点を与えている。
それからの活躍は本書に詳述してある。郵政改革や道路公団改革、政府系金融機関の再編など、ほとんどを手がけたが、それは彼の一貫した論理の延長線上にある。財投ALMの先に郵貯の預託廃止と財投債発行があり、「郵貯の自主運用が転がり込んできた」とヌカ喜びした郵政が、返す刀で民営化に追い込まれるというプロセスは、小泉改革の底流にあった経済合理性と必然性をかいま見せてくれるのだ。この論理を突破できない郵政改革反対論は、結局は不条理の温もりにすがる情緒でしかなく、到底経済政策論としては聞くに値しないのだ。
彼が霞が関の外に飛び出した(4月1日から東洋大学教授)おかげで、財務省主流はこれから枕を高くして眠れるのか。どうもそうはいかないらしい。財務省が50兆円も発行した変動利付国債の危うさ、そして金融機関が抱える含み損が5兆円に達していることなど、まだまだ彼が突きつける匕首に霞が関は震え上がるだろう。まさにトラは野に放たれた――。
トラの咆哮はこの本からたっぷり聞こえてくる。彼とは証券局、理財局時代からの付き合いだからもう15年以上になろうか。その私でも楽しめたのだから、初めての読者にはきっと面白いだろう。偉そうな政府中枢の要人が、意外やドタバタ劇の主人公となり、抱腹絶倒の場面もある。その根幹には合理性という軸がでんと座っていて、数学者の卵だった高橋氏が健全な精神の持ち主であることを物語っている。
無断のパクリ、朝日新聞のお粗末
3月30日付の朝日新聞朝刊2面に「『北朝鮮支援の核施設』 シリア空爆でイスラエル首相」という見出しの記事が掲載された。本文をここに引用する。
2月に来日したイスラエルのオルメルト首相が福田首相と会談した際、昨年9月にイスラエル軍が空爆したシリア国内の施設が、北朝鮮の技術支援を受けた建設中の核関連施設であるとの見方を伝えていたことがわかった。イスラエル政府は空爆の事実だけ認めているが、標的とした施設の種類については明らかにしていない。同政府首脳が外国政府に「核施設」との見方を示したことが明るみに出たのは初めてだ。
政府内には「事実は確認できないが、首脳会談という公式の場で伝えられた意味は大きく、信憑(しんぴょう)性は高い」(外務省幹部)と受け止める一方、「イスラエル側が都合のいい部分だけを伝えた可能性もある」(別の幹部)との見方もある。
初めて? ちょっとあきれた。これはFACTAの昨年12月号(11月20日発売)で外交ジャーナリストの手嶋龍一氏がコラムで「小麦と『アサドの核』と北朝鮮」と題して書き、さらに直近の4月号(3月20日発売)で載せたゴードン・トーマス氏がFACTAに寄稿したスクープ記事「『北朝鮮の核密輸』をモサド暴露」を下敷きにしている。
それを首相官邸か外務省にあてて確認したという記事にすぎない。パクリを隠して、さも一から取材したかのように書いているが、書いた記者と載せたデスクには、恥を知れと言いたい。
しかしながら朝日のこの記事は、英国の保守系高級紙デーリー・テレグラフ(4月2日)に転載され、トーマス氏の目に触れた。彼から以下のメールをいただいた。
I was delighted to see that the Japanese daily newspaper, Asahi Shimbun, has picked up our exclusive story on the raid in Syria. The details are splashed all over the UK press (as an example, Wednesday April 2nd, Daily Telegraph, page 18), as well as in the Israeli newspapers and several on the continent. Alas, none of them cite Facta as the original source for breaking the story - though they make good use of the information in that article.
テレグラフ紙は引用先を明らかにしているのに、朝日はもとの情報源を明らかにしていない。だから、トーマス氏の嘆きと怒りを招くことになった。FACTAはこの記事の掲載前に、日本でも裏づけ取材を行っている。その過程で、イスラエルが昨年12月にオルメルト首相の訪日を要請、日本側の都合で延びてようやく実現した2月27日の福田・オルメルト会談では、予定の10分を15分も超過してイスラエル側が説明したことを確認している。それを今頃、のこのこ行って「あの話、本当ですかね」と聞いて、鬼の首を取った気でいる。お粗末の限りだ。
もちろん、イスラエルはブッシュ政権の中東政策およびライス外交に不満で、日本を介してワシントンに警告を発しようとしたのだろう。そうした読みのないこの朝日の記者は、FACTAの中身がすでに永田町や霞が関で常識化していることをご存じないのだろうか。
朝日に抗議を申し入れるとともに警告を発しよう。
無断のパクリを反省しないような記者に未来はありませんよ。朝日新聞の国際的声価も落ちる。トーマス氏は大きなリスクを冒して、スクープを日本に寄稿したのだ。記事を読めば分かるように、この記事にはトーマス氏のモサド(対外情報機関)人脈が生かされている。それを気楽にパクって引用先を明示しない礼儀知らずの二流記者は、ルール違反こそもっと大きなリスクであることを一度思い知ったほうがいい。
海外報道について愛読者のご注文
創刊以来の読者から「海外にも鋭い目が欲しい」という厳しいご注文をいただいた。
「最近のFACTAを見ていて気になっている点がある。それは国内の出来事に対しては厳しい視点で真実をえぐっているのに対し、特に欧米に話が行くと途端に盲信するような傾向が見られることである」
そうご指摘のうえで、前号の「排出権取引で『泥縄』経産省の凋落」と「トヨタ脅かすGMの『環境対策車』」、さらに「泥仕合で浮かぶオバマの『死角』」の3本の記事の一部について、FACTAも世間の常識にとらわれているのではないかと批判している。
排出権(量)取引の記事について、IPCCの第四次評価報告書に異論のあることは承知していますが、まるで天動説に対し地動説を主張するガリレオのような全否定論者に弊誌は与しません。
ブッシュ政権下で政治的に否定論を主張した学者の研究も政治的で穴だらけだったからで、この読者の方が指摘するような、CO2が元凶ではなくて都会のヒートアイランド現象にすぎない、と断ずる主張に正直賛同できかねます。
弊誌が神学論争ともいうべきこうした科学論争に踏み込まないのは、欧米を妄信しているからではありません。弊誌が科学専門誌ではないからです。さらに現象学的にいえば、とりあえず「カッコにくくっている」からです。
しかし、温暖化ガス規制がIPCCの評価報告書を土台に動いていることは誰も否定できません。我々が批判したのは学界の主流がいずれかではなく、欧米の温暖化ガス規制に比べ出遅れた日本が「戦力の逐次投入」のような場当たり的な譲歩による「戦略なき戦略」のせいで、国際社会で孤立する恐れがあることです。その元凶である経産省を批判することが、国際的視点の欠落とは思っておりません。
編集長はこの記事の筆者ではありませんが、日本エネルギー経済研究所の有識者懇談会にも参加しており、エネルギー戦略と一体化した環境戦略の必要を常日ごろ痛感しています。
トヨタのハイブリッド車が環境対策の万能薬でないことは誰しも承知のことでしょう。プリウスが省エネになるかならないかを論じるのは本誌の使命ではないと考えます。
それに対抗するGM戦略車も、窮地の米自動車企業の戦略見通しを語ったビジネス記事であり、環境の救世主になるという視点から書かれたものではありません。この読者の方のご指摘は、記事の趣旨とはずれていると思います。
泥仕合オバマ対ヒラリーは、日本の死命を握る米国の大統領が誰になるかを占う意味で必要だと考えています。日米安保同盟にかかわるからです。この壮大なマラソンレースはどう取り上げても一面的になりますが、どうせ日本人は投票できない、と無視するのはいかがかと思います。
FACTAが海外にどんな目を向けているかは、今号の「胡錦涛訪日の『危ない橋』」や「『北朝鮮の核密輸』をモサド暴露」の二つの記事によってお分かりかと思います。国内はおろか海外でもこうした記事をご覧になったことがありますか。これは純然たるスクープです。
対象を絞りこみ、厳選された誰も知らないディープな情報に従って書くのがFACTAの基本で、網羅的だが薄口の誌面をめざしていないからこそ掲載できる、と弊誌は信じています。
そうした基本的スタンスをお汲み取りいただければ幸いと存じます。とはいえ、貴重なアドバイス、今後ともお寄せくださるようお願いします。個々の記事の切磋琢磨には一層励むつもりですから。
NGNという羊頭狗肉――「NTTの自縛」のススメ
FACTAが4月号(3月20日発売)に掲載した「『姑息なゆで蛙』NTTの人事問題」の筆者は誰かと、NTTがいろいろあて推量しているらしい。聞くところ、まったく見当違いのようだが、早い話が天下のNTTがメディアに対しスパイを仕掛けているようなものだ。無駄な足掻きというほかない。
そのNTTが今日(3月31日)からNGN(次世代ネットワーク)の商用サービスを開始する。とりあえずは東京、大阪、神奈川、千葉、埼玉の一部地域である。東京23区、大阪の「06」エリア、東日本の県庁所在地や全国の政令指定都市でサービスを始める09年3月末が、実質的なスタートだろう。
まだテスト版だからそう無理は言えないが、しょっぱなからサービス内容は貧弱で、これで次世代かと首を傾げたくなる。サービスの名称自体「フレッツ光ネクスト」と、現行の光回線をつかった「Bフレッツ」と見分けがつきにくい。
NGNに移行するBフレッツ利用者は、新たな自宅内工事も必要でなく、料金も戸建て月4100円、マンション月2500~3500円の料金も据え置かれる。高速ネット接続の通信速度もBフレッツと同じである。
何が違うかといえば、月200円の追加料金を払って毎秒数十メガビットの速度保証サービスを受け、パソコンでハイビジョン映像の配信が可能になることぐらいだ。パラボラアンテナと薄型テレビで地上波デジタルやBSデジタルを受信している層にはほとんどメリットがない。VOD(ビデオ・オン・デマンド)を高画質で見ることができるといった程度でどれだけとびつく顧客がいるだろう。
将来は地デジも配信する予定で放送各社と交渉中とはいえ、あとの目ぼしいサービスがハイビジョン・テレビ電話と高音質電話程度では、NGNという名が泣く。まったくの羊頭苦肉である。
NGNについては、06~07年にIP電話の大規模な通信障害が起きた際、その排他性と技術的な脆弱性をFACTAは批判してきた。チョウチン記事の洪水のなかで、数少ない批判記事だったと思う(2006年9月号「『次世代ネット』の大風呂敷」、2006年11月号「NTT東『ひかり電話』の陥穽」)。
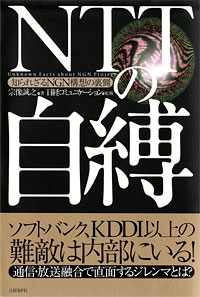 さて、すっかり書評が遅れてしまったが、日経BP出版センターから2月に出版された『NTTの自縛~知られざるNGN構想の裏側』(1800円+税)は、NGNの貧弱さの裏にNTTの宿痾である病根が巣食っていることを抉り出した好著である。
さて、すっかり書評が遅れてしまったが、日経BP出版センターから2月に出版された『NTTの自縛~知られざるNGN構想の裏側』(1800円+税)は、NGNの貧弱さの裏にNTTの宿痾である病根が巣食っていることを抉り出した好著である。
筆者は昨年まで、専門誌『日経コミュニケーションズ』にいた宗像誠之記者(1月から日本経済新聞産業部に出向)である。よく取材してあり、凡百のNTT礼賛記者には書けない本である。
NGNは昨年のフィールド・トライアル中から目新しさのない点が気づかれ始めた。『自縛』でも、こんなNTTグループ関係者の証言を載せている。
「仕事で関係のある企業ユーザーや、大学の教授といった有識者をショールームに連れていったが、いつも憂鬱になった。見学が終わるとほぼ必ず、『これって今のIPネットワークやフレッツでできるものだよね?』って聞くわけ。まったくそのとおりで、NGNの何が新しいか答えられない」
自縛とは、電話事業を独占していた旧電電公社時代に染み付いた「電話屋」的価値観だという。次世代といいながら、前世代の電話独占に回帰するしか能がない。新たな通信のヴィジョンなぞ望むべくもないことが、発想の貧困を生んでいることに本人たちが気づかない。
『自縛』によれば、NTTグループのある幹部が
「誰も展望がないまま走り出した。NGNの肝心の中身はからっぽのまま構築は進んでいる」
と漏らすほど重症なのだ。そのあげくに、批判記事の筆者探しなどあきれて口がきけない。『自縛』の筆者も彼らにはペルソナ・ノングラータ(好ましからざる人物)なのだろうか。念のため言っておく。この筆者はFACTAに寄稿したことはない。ただ、真面目に取材すれば同じ結論になるというだけのことだ。
電源開発とTCIの電話交渉決裂
 講談社の週刊現代元編集長、鈴木章一さんから、いま手がけている「セオリー」シリーズの単行本が送られてきた。「もの言う株主ヘッジファンドがやって来た」(税込1890円)である。
講談社の週刊現代元編集長、鈴木章一さんから、いま手がけている「セオリー」シリーズの単行本が送られてきた。「もの言う株主ヘッジファンドがやって来た」(税込1890円)である。
筆者の一人の名をみてはっとした。W・G・ザイフェルト――ドイツ証券取引所の元トップである。ロンドン証券取引所(LSE)の買収という大胆な試みが成功目前で、英国のファンド、TCI(ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド)の逆襲にあい、辞任に追い込まれた人物だ。まさに敗軍の将、兵を語るの本である。
TCIについては、昨年5月号(4月20日発売)の「企業スキャン電源開発」で、雑誌としてはもっとも早く特集した(TCIのクリス・ホーン代表の写真探しに苦労したほど)のを皮切りに、そのアジア代表、ホー氏との会見、さらにTCI排除に動こうとした経産省の狼狽振りまで連打したから、ご存知の読者も多いと思う。
正式の発売日は今日、つまり3月25日である。いの一番に送ってくれた鈴木氏に感謝しよう。早速、読み始めたが、ああ、これかと思った。失意のザイフェルトがようやく知人の大学教授と共著で内幕話を書き、それに「イナゴの来襲」というタイトルをつけたことは、取材で聞いていた。まさにその「イナゴの来襲」Invasion der Heuschureckenの翻訳である。
負けた側だから、当然、TCIには恨み骨髄。ファンドを「イナゴ」と断じるあたり、憤懣やるかたない怒りが現れている。中身については、ここらでお預けにしよう。次号のFACTAの書評コラムで同書を取り上げることにしたからだ。もしご興味のある方がいたら、赤い装丁なので書店で手にとってみてください。
鈴木氏にしてみれば偶然かもしれないが、この出版、絶妙のタイミングだったかもしれない。というのはこの週末、TCIのホーン代表と、日本で攻勢を受けている電源開発の幹部が電話で交渉し、ホーン氏側の妥協案を電源開発(Jパワー)がことごとく蹴って決裂したからだ。
電源開発のこの強硬な非妥協的姿勢は、裏にいる経産省のゼノフォビア(対外恐怖症)を反映したものだろう。ということは、これだけ日本株が外国人投資家に売られて、日経平均が一時1万2000円を割っても、経産省はまったく懲りていないということだ。
株式会社のガバナンスの原理を否定する北畑“優等生”次官は、やはり金融庁や東証の危惧などものともせず、TCIが宣した20%までの電源開発株買い上げについては、5月まで時間稼ぎをしたあげく、外為法をタテに拒否する気なのだろう。
NECエレクトロニクスの大株主である米国のファンド、ペリー・キャピタルが提起したNECの「親子上場」問題でも、NECの矢野社長は感情的になって、ペリーの提案に耳を貸さないどころか、会おうともしないが、これまた利害相反の議論に鈍感な経産省の姿勢を反映したものだろう。
ハゲタカの次はイナゴ。ザイフェルトの本は、彼ら“攘夷派”の意固地の火に油を注ぐかもしれない。しかしキース・ジャレットのジャズピアノを愛好するザイフェルトは、ドイツの古きよき時代の温もりに執着し、名士の座から滑り落ちた腹いせを隠さない。それを承知で割り引きしながら読める読者は日本にどれくらいいるのだろう。ま、当事者能力をとうに失っている電源開発の幹部や社員は、わけもわからず溜飲を下げるだろうが……。
この本をどう判断するかは、読者にとっても試金石かもしれない。
キャスター役も登板します
お問い合わせがありましたので、お答えいたします。昨年12月からBS11の毎週金曜「インサイドアウト」でキャスター役をつとめておりますが、約1カ月お休みしていました。最初は風邪をこじらせたのですが、入院するなど全快に思いのほか時間がかかりました。
ご心配かけて恐縮です。ブログもほとんどお休みだったのですが、いかんせん声がでなくてはキャスターはつとまりません。その声もようやく元に戻りました。
というわけで、本日午後10時からの「インサイドアウト」でキャスターを再開します。お招きするのは、小泉・安倍政権の知恵袋だった財務省出身の高橋洋一・内閣参事官(4月から東洋大学教授)で、お題は「新銀行東京」です。ちょっと血が騒ぐテーマ。お楽しみに。
新銀行東京の経営破綻に最初に警鐘を鳴らしたメディアがFACTAだったこともあり、私自身も現実に取材対象としていたこともあって、キャスターの立場を踏み越えてしまうかもしれません。
高橋氏とは90年代の大蔵省証券局、理財局時代からの知り合い。郵政改革や政府系金融機関の整理で霞が関にその名を轟かせた異色官僚ですが、彼が金融検査部で不良債権の山と格闘した時代や、破綻した長銀の頭取の裁判に証人として出廷したことも知っています。関東財務局部長の時代には、新銀行東京の立ち上げ期と重なり、このテーマには最もふさわしい人材でしょう。議論が盛り上がるといいな。
ところで、最新号のFACTA。霞が関の官僚OBの方からお褒めのメールをいただきました。「企業スキャン新日本製鉄」です。アルセロール・ミタルの合併以来、海外勢の脅威に対抗する新日鉄の戦略を正面から批判したものです。要点は4月に会長に就く三村明夫社長の戦略は、グローバル化の大波に対し国内カルテルに閉じこもろうとする姑息なもので、中国・インドなど新興経済の台頭でダイナミックな変化を遂げる市場のなかで真に対抗できるものではないというものです。いただいたメールは
「新日鉄の記事を読みました。いいですね。Aさんも日本経済を悪くしたのは新日鉄、それも三村さんだと言っています。私も同感です」
という感想でした。市場の閉鎖性とともに、今後の議論のたたき台になることを期待しましょう。
もうひとつは「しっかりせよ皇太子殿下」に対し違和感を感じたとのメール。「雅子妃に対する悪意に満ちた文章で、社会的に活躍する有能なキャリア女性は嫌いだという男性の本音ばかりが透けて見えます」とあり、5項目ほどご指摘いただきました。
記事へのご批判は貴重な反応として承りますが、ともすれば感情的になる皇室論議に、一石を投じる記事そのものを「悪意」と退ける姿勢には同意しかねます。この記事を書いたライターに、雅子妃への悪意やキャリア女性に対する嫌悪があるとは思えません。中高年の男性が「有能なキャリア女性」に嫉妬するという考え方のほうが、よほどステロタイプかと思われます。弊誌は今後とも、もっと自由に皇室問題を論ずべきだと考えています。
ご意見・ご批判お待ちしております。
4月号の編集後記と「ブックマーク」リニューアルのお知らせ
読者と編集部がネットの最新情報を共有するためのサービス「FACTAブックマーク」をリニューアルしました。サービス開始から1年以上経ちましたので、お寄せいただいたご意見・ご要望を参考に、いくつかの機能を変更しました。
ご購読者でもオンライン会員登録がお済みでない方や、購読を検討中の方にも雰囲気が伝わるように、一部のページをフリー公開にしましたので、ぜひ覗いてみてください。ポータルサイトとは一味違ったニュースが並んでいますよ。
以下はFACTA最新号(4月号、3月20日発行)の編集後記です。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
茫と烟っていた。南新宿の高みから遠望した東京の空。眼下の御苑の濃い緑に、綿毛のように浮かぶ白と薄紅は、梅の花だろうか。病癒えて退院する日、足慣らししようと、コートの襟を立て、マフラーを巻き、マスクまでして歩きだしたが、あまりの陽気に阿呆らしくなった。眩しさに目を細めるモグラのように、行き交う人の群れをぼんやり眺める。
▼少し休もう。2世紀前のドイツの詩人ヘルダーリンが発狂した後の偶成に「春」という詩がある。
ひとつの家が空高く築かれて輝くとき/野は人のなかにひろがり/道は遠く走って/あたりを眺めやる者がひとりいる……
アポロの霹靂に打たれたような往時の緊迫はない。すでに彼は天才の抜け殻でしかなかったが、この素人のように平易で澄明な言葉は、無残なだけに切なくて忘れ難い。
▼亡くなった川村二郎氏(50ページ「ひとつの人生」参照)の訳詩集は、ヘルダーリン後半生の詩を3篇しか載せていない。「春」はなかった。なぜこの哀しいカデンツァを外したのか。枕頭にその薄い文庫本を置き、部屋のカーテンを引いて眺めた。薄暗がりのなかで、都会は遠くの潮騒のように退いていく。言葉は追わない。好きにページを開き、ただ目でたどるだけ。そういう自堕落な読み方を、この十年来忘れていた気がする。
▼もう急ぐまい。ふらりとHMVに立ち寄って、久しぶりに音楽CDを衝動買いした。タンザニア出身の女性ジャズ歌手リャンビコ。まったく知らない人だが「ニーナ・シモンに捧ぐ」の惹句が効いた。冒頭の曲は40年前に聴いたDon’t let me be misunderstood(邦題「悲しき願い」)。ああ、そんな時代があった。不覚にも身が震える。悲傷はいきなり訪れ、いきなりまた去る。芭蕉はそういう瞬間をよく知っていた。
誰人か菰著きています花の春
日経ヴェリタス創刊、絶妙のタイミング
しばらく休んでいたが、今日からブログを再開する。
16日に私の古巣、日経新聞が週刊のタブロイド投資専門紙「日経ヴェリタス」を創刊した。先輩面をするつもりはないが、編集長やデスク陣、記者は後輩にあたるから、ひとまずおめでとうと申し上げよう。
それにしても、この創刊、絶妙のタイミングだ。創刊号の頭見出しは「それでもニッポンを買う」である。編集部はよほどコメディー感覚があると思える。創刊翌日の株式市場がどーんと急落、日経平均株価が一時1万1700円を割り込んだことはご存じの通り。はたして、ヴェリタス創刊号の読者はこの見出し通りの行動をしてくれるかしらん。
野村編集長も、荒川筆頭デスクも、創刊号がどんな評判かと鵜の目鷹の目だろう。私も20年前にこのヴェリタスの前身、日経金融新聞の創刊に立ち会ったから、気持ちはよく分かる。だが、市場は冷酷なものだ。87年10月1日創刊の金融新聞は、2週間後にブラックマンデーに遭遇した。創刊のユーフォリア気分など吹っ飛び、最悪の船出となって、その後も長い低迷を脱せなかった。ヴェリタスは同じ歴史を繰り返さずに済むだろうか。
しかし、1面サブタイトルの「JAPAIN超えJAGAIN」の駄ジャレには苦笑せざるを得ない。初っぱなから、英国のエコノミスト誌の日本特集の見出しを安易に借用するなど、志が低すぎはしないか。タイトルにどこかの雑誌さながら「真実」という意味のラテン語を使うなら、それなりの気概を見せて欲しかった。
創刊号を見れば力量が分かる。編集部も先週の相場から逆境の船出になることは予測していて、それをあえて「逆張り」で目を引こうとしたのだろう。
その冒頭のエピソードで唖然とした。ダヴィンチ・アドバイザーズの金子修社長と、モルガン・スタンレーの日本不動産部門のフレッド・シュミットが交わした、日本の不動産にもっと投資するという会話である。いたいけなヴェリタスの記者・デスク諸君、彼らがどんな評判か、これまでどんな行状だったか、ご存じないのか。
彼らのポジション・トークを「日本買い」の根拠にするなんて、プロには笑われますよ。市場の裏を知るジャーナリストと17日にその話題がでて、彼らのような人種しかネタ元でないとなると、ヴェリタスの前途はまことに洋々たるものだ、と大きなお世話だろうが心配しあった。
日曜にもかかわらずFEDが利下げし、ベアーをJPモルガンが買収する事態である。またもや、日経お得意の気休めのトランキライザーなのか。小手先の楽観論は市場に通じない。「危機はすぐ終わる」の日経のマントラは、失われた10年に何度外れたかご存じか。暇人のアームチェア・インベスターに売り込む週刊紙を志しているわけではあるまい。
こういう紙面なら、金融新聞と同じく、スクープがヴェリタスに載る可能性はなさそうだ。日経本紙に競り勝つような紙面では、大事な本紙読者が痛むか。
だが、今後もスクープなしの、こういう「アカルイ未来」的紙面で、どこまで読者を維持できるかは未知数だろう。編集部諸兄の健闘を祈る。