EDITOR BLOG

河野洋平の“後継者”牧島かれんとは――地盤継承の新しいカタチ
政治ほどリスキーな商売はない。何かを実現するため議員バッジを胸につけようとする方々には「なんと奇特な」と賛嘆するほかないとはいえ、興味津々である。非政治的な人間と自認しているから、自分で政治に身を投じようと考えたことは一度もない。だが、目前に迫った総選挙で身近な人が何人か立候補に名乗りを挙げた。
そのひとりが、引退を表明した衆議院議長、河野洋平氏から後継を指名された早稲田大学公共政策研究所客員講師、牧島かれん(可憐)さんである。彼女がアメリカ留学から帰国して、大学で助手や講師をつとめ出して以来、ご縁がある。国際基督教大学(ICU)大学院行政学研究科で今春博士号を取得されたが、それまでのあいだ、FACTAの創刊準備やトークショー「FACTAフォーラム」などでお手伝いしてもらった。
彼女が政治家志望であることは聞き知っていた。それでも、血縁でもなく地盤でもない神奈川17区で、河野議長がいきなり後継者に彼女(横須賀出身)を指名するとは、後援会も目を丸くしたろうが、私にもちょっとした驚きだった。「河野王国」と言われる磐石の地盤が小選挙区で二分され、議長の長男、河野太郎氏がすでに神奈川15区の地盤を継いでいるという事情があったにせよ、「地バン看バンカバン」の3バンが不可欠とされた従来の継承とは別の、新しいモデルが出現したかに見える。

河野議長と並んで会見した翌日の9月19日、河野派を継承している麻生太郎氏の個人事務所(東京・赤坂)を牧島さんが訪ねた折に、彼女にその経緯と抱負を聞いてみた。
自民党総裁選挙も終盤で、最有力候補で幹事長の麻生氏のスケジュールは分刻み。この朝も「みのもんたの朝ズバッ」に出演したあと、有楽町の外国人特派員協会で他の候補4氏と共同会見に臨む予定で、合間を縫って二人並んで写真を撮りながらの時間だった。
牧島「きのう議長と記者会見させていただきまして」
麻生「あ、後援会でも決まったんでしょ」
牧島「役員会に途中で呼んでいただきまして(後継が)決まりました」
麻生「前の息子のときは紛糾して3時間ね(笑)。おれなんか散々待たされて(笑)。中選挙区から小選挙区への移行で、太郎を出せ、とかえらい騒ぎで……。でも、今度は『おれが決める』とえらい突っ張ってたな。で、あなたに決めたんでしょ」
牧島「はい、議長がご意志を通されて」
麻生「だいたい、(政治家ってものは)辞めるときは人に相談せずに決めるもんなんでね。(河野氏が1995年の)総裁選に出馬しないと言ったときもそうだった。こっち(派閥)は選挙する気だったんだが……。あなたもね、何十年も先になるかもわからんが、辞めるときは、最後は自分で決めるんですよ」
牧島「はい」
麻生「結婚するときは、母親に相談したほうがいいけど(笑)」
牧島さんの政治家志望は、父、功氏の影響が大きいと思える。功氏は学生時代に地元政治家、小泉純也氏の選挙運動に参加して、大学卒業後にその秘書になった。が、66年に純也氏がガンで急逝、ロンドンから帰国した息子の純一郎氏の弔い合戦は敗北に終わった。72年に純一郎氏が当選したのち、74年から独立、75年に横須賀市議に自民党公認が取れなかったにもかかわらず当選した。市議を3期務めたのち87年に県議に当選、98年に参院選神奈川選挙区から自民党候補として出馬した。
かれんさんが河野氏の知遇を得たのはこの選挙から。河野氏に父の選対本部長になってもらい、それからは小田原地域が父の恩人の地盤であり、「第二の故郷」になったという。当時は大学3年で、候補者の娘として17小選挙区を回り、選挙の舞台裏をつぶさに見た。しかし金融不安と恒久減税をめぐる橋本龍太郎首相の迷走などで自民党が惨敗、神奈川選挙区でも2人が共倒れとなった。落選した父はその後県議に戻り、2005年から県会議長をつとめた。
「98年参院選では結果を出せなかったが、応援していただいた方々に申し訳ないという気持ちと、応援に感謝する気持ちの両方が残りました。どうやって恩返しできるかと考えました」という。まず追求したのは「学問としての政治」である。彼女はICU教養学部社会学科を卒業後、米国のジョージ・ワシントン大学大学院ポリティカル・マネージメント大学院に留学し、修士号を取る。
帰国してからは東京純心女子大の講師や桐蔭横浜大学の助手をつとめ、母校ICUの大学院で博士号を取った。博士論文は「レトリカル・リーダーシップとアメリカ大統領――政治的コミュニケーションとその制度化」というタイムリーなテーマ。一種の選挙論で、過去の米大統領選挙でマスメディアをつかって発せられたメッセージの分析である。この分析ツールを使ってオバマ対ヒラリー、オバマ対マケインの戦いを分析したら面白そうだ、と思っていたが、彼女は「学問」から「実践」に軌道を変えた。
その契機は博士論文を仕上げて、早稲田大学の公共政策研究所の河野洋平特別プロジェクト「戦後内閣の軌跡」に参加したことにある。早稲田大学の特命教授に就任した河野氏らと今秋から一緒に講義することになったが、9月に議長サミットを終えた河野氏に呼ばれ、「実践としての政治にかかわる意思はあるのか。よく考えてください」と言われた。河野氏の目には、10年前の女子大生から彼女が成長したこと、自民党が逆風に立つなかで時代を担う人材が必要であること、そして父の選挙を経験して政治がどんなものか分かっていることなどが、白羽の矢を立てた理由らしい。「自民党が新しい方向に向かう最中だし、日本の社会も重大な転機を迎えていると思いました」と彼女も決断の心境を語る。
彼女は地盤の継承でなく、理念を継承する。だが、その理念とは何か。宮沢内閣の官房長官だった河野氏が出した従軍慰安婦をめぐる談話は、「河野談話」として今でも日本の戦争責任論議の的になっている。後継者としての彼女は、反中、反韓ナショナリストの標的になってきた河野氏のリベラリズムを継承するのかと問われるだろう。そして「自民党をぶっ壊せ」と呼号した小泉改革をどう評価するかも試金石だろう。
「創造的破壊と言われた時代でしたが、日本の魅力や底力は十分に生かされていません。女性の力を生かし、自然や人々と共生していくことを通じて、それをもう一度引き出していく努力が重要だと思います。日本の魅力を再定義し、地域を再生したい。破壊や(暴力的な)資本主義よりも、歴史や文化遺産が次の世代につながっていく国、中庸でゆっくりと合意を形成する国づくりをしたい」
たぶん、主張するだけでなく、誰もの意見を聞き、穏やかに説得し、話し合うプロセスを尊ぶことに、本来の保守の意味があると言いたいのだろう。それがどう肉付けされ、どう実現されるかは、これからになる。
10月号の編集後記
FACTA最新号(10月号、9月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
ロードムービーが好きだ。荒寥とした赤茶けた大地をどこまでも走る無人の道。錆びた車のサイドミラーに蒼穹と土埃が映っている風景が、なぜか無性に懐かしい。アメリカの大平原を独りで疾走した経験なんてないのに、不思議とデジャヴ(既視感)に襲われる。『イージー・ライダー』『ペーパー・ムーン』『パリ、テキサス』『アメリカ、家族のいる風景』『イントゥ・ザ・ワイルド』……挙げていけばきりがない。
▼行き先もなく連れもない旅。やみ難いほどの憧憬を覚えるのは、放浪癖があるからだろうか。民俗学の祖、柳田國男にも生来その癖があったらしい。幼時ふっと神隠しにあい、近所総出で捜索したら、隣村をすたすた歩いていたという。遠方に親戚がいると空想して歩き始めたというから、トランス(入眠幻覚)に陥っていたのだろう。実は私にも経験がある。5歳で家出した。
▼何が気にくわなかったのか覚えていない。ただうつむいて歯を食いしばり、ひたすら西へとぼとぼ歩いた。見慣れた風景が異様な光を帯びだした。傾いた電信柱のブリキ看板や、木のゴミ箱に端座するネコ、リヤカーの轍に光る水たまり、曇天の風に不気味に鳴る電線――今も鮮やかに脳裏に浮かぶ。不意に悟ったのは、風景が心の内景であることだった。帰心ある限り人はどこにも到達できない。物自体は不可知なのだ。幼いカントは、そこで引き返した。ヘンゼルとグレーテルのように、記憶のパンくずを拾って。
▼アレクサンドル・グロタンディークという天才数学者がいる。ユダヤ人収容所を生き延び、戦後は代数幾何を根底から書き直そうと、ユークリッド『原論』の現代版に挑んだ。91年、世間も家族も捨ててピレネー山中に消えた。中世の隠遁者のように誰にも会わず、消息もない。生きていればいま80歳。彼はついに物自体に触れたのだろうか。
ブログ再開 オーマイガッ!
最悪のタイミングである。15日のリーマンの連邦破産法申請は、FACTAにとっては締め切り後から印刷、発送までの「空白」期間に相当し、手も足も出ない。リーマン社員もウォール街もそうだろうが、身売りが成功するかどうかは直前まで読めなかった。次号は到底間に合わないと思い、次々号へ見送りと泣く泣く決めたのが、裏目に出たようだ。
それでも直前、頼みのバンカメがメリル買収に急転、見捨てられたリーマンが白旗、という急展開には、やはり歯ぎしりである。3月にベアー・スターンズが破綻して、JPモルガンに吸収合併された際の分析で、資産の傷み具合ではリーマンとベアーにほとんど差がないことを指摘し、前号では最大手メリルも危ないことを指摘してはいたが、正直、崩壊がこれほど早いとは想定外だった(表は2008年5月号「信用収縮の次は『ドル危機』」に掲載した米大手金融機関保有有価証券の“毀損”状況)。
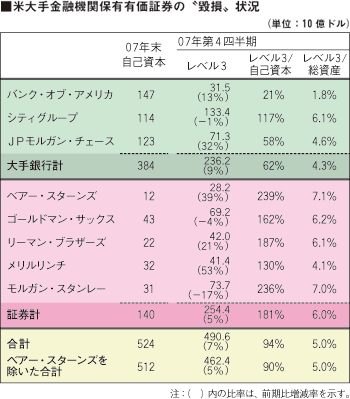
たぶん、リーマンにはバンソウコウ的な救済策が発表され、そこで株価は辛うじて踏みとどまると見ていた。それでもやはり金融市場の不安は消えず、再びさらに一層大きな津波に見舞われるだろう。小康状態でも不安の根が残っていることを論証し、第3の危機を予測するのが次に予定していた記事の狙いだったが、事態の予想外の急転で、タイミングを逃したのかもしれない。
悔しい!の一語に尽きる。次号はただでさえ、自民党総裁選が刊行日2日後の22日という不利な条件だった。選挙は水モノだけに「麻生総裁」を100%決めてかかるわけにもいかず、こちらはこちらで雑誌編集は難しかったのだ。
“埋蔵金男”の高橋洋一・東洋大学教授には先日、ジャーナリズムの近視眼を指弾されたが、うーむ、これがデッドラインのある世界の辛さだ。見通しが外れることも覚悟で、えいやっと飛ばないと、形にならないのだが、失敗したらそれこそ惨めの極になる。前門の虎に後門の狼、二重苦のなかでの賭けはどうやら一方はうなくいかなかった。
16日午前の日経平均株価は1万2000円を大きく割り込んで618円安。午後はどうなることやら。次は保険の巨人、米AIGの経営危機説が流れて、ポールソン財務長官らは休む暇もない。
こちらも次々号では雪辱戦を期さないと。
9月号の編集後記
FACTA最新号(9月号、8月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
棺を覆いてのち評価が定まらぬ人がいる。8月3日、89歳で亡くなった作家アレクサンドル・ソルジェニーツィンもそのひとりだろう。迷った。本誌の「ひとつの人生」に追悼記を載せるかどうか。「Gulag」というロシア語、「Archipelago」というギリシャ語を耳にしたのは彼の大作のおかげだ。でも、『収容所群島』と訳されて、抜き難い違和が残った。
▼archiは「原」、pelagoは「海」、ギリシャの多島海、エーゲ海のことである。あの果てしない殺伐たるシベリアに点在する収容所の見えざる海図。弧状に連なる日本列島のイメージではとても代用できない。類を絶した暗鬱な囚人の群れと、無数の粛清は翻訳不可能なのだ。出版されればソ連が崩壊し、世界が変わると言われた『収容所群島』は、本になったら退屈で何も起きなかった。
▼ロシア人も彼を忘れた。亡命したソルジェニーツィンは、西欧でもてはやされる反体制知識人の役割を拒んだ。祖国の知識人への呪詛。その孤立を金甌(きんおう)無欠と称えるのか、傲岸不遜と難じるのか、狷介佶屈(けんかいきつくつ)と恐れるのか。ソルジェニーツィンの暴露の意味を解ける人が日本にいるとは思えなくなって、倉卒な追悼記の掲載は見合わせることにした。
▼北シベリアにノリリスクという極北(北緯69度22分)の都会がある。ニッケルで知られるが、30年代、グラーグの囚人が酷寒のもと夥しい犠牲を払って築いた鉱山町だ。そこで今春、モスクワのマーリイ劇場が公演した。世界初、ワシーリー・グロースマンの小説『人生と運命』劇場版である。60年に完成したこの傑作は、スターリングラード攻防戦と収容所を描いてナチズムとスターリニズムの同質性を暴いた。発禁・没収となり、著者は陋巷に死んだ。奇跡的に海外に持ち出されて81年に出版され、とうとうグラーグのネクロポリスで演じられた。死者の沈黙の上に、記憶もまた蘇る。
「解読! アルキメデス写本」のススメ
8月3日、熊本日々新聞に書評を載せました。本は素晴らしいのですが、紙面のゲラをみたら、小生の名前がやけに大きいのが恥ずかしい。アルキメデスさまに申し訳ないと思いました。
*****
『解読!アルキメデス写本羊皮紙から甦った天才数学者』
リヴィエル・ネッツ/ウィリアム・ノエル
吉田晋治監訳
(光文社2100円+税)

「パリンプセスト」(Palimpsest)という奇妙な響きの綺語がある。古い羊皮紙の字を消して上書きした再利用の古文書のことだ。日本流に言えば「襖の下張り」である。
ああ、あれか、と思ったのはウンベルト・エーコの『薔薇の名前』。アリストテレスの『詩学』の欠落した幻の後半が、どす黒く汚れた反古の巻物から浮かびあがる場面があった。本書はそのアルキメデス版、紀元前3世紀の天才が書いた未知の数学理論の解読という、つい最近の奇跡のような実話である。
謎解きだけで胸が躍る。第2次ポエニ戦役の籠城戦で『墨攻』のようにローマ軍と戦った軍師であり、裏切りで落命したアルキメデスの数奇な運命。写本の運命もそれに劣らず波瀾万丈で、コンスタンティノープルからパリ、アメリカへと転々として2200年を生きのびた。
それだけではない。この「裏張り」を透視するために、X線画像化技術、古文書学、文献学、数学などの知識を総動員した専門家チームが組まれる。本書は当事者の2人――写本解読と数学の専門家が、章を交互に分担して書いている。
このディアローグの手法は卓抜だ。数学一辺倒でもなく、歴史一辺倒でもないから、素人でもアルキメデスの実像を立体的に把握できる。研究者の応答に立ち会っているようで、解読の臨場感が高まり、読者は退屈しない。サイエンス本の傑作と言っていい。
アルキメデスといえば、浴槽で浮力の原理を思いつき、「エウレカ!」(分かった!)と叫んで素っ裸で飛び出した逸話で名高い。が、原典はそんな単純なものではないらしい。それどころか、幾何的な発見は驚異としか言いようがないものばかりだ。
ニュートンやライプニッツの微積分学に1800年も先んじて「可能無限」に達していたし、このパリンプセストにしか残っていない『方法』の断片で「実無限」を応用していたことも明らかになっている。けれども、彼の同時代人で何人がそれを理解できたのか。
アルキメデスは剽軽だ。エウレカの裸踊りは別として、論文でも引っかけや謎かけ、背理法やまわり道が大好きで、彼にとって数学は遊びなのだ。典型がこの「裏張り」解読の最大の成果である「ストマキオン」(腹痛)だろう。
三角形や不等辺五角形など14片を並べ換えて正方形にする「知恵の板」(タングラム)のことだが、解くのが難しいので「腹痛」と命名された。冒頭の断片しかないが、アルキメデスは何をしようとしていたのか。本書の筆者は、正方形になる組み合わせが何通りあるか数えること、という仮説を立てる。回転や置換を駆使する史上初の「組み合わせ」論。ここでもアルキメデスは、パスカルやフェルマーに先んじていたという。
意外に解は難しい。コンピューターのない古代では複雑な計算を必要とする。イタリアの古代数学専門家やスタンフォード大学、カリフォルニア大学に支援を仰ぐ。ついにコンピューターのアルゴリズムが考案され、解の1万7152通りが突き止められた。賞金100ドルだが、ほとんど無償の謎解きにみんなが夢中になった。
いつのまにか、現代がアルキメデスの術中にはまっていた。究極の遊戯。あなたも数学の快楽に叫んでみませんか。「エウレカ!」と。
消えたり現れたりのサイト――御巣鷹の夏Ⅱ
「御巣鷹山の日」8月12日が近づいている。7月20日号の編集後記に、映画『クライマーズ・ハイ』の公開にちなんで、その日の私を書いただけに、気になっていることがひとつある。
あの日のフライトレコーダーと日航123便の航跡を合体させたサイトのことである。亡き作家、藤原伊織から教えられて、そのあまりの生々しさに慄然とした。今でもリアルとは何かを思い返すとき、そのサイトでこの管制塔とコックピットの応答を聞いてみる。何度聞いても背筋が寒くなる。
だが、この生々しさは遺族ら関係者をいたたまれなくするとの批判があり、時々閉鎖されてしまう。とにかく機会があれば、この千万言を費やしても追いつけないものを耳にしてください。
http://members.at.infoseek.co.jp/tinsukou114/JAL123.swf
佐々木俊尚『インフォコモンズ』のススメ
 ルビの魔術に憑かれたのはいつごろだったろうか。単なる「読み」ではない。漢字の意味とルビの微妙な落差が、何か別の言語のような夢想に誘いこむ。
ルビの魔術に憑かれたのはいつごろだったろうか。単なる「読み」ではない。漢字の意味とルビの微妙な落差が、何か別の言語のような夢想に誘いこむ。
我が家の書棚には、酸性紙でぼろぼろになりかけた戦前の鏡花全集がある。20代で全巻を読み通したが、総ルビゆえに朗詠調で読めた。佶屈なのに流暢、古風でいてモダン、文語でありながら俗語、和文脈でいながら洋文脈、という変幻自在の文体になる。
これは恐らく和洋折衷の現代日本語のなりたち、その本質に根ざした言語の拡張機能と言えるもので、『インフォコモンズ』もその延長線上にある。
中間共同体(マジックミドル)、情報共有圏(インフォコモンズ)、過負荷回路(オーバローデットサーキット)、媒体(コンテナー)、情報洪水(インフォフラッド)、私的空間(パーソナル)、公的空間(パブリック)、個別・分散化(マイクロコンテンツ)……など、本書のキーワードにふられたルビは、鏡花の異空間と同じく幻想領域を仮構するからだ。
佐々木氏とはどこかの講演会でお目にかかったことがある。本書も講談社からゲラの段階で送っていただき、一読してから消化するのに時間がかかった。彼が本書で言っていることに異論はない。
検索エンジンやSNSなどが形成するバーチャルな幻想空間がどこへ行くかという問題意識は私も共有する。が、未知の宇宙に入るとき、どんな言語を媒体(コンテナー)とするかで、このルビの魔術が生み出す空間に立ち止まった。
たとえば暗黙(インプリシト)ウェブ――アマゾンの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」というのが典型で、ウィキペディア英語版によれば、「インターネットから拾い集めた個人情報を統合し、ひとつの人間行動の全体像に集約することを専門としたウェブ」だという。
2007年に誕生した概念だというからまだ日は浅いが、「暗黙」とはユーザーが明示的(エクスプリシト)に入力したものではないデータを組み合わせて、その人物の輪郭を絞り込んでいく。これを暗黙知と翻訳するのは飛躍があるが、explicitの裏返しのimplicitならなるほどと思う。これがルビの魔術である。
このサイトでも、暗黙ウェブのひとつである「アドウェア」の危うさをとりあげたことがあるが、知らぬまに進化を遂げているらしい。ヤフージャパンの強みが行動ターゲティング広告にあることは知っていても、英国の「ラスト・エフエム」のスクロブル機能――自分の好みの音楽だけを延々と放送してくれるFMラジオの実現などは、私も初耳だった。そこには当然、プライバシー情報をシステムに収奪されているという被害感が生じてくる。それが情報共有圏の最大の障害になるという立論は正しい。
佐々木氏はおそらく情報共有圏を「善導」することをめざしている。要点は、①情報がユーザーに再集約されること、②情報共有圏をともにする他人に対し、信頼(トラスト)だけでなく友情(フレンドシップ)を導きだせるようになることだという。信頼? 友情? ちょっと気恥ずかしい言葉が唐突に出てくる。直感的に言うと、ここでのルビは新しい異空間を想起する力を持っていない。
佐々木氏はニュージーランドのソフト開発者が打ち出した「ウェブ3.0」の定義「非集中化(デセントラライズ)した私」を引用しているが、これも現象学や精神病理学でいう「間主観性」とさして違わないと思える。19世紀的な自我の輪郭は、もう100年前からぼやけ始めていた。生物学者ユクスキュルの「環世界」を援用したハイデッガーの「世界-内-存在」がそのあかしだろう。情報の非対称性まで話を広げると、中沢新一みたいになってしまう。
ルビの魔術に話を戻そう。かつて黒丸尚というSF翻訳家がいた。東大法学部を出て、あの電通に入社したが、90年代に病死したと聞く。個人的には知らない人だが、彼が翻訳したウィリアム・ギブスンの「ニューロマンサー」は、私もP・Kディックの「ブラッドマネー博士」を翻訳していたころだからよく覚えている。黒丸氏もルビの魔術に耽溺していたが、そこに描かれた異様な未来像にぴったりだった。
データ交換の頻度を表示する地図をプログラムしてみよう。巨大なスクリーン状のひとつの画素(ピクセル)が千メガバイトを表す。マンハッタンとアトランタは純白に燃え上がる。それか脈打ちはじめる。通信(トラフィック)量のあまり、この模擬実験(シミュレーション)が過負荷になりかけているのだ。地図が新星化してしまう。
このSFは84年に書かれた。当時、トラフィックやピクセルは聞き慣れない英語だったが、今では珍しくもなんともない。電脳空間(サイバースペース)という言葉の発祥地となった作品であり、「攻殻機動隊」や「マトリックス」のアイデアの源泉はすべてここにあると言っても過言ではない。臓器移植で肉体をパッチワークした人間が蠢く未来の千葉と、発泡スチロールで埋まった黙示録的な東京湾は、「非集中化した私」の象徴といっていい。電脳空間から放逐された主人公ケイスは、リアルな肉体を呪う。
体など人肉なのだ。ケイスは、おのれの肉体という牢獄に堕ちたのだ。
「インフォコモンズ」のルビの宇宙は、実はこのギブスンの想像した暗い近未来を出ないのではないか。ギブスンはベトナム戦争の兵役を忌避して、カナダに亡命したアメリカ人である。彼の電脳空間とは、その逃避行の昇華と思える。祖国を捨てたがゆえに、おそらく自我の危機に陥った彼の夢想するユートピア、国家に代わる夢の共有圏(コモンズ)なのだ。
そこに信頼や友情が可能と思うのは、佐々木氏もユートピアンだからだろうか。
シンジケートコラム「時代を読む」 米住宅公社編
環日本海の地方紙10紙に配信していただいているシンジケートコラム「時代を読む」の順番が来て、7月26日(土)に一斉に掲載された。それをこのサイトに再録する。
今回は7月に入って信用不安の広がりから、にわかに焦点が集まったアメリカの住宅抵当公社、ファニー・メイとフレディ・マックを論じた。実は両社の危機について、最新号のFACTAは追いきれなかった。株価が急落したのは7月第2週の後半とほとんど最終デッドライン(締め切り)で、記事をつっこめない。月刊誌の宿命とはいえ、指をくわえてみているほかなかった。
だが、この端境期に勃発した信用不安は、天文学的な規模もなることながら、アメリカ経済の奥深く潜む病を照らしだした。経済ジャーナリズムとして沈黙するわけにはいかない。しかし、いかんせん、自分の雑誌ではカバーできないので、私が出演しているTBSラジオの早朝番組「生島ヒロシのおはよう一直線」や、BS11の「インサイドアウト」で取り上げさせていただいた。それでも、時間的制約もあり、いささかもの足りない。で、「時代を読む」のコラムの場を借りて、少し踏み込んで論じてみた。
仮題は――「沈む『資本の浮島』の転生」
ちょっと宮崎駿の「天空の島ラピュタ」のイメージだが、藤沢令夫訳のプラトン『国家』(岩波文庫)には、高層ビルの中継階のような牧場の図像が載っている。機動戦士ガンダムのスペースコロニーに似ているのが面白い。女神アナンケが回す紡錘状のはずみ車の絵もあるが、これまた祭りの夜店で見るようで懐かしい。そのイメージを思い浮かべながら、ご笑覧あれ。
*****
「エルの物語」をご存じか。映画化された人気漫画「デスノート」の引きこもり探偵「L」のことではない。プラトンの『国家』の最後に現れる戦士エルの話である。
彼は戦いで命を落とした。死体は腐らず、12日目に荼毘(だび)に付そうとしたら、にわかに生き返った。死後の世界を見てきたという。三途の川に似た「忘却の野」「放念の河」などもあったが、忘れ難いのは死んだ魂が集められる宙に浮いた島だ。
エレベーターのように、天と地からひっきりなしに魂が昇降している。空港ターミナルのような場所だが、その牧場で魂は7日間のトランジットを過ごさねばならない。
生前の悪行によって10倍の懲罰が加えられ、皮を剥がれて地獄落ちとなる者もいる。あとは、女神アナンケが回す巨大な紡錘の前でクジを引き、次の宿世を自ら選ぶ。
ありふれた臨死体験と言えば言える。誰しもイザナギノミコトやオルフェウスの冥界下りを連想するだろう。だが、この浮島、現代のアメリカのGSE(Government Sponsored Enterprises、政府支援法人)によく似ている。
7月中旬、GSEである住宅公社、ファニーメイ(連邦住宅抵当公社、FNMA)とフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社、FHLMC)が信用不安を起こし、株価が急落した。両社とも民間の住宅ローン専門業者からローン債権を買い取り、債券や証券化商品として機関投資家に売りだす大黒柱なのだ。
住宅ローン回収リスクを「政府支援」の保証で肩代わりして、ローン債権に流動性を与える仕組みだから、魂のふり分けに似た現代版の「アナンケの紡錘」である。
罪の重い魂が地獄に落とされるように、低所得者向けのサブプライムローンは埒外だったが、危機到来で買い取り基準を緩めて支えたのが裏目に出た。2社の資産は劣化し、大手投資銀行リーマンが「民間並み会計基準を適用すれば、両社合わせて750億ドルの資本不足」とレポート、「政府支援」の浮島が沈みかけて金融市場が青ざめた。
無理もない。「事実上の政府保証債」として米国債に順ずる信用力がある両社の社債発行残高は1兆6000億ドル、証券化商品を入れると債務保証額は5兆ドルに達する。
全額吹っ飛ぶことはありえないとはいえ、日本のGDP(国内総生産)を上回る500兆円以上が評価額低下の危機にさらされているのだ。万一、デフォルト(債務不履行)になったら、日本のメガバンクや生命保険など大手機関投資家も兆円単位で保有しており、確実に大恐慌が再来する。
ポールソン財務長官は国有化を否定、公的資金による資本注入を宣言して、浮き足立つ市場を鎮静化させようとした。連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長も緊急融資に応じるとして、文字通り国家全面支援の構えを見せている。議会も急ぎ支援法案を通過させている。
実はGSEの浮力の源泉は曖昧なのだ。両社は上場しているから、株主が増資などに応じて資本不足を埋めるのが筋。現に議会では、事実上の税金投入を余儀なくされるのになぜ株主が免責になるのか、と疑問の声が出始めた。1990年代の日本で住宅専門会社(住専)危機に噴出した公的資金注入と銀行救済への反対論によく似ている。「いまそこにある危機」を回避するために、資本の鉄則を曲げていいのか、という議論である。
もういちど「エルの物語」に立ち返ろう。プラトンはこの魂の不死と転生のエピソードを、「正義とは何か」に始まる国家論の末尾に置いた。しかも、ソクラテスが語る哲人支配の理想国家が堕落して、名誉支配制から寡頭制、民主制、僭主制の四段階で変質するという有名な章のあとである。なぜだろう。
いかなる国家も堕落する。だが、国家もまた魂と同じく転生のサイクルを持つ。マクロコスモスとミクロコスモスの相似をプラトンは言いたいのだろう。その深奥にはエソテリシズム(秘教)の幽冥がある。
エルの物語では、最後のクジ引きにエンマ大王はいない。何に転生するかを選ぶのは自由意志、と神官が言う。だが、その選択は、哀れとも、驚きとも、笑いを誘うとも言えた。オルフェウスは白鳥になり、アガメムノンは鷲になり、オデュッセウスは凡人に転生した。
両性具有のGSEは、いったい何に転生すべきなのだろうか。
8月号の編集後記
FACTA最新号(8月号、7月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は25日からです。
*****
もう共同通信のピーコを聞かなくなって久しい。「ニュース速報」を告げるチャイムが鳴ると、新聞の編集局は本能的に緊張が走る。「御巣鷹の夏」もそうだった。私は整理部で第1面を製作する面担だった。午後7時過ぎだろうか、あの鐘が鳴って「日航123便がレーダーから消えました」との音声が響き渡った。乗客・乗員524人と聞いて血の気が引く。微かに胴ぶるいがきた。
▼まさに「ハイ」である。1985年8月12日。地元の新聞記者だった作家、横山秀夫が描いた『クライマーズ・ハイ』のその日は、私も23年たって忘れ難い。映画も見たが、主人公悠木の葛藤と屈託に胸が熱くなった。悠木は土壇場でスクープに逡巡し、私は最終版で勇み足の見出しをつけた。1面2段ぶち抜き、黒ベタで「絶望」と打つ。翌日、ヘリで救出される生存者の映像を見た瞬間、深い悔恨を感じた。
▼奇跡に歓声があがるなかで、独り俯(うつむ)いた。整理部はニュース判断やレイアウト、見出しなど紙面製作工程に全権をふるう代わりに、取材をしない内勤職場だ。「左遷」「座敷牢」と悶々とする記者もいるが、私は嬉々として働いていた。新聞の第一読者、もっとも深く記事を読み込む心意気を感じたからだ。横山の小説でも、整理部の亀嶋部長や吉井部員は、愛嬌ある理解者に描かれている。
▼自分もああだったのか。だが、あの日、私の矜恃は粉みじんに砕けた。眼光紙背に徹するなんて嘘だ。野次馬にはものが見えない。どんなことがあっても取材に戻ってみせる――密かに決意した。恐らく横山とはすれ違いだろうか。「下りるために登る」というクライマーの比喩は、記者を辞めた彼の本音とも聞こえる。クライマーズ・ハイとは痛切な新聞批判なのだ。彼は小説という現場なき雑観を書き続け、私は雑観を捨ててスクープを追う。今は黙々と自分の衝立岩を登るしかない。
9年前の7月、私はイランにいた
TheEconomist誌の最新号(July12th-18th)の記事にはっとした。
Iran and the Economist SILENT NO MORE
と題する記事である。9年前の同誌の表紙の写真が載っている。血痕のついたTシャツを掲げ、緑のハチマキを巻いた青年の写真だ。その表紙には見覚えがあった。
9年前の7月、私はイランにいた。ケンブリッジが夏休み入りし、1年間の客員研究員暮らしを終えた私は、帰国の途上、まだ足を踏み入れたことのないイランを旅した。
民主派のハタミ大統領のもとで、ようやく門戸を開いたせっかくのチャンス。私一人で入国し、車と運転手、ガイドをチャーターした。北はカスピ海沿岸からアゼルバイジャンとの国境まで、南はペルシャ湾まで1カ月弱かけて走る計画だった。総走行距離は5000キロに達したろうか。
ホメイニ師の本拠である宗教都市コムも、ツァラストゥストラがほとりに住んでいたというウルミア湖、アサッシン(暗殺犯)の元祖「山の老人」が立てこもったアラムトの砦、恐竜の骨のようなザグロス山脈、そしていまは原発建設で世界の注目を集めるブーシェールの港などを回った。取材もした。
エスファハーンかシーラーズかのホテルに一枚のFAXが届いていた。日本大使館からだった。行き先など何も申告していないのに、なぜ?と思ったら、日本名でイランに入国した人間を懸命に追跡したらしい。大々的な学生デモが発生、死者も出ているので、注意喚起(暗に退去要請)する内容である。
デモが荒れたのは首都テヘランの話である。ガイドに全土の情勢が不穏なのか、と聞いた。かぶりをふった。ただ、彼も大学出で学生デモには同情的だったから、この街のデモに参加したいという。私は炎暑と下痢でへばっていたので、「暴れるなよ」と言って、翌日は一日休養日にした。彼は嬉々としてデモに参加し、「聖職者は嫌われているんだ」と憤然としていた。
イラン内にいると、デモがどれだけ世界に衝撃を与えたのかは分からなかった。だが、帰国してThe Economistの表紙(99年7月17日号)を見て、このハンサムなイラン人青年の思い詰めたような表情が忘れられなくなった。
9年後の記事によって、この青年が当時21歳のアハメド・バテービで、写真に撮られたため逮捕されたことを知った。「これでおまえは死刑執行令状にサインしたようなもんだ」と言われたという。
目隠しで殴られる拷問が繰り返され、眠らせまいと傷口に塩をすりこまれ、下水に首を突っ込まれて彼はもがいた。それでも友人のデモ参加者の名を明かすことも、テレビでTシャツの血はペンキだったと証言することも拒んだ。結局、死刑を宣告される。が、世界中から届いた減刑嘆願書のおかげで、懲役15年に減刑された。写真のおかげで命拾いしたのだ。
とはいえ、それは世界の非難をかわす当局のポーズ。彼は2年間も独房に閉じこめられた。たびたび拷問を受けたため、半身の触覚が麻痺してしまった。その治療で今年いったん獄外に出た彼は、イラン暦の新年であるノウルーズにイラクへ脱出、6月にアメリカにたどり着いた。
The Economist誌と接触したのは7月7日である。七夕のように、彼は若き自分の写真と対面した。怨んではいない、と言った。「自分もカメラマンなので、The Economistが載せなくても、他誌が載せたろうから」と。同行してきた弁護士であり、友人であるリリー・マザヘリは、写真に涙したという。まだ拷問の傷痕のないすべすべの腕が写っていたからだ。
私も同じイランにいた。自問せざるをえない。この9年間、いったいおまえは何をしてきたのか、と。
彼は逃避行の詳細を語りたがらない。でも、携帯電話のカメラでスナップを撮ったらしい。それにコメントをつけて近く公開(たぶんネットで)するという。
ぜひ見てみたい。存在証明、生きたあかしとは、こういうスナップを言うのだ。
田村秀男著「経済で読む『日・米・中』関係」のススメ
産経新聞特別編集委員の田村秀男氏(われわれの通称「タムヒデさん」)は、日本経済新聞時代に私の先輩だった経済ジャーナリストである。ちょっと頼みごとがあって先日会ったが、野武士のような風貌が最近はきれいな白髭になって、なかなか凄みが加わってきた。その炯々たる眼光は、いっこうに衰えを知らない彼の取材ぶりをよく表している。「生涯一記者」を彼ほどみごとに生きている人はいないと思う。
その彼に頼まれて、産経新聞に彼の新著の書評を書いた。扶桑社新書から出た本でタイトルは
経済で読む「日・米・中」関係 ~国際政治経済学入門~
(扶桑社新書 760円+税)
産経のタブロイド紙「SANKEI EXPRESS」で連載している「国際政治経済学入門」のコラムを本にしたものだが、タムヒデさんの年来のテーマが浮かびあがって面白い。彼は日経で80年代後半のワシントン、97年返還時の香港の特派員だった。米国駐在時は財務省やFRBの幹部によく食い込んで、確か20年前に通貨の管理変動相場制をスクープした。東京で金融記者だった私を愕然とさせた。
1997年の香港返還時は、ロンドンに私が駐在していたから、返還される側とする側と裏表から香港と中国を見ることになった。それだけに彼の視点はよく分かる。正直、扶桑社の編集者はそれがよく分からなかったのではないか。この本のタイトル、ちょっとありきたりだ。
私なら、ずばり「シニョレッジの魔」とつける。シニョレッジとは一般に「通貨発行益」と訳すが、ほとんど誤訳に近い。この言葉、必ずこれからのキーワードになると思う。この本の本質は、それを予見している内容であることだ。FXのデイトレーダーたちの狭い視野では、とても届かない通貨のサンクチュアリーがかいま見える。私の書評は7月6日、産経新聞読書欄に掲載された。
*****
シニョレッジの魔

貨幣には魔が2匹棲んでいる。1匹は言わずと知れた金満、強欲のマモンの神だが、こちらは筆者も後輩の私もとんと縁がない。が、もう1匹――シニョレッジ(通貨発行益)の魔には、2人とも憑かれている。ワシントン、香港で新聞特派員を務めた田村氏の新著は、その第二の魔を追う執念の賜だ。
シニョレッジとは何か。「封建領主」を意味するフランス語seigneurから派生した言葉で、中世欧州では諸侯が貨幣を鋳造し、額面と貨幣の製造原価との差益を収入としたことに由来する。現在では、基軸通貨国アメリカが、ドルを海外で流通させ、米国債を海外で保有させている限り、インフレなしに貨幣発行額を増やせるという“特権”をさす。
経済大国アメリカのパワーの源泉であり、本書はサブプライム危機から日本の閉塞、人民元台頭まで貫く一本の赤い糸として、ドルのシニョレッジの「黄昏」を透視している。その鋭さと肉薄ぶりは脱帽するほかない。
一例を挙げよう。英国と北朝鮮を結ぶコネクションである。06年にロンドンで始まった「朝鮮開発投資ファンド」代表のコリン・マクアスキル氏は、英海軍出身だが、恐らくインテリジェンスの人だろう。28年以上も北朝鮮に関わり、対外債務減免交渉の代理人として平壌の絶大な信頼を得た。
その背後には、北朝鮮への進出を狙う米国の穀物資本カーギルや鉱山開発大手ベクテルなどが控えている。手のひらを返すようなブッシュ政権の対朝「宥和」の裏には、イラク侵攻の泥沼でネオコンが総崩れになったばかりでなく、こういうコネクションの暗躍があることを本書は示唆している。
見え隠れするのは、ドルのシニョレッジがいかに貪婪かである。それを守るためなら外交上の裏切りも辞さない。その魔を知る人は稀だ。いわんや、魔を失いかけているアメリカの怖さを知る人はもっと稀である。
しようがないなあ、電通は
前号に続き最新号でも、「広告の巨人」電通の知られざるスキャンダルを報じた。前号はスイスのFIFA裏金編だったが、今度は中国不正経理編である。6月27日の株主総会がどうなるか、ぜひとも知りたいのだが、株主以外には非公開、つまり取材は不可ということらしい。
残念だなあ。弊誌報道にかかわる株主からの質問にどう答えるかという興味だけでなく、上場当初は30万円台をつけ、06年には40万円の大台乗せを実現した株価が、今はピークの半分の22万円台。下手をすれば初値の18万円に顔合わせしかねないだけに、この株価低迷を経営陣がどう説明するのか、ぜひとも知りたいところなのだが……。ちなみに私は株主ではないから、株主として出席はできない。
それにしても、なぜ取材不可?
――上場当初は記者を受け入れたこともあったが、誰も来ないのでやめました。
今度は少なくとも一人は来ますよ。つまり、FACTAが取材しますが。
――申し訳ありませんが、無理だと思いますね。
会場とは別室にモニターを置いて、そこで議事進行を拝見するというのは?
――いや、それも無理ですね。
せめて検討することくらいは?
――そういうことにはなっておりませんので。
という応酬だった。しようがない。灯台もと暗し。あきれたものだ。PRの元締めのくせに、自らのIRにかくも閉鎖的な広告代理店なんて、上場資格があるのだろうか。あれだけ恥部を書いてもまだ反省しないなら、中国ご当局に踏み込んでもらおう。首を洗って待ってらっしゃい。
ついでにもうひとつ、電通恥さらしの話題を提供しよう。
中国本土企業として初めて東証マザーズに上場したアジア・メディア・カンパニーの崔建平CEO(最高経営責任者)が6月23日辞任した。すでに6月12日のプレスリリースで明らかになっているが、崔CEOは同社の100%子会社、北京寛視網絡技術有限公司の保有する定期預金口座(残高1億690万元)を取締役会に無断で担保に提供、これによって得た銀行ローン1億300万元を自分の会社である北京海豚科技発展公司に流用したのだ。
 アジア・メディアはテレビ番組の情報ガイドという、ちゃっちい商売である。チャンネル数が多い中国で、紙媒体では報じきれないテレビ番組を携帯で発信するのがミソというが、中国情報局NEWSというサイトでこの3月10日、ぬけぬけとインタビューに応じていて「弊社の株価がこの程度というのは納得できません」などと答えているからお笑いだ。
アジア・メディアはテレビ番組の情報ガイドという、ちゃっちい商売である。チャンネル数が多い中国で、紙媒体では報じきれないテレビ番組を携帯で発信するのがミソというが、中国情報局NEWSというサイトでこの3月10日、ぬけぬけとインタビューに応じていて「弊社の株価がこの程度というのは納得できません」などと答えているからお笑いだ。
このインタビュアー(如月隼人)は、公私の別もつかないこのイカサマ中国人の正体を見破れない。番組ガイドの延長線上で広告代理業も営んでいるとうそぶく崔に、相づちをうつばかりだ。しかし、崔に騙されたのは如月氏だけではない。実はアジア・メディアには電通が出資しているのだ。
電通は上場前にファンドを通じて出資し、株式の6.71%を取得しているという。しかも社外取締役兼監査委員に就任したのが、高島鉄郎・電通インタラクティブコミュニケーション局長である。
崔建平は、03~04年に中国で話題になった上場ソフトウェア会社の資金消失事件で疑惑の人物として名前が上がっているそうだ。こんな人物の身元照会もせず、出資した電通もアホなら、その主幹事となり、マザーズ上場を実現した野村證券も、また上場を認めた東証もアホの極みである。
中国人パートナーに食い物にされた電通中国のお粗末さは、アジア・メディア出資でも立証された。生き馬の目を抜く中国では、電通はじめ日本ではお山の大将の企業はまったくの張り子のトラ。結局、損するばかりではないのか。
7月号の編集後記
FACTA最新号(7月号、6月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
私事で恐縮ながら、高校以来の親友、山本一生君が第56回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した。受賞作品は『恋と伯爵と大正デモクラシー』(日本経済新聞出版社)である。賞など無縁の世代かと思っていた。1年前に逝った直木賞作家、藤原伊織もそうだが、青春の火宅を潜り抜けた者しか書けない抒情が、今こうして報われるのはうれしい。
▼それにしても、この本のジャンルは何だろう。旧久留米藩主家に生まれ、大政翼賛会の事務総長、戦後はA級戦犯容疑で巣鴨プリズン入り、のち中央競馬の「有馬記念」の生みの親という伯爵有馬頼(より)寧(やす)の秘話、それも1919年の不倫の恋を追っている。歴史?いや、論証を超えている。小説?いや、ミステリーを超えている。いざ受賞してみると、なるほどエッセーなら座りがいい。
▼エッセーは何も花鳥風月、身辺雑記と限らない。モンテーニュの『随想録』は哲学の断章である。『坂の上の雲』のネタ本になった島田謹二『アメリカにおける秋山真之』や、松本重治『上海時代』もこの賞を受賞しているから、歴史の襞に深く分け入る文章は広義のエッセーと言っていいのだろう。司馬遷の『史記』も本質はエッセーだと思う。この210 0年以上前の史家の文章は、押し殺した胸中の熱塊そのものだから。
▼周本紀第四には、幽王の2年、西方の「三川、みな震す」とある。四川大地震を連想するが、この三川は涇水、渭水、洛水のこと。司馬遷は周に仮託して国の暗い行方を語る。
「周まさに亡びんとす。……いま三川、実に震するは、これ陽そのところを失ひて陰に填(とざ)さるればなり。陽失ひて陰に在れば、もと必ずふさがる。もとふさがれば、国必ず亡ぶ」
幽王は笑わぬ女、褒姒(ほうじ)を寵愛して周を滅ぼす。北京五輪のマスコット「福娃」に凶兆を見る無意識と同じだ。エッセーとは、天地を照射する一瞬の光芒ではないのか。
FACTAフォーラム「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」4
コロンビア大学教授のジェラルド・カーティス氏と、外交ジャーナリストの手嶋龍一氏のお二人を迎えて、5月26日(月)に本誌主催で開いたFACTAフォーラム・緊急トークイベント「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」の要旨の最終回です。リーダシップ論に話題が絞られてきました。

*****
手嶋アメリカ大統領選挙の候補選びの山場、2月のスーパーチューズデーで、カーティス先生は「オバマの命が本当に心配でならない」と仰っていました。アメリカの憲法は人々が武装する権利を認めています。このためミリシアと呼ばれる私的に武装した軍隊がディープ・サウスにはいまなお存在しています。これらの人々はプアー・ホワイトという所得の低い白人層が中心であり、人々の海の中に潜んでいます。オバマはそんな身の危険を承知で、選挙民の海の中に入っていく。アメリカは大統領選挙を通じて人種の軋轢を徐々に乗り越えていく可能性があると思いますが、アメリカ政治の政治地図の極右に潜む「少数の刃」を抜き取ることは至難のわざでしょう。
カーティスアメリカは銃を持つのは自由だから持っている人が多い。誰かが大統領を殺そうとすることは充分あり得る。成功した例もある。僕だけじゃなくて、みんな暗殺の問題を心配している。ヒラリー・クリントンが、ロバート・ケネディは6月に暗殺された、だから私は選挙戦を降りない、と失言したことに大きな反響があった。みな暗殺が頭にあるから、(オバマが殺されればという)意味ではなくても問題になりました。彼女が「(この失言で)ケネディ家が気分を害したのだとしたら謝る」と釈明しましたけどね。オバマはシークレットサービスが昨年夏からついているが、誰かが殺そうと思えばその可能性がある、もしも選挙の前に暗殺されたらアメリカの社会はどうなるのか、非常に怖いことだと思う。
手嶋上院議員になって早々の青年政治家オバマとは、私もワシントンで言葉を交わす機会がありました。でも、大統領への道をめざしはじめて、シークレットサービスを従えたオバマは、やはり別人のように見えます。「暗殺されるかもしれない。にもかかわらず大統領への道を歩む」という堅い意志がオバマという青年政治家を鋼のように鍛えているのでしょう。
カーティスオバマだけではなく、ヒラリーもそういう思いで出馬したと思う。アメリカで政治家として挑戦するとなると、日本ではとても考えられない、死と背中合わせの危険性があります。
手嶋日本のリーダーは暗殺の対象にすらなりませんね。でも1960年代、社会党の浅沼委員長が右翼の青年に暗殺された頃までは、日本の政治も暗殺の季節のなかにあったのです。
カーティスアメリカは西部劇そのもので、これは非常によくない。ただ実際問題として、アメリカは常に暗殺のリスクに直面している。犯罪そのものがアメリカでは誰も驚かないことだから。日本は幸せな国なんです。暗殺される危険がないから、もう少し勇気を出して、命がけで政治をやればいいのにやらない。
1週間ほど前に福田総理と1時間話をしたんです。僕は福田さんのバランス感覚、外交の考え方などを評価しています。面白かったのはとても元気だったことです。半年前、大連立未遂のちょっと前もお会いして楽観的だったんですが、今回は前よりも元気でした。「国会がもうすぐ終わる」「まだ総理大臣の座にある」からでしょうか(笑)。中国から胡錦涛主席が来日されて、戦争責任の話は一切なしで会談した。中国では首脳会談の報道が放送された。この訪日はとてもよかったと思う。できるだけのことはやっているし、それ以上はしょうがない、という。
でも、福田さんには戦略があるようにみえません。小沢さんも「早く政権交代」と自民党を追い込むだけで、それしかない。 政治家は戦略、ビジョン、説得、これが一番大事です。福田さんは戦略もビジョンもなく、説得の努力が足りない。オバマは演説上手ですが、何日も準備しているんです。ほとんど暗記して練習する。福田さんも小沢さんもそのような努力をすべきです。国民を一生懸命説得する努力は政治指導者の義務だと思います。
二人で話をすると、説得力のある話も出てくるんですが。国民にむかって、自分のやりたいことはこうだ、ビジョンはこうだ、と丁寧に説明して説得するのがリーダーシップでしょう。福田さんは「いい事をやれば、国民もそのうちわかってくれる」と言う。これはリーダーの言葉ではありませんね。
野党と協力が出来なければ、野党のことなど放っておいて、国民に顔を向ければいいんです。小泉さんのようなカリスマ性がある必要はない。8年間大統領をつとめたアイゼンハワーもカリスマ性はなかったが、安心感があった。一番大切なのは説得すること。それが日本の政治家には足りない。今の日本の政治家の大きな構造的問題だと思う。
阿部カーティス先生の新著「政治と秋刀魚」のうち「秋刀魚」の意味は、東京郊外の西荻窪に先生が下宿したときに初めて秋刀魚を食べ、それ以来、日本が好きになったということです。懐かしいあの庶民の味に日本の良さがある。今は一見リーダーシップを失っているようですが、日本の復活へ励ましの言葉と受け取りたい。復活の芽に何があるのか、最後にひとつ挙げていただきたいと思います。
カーティスそれの話題をおしゃべりするだけで、また2時間必要になりますね(笑)。日本人は日本を悲観するのが好きな民族だと思う。小松左京が「日本沈没」という小説を書きましたね。大ベストセラーになって、日本は沈没するだろう、ダメになるとみんなが言った。小渕総理も「何かしないと日本に明日はない」というのが口癖だった。小泉さんは全然違う。沈没論的なことを言ったことがない。「がんばればよくなるよ」と。楽観的なメッセージが必要なのをよくわかっていた。
日本には「グローバリゼーションにのっかると国がダメになる」と言う方々が多い。他方で「アメリカをまねすべきだ」という勢力も多い。両方の共通点は、日本に自信がないことです。アメリカを真似しないとダメになるという意見に反対する人たちは、ナショナリストを自称していますが、実はいちばん自信のない人たちですね。
日本は2千年近い歴史をもって、思想も言葉もアイデアも外国から吸収して自分のものにしてきました。戦後もアメリカが6年間も占領していろいろ改革しましたが、アメリカのような社会にはならなかった。もっと日本に自信をもって、日本を変えていく必要があります。そういうリーダーが求められていると思うが、なかなか出てこない。いずれ出てくると思って、日本の研究を飽きずに続けたいと思っているんですがね。
難しい時にリーダーが希望を与えるのは非常に大事なことです。今のアメリカは希望を与えるリーダーが必要です。だからやっぱり希望を与えるオバマが台頭してくるんです。希望を与えて行き先を見据えるのが、リーダーにとって重要だと思います。日本のいいところ、価値のあるところは、もう話す時間がないから、私の本を買って読んでもらえればと思います(笑)。
(了:4/4)
FACTAフォーラム「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」3
コロンビア大学教授のジェラルド・カーティス氏、外交ジャーナリストの手嶋龍一氏をお迎えして5月26日に行われたトークイベントの続きです。大詰めを迎えたアメリカ大統領選の民主党候補選びから、日本の政治のリーダーシップへ話題が移ってきました(司会はFACTA編集長、阿部重夫)。
*****
阿部カーティス先生は1960年代、日本の政治家に密着しつぶさに観察して「代議士の誕生」という名著を書かれました。日本の政治が遅れているという通説に対し、そこに積極的な意味を見いだしてきたと思うのですが、日本の政治の現状をどうごらんになっていますか。
カーティス最近のエピソードを申し上げましょう。僕は3週間前に北朝鮮の平壌に行ったんです。北朝鮮外務省の招待で政府高官と話し合った。向こうも我々のことをよく調べていて、日本の話になった。シンガポールで米朝交渉が前日にあり、北朝鮮側は「われわれはアメリカと交渉し、なんとか第2段階を成功させてテロ支援国家指定から解放され、経済制裁の解除にもちこみたい」と言ったうえで最後にこう付け加えました。「対米交渉がうまくいけば、日本のほうが慌てて飛んでくる」

こんなふうに日本がバカにされるような状態なのは非常に残念ですね。福田総理は北朝鮮と交渉したいと思いますが、その力がない。でも福田総理がやめてもこの状態は変わらない。何か構造的な問題だと思う。
僕の新刊の副題は「日本と暮らして45年」です。いろいろな日本人と知り合いましたが、昔の政治家は面白い人がいっぱいいた。大平正芳さんとか、今の福田総理のお父さんの福田赳夫さん、官僚上がりなだけじゃなくて、官僚を使う方法をよく知っていた。今の日本の政治家はみな小さく見えます。「時事放題」で中曽根(康弘)元総理と一緒になりましたが、90歳になられたのに凄い人だと思いました。私と必ず意見が合うわけではないが、でもすごい。中曽根さんは一番最初に会った日本の政治家ですが、会うたびに勉強になります。
今の政治家はみな2世議員ですね。小選挙区制は日本にとって非常に悪い制度だと思います。エネルギーがない。民主党が強くない選挙区だったら、自民党の2世議員は競争する相手がいない。それで質が悪くなっていると思う。福田さんがやめて麻生太郎さんになっても、小池百合子さんになっても、政治がよくなるとは思えませんね。もうちょっと時間が経って若い人が出てきたら、政権交代が起きてよくなる可能性が出てきます。民主党には今のところ政策通は多いが、政治通は少なすぎます。政権をとって政権を持つ経験をして、政治がわかる人たちがそろえば、もっと日本の政治はよくなる。
日本では「創造的破壊」というが、意味は「建設的破壊」ということですね。今の日本はそういう段階にあると思う。見えるのは破壊だけですが。早くジェネレーション・チェンジ(世代交代)すること。オバマは40代です。大統領に当選すれば、新しい人たちをワシントンに連れていって、新しいエネルギーが生まれる。日本の近い将来は悲観、中期的には新しい展望が生まれる、そういうふうに僕は見ています。
阿部僕らジャーナリストが見て、どうにもならないと思うのは福田政権の支持率の低さ。2割前後でねじれ国会。政策がほとんどできない。衆議院で3分の2の再可決が最後の手として使えますが、福田さんが自嘲したように「気の毒なぐらいがんばっても」何もできない閉塞状況にある。この打開策はあるのでしょうか。

手嶋この会場におられる方々で、一人も賛成を得られないと思いますが、明治の日本は「お雇い外国人」がいたように、首相に「お雇い外国人」を置いたらいかがでしょうか(笑)。サッチャーさん、リー・クアンユー、李登輝さん、みな立派な方々で、そういう方に日本の総理になってもらったら、と考えます。
昨年夏、李登輝さんにインタビューしましたが、哲人政治家の名前にふさわしい方で、自宅が天井から全部本なんですね。「この本は全部読んでいないと思っているでしょう、どこでもいいから見て下さい」と仰るので本を開いたら、随所にアンダーラインが引っ張ってあった。レーガンが好きでよく読んでいましたね。
なお今、世界が自分を求めているのなら、今すぐにでも行って政に、という人たちはたくさんいますよね。その方々にお願いしたらと思うほど、日本ではリーダーになるシステムが崩れている。カーティス先生は「人種問題をアメリカが乗り越えつつある、そう信じたい」と仰った。ひょっとしたらアメリカ国民は大変なエネルギーでそれを乗り越えつつある、今までの形でなく新しい段階に行けばこの国はものすごく強くなる、そう思います。やっぱりその点で、リーダーを選ぶプロセスは非常に重要だと思う。
阿部日本人はこれだけリーダーが頼りないと、過剰なほど自信喪失に陥る。アメリカはイラクでこれだけ泥沼にはまり、経済もサブプライムで大変なのに、ああいう激烈なリーダー選びでなんとか再生しようとしていますね。
カーティスそれは自信喪失の問題ではなくて危機感があるかどうかだと思う。小泉さんが総理大臣になって5年目の夜、二人で食事をして、彼が振り返って話をしてくれた。なぜ総理大臣になったか。そのときに日本人の危機意識が強かったから。あの「構造改革なくして経済成長なし」という小泉さんは自民党総裁選に三回も出たが、三回目の2001年に総理になれたのは、日本にその前になかった危機意識があったからでしょう。今は自信喪失というが、多くの場合日本人に危機意識がない。「日本の経済は順調、輸出も強い」と財界人に危機意識がない、一般国民も不安があっても危機感は乏しい。だから福田さんみたいなタイプが総理大臣になれる。
アメリカはやっぱりイラクの大失敗が原動力です。日本で格差問題がいろいろいわれるが、アメリカはその比ではない。私の大学の事務所の窓から眺めるのはハーレムです。暖房もない部屋に住む人が多くて、若い人たちが犯罪に走る。小学校で武器をもっていないか調べる。日本では考えられない貧しさがある。
アメリカの4分の1がブッシュは建国以来最悪の大統領という。これが4年前だったらありえない話です。福田さんは2世議員で、大臣は官房長官しかなったことがない。それ(経験不足)が問題というより、一般国民に危機意識がないことのほうが問題ですね。怒らない、怒りがない。本当に怒ったら、日本の政治家も応えると思う。
それと、日本のジャーナリズムの問題が大きいと思う。政治報道は番記者制度と記者クラブ制度に毒されています。後期高齢者医療制度、2年前に法案が通った時に「こういうことになる」という情報を与えてない。なのに今は非常にエモーショナルになっている。昨日、「時事放談」から始まって「報道2001」、NHK、田原さんの番組(サンデープロジェクト)を全部見てましたが、イヤになりますね。
舛添さん(厚生労働大臣)が番組に出演した。アンカーは「厚労省の官僚が悪い。貴方は騙されています」という。でも、官僚が悪いのは大臣の責任。そのことをいわないで「政治家はかわいそうだ」というインタビューをするような記者の発想は古い。そのとき、大臣は[そう言わないで欲しい。責任は私にありますから官僚のせいにすべきではない]というべきだと思うが、官僚バッシングは政治家もジャーナリストもやりすぎると思います。それに、政治記者は政界記者とか政局記者ではないはずなので、もっと政策の話をしなければ。今の日本ではなんでも財政再建ですが、財政のプライマリー・バランス(基礎収支の均衡)を2011年までに均衡させるのが本当にいい事かどうか、なんでも小さな政府にすることが高齢化する日本にとっていい選択かどうか、消費税を上げるのは本当に良くない事かどうか、日本のジャーナリズムはもっとこれについての情報と分析を国民に与えるべきのではないでしょうか。
手嶋ホワイトハウスにもプレスクラブはありますが、日本の記者クラブとはまったく違う。日本の記者クラブは談合組織です。ゼネコンも今や談合をしていないわけですから、もっとも劣悪な談合組織です。いま日本にある記者クラブ制度のようなものは、日本以外にはジンバブエだけと言われるほどです。
中国の胡錦涛主席が日本を訪問したとき、歯の浮くような共同声明を出した。小泉政権の時代からどんなふうに中国が舵を切ったのか、精緻なレポートは日本のジャーナリズムにまったくない。FACTAには載っていますよ、(安倍訪中の)スクープもしていますよ、でも一般の新聞にはまったくない。一部140円に値するような情報をほとんど受け取っていない。東京地検のニュースでも、当局のお墨付きが出て初めて書く。これは本来のジャーナリズムといえるでしょうか。
阿部リークということですね。政府は一番都合のいいときに都合のいいことをもらす、そこで記者クラブで全員右へならえの報道が始まる。だからほとんどスクープは存在しない。厳しいチェックがないから、政治も官庁も楽をして、自分の思うように日本の社会を動かしてきた。カーティス先生が日本の政治を悪くした理由と断罪されるのももっともだと思います。
(続く:3/4)
FACTAフォーラム「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」2
コロンビア大学教授のジェラルド・カーティス氏、外交ジャーナリストの手嶋龍一氏をお迎えして5月26日に行われたトークイベントの続きです。大詰めを迎えたアメリカ大統領選の民主党候補選び。土壇場でヒラリー・クリントン候補が「起死回生」を狙って始めた人種キャンペーンが話題になりました(司会はFACTA編集長、阿部重夫)。
*****
カーティス人種問題にはいろいろな側面があります。まず今のアメリカで、もっとも人数が多いマイノリティは黒人ではなく、ヒスパニックです。劇的な変化で、1990年から去年までヒスパニックの人口は2倍になりました。その半分がテキサスとカリフォルニアに住んでいます。ヒラリーが両州で勝ったのはヒスパニックのおかげと言えるのです。

ヒラリーの支持者層は、女性と白人労働者、それも教育水準の低い人たちです。オバマの支持者は若い人、所得水準の高い人、そして黒人ですね。面白いのは、オバマが黒人のほとんど住んでいない州で圧勝しているのに、黒人の多い大都市で苦戦していることです。どうしてか。ワイオミングとか、サウスダコタとか、アイオワのように黒人が少ない州では黒人への恐怖感がない。オバマをただ素晴らしい候補者として見ています。
しかしニューヨーク、ニュージャージー、ロサンゼルスなどの教育水準の低い白人は、肌の黒い人に対して恐怖感がある。コロンビア大学もニューヨークのハーレムに隣接していますが、その地域の黒人の青年のおよそ50%が刑務所に入った経験があると言われます。そのハーレムの近くに住んでいる白人は黒人を怖がっています。オバマはそれを乗り越えられるかどうか。11月の本選挙では、アメリカにまだ人種差別がどれだけあるのかが見えますね。
白人労働者がヒラリーを支持しているのは、オバマが黒人だからなのか、それともオバマのほうがエリートで、労働者の気持ちがわからないと思われているからなのか。先日、オバマは労働者階級が好きなボーリングをやってみせました。ところが、ネクタイも緩ませないで投げ、ガターだらけで点数は30点台。いかにもボーリングをしたことがないエリートだという感じが出て逆効果でした。
ヒラリーもエリートだが、そのへんは上手なんですよ、労働階級の人たちに親しみを感じさせる才能がある。オバマが民主党の候補者になれば、そういうヒラリーを支持した白人の労働者が、オバマを支持するのか、マケインに投票するのかわからない。わからないけど、基本的な観察では、私はそういう差別で投票する人は案外少ないだろうと思うし、思いたい。アメリカの奴隷制度が定着したジョージア州の予備選挙では、オバマが黒人票の80%を獲得したが、45%の白人の男もオバマに入れた。あのディープサウスでこれは革命的なことです。
阿部対する共和党はマケイン候補に確定しています。先日、日本の外交官と話をしていて、オバマが勝った方が日本にとって得なのか、マケインのほうが得なのか、という議論になりました。日本の第一線外交官にとっても、オバマは新顔で、ブレーンもよくわからない。日本はアメリカに巻き込まれる恐怖、見捨てられる恐怖の間を行ったり来たりしています。
手嶋そういう問いの立て方は、トヨタの最高経営責任者が今後の経営をどういうふうにすればいいのか、占い師に聞くようなものだと思うんですね。それは日本のリーダーシップがいかに疲弊してきているかということだと思います。世界第1の経済大国と第2の経済大国である日本。しかも日米同盟で東アジアの要石となっている日本が自ら外交上のリーダーシップを発揮すれば、「ジャパンナッシング」「ジャパンパッシング」など決してさせないのではないか。それは私のみならずカーティス先生の言葉として僕は紹介しているんですが。
カーティスマケインとオバマ、どちらがいいかはいろいろ意見があると思いますが、まず大事なのは、それを言わないほうが日本の政治家にとって賢明だと思います。「マケインがいい」と公の場で政治家が言ったとします。もしオバマが大統領になれば、その人を警戒しますよ。あくまでもニュートラルを維持することが大事です。
ビル・クリントンが大統領退任前にイギリスに行った時、トニー・ブレア首相が演説しました。クリントンをずっと褒め称えたが、締めくくりに次のブッシュとも同じように親しい関係を築くと言いました。当然でしょうね。イギリスは民主党とか共和党ではなく、アメリカとの特別な関係にあるという立場ですから。日本もそうでしょう。
もうひとつ、共和党が親日、民主党が反日という神話は、いつから始まったのでしょうか。佐藤栄作首相の頭越しに、キッシンジャーを中国に送りこんだのが共和党のニクソン。日米繊維交渉もニクソン政権でした。日本車輸出の自主規制はレーガン政権でしょう。ただ、民主党であってもたぶん同じことをやったと思う。民主党と共和党で対日政策はほとんど違わない。オバマもマケインも、日本との関係の重要性をよくわかっていると思う。
日本人が考えるべきは、どういう人が大統領になれば世界でアメリカの評判がよくなるか。もしも中東を平和的な地域にできるならば、それは日本にとって何よりも重要。日本の原油はほとんどそこから来ている。よく日本のジャーナリストにきかれるのは、オバマが大統領になったら何を求めてくるのか、ということですが、質問が古い。オバマに日本は何を求めるのか、日本はどういう世界にしたいのか、そのためにアメリカとどういう関係を持ちたいのか。そう考えるべきだと思います。
日本との関係をもっと重視して、早く日本を訪問してくれといったら、オバマさんは「WHY?」ときくと思う。忙しいし他の国も台頭しているし。Why Japan, forget about Japan(なぜ日本に構うのか、日本なんか忘れろ)がワシントンでよくいわれる言葉です。それに対して、日本から求めることを考えてほしいと思う。そういう政治になってほしい。
阿部大変いいご指摘だと思う。ニクソン訪中のお話が出てきましたが、1972年のアメリカの外交教書の中で、日本のアメリカ依存に触れています。「日本はアメリカに依存していて身勝手。アメリカが突然、中国に接近してもそれは日本の目を覚まさせるのにいいことだ」と書いてある。事前にニクソン政権はシグナルを発していたのですが、さきほどの設問の主体性のなさが早くも指摘されています。
日本はアメリカから受け身で、同盟の利益を享受する立場にあって、何も積極的に働きかけようとしない。このフォーラムのタイトルの後半部分、「秋刀魚」の話になっていきますが、日本はどうするのかでなく、高みの見物をしているところがある。手嶋さんは日米関係の空洞化を指摘されていますが、今の福田政権はそういう病気が治っていないということでしょうか。
手嶋私は二言目には「アメリカでは」と言い出す「出羽守」ではありません。それでもこの大統領選挙を見ていて、日本の政治との決定的な違いを感じます。プライマリー(予備選挙)やコーカス(党員集会)という過酷なレース、ほとんど1年以上前から過酷なレースが始まっている、それに出馬するだけでなく、圧倒的な影響力のあるアメリカのメディアが待ちかまえている、一瞬でも戦術上の誤りを犯したり一瞬でもハプニングが起こっても、有力候補の座からすべりおちる、そういう過酷なレースを走り続けてきた3人は、いずれも2世ではありません。
クリントン候補にはあそこまで粘らなくても、と思いますが、あれほどの強い意志をもってレースを走り続けるタフさは、端倪すべからざるものがあります。これに対して福田さんのように、安倍政権崩壊のあと「今度は大丈夫そうだから」と総裁選挙に出馬する人の間には大きな違いがあります。
過酷なレースを走ることは文句なくいいリーダーを引っ張り出す。日本では指導者を生み出すシステムに、重大な欠陥があるように思います。日本にいいリーダーがいないのは日本だけの問題でなく、世界に重大な影響を与えています。やっぱりいいリーダーは必要です。政治家はこの程度でいいという俗論が流布したことがありますが、それがいかに俗論かということをこの機会に考えたいですね。
(続く:2/4)
FACTAフォーラム ジェラルド・カーティス氏×手嶋龍一氏×阿部重夫「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」1
6月3日、米大統領選挙の民主党候補者指名レースでバラク・オバマ候補の獲得代議員数が過半数に達した。ライバルのヒラリー・クリントン候補は近く敗北宣言する見通しで、これで11月の本選挙はオバマ対マケインになる公算が強まりました。ファクタではこれに先立つ5月26日(月)に本誌主催で、日本政治研究の第一人者であるコロンビア大学教授のジェラルド・カーティス氏と外交ジャーナリストの手嶋龍一氏をお招きして、FACTAフォーラム・緊急トークイベント「オバマと秋刀魚~日米政治の分かれ目」を開催。ここでは、その要旨を4回にわたって連載します。
*****
阿部今日のテーマは少しシュールなタイトルです。「オバマと秋刀魚」。「マ」の脚韻を踏んだ単純な駄洒落ですが、カーティス教授の新著のタイトルの一部を拝借しました。さて、混戦のアメリカ大統領選挙は、ヒラリー・クリントン候補が勝ち残れる可能性が薄くなって、バラク・オバマ対マケインの戦いになりそうです。
カーティス先生もニューヨーク出身で、おそらく民主党支持だと思いますけれど、オバマ候補の登場の意味とインパクト、共和党のジョン・マケイン候補に対し優位に立てるのか、といったお話を最初にお願いします。

カーティスこの大統領選挙、ひょっとしたらアメリカの歴史の中で一番盛り上がって面白い、一番意味のある選挙の一つになるのではないかと思います。選挙に無関心だった有権者もみなCNNをつけっぱなしです。予備選挙の投票率はふつう低いけれど、今年は非常に高く、4年前の倍以上の人が投票している。その60%が女性。これはヒラリー効果だと思うんですが。1月のアイオワ州、ニューハンプシャー州の幕開けから半年、やっと6月3日の予備選挙で全部終わる。候補を決めるのは代議員ですが、予備選挙で選ばれている代議員の多数派がオバマ支持ですし、3日の予備選挙が終わって1週間以内に、まだ表明していない人の多くがオバマを支持する。
問題はヒラリーがそこでやめるのか。党大会まで降伏宣言しない可能性はないといえない。いずれにしてもオバマが候補者になります。それで厳しい選挙戦になりますが、何が起こるかわからない。たとえば9・11テロのようなことが起こったら、防衛問題が国民の一番の関心になって、マケインが勝つでしょう。ただ国内問題――経済、保険、サブプライムなどに国民が注目するならばオバマが勝つと思う。
阿部日本人には考えられないほど長い耐久レース。国民に飽きはきませんか。
カーティス長びいた選挙戦で面白い変化が起きました。キャンペーンが長すぎるとか、お金がかかりすぎるとかの声はほとんどきかない。専門家にも分からないこの複雑なマラソンレースをいいなと思う人が多くなった。もしも1月だけで候補選びをやれば、クリントンが大統領候補になった。オバマさんを知らない人が多かった。が、オバマのすばらしさがわかってきて、今の時点では「ヒラリー大嫌い」と思うアメリカ人が多くなった。演説はみな上手ですが、問題は候補者の人格や性格。それが見えてきた。
プライマリー(予備選)は大勢の人たちの前で演説し、テレビ広告新聞広告をする。コーカス(党員大会)は20人、30人が集まってコーヒーを飲みながらオバマかヒラリーを囲んで話し合う。プライマリーはホールセール、卸売りの政治、コーカスはリテール、小売の政治です。両方あるのが非常にいいと思う人が増えた。
また、インターネットが選挙に革命を起こしました。オバマは2月だけで55億円集めた。それを寄付したのが73万人。100ドル以下が90%、20ドル以下がその半分。すでにオバマは150万人から寄付を集めている。ヒラリーはたぶんその半分くらい。これまでのように利益団体とか労働組合とか大企業の寄付だけではなく、貧しいおばあちゃんが封筒に入れて送ったり、学生がVISAカードで送ったりする例が増えている。これは政治参加ですね。少しの金額を寄付することですごくコミットメント(関与度)が大きい。
日本は選挙の公示となると、ネット献金ばかりか候補者がメールをして有権者とコミュニケーションすることが禁止されています。ネットの影響力をよくわかっているのがオバマですね。彼は21世紀の候補者、ヒラリーは20世紀の候補者、マケインはどちらかというと19世紀の候補者かもしれないですね(笑)。
阿部しかしオバマの肌の色は不利ではないのですか。
カーティス日本では黒人というが、アメリカでは彼をアフリカ系アメリカ人とよく言います。オバマはお父さんがケニア人、お母さんが白人です。彼のおかげで今、アメリカの黒人は、イタリア系など他のアメリカ人と同じように、アフリカ系アメリカ人と呼ばれるようになった。この意味は大きい。
面白いことに、1月の中旬ごろまでニューヨークの黒人のタクシー運転手に聞いても、一人もオバマ支持者はいなかった。「残念ながらこの国はまだ黒人を大統領にする国になっていない。それよりもヒラリーを支持して民主党政権にすることのほうが大事」といっていた。しかし、住民のほとんどが白人という州でオバマが勝つと、アメリカの黒人に大きな衝撃を与えた。オバマは大統領になれるかもしれない、そうなれば新しい希望を持てる――というムードが強まった。
私もその通りだと思います。オバマが民主党候補になって無党派層の支持も集め、大統領になったら、アメリカ国内だけではなく、世界にとってもいいことだと思う。
阿部FACTA最新号では、外交ジャーナリストの手嶋龍一氏がコラムで書いています。ヒラリーが人種問題に触れたこと、「恥を知れ」と激しい言葉でオバマを批判したことは「禁断の木の実」だと。オバマがヒラリーを副大統領候補にする可能性も取りざたされたんですが、あの批判でパンドラの箱を開けた気がします。
手嶋今、カーティス先生は非常に正確なことをいわれました。アメリカはメイフラワー号にのってきた移民の子孫と奴隷の子孫の国、といわれます。従来は奴隷と移民の間には高い壁がそびえ立っていた。今でもそうです。では、オバマはどちらなのか。

系譜としては移民の子孫です。奴隷としてアメリカに連れてこられた黒人ではありません。だからといって、オバマが白人に近いエリートの黒人とは私もいいません。カーティス先生もおっしゃらないと思います。白人のおばあさんが、暗い夜道を黒人がやってきて思わず怖くて避けた、という話を若いオバマはつらい気持ちで聞いた。オバマは黒人の苦しみをわが苦しみとしている。
私は2004年のボストン党大会の演説を身近にきいた者のひとりですが、「黒人のアメリカはない、白人のアメリカはない。今こそ人種の心をひとつにしたアメリカを」という名演説をオバマがして、彗星のごとく政界に躍りでてきたのです。
しかしヒラリーはまさに禁断の木の実、人種問題に触れて、オバマを攻撃しました。オバマは人種の統合を説く候補者だが、非常に狭い黒人のコミュニティを代表する候補者だと責めたのですから。この“毒まんじゅう”に手を出したヒラリーを、人間としてもステーツマン(政治家)としても後世は許さないかもしれません。
しかし、当座の戦いに勝ち残ろうという選挙戦術として、これほど起爆力のある戦術はなかった。オバマのスピーチでなく、オバマの師、ジェレミー・ライト牧師の発言から白人を攻撃する発言を取り上げ、オバマは狭い社会の代弁をしているに過ぎないと主張して、人種問題の扉を開いてしまった。これは何を意味しているのか。
黒人コミュニティの風下に立つ人たちがいる。とりわけ「プア・ホワイト」(貧乏な白人)といわれる層から「黒人の風下に立つのか」という不満を噴き出させる。それはすごい戦術だが、触れてはいけない戦術だった。大統領選挙に占める「プア・ホワイト」の動向、ヒスパニックの動向について、カーティス先生はどうお思いですか。
(続く:1/4)
写真:大槻純一
*****
FACTAフォーラムとは?
FACTAでは、プリント(印刷媒体)+ウェブ(インターネット)に加えて、第3の情報発信の場として定期的なトークイベントを開催しています。各分野の第一線エキスパートと読者の皆様をつなぐ橋渡しの場でもあります。過去の開催内容など詳細はこちらをご覧ください。
手嶋龍一『葡萄酒か、さもなくば銃弾を』の書評
FACTA6月号のBOOKレビューに取り上げたこの本に、私自身で書評を書いた。
文中の何篇かが本誌連載コラムに載せたものなのでご縁があるし、先日のFACTAフォーラムでも著者サイン会などを開かせていただいた。ただ、自分の雑誌に自分の書評を載せるのは遠慮して、手嶋氏と一緒にコラム「時代を読む」を連載している新潟日報など地方紙にこれを掲載していただいた。
以下の各紙に掲載されたものです。
5月18日 新潟日報、福井新聞・山陰中央新報
5月19日 東奥日報
5月25日 神戸新聞
5月28日 北日本新聞社
このブログで再録します。
*****
ディプロマシーの崖っぷち
 ある晩、源氏物語の雨夜の品定めのように、手嶋式美文がひとしきり話題になったことがある。「ちょっとキザ」「あれはサービス」「凝りすぎじゃないか」……中で一つ、至言と思える評があった。「そんな一筋縄でいかないよ。毒杯のなかに蜜、ドルチェの下に短剣が忍ばせてある。まさに手練手管、文章そのものがディプロマシー(外交術)なのさ」
ある晩、源氏物語の雨夜の品定めのように、手嶋式美文がひとしきり話題になったことがある。「ちょっとキザ」「あれはサービス」「凝りすぎじゃないか」……中で一つ、至言と思える評があった。「そんな一筋縄でいかないよ。毒杯のなかに蜜、ドルチェの下に短剣が忍ばせてある。まさに手練手管、文章そのものがディプロマシー(外交術)なのさ」本書のタイトルがそうだ。人事を尽くした駆け引きの果てに、事が成就すれば乾杯の美酒、さもなくば暗殺の銃弾に倒れて、遺影に微笑を残す。そんなディプロマシーの崖っぷちを、二十九人の人物スケッチで語ろうという企み。真のインテリジェンスとは、そういう危地を生き延びる知恵のことだろう。
文章のディプロマット。手嶋氏はどこでそれを体得したのか。恐らくジャーナリズムの悪徳――常套句からである。「新聞雑誌のどんなに深い澱のなかに埋もれていても、常套句をその夜の闇から救いだそうと、言葉の翼に乗って舞い降りてくる声の襲撃」(ヴァルター・ベンヤミン)から、手嶋氏が織りなす美文もまた無事ではない。その裂け目に一瞬あらわれる毒と蜜こそ、巧言と奸略のディプロマットらしい自画像かもしれない。
手嶋氏は先読みの人だ。巻頭の一編にバラク・オバマを掲げたのは、ヒラリー・クリントンの大統領選撤退近しを待ち伏せてのことに違いない。もしかしたら、未来のオバマ暗殺まで予見しているのかもしれない。沖縄返還交渉の密使、若泉敬のエピローグまで、一見アトランダムに並べたようでいて、この二十九編の群像劇には周到な企みが隠されている。
若泉の掉尾ではっとした。福井に隠棲したこの憂国の士が見せた最晩年の悲憤を、私も知っている。没後訪れた鯖江の遺宅は無人だった。軒上に沖縄の獅子像の瓦。ああ、刹那の光芒。この本の群像は、慷慨のエピファニー(顕現)集ではないか。
1957年のグールド
過去の自分の文章をちょっと引用させていただこう。日本経済新聞1991年12月21日付朝刊の芸術特集「美の回廊」の文章である。
グレン・グールドは、ひとつの神話だった。演奏をこの目で見、聞いた日本人は数えるほどしかいない。ソニーの大賀典雄社長はそのひとりだ。一九五七年、留学先のベルリンで見た印象を今もありありと覚えている。
「えらくイスを低くして、手長ザルみたいなんだね。ベートーベンの協奏曲三番の長い前奏の間、指揮のカラヤンを尻目に、ピアノの前でタクトを振るように手が舞うんだ。驚いたね。いざ弾き出すと、目のさめるような音で、強烈な欧州デビューだった」(「最後の風景」4 孤独の化身の誘惑)
われながら懐かしい。当時の肩書きは金融部編集委員兼論説委員。それがなぜか「美の回廊」取材チームに投入され、同年12月にカナダのピアニスト、グレン・グールドを取り上げた。大賀氏に思い切って取材を申し込んだのは、ソニー入社前、ベルリン国立芸術大学に留学していたころ、カラヤンとグールドという奇跡の競演を目撃した日本人と聞いたからだ。正直、気安く快く応じてくれたのには驚いた。
こちらはクラシックにまったく素人の記者。それでも、あの忙しい身で30分も時間を割いてくれたのだ。声楽家を志した人だけに、金融記者の背伸びした質問にも、目を輝かせながら答えてくれた。大賀さん、改めて感謝します。
1957年のグールドは、前年にバッハ「ゴルドベルク協奏曲」のレコード・デビューで全世界を驚愕させたばかり。この年、北米出身のピアニストとして大戦後初めて旧ソ連で演奏旅行した後、欧州に帰ってベルリンで巨匠カラヤンと組んでベートーベンを弾いたのだ。大賀氏も言うように「鮮烈な欧州デビュー」だったのに、いくら探しても録音したレコードがみつからない。カラヤンとグールドという二大スターだけに、版権の調整がつかなかったのかと思うとともに、耳にした大賀氏に羨望を禁じ得なかった。

この記事から実に16年半。幻の演奏がとうとう世に現れた。ソニーBMGが「The legendary Berlin Concert」と銘打って、ライブ録音のCDを発売したのだ。録音日時は1957年5月26日、今から51年前である。ジャケットの写真でみるカラヤンも若々しいが、グールドはまるで少年としか見えない。ようやくわれわれも、若き大賀氏が体験した至福を耳にすることができる。そして幻の競演を書き留めた私の文章も、ついに証人を得た気分になった。
さっそくCDを試聴した。原テープはモノラル録音だろう。当時の録音技術ではやむをえないことだが、ホールでライブ録音しているため、残響がこもってオーケストラが時代がかって聞こえる。カラヤンのベルリン・フィルというより、メンゲルベルクのコンセルトヘボウでも聞くような気持ちになる。
大賀氏が言うように、ベートーベンのピアノ・コンチェルトNr. 3はオーケストラの前奏が長い。だんだん不安になってくる。カラヤンって50年代はこんなに古めかしかったのか。ノン・レガートの鋭利なグールドが入ってきたら、水と油ではないか……。
杞憂だった。ピアノのトリルが加わった途端、曲が一変する。ホールが息をのむのがわかった。一音一音が明晰なアーティキュレーション。紛れもないグールドがそこにいた。カラヤンとベルリン・フィルは、あっというまに主役を奪われて、コンチェルトはグールドのものになってしまう。世界がこのカナダの“手長ザル”にひれ伏した瞬間だった。
第2楽章はピアノのソロから始まる。もう独壇場である。怒濤のような第3楽章を終えると、ホールは万雷の拍手に包まれた。錯覚かもしれないが、カラヤンが負けたように聞こえるのはこれが初めてだった。このCDには、このあと演奏されたシベリウスの交響曲が入っているが、いかにもカラヤンらしい色彩豊かで豪華絢爛な演奏である。もちろん、グールドはそこにいない。が、前奏のピアノの音が観客の耳底でまだ響いていたのか、演奏後の拍手は心なしかベートーベンより小さかった。
新しい才能の出現を喝采で迎えたこの夜の観客たちが知るよしもないことがあった。グールドはそれからわずか7年後、コンサート・ピアニストから引退を宣言した。以後、スタジオにこもって平均律やパルティータなどバッハの録音に専念、舞台のグールドを目の当たりにする夢は幻となってしまったのである。
この貴重な一夜を体験した大賀氏のソニーによって、グールド対カラヤンの幻がよみがえったとは何という奇遇だろうか。大賀さんもこのCDを聴かれただろうか。茫々と51年。いまやグールドもカラヤンも世にない。
求む!アミーゴ
琴欧州が大相撲で優勝した。朝青龍と対戦する直前、「まさかがまさかかもね」って議論をしたばかり。あれよあれよという間に実現してしまった。
実は小生のお世話になった弁護士先生が、琴欧州の後援会会長なのだ。25日の優勝祝賀では随所にカメラにとらえられていた。彼のご縁で私も恥ずかしながら後援会の一員である。
それにしても、忍の一字だった。とにかく弱い大関だったもん。
それが、カド番に追い込まれて開眼するのだから、相撲は分からない。で、本日はわが右腕、宮嶋君がそちらのお祝いに出陣、私は秋葉原でFACTAフォーラムの司会役という一夜だった。
フォーラムにお呼びしたのは、最近『政治と秋刀魚』という新著を出版したコロンビア大学教授のジェラルド・カーティス教授と、盟友の外交ジャーナリストで新著『葡萄酒か、さもなくば銃弾を』を出したばかりの手嶋龍一氏である。満席の盛会だった。このサイトをお借りして、改めて御礼申し上げます。
タイトルは「オバマと秋刀魚――日米政治の分かれ目」。語尾が「マ」の押韻を踏むシュールなタイトルだが、その意のあるところはおくみとりいただけたかと思う。民主党の大統領候補の座をほぼ手中にしたバラク・オバマに見る米国政治の転換と、それを対岸で仰ぎ見る日本の政治の対照である。カーティス、手嶋氏とも座談の名手だけに、会場の皆様にもトークをお楽しみいただけたかと思います。その内容は後日、また要旨を連載することにしております。
おふたりの新著『政治と秋刀魚』も『葡萄酒か、さもなくば銃弾を』も、それぞれ三刷が決まったそうで、めでたしめでたし。会場でのサイン&即売会も好調だったようで、さらにめでたしめでたし。
FACTAもついでに宣伝させていただくと、以前、アソシエーツ(友の会)組織を始めたいと広告を打ったことがありますが、ようやく規約などの準備が整ってきたので、会場の皆さんにもご紹介しました。有料のプレミア会員制で、記事化されていない情報などを交換・共有するもので、FACTAの新しい試みです。さっそく反応がありました。いずれこのサイトでもご案内を掲載します。
一言で言えば、アミーゴ(友)を募って、情報のお仲間になりましょう、ということです。よろしく。