EDITOR BLOG

FACTA1月号「裏ポーク」記事の訂正
弊誌2009年1月号42~43ページに掲載した「死を賭した『裏ポーク脱税』の告発」の記事中、千葉地裁で行われている差額関税59億円脱税事件(千葉地裁、事件番号は平成19年(わ)第331号、田辺正明被告)について以下の記述がありました。
08年5月30日に行われた第5回公判では日本養豚生産者協議会会長、志澤勝が証言台に立った。協会は農水省傘下の団体であり、農水省からの補助金のほか、独立行政法人の農畜産振興機構からもおよそ7千万円(平成19年度)の補助金を受け取っている。
これに対し、日本養豚生産者協議会から、「農林水産省から7000万円の補助金を受け取っていたのは社団法人日本養豚協会である。会長は両団体とも志澤勝氏が務めているが、日本養豚生産者協議会は補助金をもらっていない」と事実誤認の指摘がありました。
弊誌編集部はこの第5回公判の速記録を取り寄せて検証しました。志澤証人と検察官のやりとりの一部を抜粋しますと、冒頭では
検察官「あなたは、日本養豚生産者協議会の会長なのですか」
証人「はい、そうです」
検察官「日本養豚生産者協議会というのは、国内養豚業者が養豚業全体の発展などのために自主的に組織した団体なのですか」
証人「はい、そうです」
検察官「また、社団法人神奈川県養豚協会の顧問なのですか」
証人「はい、そうです」
検察官「さらに、社団法人日本養豚協会の副会長(編集部注=08年5月当時、現在は会長)もなされているのですか」
証人「はい、しております」
また、速記録14ページには以下のような証人と弁護人のやりとりが載っている。
弁護人「証人は、社団法人日本養豚協会の副会長も務めているということでよろしいですね」
証人「はい」
弁護人「その協会の役員というのは、農林水産省からの再就職者の方が何人いらっしゃいますか」
証人「現在は2名ですかね」
弁護人「その協会ですけれども、農林水産省系の団体から補助金の交付というのを受けていますか」
証人「受けています」
弁護人「どの程度の金額だか分かりますか」
証人「いや、余り詳しく、細かいことは分かりません」
弁護人「それから、独立行政法人の農畜産業振興機構からも補助金を受けているということでよろしいですか」
証人「はい」
この2カ所の速記録記述から、協議会の指摘どおり、当該記事の筆者が社団法人日本養豚協会と書くべきところを自主団体である日本養豚生産者協議会と誤記したものと認めます。お詫びして以下のように訂正します。
08年5月30日に行われた第5回公判では日本養豚生産者協議会会長で社団法人日本養豚協会副会長(現会長)の志澤勝が証言台に立った。同協会は農水省傘下の団体であり、農水省からの補助金のほか、独立行政法人の農畜産振興機構からもおよそ7千万円(平成19年度)の補助金を受け取っている。
3月号の編集後記
FACTA最新号(2009年3月号、2月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は25日からです。
*****
百聞は一見に如かず。お忍びで東京近郊のイオンのショッピングモールを見て回った。うんざりするほど広い。GMS、シネコン、フードコート、レストラン、スポーツジム……何でもある。が、何もない。どこまで行っても都心のダウンタウンのイミテーションである。規格化されて、一カ所見れば十分だった。
▼思わず目を疑ったのは、新作の『レボリューショナリー・ロード』まで上映していたこと。何という皮肉。リチャード・イエーツの原作は、イオンが体現しているサバービア(都市近郊)の虚妄に、ありったけの憎悪を叩きつけた作品だ。『タイタニック』以来11年ぶりのディカプリオとウィンスレットの共演と聞いて、感動作と勘違いしたのだろう。全編、罵倒の嵐と知っていたら、イオンのシネマ担当は上映を渋ったはずだ。
▼思わせぶりなタイトルは、日本の新興団地風に「新しがり通り」とでも訳せばいい。絵に描いたような郊外の芝生の団地。住宅展示場のモデルハウスのような小綺麗な家。IBMがモデルらしき大企業に通う夫と、女優志望だったが今は二児の母の妻――傍目には理想の夫婦だが、実は互いの虚像を暴いてやまない夫婦喧嘩の日々である。設定は1955年。時代からみて『セールスマンの死』の後日編、いや、源氏の宇治十帖のようにウィリー・ローマンの子世代の物語と言っていい。
▼アメリカには呪縛がある。テレビドラマ『パパは何でも知っている』のあの豊かなバラ色の家々こそ、戦後の日本が裏も知らずにただ追い求めた涅槃(ニルヴアーナ)だった。土地神話はそこに胚胎し、ウサギ小屋のマイホームをコロニアル調にする滑稽も、あのイメージの残像からである。里山を蕪(あ)れるがままにして、農村も都会と同じ化粧に走った。恐ろしいことに、今の日本のサバービアほど、みごとにアメリカの空虚、空中庭園の寂寥を体現したものはない。
キヤノン御手洗疑惑と1年前のスクープ
映画「カサブランカ」は「君の瞳に乾杯」だけでなく、数々の名台詞のある映画である。そのひとつは主役、リック(ハンフリー・ボガード)が、経営するクラブ「カフェ・アメリカン」で、捨てた女を冷たく突き放すシーン。そこでの台詞は、悔しくなるほど洒落ている。
女「昨日はどうしてた?」
リック「そんな大昔のことは忘れた」
女「あしたは」
リック「そんな先のことはわからない」
映画のストーリーそのものを象徴しているのだが、このところのキヤノンと鹿島と逮捕されたコンサルタント会社「大光」社長、大賀規久容疑者の報道を見るにつけ、この台詞を思いだす。
FACTAがこの疑惑を報道したのは、1年前の08年2月号(「キヤノンと鹿島『裏金』疑惑」)である。毎日がその端緒を報じたが、事件全体の構図と御手洗キヤノン会長の責任を正面から追及した先駆けだったと自負している。しかもこのときは、キヤノン常務(現在は専務)が大分県公社に対し鹿島を“推奨”する内部文書までスクープしているのだ。
大分県財界の関係者によれば、御手洗と大賀兄弟はさながら家族のように育ち、切っても切れぬ関係なのだという。しかし大光の巨額脱税の一報を受けた御手洗は「迷惑している」と語った。大賀規久を高校時代から健三の弟として認識していたことは認めたものの、「お互いのビジネスには干渉しないという間柄」(キヤノン広報部)で、便宜を図ったことなどは一切否定している。
だが、本誌は興味深い依頼書を入手した。キヤノンのロゴマーク並びに本社所在地などが記載されたA4判の文書で、文章はこう始まる。
「貴公社には、大分キヤノン株式会社大分事業所の用地造成にあたり、格段のご支援ご協力を賜りましたことに対し深く感謝申し上げます」
キヤノンの常務取締役総務本部長の諸江昭彦が、05年7月1日付で「大分県地域づくり機構」(大分県土地開発公社)理事長、矢野孝徳に宛てた要望書だ。さらにこう続く。
2008年2月号「キヤノンと鹿島『裏金』疑惑」
それから1年、東京地検特捜部と東京国税局はやっと摘発に動いた。御手洗会長とキヤノン広報は、他人事のようなコメントを出しているが、この内部文書だけで、なぜ大賀容疑者が30億円以上の裏金をせしめていたかが手に取るように分かるはずだ。
今の新聞報道は、それから一歩も出ていない。この摘発が政界にもキヤノンにも波及しないとしたら、裁判員制度開始を5月に控えて、経団連に御手洗会長を訪ね、協力を求めて頭を下げた樋渡利秋検事総長の弱腰を撃たなければならないのに、どこもそこには踏みこまない。これはシラける。
FACTAは1周後れの報道合戦に参戦するほど暇ではない。だが、1年前のスクープは何だったのか。
「昨日のこと?そんな大昔のことは知らない」
そう言われないために、それをフリー・コンテンツとして公開しよう。司法記者会諸君もよくご覧じろ。
鳥居民『昭和二十年』第一部12巻のススメ
熊本日日新聞に、5年ぶりに続刊が出た鳥居民氏『昭和二十年』の書評を掲載した。それをここに再録する。文中では触れなかったが、6月14日は私の母の命日でもある。もっとも亡くしたのは昭和ではない。平成になってからだが。それでも現在までの12巻で、この1日だけが一巻をなしたのは、個人的には感慨が深いが、となると、8月15日は何巻を占めるのだろう。
*****
鳥居民著『昭和二十年』第一部(12)木戸幸一の選択【6月14日】
(草思社、2000円)

道半ば、昭和の『神曲』
万巻の書を読む――ブエノスアイレスの司書だった不思議な作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの果てしない『バベルの図書館』に憧れたことがあった。
それが、不遜、と思い知ったのは10年前だろうか。渡英してケンブリッジ大学に籍を置き、その中央図書館に乗り込んだ。大英図書館などと違って開架式なので、本を渉猟する研究者は書棚の前に立てる。それがいけない。
薄暗い書庫の端から端まで、床から高い天井まで、本また本の広大な迷宮。一生かけても読み切れない。1万冊の本を読んだところで、スズメの涙なのは火を見るより明らかだ。
天を仰いだ。人生には限りがあり、知識にも限界がある。
鳥居民氏の『昭和二十年』シリーズは、崩壊寸前の日本の全豹を宮中から疎開先まで網羅した1年間のドキュメンタリーに凝縮しようとする破天荒な試みである。
地獄に仮託して、カソリック中世の宇宙を描破したダンテの『神曲』に匹敵する。その徹底した資料収集は他の追随を許さず、世に数多く上梓されている終戦秘話や昭和天皇論の大半は、こっそり本書を種本にしている。
だが、未完なのだ。1月1日の記述から始まる第一部第1巻が1985年の刊行。今回出た第一部第12巻「木戸幸一の選択」はまだ6月14日のあたりで、23年余かけて昭和二十年の半分にも達していない。
一日千秋の思いで完結を待つ読者は、私を含めて気を揉んでいる。第11巻が出てから5年のブランクがあった。その間、鳥居氏は『「反日」で生き延びる中国江沢民の戦争』などを書いて“寄り道”した。
鳥居氏は今年、80歳になるはずだ。糊口の資を稼ぐためかもしれないが、人生には限りがある。時間が惜しい。
ようやく渇を癒してくれた第12巻の新刊も、長い空白のあとのせいか「この一年半を回顧して」と昭和19年に引き返し、「さらに前に戻って昭和十六年十一月三十日」と逆流する、なんとも悠長な足取りである。『大菩薩峠』や『ガラスの仮面』のように、だんだんテンポが緩くなって、悠久の時間が流れだし、未完となる予感がする。
むろん、この中仕切りは必然なのだろう。どうやら鳥居氏の意図は読めてきた。内大臣、木戸幸一の「不作為の作為」こそ戦争の主因だった、という断罪である。
これは戦勝国の政治意図にまみれた東京裁判に代わって、自国による検証を通じて昭和天皇から庶民まで責任の所在を問う「もうひとつの東京裁判」の試みではないか。更迭された空幕長のような不勉強「右翼」は、爪の垢でも煎じて飲むがいい。
注の部分では、原武史氏が『昭和天皇』で展開した貞明皇太后「神がかり」論への批判もあるから見過ごせない。そしてこの六月十四日、焼け野原となった帝都の日比谷公会堂で、ベートーベン第九交響曲のコンサートが開かれているのも驚きだった。
偶然だが、この日は「ブルームズデー」――ダブリンの1日にアイルランドの過現未を凝縮したジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』の日でもある。
ジョイスは完成に17年かけた。鳥居氏の昭和の『神曲』も、せめて終戦の詔勅までの第一部は書きあげてほしいと思うが、せかすのは失礼だろうか。
(了)
“健全”地銀も一皮むくと――新聞掲載コラムより
新潟日報など環日本海6紙のシンジケートコラム「時代を読む」に寄稿しました。前回は地銀を主たる対象にした「時価会計凍結」への批判でしたが、今回は金融機関強化法の成立を受けたその続編。日経平均株価がまたも7000円台に滑り落ちているなかで、いよいよ3月期末が迫ってきた地銀の憂色が濃い。いくら会計原則を曲げてゲタをはかせても、その「不健全」さは中小企業など地元企業への貸し渋りとなって、ますます景気を悪化させる悪循環の様相を呈しています。政府に資本注入を申請すると発表した第二地銀を例に、金融庁の監督行政の矛盾を書いてみました。
*****
「時代を読む」
“健全"地銀も一皮むけば
新聞はそれを「『健全』地銀に公的資金」と報じた。
1月19日、北海道を地盤とする第二地銀最大手、札幌北洋ホールディングスが、公的資金による資本注入を年度内に申請する方針と発表、それを報じた記事の見出しである。
「予防的」に銀行の資本を増強し、中小企業向け融資の貸しはがしや貸し渋りを招かないよう、昨年12月に成立した金融機関強化法に基づく申請第一号だからだ。
財務相を兼ねる中川昭一・金融担当相も「(銀行の)申請後、一定の審査等で認められた金融機関に、健全だという前提で国が資本参加し、その資金でレバレッジを効かせ、中小企業に融資できる」(傍点は筆者、「金融ビジネス」2009年冬号)と強調している。
資本注入申請で経営危機の風評被害が起き、とりつけ騒ぎになるのを恐れる地銀が多いので、「ご安心ください。申請しても、その健全性は国が保証します」という意味だろう。
だが、ほんとうに健全なのか。
札幌北洋は1997年に破綻した都銀、北海道拓殖銀行の営業を引き継いだ北洋銀行と札幌銀行が合併して設立した持株会社。第二地銀協会会長行で、中川金融担当相の地元銀行でもある。昨年9月末の自己資本比率(連結)をみると、9.2%。国内金融機関の基準(4%)を上回り、一見余裕がありそうだ。
だが、9月中間では両行合計で78億円の純損失を出している。
忘れてならないのは9月のリーマン・ショック以降の株価急落。海外勢が日本株を売るとともに、変動利付国債も投げ売りしたから、地銀が保有する株と債券の両方で含み損が膨らんだ。
慌てた金融庁は地方銀行協会の要請もあって、12月から国内基準行の有価証券評価減を自己資本に反映しない特例措置を設けた。自己資本比率にいわばゲタをはかせることになったのだ。株価や債券相場の“異常"市況がいずれ回復するという前提である。
まさに「臭いものにフタ」。しかし異常どころか、この1月下旬に日経平均株価はまた7000円台まで下がり、定着しそうな形勢だ。となると、フタをした含み損は銀行の融資にブレーキをかけ、金融庁の狙いとは逆になりかねない。
実はこうしたゲタを外して、前08年3月決算から実質自己資本比率を逆算した試算がある。それによると、不良債権のロスが前期1074億円に達していた北洋(単体)は、実質自己資本(国際決済銀行基準でいう中核的資本=ティア1)は3.90%、有価証券の含み損がなくても堂々たる基準割れだ。
1月21日には札幌北洋の後を追って、第二地銀の南日本銀行(鹿児島)も公的資金による資本注入に手を挙げた。同行は公表自己資本比率が7.07%だが、含み損を差し引いた先の試算では、日経平均8000円で何と0.57%、同7000円だと0.17%である。
どこが健全なのか。債務超過寸前ではないか。第二地銀では、この実質ティア1の4%をクリアできるところなどほとんどない。日経平均8000円でマイナス(債務超過)に転落するとみられるところが、少なくとも第二地銀で8行、第一地銀で1行はある。
やはり“アブナイ"からこそ、政府の資本注入に手を挙げるのではないか。それを糊塗する金融庁は、特例措置といい、資本注入といい、表向きだけ自己資本比率を守ることに汲々としながら、一方では「中小企業向け融資をもっともっと」と尻をたたく。アクセルとブレーキを同時に踏んでは、銀行も経済もノッキングを起こすはずだ。
財務省幹部が首をかしげる。「07年竣工の霞が関コモンゲート(38階建て)に入居して以来、金融庁はどうもセキュリティが厳しすぎて、隣人のわれわれですら3つも4つもチェックを経ないとたどりつけない。だから“引き籠もり"になったんですかね」
財務省の前身、旧大蔵省から枝分かれした金融庁は、古巣に「KY(空気が読めない)官庁」と言われたにひとしい。政策金融が民営化に踏み出したいま、中小金融の「空白」を埋められなければ、金融庁は貸し渋りの「戦犯」と名指しされるだろう。
消費税増税のドタバタ劇
3年後に消費税を増税する方針を盛り込むかどうかで揉めた2009年度の税制改正関連法案が、ようやく23日に閣議決定した。麻生太郎総理が相当こだわって、ついに押し通した形だが、終わってみればから騒ぎもいいところである。
騒ぎの背景には、麻生政権が金融危機に対応するためには景気テコ入れ策が必至で、小泉政権が「骨太の方針」で定めた2011年度までにプライマリーバランス(財政の基礎収支)を黒字化する公約を守れなくなったことがある。金融安定化のための二次補正予算までは組んだものの、閣内には財政再建派の与謝野馨・経財相を抱えているうえ、財務省もなし崩しの財政再建の反古は見過ごせない。そこで麻生総理はこの危機を全治3年とみて、3年後に消費税増税を約束、当面の大判振る舞いの免罪符にしようとした。
ところが、今年は衆議院の任期が9月に切れる「選挙の年」。消費税を創設した竹下内閣、増税に踏み切った橋本内閣が潰れたように、消費税に手をつけた政権は選挙で負けるというジンクスがある。党内には「この不況期に非常識」と反対論が巻き起こったが、麻生総理としては定額給付金問題での発言のブレが支持率急落を招いただけに、今度は頑として譲らない。そこに野党の民主党がつけこんで、政局にしようとしたからドタバタ劇が始まった。
漸くまとめ上がった文章は玉虫色。2011年度までに「必要な法制上の措置を講ずる」というもので、実際の増税の施行期日は景気回復の状況を見極めたうえで、別の法案で定めましょうという2段階方式。増税の前提として、行政改革の推進や歳出の無駄の排除を「一段と注力して行う」ことも明記してある。要は状況が変わればいくらでも変更がきく文面で、「3年後の増税が決まったわけではない」とも弁解できようになっているのだから、麻生総理の勝利とも言い切れまい。
しかし、眼目は反対派の急先鋒だった中川秀直・元幹事長ら「上げ潮派」を封じこめたことにある。21日、説得の担当だった保利耕輔政調会長が電話をかけただけで、修正案さえ示さなかったことに中川氏が態度を硬化。新党構想までちらつかされて、慌てた河村建夫官房長官が同日夜に低姿勢で説得に動く。中川氏は「消費税の必要性は分かるが、なぜ今出す必要がある。若い議員の気持ちもくんでほしい」と付則の修正文を見ながら、およそ1時間に渡り批判したものの、「そこを何とか」と頭を下げる官房長官に対して、最後は「予算には全面的に協力する。離党はしないよ」と語ったという。決定打は中川氏が属する町村派の最高実力者、森喜朗元総理の22日付朝日新聞のインタビューだろう。中川氏を「完全に反乱だ」と猛烈に批判したうえで、「(派の)代表世話人を辞めて(反対行動を)やるべきだ」と突き放したことで大勢が決着した。
一方、町村派のもう一人の重鎮、町村信孝・元官房長官は2段階方式を推進。自民党税調委員でもある町村氏は、伊吹文明前財務相と連携して「2段階」方式の修正案をまとめたが、これに与謝野経財相が異を唱え紛糾。それをさらに町村氏が巻き返して通すという、裏側での壮絶な蹴りあいもあった。安倍晋三元首相も中堅・若手の反乱を抑えるべく説得に回っていたというから、麻生総理は各派閥に大きな借りを作ったことになる。
総務会の前に8派閥首脳が集まってこの「2段階方式」を了承したことが膠着していた事態打開のカギとなっただけに、政局が動くことを期待していた向きはあて外れだろう。結局、反対派も最初から総選挙の免罪符がほしかっただけで、「どうせ麻生政権、あるいは自民党政権だって3年後にはないから、消費税増税の布石を打ったって、カラ証文になる」と踏んでいるのだ。離党の根性などハナからないから、力の弱った派閥の恫喝にも簡単に屈したとみえる。
対する民主党も国会攻防の次の攻め手を見失っている。消費税増税で自民党が迷走し、定額給付金よりも「造反が増える」とみて、税制改正関連法案から消費税の付則を削除する修正案を「第二の造反誘導策」として提出を検討していただけに、こちらもあて外れである。政調会長の直嶋正行氏が小沢一郎代表と党本部で会って、「自民の造反もあまり期待できない状況になった」と早期解散追い込み策の見直しを協議するよう進言したが、副代表の石井一氏が参院予算委で麻生総理に漢字テストを挑んで顰蹙を買っているようでは話にもならない。この未曾有(みぞゆう)の経済危機に、まったく空気が読めない党ではとても政権運営などおぼつかないだろう。
オバマ新大統領就任
米国時間の1月20日、日本時間では1月21日(水)午前2時に、いよいよオバマ新大統領の就任式がワシントンの議会議事堂前で行われる。新大統領の就任式といえば、アメリカでは国王の即位式典にも等しく、4年または8年ごとのお祭り騒ぎである。とりわけ今回は史上初の黒人大統領の誕生とあって、ワシントンポストの記念特別号は飛ぶように売れ、Tシャツやマグカップなどの「オバマ・グッズ」も大盛況だとか。空前の盛り上がりの経済効果は、17日~20日の4日間だけで、およそ10億ドル(約900億円)と試算されている。
この期待の高さは、それだけ今のアメリカが経済も対外政策もどん底であることの裏返しでもある。それを誰よりも実感しているであろうオバマは、意識して自分をリンカーンになぞらえる。自身と同じくシカゴ出身で、人種差別と戦い、南北戦争の試練を乗り越え、戦後は政治・経済とも傷ついたアメリカに宥和を訴えた大統領に。オバマが大統領選に出馬宣言したのも、若きリンカーン弁護士が過ごしたスプリングフィールドの地だ。オバマはこの1月17日には独立宣言の地、フィラデルフィアから特別列車でワシントン入りしたが、これもリンカーンの例を踏襲したもの。20日の就任式では、リンカーンが使った聖書に手を置き宣誓するというのだから、まさに「リンカーンづくし」である。
就任演説では、雄弁家のオバマらしく、1960年にJ・F・ケネディが「国が君のために何をするかではなく、君が国のために何をするかを考えよう」と語った名演説に匹敵するような歴史的スピーチを目指しているだろう。フィラデルフィアの駅頭では200人の招待客を前に「イデオロギーや偏狭な考え方からの独立」を訴えて「新独立宣言」と称したが、それを上回る格調の高いものになりそうだ。
だが、言葉に酔ってばかりもいられまい。オバマ政権は滑り出しからいきなり試練にさらされる。政権から100日間はマスメディアも大統領への批判を慎むハネムーン期間と言われるが、今はそんな悠長なことを言っていられないほど金融危機再来が迫っている。先週末には、米銀最大手のシティがグループの2分割案を発表。昨年、2度も政府の支援策を受けたにも関わらず、連結決算外の傷が深すぎて立ち直れないままだ。シティの総資産は2兆ドル(約180兆円)もあるが、これを銀行や投資銀行などの中核部門と証券業務や消費者金融などの非中核部門に分け、将来は中核部門だけを残して売却するという。日本も他人事ではなく、シティ傘下の日興コーディアル、日興アセットが非中核部門に入れられて、将来は売りに出されることになった。シティは銀行が証券、保険、クレジッドカードなどあらゆる金融業務を兼ね、ワンストップの便利さを売りにするビジネスモデルを謳っていたが、実は中はてんでバラバラだったことが露呈、とうとう空中分解に至った。しかし、話はシティだけにとどまらない。同じく追加支援を受けたバンク・オブ・アメリカ、さらに欧州や日本のメガバンクも大なり小なり同じ方向を目指してきたからだ。シティの挫折はさらなる金融機関再編の呼び水になるだろう。
オバマ新政権もそれに備えるかのように、ガイトナー財務長官ら経済チームが新たな政策を考えているようだ。発足とともにブッシュ前政権の金融安定化策は改めて見直されることになる。17日付のウォールストリート・ジャーナル電子版は、これまでのような資本注入や政府による債務保証では足りないとして、金融機関の不良資産をバランスシート(貸借対照表)から切り離す「バッドバンク、グッドバンク」構想が浮上していると報じた。「バッドバンク、グッドバンク」とは聞き慣れない言葉だが、要は不良資産を旧勘定の受け皿銀行に集中させ、銀行業務は新勘定の銀行で続けて息を吹き返させるというもので、日本でも地方金融機関などの再生にこの方式を使った経緯がある。
まさに、シティの2分割はその先ぶれにみえる。いまのアメリカの金融株急落の惨状ではまさに「待ったなし」。一部報道では、金融機関の追加支援には新たに最大1兆2千億ドルが必要だとの試算も出ているが、ブッシュ政権下の金融安定化策の残り3500億ドルに上乗せして新たな銀行支援に乗り出すのかどうか…。オバマ新政権の長く険しい初仕事が始まる。
2月号の編集後記
FACTA最新号(2009年2月号、1月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
心電図に妙な波形が現れるので、水道橋のクリニックに通っている。優に3階分はある高架駅のホームに降り立つたびに思い出す。終戦の翌年、泥酔した批評家の小林秀雄が、ここの鉄柵の間から地面に転落したそうだ。抱えていた一升瓶は粉々になったが、落ちたのが幸い石炭殻の山。奇跡的に無傷で済んだらしい。
▼未完の長編『感想』冒頭のエピソードである。ベルクソンを論じながら相対性理論に挑んで尻尾を巻き、封印した失敗作だ。改めて読んで、この人、微積分が全然分からず、力みかえっているうちに、くたびれたのだと知った。ベルクソン十八番の「ゼノンのパラドクス」を下敷きにしているが、文章そのものが堂々めぐりの祖述に陥り、亀に永遠に追いつけないアキレスになってしまう。
▼数学者を嘱望されながら哲学に転じたベルクソンは、さすがに「ゼノンの運動否定は、動体の描く軌道や曲線と運動そのものを混同した」からで、運動や時間は空間化しえないことを発見した。そのとき「果てしない野心に燃えた」とシュヴァリエとの対話で語っている。それゆえ純粋持続も生の跳躍(エラン・ヴィタール)も着想できたのだが、微積分に魅せられた人しかこの機微は分かるまい。微分がとらえた運動は空間であって時間ではないのだ。
▼先日亡くなった伊藤清・京大名誉教授の「伊藤のレンマ」を土台にしたブラック&ショールズの確率偏微分方程式と同じだ。株のオプション取引の値段(プレミアム)が、現在の株価、権利行使価格、満期までの残存期間、金利、配当率、過去の相場変動率(ボラティリティー)の6要素で決まる方程式は呆然とするほど美しい。が、それは生きた相場の近似でしかない。数学嫌いのデリバティブ(金融派生商品)性悪説は、追いつけぬアキレスを責めるようなもの。たかが微分、と観じれば相場の「水道橋」からも落ちない。
続・ニュースサイト戦国時代――長坂嘉昭プレジデント編集長に聞く
新聞に続き、雑誌や通信社も巻き込んだニュースサイトの再編が活発化している。本誌2008年11月号でも報じたが、ビジネス誌「プレジデント」を発行するプレジデント社が世界最大手の通信社トムソン・ロイターと共同でオンラインメディア「プレジデントロイター」を10月に立ち上げた。プレジデントが得意とする自己啓発やノウハウ記事とトムソン・ロイターの国際・金融ニュースを両輪に、ビジネスパーソンや投資家向けの「日本最強の仕事とお金の問題解決サイトを目指す」という。現時点でビジネス誌のNO.1サイトである「日経ビジネスオンライン」を追撃する。
FACTAでは、プレジデント編集長でプレジデント・ロイターの編集長も兼任することになった長坂嘉昭氏にインタビューを行い、今回の提携のいきさつや今後のメディア戦略について話を聞いた。
*****
阿部10月にトムソン・ロイターと提携し、両者のコンテンツを提供しあうオンラインメディア「プレジデントロイター」をオープンさせました。この時期に、世界最大手の通信社と共同サイトを立ち上げた狙いをお聞かせください。
長坂もともと「プレジデント」にも独自サイトはありましたが、雑誌の紹介や購読受付の窓口としての役割がメインで、コンテンツ配信を目的とした作りではありませんでした。実は、これまでネット化に本格的に取り組んでこなかった背景には、本誌の部数と広告が順調だったことがあります。出版業界全体で見れば、雑誌販売部数が10年連続で対前年比割れが続くなど惨憺たる状況ですが、ビジネス誌に関していえば逆風を感じるほどではなかった。プレジデントにしても2008年1~6月発行号の実売部数は前年同期比で8%以上増えています(ABC調べ)。正直、業界全体の総論として語られるように、誌面の広告収入が減少しているからネットで何か手を打たなければいけないという状態ではなかったんですね。

ただ、将来を考えるとそろそろネット化を進めなければいけない時期かなとは感じていました。とはいっても、いまさら自社開発でサイトを立ち上げようにも、先行するライバルの「日経ビジネスオンライン」とは既に何周差もついている状況だったので、単純に自前で立ち上げたところで追いつけるとは思えなかった。そんな時に、何社からか提携などの話をいただいてまして、立ち上げに要する時間を買うという意味でもどこかと一緒にやるのが良いのではないかとなったわけです。
パートナーとしてトムソン・ロイターを選んだのは、世界最大手の通信社としてのブランド力を持っていることと、お互いの持つコンテンツの強みが、プレジデントは“読み物”、ロイターは“速報ニュース”と違うけれど、読者プロファイルは非常に近いということの2つが大きな理由です。つまり、コンテンツのカニバリズムを起こさずに、相乗効果を出しすいと。例えば、企業の意志決定者や管理者には世界の動きにセンシティブであることが求められる一方で、上司として部下を使ったり、常に状況判断をすることも必要になってきます。そういう人たちが持つ情報へのニーズを2社が組むことで上手く満たせるのではないかと考えました。また、それぞれが読者に多くの投資家や富裕層を抱えているということも広告面で大きなプラスになるのではとの期待もあります。
阿部サイト全体のイメージはトムソン・ロイターの既存サイトに合わせた作りになっています。
長坂“時間を買う”ということを考えると、やはりトムソン・ロイターが持っているシステムを使わせてもらうのが一番いいだろうということになりました。デザインについてはトムソン・ロイターのグローバル・ポリシーに準拠する必要があったので、その範囲で収まる作りになっていますが、メニューを「社長の仕事術」や「達人のテクニック」「部課長の基本」といったネーミングにすることで、プレジデントらしさが出るようにしています。
阿部まだ、オープンして間もないですが、手応えはいかがですか?
長坂直近の2008年12月のPV(ページビュー)が約300万PV、1人当たりの滞在時間が約10分と、まずまずのスタートではないかと思っています。ページごとのPVを分析してみても、よく読まれている記事についはおよそ想定通りですね。ただ、中には意外に人気が出た記事もあったりしたので、しばらくは試行錯誤が続くと思います。
広告については、雑誌とネットがセットになったことで、クロスメディアとして出稿してくれるクライアント企業も増えてきており、一定の効果が出始めているところです。日本IBMの協賛を得て、日本の温室効果ガス削減目標に貢献するユニークなキャンペーンも行いました。これは、エコ先進企業を取り上げた特設サイトの記事が1PV読まれるごとに1kgのCO2排出権を日本政府へ移転するといったもので、ネットだからできた取り組みですね。
阿部ここしばらく、新聞や雑誌を含めた国内外のメディアの動きが慌ただしくなっています。立ち上げに当たって、他メディアの動きは気になりましたか?
長坂気にならなかったと言えば嘘になりますが、やはり本誌が好調だったこともあって、そこまで強くは意識していませんでした。ただ、海外の動きや国内の再編などを見ていて周回遅れからネットに参入するのは簡単ではないとは感じていました。それに、朝日、読売、日経が提携して3社ポータルを作ったり、共同通信がヤフーからコンテンツを引き上げて地方紙と一緒に独自サイトを立ち上げたりしていますが、既存のマスメディアが持つ影響力をそのままネットに持ち込めているかといえば、必ずしもそうでないことが多いので、我々も簡単には通用しないなと覚悟しています。
阿部サイトに掲載されているコンテンツに本誌との違いはありますか?
長坂今は月に約150本ほどの記事を載せていますが、そのうちの8割以上は本誌の転用になります。連載記事は発売直後から順次アップしていますが、特集記事については本誌とのカニバリズムを避けるために一部を2、3カ月のタイムラグを置いて掲載している程度です。
阿部将来的には本誌のプレジデントとネットのプレジデント・ロイターの関係はどうなっていくのでしょうか。今後、ネットが軌道に乗って収益も大きくなったときに、どこまで本誌のコンテンツをネットに載せるのかなど、社内でコンフリクトが起こる心配はありませんか?
長坂そこまでいけば立派なもんですよね(笑)。確かに雑誌をネット化させるうえでは避けて通れない議論かもしれませんが、自分たちでやらなければ他社の参入を許すことになりますから、むしろ社内で紙とネットがライバル心を持つことは会社が発展するための健全な競争だと期待を込めて思っています。
阿部今後のネット戦略についてお聞かせください。
長坂今回のトムソン・ロイターとの提携については本格的なネット化への第一歩と考えています。まずは、いろいろと勉強したい。それに、プレジデント以外にも「プレジデント・ファミリー」や「dancyu」など好調な媒体がいくつかありますし、昨年12月には株式会社ALBA発行からゴルフレッスン誌No.1の「ALBA TROSS-VIEW(アルバトロス・ビュー)」の雑誌販売権を取得したので、2月からプレジデント社が発売元になります。こういった雑誌については更なる提携もあり得ますので、総合的なネット戦略のなかで様々な可能性を模索していきたいと思います。
ただし、今後もネットにしろ紙にしろ、そのカテゴリーでナンバーワンかオンリーワンになれる媒体しかやるつもりはありません。広告全体のパイが小さくなるなかで、大手出版社のように人が余っているから新しい媒体を作るなんてことは考えられません(笑)。あとは、編集長がブランド・マネージャーとして、媒体のブランドを上手く活かしたビジネスを生み出していきたいですね。
(了)
写真:大槻純一
*****
長坂嘉昭(ながさか・よしあき)
プレジデント編集長 兼 プレジデントロイター編集長
1963年生まれ。早稲田大学商学部卒。東洋経済新報社、扶桑社を経て、90年にプレジデント社に入社。「プレジデント」編集部に配属され、幅広い業種・業界を対象とした取材活動を行う。98年同編集部副編集長、2003年同編集次長、05年同編集長に就任し現在に至る。「PRESIDENT Online」「プレジデントロイター」の編集長も兼務。
緊迫の中東情勢
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は毎週月曜日にTBSラジオの早朝番組「生島ヒロシのおはよう一直線」に7分ほど電話出演していて、生島氏から振られたニュースについて解説しています。昨年4月から9カ月経つので、さすがに月曜の午前5時過ぎに起きだし、45分からの放送に備えるのには慣れたが、よく勉強していらっしゃる生島さんには到底及びません。恥ずかしいのであまり告知してなかったが、朝早いので何人かの方から内容をブログにアップして欲しいとリクエストをいただいた。
さすがにそのままポッドキャストで配信するわけにもいかないので、テキストに起こして加筆・編集したものを載せることにしました。以下は、5日に出演した分ですが、多少内容が古くなっていることはご容赦ください。
*****
パレスチナ状勢が風雲急を告げた。年末年始に掛けて、イスラエルがパレスチナ自治区ガザを空爆。8日間余りで死者は500人を超えた(8日現在で700人以上)。
米国でオバマ新政権が発足するまで2週間を切ったが、政権移行のエアポケットを尻目にイスラエルの軍事作戦がエスカレート。民間人も含め3000人以上が死傷しており、ほとんど戦争状態である。米国発のクライシスで世界が景気悪化の不安に包まれるなかで、不穏な戦争の影がちらつく。
イスラエルとパレスチナの歴史は非常に複雑で、今回もどちらが挑発したかの水掛け論だ。ガザはイスラエルの南部に位置し、地中海に面した人口150万人ほどの非常に狭い地域で、イスラム原理主義のハマス(イスラム抵抗運動の略称)が支配しており、長年に渡り過激派の拠点になってきた。3年前にイスラエル軍が撤退してからは、ハマスによるロケット砲や迫撃砲の攻撃が断続的に続き、イスラエルを苛立たせてきた。数千発以上撃ち込まれた弾丸の中には経済の中心地であるテルアビブに届きそうなものもあり、ついに堪忍袋の緒が切れて攻撃に踏み切ったというのがイスラエルの主張だ。住宅密集地にF16戦闘機でピンポイント攻撃を繰り返しているが、武装兵よりも宗教指導者や政治家をターゲットにしていると言われており、攻撃に巻き添えになった民間人についてもハマス支持者への懲罰といった意味合いとも取れる。しかし、これまで3年間のイスラエル側の死傷者が十数人なのに対して、パレスチナ側の死者が今回の攻撃だけで500人以上にのぼるのは、明らかに非対称だ。
対するハマスは、ガザとイスラエルの境界にある検問所を閉鎖して経済封鎖に追い込むイスラエルこそ挑発者だとし、ロケット攻撃は正当防衛だと繰り返し主張。この裏側には、2006年のパレスチナ総選挙でハマスが過半数の議席を握ったことが大きく影響している。パレスチナのもう一方の自治区である死海に面したヨルダン川西岸は、故ヤセル・アラファト前自治政府議長の後継者であるマフムード・アッバス議長が率いる穏健派のファタハが拠点としており、ガザとの二重構造になっているのだ。長年、イスラエルが米ブッシュ政権と一体になり、ファタハのみを交渉相手とし、ハマスに対しては封じ込め政策を取り続けてきたことも問題をより複雑にしている。
3日、イスラエルの地上部隊がガザに侵攻したことを受けて、国連安全保障理事会が緊急会合を開き、即時停戦を求める議長声明案について協議するも、米国の反対で合意には至らなかった。フランスのニコラ・サルコジ大統領がイスラエルやエジプトを訪れてシャトル外交を試みているものの、情報機関モサド出身で次期大統領の有力候補でもあるツィピ・リブニ外相は一歩も譲歩しない姿勢だ。彼女は来月の総選挙を前にハマスを叩くことで国民の不安を取り除き選挙を有利に進めようというのだから、そう簡単に引くとは考えにくい。
米国のオバマ新政権に目を転じてみても、首席補佐官に指名されたラーム・エマニュエル氏がイスラエル生まれ、国務長官になるヒラリー・クリントン氏もユダヤロビーと近いとあって、やはりイスラエルの肩を持つ中東政策が大きく変わることは考えにくい。発足早々から、ブッシュ政権最大の難題をつきつけられた新チームは大きく躓く危険をはらんだ船出となる。
日本はといえば、麻生太郎首相が3日にアッバス議長と電話会談し、外務大臣時代にヨルダン川西岸の農業支援構想を唱えたこともあって、1千万ドル規模の緊急人道支援を行うと伝えた。しかし、アッパス議長とのパイプはあっても、ハマスにまで影響力を行使できるかといえば難しいだろう。
イスラエルは3年半前のレバノン撤退の教訓を忘れたのだろうか。地上侵攻が市街地でのゲリラ戦や自爆テロを引き起こしかねないことは明らかだ。インティファーダと呼ばれる武装蜂起運動が再燃すれば、中東のみならず世界中がまたテロの嵐に巻き込まれかねない。早晩、ガザが地獄絵図にならないことを願う。
「逆さまの地球儀」と「サンパウロのサウダージ」
まだ見ぬ国がある。何度かチャンスはあったが、南米は行き損ねた。ロンドンに駐在していた時代、無理をしてでも飛んで行くんだった、と今でも後悔する。
それは忘れた夢のようなものだ。たまたま、サンパウロに縁のある2冊の本を、この正月休みにようやく読むことができた。積年の渇を癒したので紹介したい。
・和田昌親『逆さまの地球儀複眼思考の旅』(日本経済新聞出版社1900円+税)
・クロード・レヴィ=ストロース『サンパウロのサウダージ』(今福龍太訳、みすず書房4000円+税)
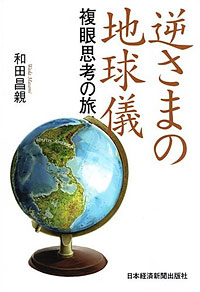
正直に言えば、前者は私のロンドン時代の上司である。彼が赴任した日は忘れもしない。1997年8月31日。ヒースローに出迎えて、宿に送り届けたはいいが、その未明、ダイアナ妃が事故死、翌日からてんてこ舞いになったからだ。
東京外国語大学を出てサンパウロ支局に赴任した経歴からも、われわれ金融記者が略称「ラ米」で呼んでいたラテン・アメリカの根っからのファンである。吉田茂のような英国好きを「アングロファイル」と言うが、「ラ米ファイル」は英語でなんて言うのだろう。
ニューヨークでデスクも務めたが、周囲は北米一辺倒の記者ばかりのなかで、南米に土地勘を持つ記者は常に少数派を強いられる。日本経済新聞の常務を昨年退いたのを機に、孤独な「ラ米ファイル」の胸襟を、地球儀を逆さまにする発想でひらいたのが本書である。
ロンドン時代も「中南米を見くびっちゃいけない」と教えられた。たまたま、銅相場の投機にからむ商社の不正事件が発覚、それを機にアフリカはザンビアの銅鉱山を取材に行ったが、どうせなら世界最大のチリの銅山を見に行けばよかった、と今でも思う。
1980年代に中南米債務といえば、いまの「サブプライム」と同じ禍々しい響きがあった。債務を流動化するブレィディ構想(ブレィディ米財務長官の提唱)が、サブプライムの証券化商品の源流になったことを思うと、確かに「中南米を見くびっちゃいけない」という言葉が切実に響く。
本書I-6「借金の文化」に書いてあるエピソードだが、業者に即金で払うのは愚で、残金が業者に対する交渉力になるという。中南米の「借金の文化」は、確かに「ラ米の居直り」として先進国には評判が悪かったが、いまや米欧金融機関がこの「居直り」の交渉力によって生きながらえようとしているのを見ると、もはや中南米を笑えない。
そういうしたたかさの底に、「北」の怜悧で冷徹な搾取の合理主義に風穴をあける可能性があると見るのが本書の主眼だろう。筆者は「北対南」という座標軸に仮託して、「西対東」という座標軸に90度向きを変えようとしているかに見える。南が北を逆転できるなら、東も西を覆せる(明治以来の欧米追随の逆転)はずだ、と。

だが、ブラジルにとって「北」は必ずしも北米に限らない。言語の母国ポルトガル、その背後にある欧州との屈折した関係は、ロンドン時代にかいま見ることができた。この11月28日に100歳を迎えたレヴィ=ストロースの『サンパウロのサウダージ』は、このもうひとつの南北軸を見せてくれる貴重な写真集である。
名著『悲しき熱帯』は一読、忘れ難い本だ。レヴィ=ストロースの悲調を帯びた叙述は、ナチスに追われてブラジルへ亡命する船旅を淡々と描写している(レヴィ=ストロースはユダヤ系)が、この写真集はそれに先立つ1935~37年にサンパウロ大学に赴任し、授業とフィールドワークの合間に、ライカを抱えて往時のサンパウロを撮影したものだ。
人が写っていても、何か寂しくもの哀しい風景である。訳者が付した現在の写真と比べても、その変貌ぶりは痛ましいほどだ。老文化人類学者の感傷ではない。ここにはヴァルター・ベンヤミンの言う過去のオーラ、消えがてのオーラが後光のようにさしている。
レヴィ=ストロースが言うように、「サウダージ」という言葉は翻訳不能らしい。母国ポルトガルのファドの歌詞にも「サウダード」(サウダージはブラジル・ポルトガル語の発音)が登場するが、悲しみ、郷愁、寂しさ……どれも何か足りない言葉なのだ。レヴィ=ストロースはそれを日本語の「あはれ」なぞらえているが、やはり違うと思う。
しかし視覚とは有り難いものだ。この写真がとらえたものが「サウダージ」だとするなら、少しわかる気がする。まだ見ぬ国だとしても、この寂しい風景は、戦前の日本の街角にもあったものだ。私はまだ「隆々たるブラジル」を信じることができないが、「サンパウロのサウダージ」には90度の座標軸回転の可能性を信じさせる何かがある。
1月号の編集後記
FACTA最新号(2009年1月号、12月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は25日からです。
*****
1904年9月、社会学者マックス・ヴェーバーは、大西洋を渡ってアメリカ大陸の土を踏んだ。妻マリアンネの日記には、ヴェーバー夫妻のマンハッタン体験が記されている。馬糞の臭いのたちこめる街路の雑踏、21階建ての摩天楼ホテルの一室の無機質と痰壺、窓から俯瞰した目も眩むような眼下の景色……。この旅のヴェーバーの反応が面白い。
▼同行者が糞ミソにアメリカをけなすと怒りだし、ドイツよりましだと弁護する。が、ベルリンの広壮な邸宅に慣れた彼に、アメリカの教授の家は人形の家(!)に見え、「パイプをふかせば濛々とたちこめそうだ」と愚痴った。4カ月かけてシカゴ、セントルイス、ボストンなどを転々とするが、アラバマ州の小さな町タスキーギで、この国の遠い未来を透かし見することができた。
▼奴隷だった混血の男が、黒人のために運営している教育機関を訪れたのである。差別を克服するには、教育と訓練で矜恃を持たせるしかないという信念に、ヴェーバーは感動する。召命=職業(Beruf)という後年の名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のキーワードがそこにあった。この本の原型をなす論文は、アメリカの旅をはさんで書かれ、いまは『宗教社会学論集』の冒頭に置かれている。
▼ヴェーバーの予感は104年後に実現した。大統領バラク・オバマとして。だが、希望と暴力が共存するアメリカに昔日の面影はない。冷え冷えとした摩天楼だけがマンハッタンに林立する。クリスマス前に帰国したヴェーバーは、年明けて旅順陥落と第1次ロシア革命の報を聞き、アメリカとロシアの同質性を剔る論考を次々に書く。こちらの予感もあたった。1920年に病死した彼は、20世紀の入り口で早くも射程が21世紀に届いていた。あやかりたい。社会学の落ちこぼれ、いや、棄教者として切にそう思う。
米貿易収支の訂正
前号(08年12月号)の「壊れた『国家版ヘッジファンド』」の記事で、7ページ最下段に
「一国の投資は国内貯蓄、または海外からのファイナンス(借り入れ)でまかわなければならない。米国の輸出がGDPに占める割合は14~15%、輸入で8~9%。差し引き4~6%が経常赤字だが」
とありますが、読者のご指摘により筆者に確認したところ、誤記があることが判明しました。筆者によれば、輸入の数字を誤記したとのことです。
米国のGDPは2008年第2四半期ベースで年14.2兆ドル。
輸出は1.9兆ドル(13~14%)、輸入で2.6兆ドル(18~19%)。
輸出は近似値とはいえ、輸入は10%分低い。
差し引き経常赤字、4~6%は正しいです。
何人かの方から貴重なご指摘、有り難うございます。冷静に読めば、輸出より輸入が少なく、貿易黒字になってしまうことが分かりますから、事前にチェックできたはずでしたが、編集部も見落としました。お詫びして訂正します。
京都と筑紫哲也と「百聞は一見に如かず」
前号でテレビ・キャスター筑紫哲也氏の追悼記「ひとつの人生」を掲載した。恐れ多くもジャーナリストの大先輩にあたる人だが、ずっと以前に毎日新聞本社の最上階にあるレストラン「アラスカ」で他の方々と同席したことがある。彼が癌で長期休養に入るずっと前だが、午後8時になっても悠然と飲んでいるのには驚いた。恐る恐る「大丈夫ですか」と聞いてみたが、にこにこ笑っていた。
のちに彼の番組「ニュース23」に呼ばれて出演したこともある。それを真似たわけではないが、局入りする9時半まで時間を持て余し、ちょいとドイツビールをきこし召してから出演した。筑紫さんがあそこまで平気なら、自分も大丈夫かと思ったのだが、さにあらず。あとで「顔が少し赤かった」と言われて、大いに恥じ入った。
やはり18年もカメラの前に立った人間と、一夜漬けでは覚悟が違う。これからはデジタル放送だから、毛穴まで見えそうなカメラの前で、万が一にもアルコールなど飲んで出られないと肝に銘じた。BS11のキャスター役をこの秋で卒業させていただいたのも、ひとつの理由は金曜夜に禁酒を課せられるのが、だんだん辛くなってきたからである。
さて、筑紫さん追悼記の後日談を書こう。

記事のなかで晩年の彼が治療のあいまに京都で暮らし、ときに姿を見せた「天ぷら 松」の話が出てくる。野中広務・元自民党幹事長、作家の瀬戸内寂聴の3人が離れで歓談しながら揮毫した書があるというのだが、取材のお礼をかねて先週末にその「天ぷら 松」を訪れてみた。
というのは店主の松野さんに電話で取材したおり、書がどういう状態で保存されているのか、よく分からなかったからだ。記事では「螺鈿の飾り棚」とあるが、実物を見ないと釈然としない。食いしん坊でもあるので、「天ぷら 松」の料理がどんなものか味わおうとの魂胆から訪れたのだ。
結論から言う。筑紫さんの墨痕鮮やかな書体をなぞって、薄い螺鈿を切り取り、それを飾りの板に貼り付けたものだ。螺鈿は半透明だから、光を反射させないと見えない。写真はもとの墨書とその螺鈿版である。離れに飾ってあったのをわざわざ外して見せてくれた。
なるほど、百聞は一見に如かずである。ついでに野中さんの揮毫を「愛の味」と書いたが、これも電話で聞いたからで、ほんとうは写真のように「愛味」と「の」が余計だった。訂正させていただく。野中さんと瀬戸内さんの揮毫は、筑紫さんの飾り板とは別仕立てになっている。

さて、もうひとつの結論。料理は文句なく素晴らしい。店は桂川沿いだが、渡月橋からかなり南で歩いてはいけないのに、客がひきもきらないのも納得できる。筑紫さんがこの夏、最後に来店したときの席に座り、レアの雲丹を浮かべた汁物や松茸、津居山の蟹に舌鼓を打った。
京都は絢爛たる紅葉のフィナーレ。故人をしのぶにはいい季節だった。
12月号の編集後記
FACTA最新号(12月号、11月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日からです。
*****
古巣に後ろ足で砂をかけるとロクなことがないから、各紙の社説を難じる「新聞エンマ帳」は本誌に載せていない。私も論説委員経験があるが、あの無人称の社論がどうにも苦手だった。それでも看過できないのは、10月27日付の日本経済新聞朝刊社説「時価会計『凍結』の意味を考える」だ。正直、思考停止には天を仰いだ、とあえて言おう。
▼「考える」とあるが、実は「時価会計の緩和が世界標準になりつつある以上、会計基準を米欧と同一条件にそろえるべきだろう」「理外の理で、独自の政治判断での時価会計の一時停止もありうる」というあたりが結論らしい。では、借問しよう。「理外の理」とは何ぞや。筆者の本音は、10月7日付のコラム「一目均衡」を読めば明らかだ。投資銀行のビジネスモデル崩壊を「現在価値革命の暴走」とみて指弾している。
▼おいおい、時価以外のどこに価値があるんだい。それを「計測できないものも計測し、時価を利用し尽くす欲求」と断じるのは、企業会計のスコラ主義だ。ケインズの美人投票はありきたりだから、13世紀の盛期スコラ学が憑かれた「普遍の実在」という夢にたとえよう。聖ボナベントーラや聖アクィナスらは、「普遍的な猫が質量を得て、無数の個別的な猫になる」個体化の原理(principium individuationis)を信じた。皮肉にもそれは実在論(リアリズム)という。
▼これに対し「オッカムの剃刀」のウィリアムらの唯名論(ノミナリズム)は「万物はそれ自体によって個物であり他の何物にも依らない」(omnis res est se ipsa singularis et per nihil aliud)と唱えた。『資本論』の使用価値と交換価値はその別バージョンに過ぎない。価値実在論の社説の筆者は現場を知らないのか。今は「普遍の猫」でなく「シュレジンジャーの猫」の時代だ。「日経ヴェリタス」6月29日付のソフトバンク記事は歴史的な愚論である。
山崎潤一郎「ケータイ料金は半額になる!」のススメ

燈台もと暗し、とはよく言ったものである。
実は今夏、赤坂でタクシーを降りた途端、携帯を置き忘れたのに気づいた。あわててタクシーを追いかけたが、すーっと車道に出て、車の列に消えていった。
しまったと思ったが、幸い、タクシーの領収書が手元にある。さっそく公衆電話を探した。携帯を置き忘れたとタクシー会社に通報し、運転手に無線連絡で確保してもらおうと思ったのだ。
運悪く公衆電話は外国人が占領していて長電話。じりじりしたあげく、やっと連絡がついたときは後の祭り。後の客に拾われたのか、後部席にはないという。
泣く泣く代替機種を買った。そのとき言われたのは、料金プランが「お客様の使用形態に合っていない」ということだった。商売柄、使用頻度は多いが、プランは契約当初からほったらかし。
半信半疑で変えてみて驚いた。翌月の請求書が半分に下がったのだ。あれだけ携帯料金の高止まりを批判する記事を自分の雑誌に載せていながら、何たる怠慢! ということは、これまでむざむざ倍の料金を払ってきたのだ。おお、切歯扼腕である。
というわけで、山崎潤一郎さんの新著「ケータイ料金は半額になる!」(講談社、1300円+税)の紹介を、このブログで敢行することにしました。
私のケータイ料金が半額になったのは、これまで理解できなかった最近の複雑な料金プランを適用したためだが、本書はキャリア各社の料金プランの啓蒙書ではない。実質値下げを進めてきた現行料金体系でも、朝三暮四の手品に似てまだ高いことを指摘し、適切な料金とは何かを問題提起している。
一言で言えば、基地局網からコンテンツまでの一貫サービスを提供する「垂直統合モデル」が、必然的にもたらすガラパゴス化と競争条件の固定化が、料金を高止まりさせているというのだ。本誌FACTAでは、そのアングルから携帯業界の宿痾を何度も記事にしたが、本書もそういった問題意識を共有している。
だから、経済紙などが喧伝する携帯ビジネスの「官製不況」論には与しない。総務省のモバイルビジネス研究会が、携帯ビジネスの成熟化からの脱出口として提示した「水平分業モデル」により、販売奨励金漬けからの離脱を余儀なくされた携帯業界が、販売台数の急減に見舞われているのは事実だが、それを総務省のせいにするのはお門違いである。
「ユーザー無視」の高収益が減ったと、自らのエゴをお上に責任転嫁するようなものだ。携帯の「官製不況」論を吹聴する記者は、一皮むけば携帯大手の代弁者にすぎない。
携帯ビジネスはすでに行き詰まっている。普及台数が1億台を超え、早晩需要が頭打ちになることは見えていたし、新しいサービスもコンテンツも生み出せないのに、新製品の回転率を速めるだけのモデルでは、もはや需要が喚起できなくなっていた。
それを理屈でなく、ドコモ対日本通信の「接続」戦争など、具体的な紛争を例にあげてジャーナリスティックに解き明かしたのが本書である。一見わかりにくいMVNO(仮想移動体通信事業者)なども、「ふるさとケータイ」という事例を通じて具体化してみせている。
本書は携帯ビジネスの明日を占ううえでも、いいガイドになる。ユーザーのライフログ(コンテンツ視聴履歴)の独占をキャリアに許していいかという問題と、ライフログの売買によって個人情報が無制限に広がる問題が、今後の課題としている点だ。
垂直統合、つまりは寡占に拘泥する日本の携帯大手が、この近未来の衝撃に耐える戦略を持っていないことは、本書からも明らかと思える。
高橋眞司『九鬼隆一の研究』のススメ
熊本日日新聞08年10月26日付で書評が掲載されました。
高橋眞司著
「九鬼隆一の研究隆一・波津子・周造」
(未来社、6800円+税)
ここに再録します。紙面では10行ほどあふれたのでは削りました。ここでは原文のままを載せますが、大意は変わりません。
*****
「天皇の官僚」が犠牲にしたもの

三田には2つの読みがある。「さんだ」と「みた」。九鬼隆一はそのはざまを生きた。昔の攝津国(兵庫県)三田(さんだ)藩に生まれ、丹波国綾部藩の家老のもとに養子に入り、明治政府に出仕して教育官僚となり、のち男爵に出世した。
彼には藩閥の後ろ盾がなく、三田(みた)の慶応義塾に入塾して福沢諭吉に親炙した。ところが、明治14年の政変で薩長政権にすり寄り、大隈重信と諭吉が謀反を企てていると讒言して師を裏切った。諭吉は「賎丈夫の挙動」と蔑み、晩年まで彼を許そうとしなかった。
自身の咎ではないが、隆一の名は明治31年のスキャンダルでも世を騒がす。彼の配下、岡倉天心を誹謗する怪文書がまかれ、「強烈ナル獣欲ヲ発シ」の一文で天心は東京美術学校長の座を追われたが、情事の相手波津子の夫こそ、ほかならぬ隆一だった。天心のエスコートで波津子が米国から帰国した11年前が発端だが、そのとき波津子の腹にいたのが後に『「いき」の構造』を書いた哲学者、九鬼周造である。
彼らのなかでひとり隆一だけ歩が悪い。波津子の離婚要求に応じず、ついに発狂にいたらしめ、精神病院に幽閉したコキュ(寝取られ夫)となったからだ。諭吉に嫌われ、色悪のイメージが定着した。本書は精緻な評伝を試みながら、斬新な視点を提供する。英国の政治哲学者トマス・ホッブスのカレイドスコープ(万華鏡)のもとで新しい光をあてている。日本におけるホッブス受容の変遷を追究した『ホッブス哲学と近代日本』の筆者ならではだろう。
隆一は黎明期の日本の学制を設計する立場(文部少輔)にいた。当時燃えさかっていた自由民権運動を抑圧するため、地方分権に寛容な「教育令」を覆し、仁義忠孝を柱とする中央集権的教育に転換する。その一環として明治16年、拂波士(ホッブス)著『主権論』――『リヴァイアサン』抄訳を刊行した。
そのホッブス理解は「(主権者ノ)諸権ハ決シテ共有スベカラズ亦分離スベカラザルモノナレバナリ」という主権帰一の論、すなわち専制論に偏っていた。「万人の万人に対する戦争」の前提である「人は生まれながらにして平等」という自然権、自然法を論じた第一部が欠けている。この抄訳と『リヴァイアサン』原典の落差は、天賦人権説の駁撃者から擁護者へ180度旋回した日本のホッブス理解とパラレルなのだ。意図的な“誤解”の先駆者として隆一は位置づけられる。
そこに満州からの引揚者である筆者の近代批判――地方分権を抑圧した「天皇の官僚」への批判、戦後もその弊は延々と尾を引いて教育改革の挫折をもたらした、というモチーフが浮かびあがる。波津子の悲劇についても、周造に実家(杉山家)の家名再興の希望を託したことからみて、心底に維新の敗者のルサンチマンがあったろうと考察している。大岡信や近藤富枝が陥ったロマンチックすぎる情痴論とは一線を画し、彼女を「皇室の藩屏」の犠牲者として、ホッブス歪曲と並行して捉えようとしている。
私は専門家ではないが、本書の篤実な記述と考証には敬服を禁じえない。「秘仏」法隆寺夢殿観音の開扉に誰が立ち会ったかを確かめるため寺僧を訪ね、天心やフェノロサの記述、和辻哲郎の『古寺巡礼』の間違いを指摘している。周造の別れた妻、縫子にも生前会って貴重なインタビューを記録している。
ひとつ尋ねたいことがある。松本清張がその天心論で暴露した、波津子の狂態を記す巣鴨病院長宛申請書の真贋である。私の記者経験に照らして、書写であって原本がなく、誤字脱字だらけ、ずらずらと著名人の署名を並べ、妙に暴露的なこの文面はよくある怪文書そっくりだ。偶像破壊的ないやらしさは、天心を貶めた福地復一の怪文書と変わらない。なぜ本物と言えるのか。もしかしたら、これはもうひとつの『或る「小倉日記」伝』かもしれない、と勝手に妄想したくなる。
時価会計「凍結」の愚
日経平均株価がバブル後最安値の7100円台に急落したのを受けて、麻生首相は10月27日、関係閣僚と与党に対し緊急市場安定化策の取りまとめを指示しました。
柱はすでに新聞でも報道されているように、銀行株買い取り、会計基準緩和、株式市場規制緩和、金融機関資本注入ですが、当面打てる政策を洗いざらいかき集めただけに、相矛盾する政策が盛り込まれそうです。なかでも筋が悪いのが時価会計の骨抜き。麻生総理も中川財務・金融担当相も時価会計にかねてから疑問を呈していましたが、欧米と歩調を合わせたここでの逆コースは、「失われた10年」で何度も繰り返された光景。企業買収の恐怖に乗じた経営者の保身に利するだけです。
10月26日に新潟日報など環日本海7紙に同時掲載するコラム「時代を読む」を書きましたので、ここに再録します。
*****
時価会計「凍結」の愚
ヤブ医者ほど罪なものはない。これぞ頓服と銘打ちながら、とんだ劇薬で病人を死地にさまよわせる。全世界を覆う金融危機を封じこめようと、大胆な処方箋がいくつも提示されたが、もっとも筋が悪いのは「時価会計の凍結」だろう。
時価会計とは、企業が保有する金融資産を期末時点の流通価格で再評価するもの。1億円で買った株式が期末に半値に下がったら、5千万円の損を計上する。購入した時点の価格(簿価)で計上していると、時価との差額が常に「含み損」「含み益」になるから、時価会計のほうが実態を反映して企業財務の健全性に資するとされてきた。
ところが、サブプライム関連証券化商品の市場“蒸発”で米国が心変わりする。難産の末に成立した金融安定化法には、証券取引委員会(SEC)に凍結権限を与える条項が盛り込まれ、投げ売りの価格を正常取引とは認めないなど基準緩和の指針を打ち出した。
欧州でも、国際会計基準を採用する欧州金融機関が米国勢に比べて不利にならないよう、国際会計基準審議会(ISAB)が、いったん「売買目的」とした投資有価証券でも満期保有の証券に分類を変更、時価を決算に反映しなくても済むようにした。
米欧のご都合主義にはあきれる。日本がバブル崩壊後の「失われた10年」に時価会計導入の遅れをいやというほど指摘されたことは記憶に新しい。それがいざ我が身に累が及ぶと、あっさり原則を覆す。時価会計は政治の所産か、と疑われてもしかたがない。
しかし、もっと情けないのは日本の経営者だろう。それみたことか、と一斉に時価会計の骨抜きに走りだした。10月15日、中川昭一・財務・金融担当相は金融機関トップと会談、その場で横浜銀行の小川是頭取らから時価会計停止を要望され、金融庁に保有区分の見直しなど基準変更の検討を指示している。
天を仰ぐほかない。経団連はじめ日本の経営者の間で、時価会計は経営のノリシロをなくし、長期安定経営を損なうとの警戒心が強い。うかうかと国際会計基準を採用すれば海外から買収の魔手が伸びてくると、蛇蝎のごとく嫌っている。
だが、これはあくまでも「買われる側」の論理。買われたくないから、本当の姿を見せたくない。しかしサブプライムで傷の浅い日本は今後、叩き売りされる米欧企業を「買う側」に回る。買い物が「ヤミ鍋」では困るのだ。ここは逆手をとって、米欧に時価会計を迫らないと、とんだ高値づかみをさせられる。
いい例が三菱UFJだろう。モルガン・スタンレーの少数株主になるために、資産査定なしで9千億円もはたいた。十年前に破綻した日本長期信用銀行でもわかるとおり、かつてハゲタカに裸にされた日本は、今度は「逆ハゲタカ」で相手を裸にする番なのだ。
でなければ、この千載一遇のチャンスを生かせない。天下りの元大蔵事務次官である小川頭取にはその機微が分からないのだ。
地域経済の沈下とともに優良貸出先が乏しい地方金融機関は、有価証券に資金運用をシフトさせてきた。だが、日経平均が8000円割れ寸前まで一時急落して浮き足立った。地銀などは、地元取引先との持ち合い株を多く保有している。それが軒並み評価損では経営責任に直結するからだ。
たとえば2年前、王子製紙の敵対的買収(TOB)を受けた北越製紙。一株860円のTOB価格だったが、607円での第三者割当増資に応じた三菱商事など持ち合い株主のスクラムで防衛した。いま北越株は300円台。TOBに応じなかった第四銀行などは逸失利益をどう株主に説明するのか。似たような例は全国に無数にある。
金融機能強化法改正による公的資金の資本注入と時価会計凍結、さらに自己資本比率規制緩和という「イチジクの葉」で、地域金融機関は当座をしのごうとしているにすぎない。だが、隠せば隠すほど疑心暗鬼は募る。「直前にOB杭を移動」させた9月中間期決算を、市場の誰が信用するだろうか。
持ち合い株という“塩漬け”リスク資産を圧縮しない限り、地銀の中小企業向け融資の貸し渋りや貸しはがしの根本原因はなくならない。それが「失われた十年」の教訓ではなかったか。その教訓を忘れたヤブ医者ばかりが、中川財務・金融相の耳にエセ療法をささやいている。金融庁よ、しっかりせい!
11月号の編集後記
FACTA最新号(11月号、10月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は27日からです。
*****
英国の「エコノミスト」誌に掲載されるカートゥーニスト、KALの1コマ漫画には毎週、脱帽させられる。政治や経済の硬派ネタを一瞬で把握し、機知にくるんで人をニヤリとさせる才覚は、なまなかには生まれない。貪欲に咀嚼(そしゃく)し、すべてを戯画にする精神の牙。強靱な意志がなければ、ありきたりの劇画家か、生ぬるいイラストレーターに終わってしまう。日本の新聞では日々の緊張に耐えられないのか、いつのまにか1コマの政治漫画は傍流になった。
▼KALは通称で、本名ケヴィン・カロハー(Kevin Kallaugher)の略である。10月11~17日号には息をのんだ。銀行前の路上で「RESCUE」と書かれた救援の丸い布を手に、みんな目を丸くして空を仰いでいる。俯瞰するアングルだから、上空に何があるかは見えない。いや、路面に黒々と落下する人影。丸い布よりはるかに大きく、とてもキャッチできない恐怖。やがて、それが落ちていく自分自身の影と気づくのだ。
▼米欧市場を凍りつかせた金融パニックを、これほど巧みに絵にした例はない。画面に吸いこまれるように視線が往還するうち、いつしか立ちくらみしてくる。眩暈は三半規管のせいとは限らない。例えばヴェラスケスの「侍女たち」は、中心の幼い王女のかたわらに、こちらをみつめる画家自身を置き、その奥の姿見に親の国王夫妻を映して、見る側に自己言及を循環させる鏡の魔術である。信用恐慌は、そうした自身への恐怖の共振、眩暈の連鎖なのだ。
▼そこに何が起きるか。茫然自失、一種の離魂症である。京都の北、貴船明神に参詣した和泉式部は、川のほとりに乱れ飛ぶ蛍を詠んだ。「物思へば沢の蛍もわが身よりあくがれいづる魂(たま)かとぞ見る」。式部は死に憑かれて命の明滅を蛍に見ている。すでにそれはあの世の目だ。その耳に滝の轟音とともに明神の声がこだました。「たまちるばかり物な思ひそ」
今の市場に聞かせたい。
一足早く麻生太郎首相にぶら下がり取材
私は政治記者だったことはないから、番記者の経験もなければ、国会の廊下トンビをやったこともない。公用車に同乗して話を聞いた経験はあるものの、ぶら下がり取材を体験していない。で、総理官邸で日に2回行われる番記者のぶら下がり取材をテレビで見ていて、どうしてああも下手くそなのか、不思議でならなかった。

短時間なのだから、質問も簡にして要を得なければならないのに、紋切り型の歯がゆい質問ばかり。スポーツ中継の押しつけインタビューと代わらない。福田康夫・前総理最後のぶら下がり会見でも、意味不明の質問を浴びせて、去りゆく総理をむっとさせていた。ワンフレーズを求めようとする余り、記者が痴呆になってはしようがない。
そこで、隗より始めよで、自分でぶら下がり取材を試みた。単独取材を許さない新聞の“カルテル組織”内閣記者会から雑誌は排除されているから、本来ならできない。が、間隙を縫う「突貫取材」は、「不肖宮嶋」カメラマンにも負けないつもりだ。一足先に、FACTA版ぶら下がり取材をすることで、嫉妬深い新聞の鼻をあかそう。
*
――小沢民主党と総選挙で雌雄を決する麻生・自民党政権が発足するにあたって、国民にとって喫緊の課題が四つあります。第一は米国のサブプライムローンに端を発した世界的な金融危機、とりわけ信用収縮による景気への影響。国民の不安は深刻ですが、新政権はどう対処するのでしょうか。
麻生すくなくとも日本には、1997年に三洋、山一證券、北海道拓殖銀行が相次いでつぶれた経験がある。あのときもそうだったが、実物経済としてどうなのか、システムクライシスとしてどうなのか、という議論がなされた。今回のアメリカの危機も、それを踏まえた対応を考えていかねばならない。
――第二の国民の不安は、北朝鮮の金正日総書記の重病説が流れていることです。従来のような核問題や拉致問題だけではなくなります。日本海にボート・ピープルが溢れだす事態を想定して、日本も備えが必要になるのでは。
麻生まだ、いろいろな情報が流れていて、どうも様子がよく見えない。ただ、なんとなくおかしいとは言える。どうも(国境を接している)中国のほうが神経を尖らせている。ここは中国と一緒にやっていかなければならないと思う。ボート・ピープルと言っても、なかには武装難民が混じっているといった事態も考えられるから。
――第三の不安は、汚染米または事故米でしょう。農水大臣が辞任し、事務次官が更迭されましたが、三笠フーズからの400社近い流出先の公表や、中国産乳製品のメラミン汚染など、食品の汚染は子供を持つ親に強い不信感を植え付けました。
麻生これはね、(汚染米を主食用などに)売ったやつが悪いということは明らか。ただ、それを管理していた側にも責任がある。食糧庁は私が政調会長のときにつぶした(現在は農水省食糧部)経緯があるが、ここを何とかしないといけない。しかし、これはうまくやらないと、だから役人を増やさないといけないという話になる。マスコミが(不安を)あおればあおるほど、そういう(役所の焼け太りの)話になる。そうならないようにしなくちゃいかんが、マスコミはそれがわかっていないな。
――最後に、安倍、福田政権と自民党政権のクビキになってきた年金問題。厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の改ざんが6万9000件以上、舛添・厚生労働相が社会保険庁の組織的関与を認めるなど、一段と年金不信を募らせる事態となっていますが。
麻生改ざんの話はね、これは明らかに罪ですよ。(社会保険庁の)サボタージュ、意図的に組織的にやっているとしか思えない。個人的に改ざんに関わったやつは、これはもうさっさと辞めさせなきゃならない。一方で(5000万件の)消えた年金記録問題はきっちり(記録照合をやっていかなければならない。役所としても8月も9月も進めている。こちらの問題は大きいし、改ざんの問題とは似て非なるもの。時間をかけても(記録照合を)進めなければならないという本筋は外しちゃいけない。
*
と、こんな具合である。まだ所信表明演説前だから、「麻生施政方針」の詳細を聞き出すのは時期尚早だろう。が、補正予算成立後に総選挙に突入するとすれば、多少の時間はある。本職のぶら下がり記者諸君の健闘を祈る。