EDITOR BLOG

月刊総合誌FACTAは日本振興銀行に対し不当訴訟の損害賠償請求訴訟を提起します
日本振興銀行前会長、木村剛が本日、検査忌避による銀行法違反容疑で逮捕された事態を受けて、弊誌は同行および木村、小畠晴喜取締役会議長(14日夕に社長就任を発表)をはじめとする同行経営陣に対し、不当訴訟による損害賠償請求訴訟(請求額約3000万円)を提起いたします。
本件の立件に1年以上先駆けて、弊誌は昨年5月号(09年4月20日発行)から4回にわたり振興銀行の内情を調査報道しました。これに対し同行は名誉を棄損されたとして、多額の損害賠償及び謝罪広告掲載を求める訴訟3件を提起しました。弊誌の言論および取材を訴訟によって封殺し、実態が露見するのを妨害しようとするとともに、弊誌報道に追随しようとした他のメディアに対しても「書いたら訴える」と威嚇する意図を持っていたことは明らかです。
先般の警視庁による家宅捜索を受けて、日本振興銀行は代理人を通じて上記3件の訴訟をすべて取り下げました。しかし、訴訟提起から1年余にわたり、弊誌は訴訟対策のために厖大な時間と少なからざる所用経費を割き、他の取材や報道にも支障を来しました。かかる不当な訴訟提起行為は、メディアの表現の自由を圧殺するものとして断じて許されるべきではありません。
捜査当局のリークによらずとも調査報道によって社会的不正を知らしめるべきだとするメディアに対し、ともすれば訴権を濫用することによって隠蔽しようとする企業や組織、さらにはそれに便乗する弁護士が増えております。裁判所もメディア叩きに迎合し、慎重かつ妥当な取材に基づく報道に対しても、厳しい判決を下す例が増えております。このままでは調査報道は萎縮するばかりだと考え、かかる現状に警鐘を鳴らすため、弊誌は訴訟を提起することにいたしました。
日本振興銀行問題を他に先駆けて報道した弊誌は、検査忌避による立件は表面的かつ形式的なものにすぎないと考えます。背景には粉飾決算や特別背任等の成立の可能性を含む実態があり、捜査当局には今後ともそうした実態の捜査を進めていただきたいと考える次第です。
以上
<本件に関するお問い合わせ先>
FACTA編集部
TEL:03-5282-7044FAX:03-5282-0955
Email:support@facta.co.jp
J・M・ケインズ「確率論」のススメ
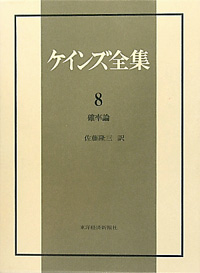
熊本日日新聞のコラム「阿部重夫が読む」に書評を載せました。尊敬する経済学者、ジョン・メイナード・ケインズの『確率論』(佐藤隆三訳、ケインズ全集第8巻東洋経済新報社)です。
とはいえ、たぶんこの本を書評するなどという無謀な新聞は、ほかにはないかもしれない。歯ごたえがありすぎる。
先日(7月4日)、たまたま東京お台場の「東京カルチャーカルチャー」で、水野俊哉+山本一郎(切込み隊長)+中川淳一郎氏のトークショー「ビジネス本作家の値打ち」を聴く機会があったが、聴衆の誰一人としてケインズのこの本に興味は持たないだろうなということは確信できた。
ケインズは数学者であり哲学者だったのだ。ご興味をそそられても、まだハードルがある。『確率論』のお値段は12000円とバカ高いのだ。でも、その価値はある。乱作されるカツマーの本はあっという間に消えても、この本はずっと残るだろう。
*****
合理は真理ならず
待望久しいケインズの幻の処女作、それも彼が経済学者になる前に哲学と数学を志していた時代の野心作が、初めて邦訳された。
私が『確率論』の所在を知ったのは、“転向”後の清水幾太郎が一九六八年から雑誌「思想」に連載した『倫理学ノート』によってである。その毒がいまだに抜けない。
清水はケインズと『チャタレー夫人』のD・H・ロレンスの出会いから筆を起こす。第一次大戦さなかの一九一五年、バートランド・ラッセルの朝食会に出たロレンスは、ケンブリッジ知識人の鼻持ちならない特権意識とインモラル(青年ケインズは同性愛者だった)に怖気をふるい、彼らを「サソリのように咬みつく油虫」と呼んだ。
後年の「若き日の心情」でケインズ自身も「ハーベイロードの前提」を反省しているが、没落士族のルサンチマンを抱く清水はその憤りをロレンスに仮託した。それをベンサム功利主義脱出の起点にしたために、ケインズやラッセル、『確率論』と同年に『論理哲学論考』を出版したルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン、その『論考』を十九歳で英訳したフランク・ラムジーらが、侃々諤々論じていた確率問題の視野を狭めてしまったと思う。
私がケンブリッジ中央図書館で原典を借り、ライプニッツのエピグラフから読み始めた日から十年余り経つ。「油虫」観を少し解毒できたのは、伊藤邦武の『人間的な合理性の哲学』と『ケインズの哲学』、伊藤が訳した『ラムジー哲学論文集』のおかげである。
それでも一読感じた難解さは『雇用、利子および貨幣の一般理論』と同質だと思った。一九〇七年、フェロー申請論文として提出された『確率論』初稿を審査したホワイトヘッドも苦言を呈している。
「ケインズ氏が文学に適した文体と論理的、哲学的研究に適した文体とを十分に区別したかどうかについて疑わざるをえない」
ふんだんに論理式が出てくるが、平文は名文すぎてとらえどころがなく、柳田国男の文体で論理学を読まされる感じがする。が、今思うと、それこそ彼の本領ではなかったか。
ケインズはユークリッド幾何学のような決定的かつ演繹的な推論ではなく、合理的であっても確実ではない推論(帰納的推論)の体系的理論をめざしていた。
その「確率」(Probability、ありそうなこと)はサイコロや保険の確率ではない。ある命題から別の命題へといたる推論の蓋然性」の判断であり、命題間の蓋然性に関する関係(確率関係)は直観されるもので、定義は不可能であり、数値で表現できるとも限らない。
合理は真理ならず。
まさに『一般理論』の美人投票である。平均的好みにもっとも近い人が賞金を獲得するという類のコンテストは、平均的期待への平均的期待という無限のフィードバックを起こすが、本当の美人にはたどりつけない。この逆説は全会一致、非独裁、選択対象からの独立性、定義域が非限定な時は解がないという「アローの不可能性定理」と同じだ。
一九二六年、ラムジーが『真理と確率』という題の短い論文を発表し、ケインズに鋭い批判を加えた。『確率論』は形式論理学を拡張して、確率判断(計算)と帰納法を同時に正当化しようとしたが、前者は公理化できても、後者は進化論的な説明しかできないという。その四年後、三十歳で急死したラムジーをケインズは悼み、批判を大筋で受け容れた。以後、確率論は身を潜めて『一般理論』の下地に溶けこんでいく。
菅直人総理のブレーンには似非ケインジアンがいる。その詭弁を見破るには『確率論』を読むに如くはない。然り、ケインズは「油虫」にあらず。
マイク・モチヅキ教授の寄稿原文と訂正
最新号の7月号の一部に訂正があります。
p66~69に掲載したマイク・モチヅキ教授(ジョージ・ワシントン大学)の寄稿記事「普天間で鳩山『四つの誤算』」の記事では、p68最下段の右から4行目、「陸上ヘリポート」を「ヘリパッド」と訂正します。関係者にご迷惑をおかけしました。誤訳を見落としたもので、原文ではHelipadでした。
あわせて、モチヅキ教授の原文をここに掲載します。
*****
For most of the US policy community, Prime Minister Hatoyama Yukio faced a fundamental choice between the U.S.-Japan alliance and the coalition with the Social Democratic Party (SDP). In the end, Prime Minister Hatoyama made the right and courageous choice for which President Obama expressed his personal gratitude in a phone call. But against the backdrop of plummeting public support, Hatoyama was in the end forced to resign. Upon becoming the new prime minister, Kan Naoto has stated that he would follow through on the US-Japan joint statement regarding the Futenma Replacement Facility (FRF), but he also acknowledged how difficult the road ahead would be. To better understand the difficulties up ahead, it would be good to examine how and why Hatoyama arrived at a point that he had to resign and to see if there was another possible path. There are at least four explanatory factors.
First, the Hatoyama government started out with unrealistic expectations about the Obama administration’s willingness to be flexible about the 2006 base realignment agreement. Barack Obama won the U.S. presidential election by stressing the theme of change and by rejecting the foreign policy approach of his predecessor, George W. Bush. Hatoyama echoed this theme of change during the August 2009 House of Representatives election, so it probably seemed natural that he and President Obama might usher in a new era in U.S.-Japan security relations. By promising to provide $5 billion in aid for Afghanistan’s reconstruction in early November 2009 right before President Obama’s visit to Tokyo, Hatoyama may have hoped that Obama might be more flexible about the Futenma issue. The Obama Administration, however, was not receptive to such an implicit bargain. If anything, the large Afghanistan aid package was seen in Washington more as a substitute for the Japanese refueling mission in the Indian Ocean, which the Hatoyama government decided to terminate.
The reality has been that there is more continuity than change between the second term of the Bush Administration and the Obama Administration regarding much of U.S. security policy. This continuity is symbolized by Robert Gates staying on as Secretary of Defense and by Hillary Clinton (who has been more hawkish on security policy than Obama) serving as Secretary of State. Secretary of Defense Gates indeed sent a strong message during his trip to Tokyo in October 2009 about America’s expectation that the Hatoyama government uphold the 2006 realignment agreement.
Second, Prime Minister Hatoyama managed the Okinawa issue poorly within his own government. Rather than appreciating the sensitivity and complexity of this issue and assuming strong leadership in developing his government’s position, he allowed his cabinet ministers to send mixed public messages. For example, Foreign Minister Okada Kazuya provoked controversy by resurrecting the idea of integrating the Futenma operations into Kadena Air Force Base without fully considering the strong resistance this option would provoke not only from residents living near Kadena but also from the U.S. Air Force. Hatoyama also made the mistake of appointing his Chief Cabinet Secretary Hirano Hirofumi to be the key person to come up with the government’s position on the Okinawa issue. The Chief Cabinet Secretary’s role is to coordinate the overall operations of the cabinet and to be the main spokesperson for the government. In many ways, the Chief Cabinet Secretary in Japan combines the functions of the Chief of Staff and the Press Secretary in the U.S. White House. Mr. Hirano certainly was not the right person to take on such a politically sensitive issue, especially given that he had little prior experience regarding security policy or Okinawa base issues. Consequently, as Hirano went about studying different options, he provoked a media frenzy, which had the effect of making Hatoyama appear weak and vacillating.
Hatoyama should have coordinated with Foreign Minister Okada and Defense Minister Kitazawa to appoint an influential and knowledgeable person within the Democratic Party to come up with a viable alternative to the 2006 agreement. Such a person could have consulted with the Democratic Party (DPJ) broadly and the DPJ’s coalition partners as well as hear the views of representatives from Okinawa and other relevant prefectures and of outside experts on defense policy. Hatoyama was hampered by the rigid separation that he and DPJ Secretary-General Ozawa Ichiro instituted between the government and the ruling party. If Hatoyama had facilitated systematic discussions and consensus-building in his own party, he would have been less isolated and more able to engage the United States in tough negotiations.
Third, Prime Minister Hatoyama missed a political opportunity to settle the Futenma issue soon after his November 2009 meeting with President Obama. He could have insisted on modifying the 2006 base realignment agreement along the lines that Okinawa Governor Nakaima Hirokazu had been advocating. This would have entailed moving the proposed V-shaped runway at Henoko a bit further out to sea to reduce the noise for local residents and terminating as soon as possible the operations at Futenma that pose the greatest hazards to people living near the Marine Air Station. By making these changes conditional for implementing the 2006 agreement, the prime minister could have demonstrated that he is indeed promoting the interests of Okinawans. Washington may have resisted such a revision of the original agreement, but Tokyo could have argued that without such a compromise it would be impossible to construct a new Marine air facility on Okinawa and to move ahead with the troop transfer to Guam.
Of course, the Social Democratic Party (SDP) would have opposed such an outcome and threatened to leave the governing coalition. But Hatoyama could have replied that without forging such a compromise, there was a real danger that Futenma would remain in operation as is. He could have also pointed out that the three-party government policy agreement between the DPJ, SDP and the People’s New Party did not explicitly mention moving the Futenma replacement facility (FRF) outside of Japan or even outside of Okinawa. If the SDP still had decided to bolt the coalition, the political damage on Hatoyama would not have been as severe as it eventually was in May 2010. Hatoyama would have shown that he was able to make the tough decisions, and his efforts would have been applauded by Governor Nakaima of Okinawa. By missing this opportunity, however, Hatoyama fundamentally altered the political dynamics of this issue. He raised expectations that he would indeed push for locating the FRF outside of Okinawa, he placed Governor Nakaima in an awkward position, and he facilitated the election of an anti-base candidate for mayor of Nago City. Hatoyama now had to meet public expectations or face his own political demise. Dr. Jeffrey Bader, Senior Director for Asian Affairs in the National Security Council, recently told a Washington, D.C. audience that Hatoyama made a big mistake in not keeping his December deadline for making a decision about Futenma.
Fourth, once the December deadline had passed, Hatoyama embarked on a treacherous course, but he lacked an effective and knowledgeable team to negotiate an alternative base realignment plan with the United States. Although there were differences of views within the U.S. government about how patient to be with Japan, every American official insisted that the 2006 agreement or some version of it was the best and only viable option for closing down Futenma. Although numerous DPJ politicians and advisers went to Washington to probe for possible areas of flexibility, they all found U.S. officials across the board to be firm in their commitment to the existing realignment plan. There were, of course, some American policy analysts and scholars outside of government (including myself) who believed that there were indeed other options that could dramatically reduce the burden on Okinawa without jeopardizing “critical operational requirements” of the U.S. military or weakening deterrence. But such voices were in the minority and had little influence on government policy.
Among Hatoyama’s official and informal advisors, a few imaginative proposals did emerge. One such proposal involved the following points: (1) closing down the operations at Futenma, but having the Japan Self-Defense Force maintain the facility for possible use during a military emergency, (2) constructing a land-based helipad in Camp Schwab (rather than a full-scale runway) that could accommodate about two-dozen Marine helicopters for routine daily training, and (3) transferring the rest of the Marine aircraft from Okinawa to JSDF bases outside of Okinawa such as those at Kanoya and Nyutabaru in Kyushu (both of which were mentioned in the 2006 realignment agreement) but making them available for training exercises in and near Okinawa on a rotational basis. This proposal was so clever that I thought Prime Minister Hatoyama might embrace it as part of his so-called fukuan. It was much more politically viable than the Tokunoshima option that received so much public attention.
But even such a clever proposal was bound to be fiercely opposed by the Pentagon because the U.S. Marines would insist on the necessity of having a full-scale runway near their ground forces. In order to have any chance of convincing the Obama Administration to compel the Marine Corps to be more flexible, Hatoyama needed the help of Japanese experts and officials with sufficient knowledge of defense operations to counter American arguments and to engage in tough negotiations. Unfortunately, while there are plenty of brilliant scholars of diplomatic history and foreign policy in Japan, there are few who are truly knowledgeable about defense operations, and practically all of them were working against Hatoyama. Therefore, in the end, Hatoyama was forced to give up and apologize to the Okinawa people for not being able to fulfill his promises.
How then does the Obama Administration see things developing under Prime Minister Kan? U.S. officials are hopeful that the Kan government will make progress on the FRF as outlined in the June 2010 joint statement. They are encouraged by Prime Minister Kan’s statements and by the fact that he kept Mr. Okada and Mr. Kitazawa as foreign and defense ministers respectively, thereby insuring policy continuity. They also admit that it was unfortunate that the Futenma base issue was allowed to become the central issue in U.S.-Japan relations. They therefore would like to re-focus the alliance around a broader agenda that includes such issues as climate change, nuclear non-proliferation and disarmament, policy toward North Korea and Iran, and dealing with the rise of China.
But at the same time, the Obama Administration recognizes that the Futenma issue could continue to haunt U.S.-Japan relations and the Japanese government. U.S. officials understand that many in Okinawa are angry about what they view as Hatoyama’s betrayal. In this political climate, it will be difficult for Governor Nakaima to approve the land reclamation necessary to construct the runway off Henoko. Any move in this direction carries the risk that he would be defeated in the November gubernatorial election, and an Okinawa governor who is much more opposed to U.S. military bases could be elected. And it is hard to imagine that a prime minister who started his political career as a citizen activist would attempt to use national legislation to force the construction of a new U.S. military runway on Okinawa. Indeed many American scholars of Japanese politics doubt that the Futenma Replacement Facility will ever be constructed as sketched out in the June 2010 joint statement. In short, both the 2006 realignment plan and the June 2010 joint statement may experience the same fate as the 1996 SACO plan. But the danger this time is that emotions have become so intense that Okinawans may no longer tolerate a political stalemate that keeps Futenma Marine Air Station in operation.
Finally, the United States faces a dilemma about how strongly to press the Kan Cabinet to implement the June 2010 joint statement. Although the Obama Administration does want the FRF constructed on schedule, it does not wish to trigger the fall of another Japanese government. From America’s perspective, having Japan go through so many prime ministers since Koizumi’s retirement in 2006 is unfortunate. Despite the growing importance of China for U.S. foreign policy, Japan still remains a key partner for dealing with pressing global and regional challenges like climate change, nuclear proliferation, and the North Korea issue. The Obama Administration wants Japan to re-emerge as an influential international actor with an effective and stable government.
長谷川幸洋「官邸敗北」のススメ

政治報道は難しい。
FACTAにおいてもそれは例外ではない。表層に見えるのとは違う動きが水面下で幾重にも錯綜し、突然流れが変わって動き出すと、わずか1日でだれも予測できなかった結果が出てくる。月刊誌の宿命とはいえ、毎月誌面を考えるたびに政治の3歩先を読むのは至難の業である。
とりわけ鳩山政権のように、国家の経綸もなく、経験も浅く、それぞれの政治家の習性や癖も、自民党政権のように知られていないケースだと、ベテラン政治記者の大半は無力感を覚えているはずだ。
現に私の知っていた「閥記者」たちも、わけ知り顔で語るだけで、多くは昔語りになっていった。この政権のつかみどころのなさを嘆き、難じるだけで、内懐に入ることのできないもどかしさがありありである。
長谷川幸洋さんは政権交代によっても筆法が衰えることのない、数少ない例外だと思う。それはFACTAのコラムニスト(コラム「政々堂々」を連載)であるというひいき目から言うのではない。
月刊現代にペンネームで書かれていたころは、安倍内閣の裏方チームの一角に属していたが、その後の麻生内閣、鳩山内閣でも敵視や反発は軽々と乗り越えて、政局の核を鷲掴みにしているのは驚くほかない。派閥や領袖の「ポチ」となり、権力への距離は食いついた政治家の権勢に比例するという、小判鮫型の政治部記者は数多いが、彼はなぜそれを免れられたのか。
その秘密は政策理解にあると思う。財政審や政府税調委員を務めて、官僚の手口に通暁していることが彼の強みなのだ。単なる政局記者はもう役に立たない、というのが私の年来の主張だが、長谷川さんはまさに政局と政策の双方を見る目を持っている立体思考の珍しい存在である。
「脱官僚」を旗印にした政権なのだから、政治報道を3D化させて政策と政局の両方の光をあてなければ、永田町と霞が関の深層を解けるわけがない。鳩山政権のダメさを、小沢周辺や反小沢派の個々の政治家の資質や人間関係(つまり好き嫌い)に期する平板な書き方を彼はしない。
「官邸敗北」(講談社、1600円)は政権発足8カ月でなぜ鳩山内閣が「ドーナツ化」したのかを、財務省との葛藤と屈服の過程として追っていく。そこでは長谷川氏も登場人物の一人で、財務省側からの接近と抱き込みが生々しく描かれている。怒声と怨嗟、猫なで声と無言の威圧……私も論説委員だったことがあるが、官僚たちの生態は20年前とほとんど変わっていない。
鳩山政権は無残にも霞が関に呑みこまれた。その痛ましい編年史(コロニカ)をいつか編まなければなるまいが、本書はその貴重な証言録になるだろう。権力のアメという「毒草の種」は、いかなる理想をも腐食する。
深くため息をついて本書を閉じる。それからラス・カサスの「インディアス史」を読み始めた。1492年のアメリカ発見から60年後、クリストバル・コロン(コロンブス)を徹底批判したこの本に、未来のコロニカの鑑を求めて――。
高橋洋一「日本の大問題が面白いほど解ける本」のススメ

わが社の近所にある三省堂書店本店に立ち寄ったら、ノンフィクションの棚に「高橋洋一」本のコーナーがあるのに驚いた。豊島園のわけのわからない珍事から1年余、ほぼ社会復帰を果たして、この4月から嘉悦大学教授として教壇に立っているばかりか、次々に新著が出てくる驚異的な多産ぶりには驚く。
「あんまり変な共著者と組んで本を出すより、単独で本を出すほうがいいよ」
と、ご当人にアドバイスしたら、今度は光文社新書から本が出た。編集者がつけたのだろうが、どうも最近の新書のタイトルは身も蓋もないのが多い。
でも、副題の「シンプル・ロジカルに考える」というのはいい。高橋氏(というよりはこの本のように「タカハシ先生」と呼ぼう)の普段の思考法やライフスタイルが、まさに「シンプル・ロジカル」そのものだからだ。
彼は「異色の官僚」と呼ばれ、霞が関からは蛇蝎のごとく嫌われているが、数学科出身の彼が法学部系官僚が好んで隠れ蓑につかう「繫文縟礼」をあっさり蹴飛ばすためなのだ。
秀才官僚は「あんた、アホか?」と言われるのをもっとも嫌う。しかし彼の頭脳は一直線に非合理を見抜く。それを言い繕う輩を「アホかいな」といわんばかりに容赦なくやっつける。それがあまりに鮮やかなので、秀才嫌いの世間は喝采を送る――というのが「埋蔵金」以来の彼の人気の秘密だろう。
最近、彼の舌鋒は「アホなマスコミ」にも向けられるので、われわれもウカウカしていられない。この本でも八ッ場ダムにはじまって地方分権にいたるまで21の質問を、彼が快刀乱麻に解いていくという形式だ。
ちょっとくやしいけれど、私も目からウロコの部分がたくさんある。菅直人財務相が頼りにしている小野善康阪大教授の「増税で景気がよくなる」論の死角を、数学モデルなど歯牙にもかけず、これだけズバッと言える人はそうないのではなかろうか。菅財務相も付け焼刃で「サミュエルソンの経済学」を斜め読みするよりよほど役に立つ。
ところで、先週会ったタカハシ先生、えらくくつろいだ服装をしていて、「マクロばかり書いてミクロを知らない、なんてどこかのブログに書いてあったけど、反論しといてよ」と言っていた。
おっしゃる通り、タカハシ先生には隠れたる名著がある。「新版ケース・スタディによる金融機関の債権償却」(金融財政事情、1993年)である。彼は金融庁に分離される前の大蔵省金融検査部に所属していたことがあって、金融機関の不良債権償却のガイドラインと実務をこの本で詳細に説明しているのだ。当時の銀行のバイブルである。その後の長銀や日債銀などの粉飾にも大いに影響した。まさにミクロ中のミクロである。その悪戦苦闘があってこその「シンプル・ロジカル」だと、本書を読む人は肝に銘じてほしい。
ウォール街は悪の枢軸か――環日本海紙シンジケートコラム
新潟日報などに3カ月に1度掲載しているコラム<時代を読む>を書きました。
ウォール街は「悪の枢軸」か
「二十一世紀は精神的な時代になるか、あるいは存在しないだろう」
ドゴールの文化相を長く務めたフランスの作家、アンドレ・マルローの予言が、今さらのように気にかかる。
米証券取引委員会が4月16日、最大手投資銀行のゴールドマン・サックスを証券詐欺容疑で提訴した。07年に販売したサブプライムローン(信用度の低い住宅ローン)債権の債務担保証券(CDO)の組成と販売にあたって、ゴールドマンは買い手の投資家に適切な情報開示をしなかったという理由である。
合成CDOに組み込む証券の選定に関わったヘッジファンド(ポールソン&カンパニー)が、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)で売り浴びせ、証券の価格が下がることを知っていながら、ゴールドマンは口をぬぐっていたというのだ。
くだけた言い方をすれば、いずれ叩き売りにあってボロになると知っていながら、何食わぬ顔で売りつけたのは「詐欺」にあたるという嫌疑である。
一見、理屈はもっともらしいが、SECの5人の委員の評決が3対2の僅差だったところをみると、この「詐欺」認定はけっして自明ではなかった。
ゴールドマンのみならず金融取引仲介業者(広義の証券会社)にとって、ある金融商品が無価値になるかいなかは一つのリスク。リスクは投資家が負うべきであり、ババをつかんだからと言って、仲介者のせいにするのはお門違いという論理も成り立つ。
相対(あいたい)取引で嘘をついたら詐欺だが、それらの証券には市場価格がついていた。他の投資家もその時点で値が妥当だと判断していたことになる。
それでも、潜在的な売り手がいると知ったら、仲介業者は投資家に耳打ちして、買い意欲をそぐべきなのか。おそらくこれは金融の根幹に関わる問題だ。市場は一定の情報公開を義務づけているが、情報の完全な対称性を実現したら市場は成り立たない。
リスクの分散という市場メカニズムは、情報の非対称性とコインの裏表なのである。
現にゴールドマンのブラックファインCEO(最高経営責任者)は、ゴールドマンもこの取引で損を出したのだから、故意に投資家をミスリードした詐欺ではないと反論した。
徹底抗戦の方針である。しかしニューヨーク・タイムズ紙のポール・クルーグマンのコラム「(グッチの)ローファーを履いた略奪者」が指摘するように、ゴールドマン・サックスは、客を殺しても荒稼ぎするウォール街の「略奪」(サックス)の代名詞になっている。
SECの提訴は、それに対するオバマ民主党政権の「みせしめ」、1月に大統領が提唱した「ボルカー・ルール」の露払いとも見える。
3月には新しい金融機関規制案のたたき台が上院銀行委員会で示されたが、ゴールドマンなど金融界は骨抜きにしようと、猛然とロビイングをかけていた。それに、オバマ政権とSECはカウンターパンチを食わせたのではないのか。
ゴールドマン、CDO、CDS、ヘッジファンド……その組み合わせだけで、ウォール街の「悪の枢軸」がそろい踏みの感じがする。
リーマン・ショック以降、納税者の血税を注ぎ込んで決壊を防いだウォール街が、安堵と感謝の舌の根もかわかぬうちに、途方もない高報酬を復活させ、生き馬の目を抜くババ抜きゲームを再開しようとしている。
その彼らにオバマ政権は鉄槌を食わせようというのだ。もちろん、中間選挙をにらんだ政治ショーであり、SECの提訴もまたすこぶる政治的である。
対岸の火事ではない。鳩山政権もアメリカ=ウォール街憎悪は強い。「浪花節マルキスト」亀井静香・郵政改革担当相の「郵貯見直し」はほとんど市場否定である。
だが、資本主義は「いかなるものも超越性を許さない」という意味で唯一の超越性なのだ。金融規制に市場外の「倫理」を持ち込む――すなわち、資本主義に「対称性」という精神性を求めたら、経済社会は元も子もなくしてしまうのではないか。
ののちゃんとファド3――今度はマリーザ
病気で休載していた朝日新聞の朝刊マンガ「ののちゃん」が再開され、昨年このブログでとりあげた不遇のファド歌手兼キクチ食堂のお手伝い、吉川ロカも登場した。
3月30日掲載の4512回は、山田食堂に流れる歌に客が「陰気な歌だなあ。めしがまずくなるよな」とつぶやくシーンから始まる。そこにDeixa-me beijar as tuas águasと歌詞が流れている。
例によって何の説明もない。いしいひさいちは謎解きを楽しんでいるのだろう。
これは昨年来日したファド新世代のマリーザが歌ったBeija de saudade(サウダーデのキス)の冒頭部分である。マリーザは1973年に旧植民地のモザンビークに生まれた。たぶん染めているのだろうが、ショートカットの金髪で、やや男っぽい顔立ちですね。この曲は昨年発売のアルバムTerraに納められている。
Ondas sagradas do Tejo
Deixa-me beijar as tuas águas
Deixa-me dar-te um beijo
Um beijo de mágoa
Um beijo de saudade
Para levar ao mar e o mar à minha terra
英訳にすると
Sacred waves of the Tejo
Let me kiss your waters
Let me grant you with a kiss
A kiss of sorrow
A kiss of longing
For you to carry it to the sea
and the sea to bring it to my land
マンガでは店の人に白い目でにらまれ、「ライブはもっといいんだろうねえ」とおだてると、そのライブをロカが始めて、客は帰るに帰れない。そのとき流れているのが、
Terra da minha mãe
terra dos meus amores
これは先の歌のもっと後の部分である。
ふうむ、いしいひさいちは入院中もマリーザのCDを聴いていたのかしらん。それとも掲載前日、ポルトガル通のウェブサイトQuinta do quimでたまたまこの曲を取り上げていたのが、あれは偶然でないのかな。とにかく、歌そのものを聴きたい人は、このサイトにエンベッドされたユーチューブをご覧ください。
18日のテイラー教授講演会 司会役はこう思った
FACTA4周年記念企画、ジョン・B・テイラー教授(スタンフォード大学)の講演会とコロキウムは3月18日、東京・有楽町の朝日ホールで開かれ、盛会のうちに終了しました。前日の政策決定会合で新型オペの増額という「追加的緩和」を決めた日銀の金融政策に何らかの示唆を与えることを期待します。
またコロキウムに参加していただいた渡辺喜美・みんなの党代表とエコノミストの高橋洋一氏ほか、関係者に感謝申し上げます。
教授の基調講演は、70年代から80年代にかけて、経済のパフォーマンスが日本では持続的な高度成長、アメリカでは乱高下だったのは、金融政策の巧拙によるものだったという分析から始まった。

この後、日本の「失われた10年」となった90年代は、逆にアメリカのパフォーマンスが安定を取り戻し、日本は金融政策が不安定になり、長い低迷期を経験した。これは日米の金融政策が攻守ところを変えたことになる。
この評価は今やほぼ定説だろう。教授もパワーポイントで70年代のFRB議長アーサー・バーンズとフォード大統領の動画と音声を画面に出してみせたが、70年代の米金融政策の失敗が80年代の混乱を招いたのに対し、日本は金融政策に振れがなかったと言う。
ところが、80年代末には円売り介入と金融緩和で日本にバブルが発生、その反動で90年代から急激な引き締めと日本の金融政策が揺れ出す。これに対し、ブラックマンデーを経たグリーンスパンFRBは、テイラー・ルールにほぼ沿った金融政策で市場に安心感をもたらした。かくて日本は、繁栄を謳歌する米国を尻目に「失われた10年」を経る。
しかしこの長い低迷期も、最終的に量的緩和によって終止符を打つ。03年の円売り非不胎化介入によるゼロ金利下の量的緩和である。教授は円相場を「失われた10年」の原因と見ていない。長期低迷から日本を救ったのは「通貨供給量の影響」と言う。
さて、ここから本題だ。リーマン・ショック後の日米金融政策は、量的緩和の一点を見れば、アメリカが通貨供給を劇的に増やして1兆2千億ドルに達したのに対し、日本は「欧米ほど金融機関が傷んでいない」ことを理由にさほど増やしていない。

教授は慎重な言い回しだったが、テイラー・ルールに照らすと、アメリカの量的緩和は過剰であり、「日本はもっと量的緩和をすべきだ」という示唆が得られるという。ある市場のセグメントを救うのは金融政策ではないが、FRBはAIGやミューチュアル・ファンド、MBS市場などの救済のために買わざるをえなかったというニュアンスだ。
これらの見方はほぼFACTAと一致する。アメリカの一流のエコノミストと意見を同じくするのはうれしい。教授はバーナンキら東部系のエコノミストには対抗心を燃やすらしいが、この講演会では日米の中央銀行が俎上にあがったと思う。
私とはSFつながり(一度、J・G・バラードの追悼記を本誌に寄稿してもらったことがある)で、クルーグマンの翻訳者でもある山形浩生氏が聴衆のなかにいて、教授に鋭い質問を浴びせていた。それらを含めて次号で詳報を掲載しよう。
(写真:大槻純一)
谷口智彦編訳「同盟が消える日 米国発衝撃報告」のススメ

日経ビジネス編集委員から外務省副報道官、そして現在はJR東海の「ウェッジ」で顧問役もつとめる谷口智彦氏が、ウェッジ出版から「同盟が消える日米国発衝撃報告」(税込み1470円)という、なかなかショッキングな本を出しました。面白いので書評します。
腰巻きにある「もう日本には頼まない」にくすっと笑いたくなる。これは城山三郎の石坂泰三伝「もうきみには頼まない」のもじりだろうか。
大蔵大臣、水田三喜男に言い放ったというこの言葉、石坂の気骨を示す逸話から取ったものだが、この本では「アメリカの気骨」を示すキャッチフレーズに使われている。
とにかく、NBRというアメリカのシンクタンクが、日米同盟という“倦怠期の夫婦”を考えつめたあげく、アメリカから「三行半」を突きつける内容の小冊子を昨年11月に出したのだ。題してManaging Unmet Expectations。この本では「外れてしまった期待をどうする」、直訳すれば「期待はずれをマネージする」である。
期待とは、ブッシュ前政権の対日政策の基礎となった「アーミテージ・ナイ報告」のことである。アメリカは、日米関係を米英関係と同じく堅固なものにするという過剰な期待を抱いたが、日本は小泉政権以降、期待に応えられず、それならいっそ期待値を下げようというのだ。もう日本には頼まない、と千仞の谷に突き落とす。
そればかりか、あれこれ「別れる場合」を想定、シミュレーションしましょう、という内容である。虚飾をはいで現実をとことん直視しようとするその姿勢は、やはり軍略の専門家たちだからだろう。
リーダーはブッシュ政権の国防副次官(アジア・太平洋安全保障担当)だったリチャード・ローレスと、国防白書(QDR)を作成したジム・トマス国防次官補代理である。執筆は退役将校のマイケル・フィネガンが請け負った。
中身は大所高所論より、共同作戦行動の現実的欠陥から「ボトムアップ」で形成された議論であることに特色がある。が、時々、ユーモアを発揮する。
このような分裂を抱えた同盟とは、思うにサブプライム〔適格以下〕な同盟である。そんなふうに元々欠陥品の同盟が、喩えついでに言えばますますレバレッジのきいた〔競争条件が数等厳しい〕状況の中、ひたすら自己保全を目的にして何を試みようが、周囲の問題が一層深刻さを増してしまえばしょせんは生き残れない――。
もちろんこれは、サブプライムローンと、CDOなど「レバレッジのきいた」証券化商品の破綻をもじっているのである。ここでもくすりと笑わせる。さらに、日本を「有限責任パートナー」(LLP)とみなせ、という提言にいたると、アメリカの軍略家はこういうキャピタリズムの用語に淫しているのかとまで思ってしまう。
冗談はさておき、冷静にこの本のもたらすものを考えよう。確かに、アメリカから日米同盟を壊すことはないだろうという「甘え」を消すのにはいい。中国にこの同盟が「張り子のトラ」だと見透かされていると言われれば、その通りだろうと思う。
だが、本書には死角のように意図的にぼやかしている部分がある。「ビンのキャップ」がはじけることを、アメリカは容認するのかどうか。つまり日本と距離を置いて、同盟を限定的なものにとどめた場合、日本の核武装を容認するのか、という点である。
本書では、「日本が独自に核兵器を持とうとする可能性もありうる」とか、日本が核武装すれば、ヘッジとして韓国や台湾も持つかもしれないという中国の懸念については触れているが、アメリカ自身が「容認」するか否かの言及がない。補論Bの五つのシナリオのうち「核ゲームで孤立」が具体的にどういう状況をさすのかがよく分からない。
Thinking the unthinkableである。「唯一の被爆国」が核武装する可能性はある。中国、韓国、アメリカから孤立した日本が、自らの矜恃を回復させるための方途として、それは理論的に十分ありうる想定なのだ。日本が核武装のオプションを持たない、というのは、それこそアメリカの「甘え」ではないのか。
日本が「もうアメリカには頼まない」という瞬間が実はもっとも恐ろしい。彼らにとっても、我々にとっても。そういう政治指導者――座して死をまつよりは、と主張する政治家が現れる機運は熟している。
ところで、編訳者、というよりは、ほとんどこの本を企画し、自らの文体で咀嚼しきった谷口智彦の、これはもっとも本領を発揮した本かもしれない。
日経ビジネスやロンドン、そして外務省で、幾たびも彼の軌跡と交錯したが、その卓越した能力と憂国の志は常にその組織とはどこかですれ違っていた。でも、そういう顧慮のないところでは、つまり、この国で省みられることの少ない安全保障論においては、水を得た魚のように書けるらしい。そういう時の彼の文章は(ここでは訳文だが)、いささか古風で佶屈ではあるが、いちばん素直に流露している気がする。うらやましいことである。
手嶋龍一「スギハラ・ダラー」の熊本日日新聞書評

3月7日付の熊本日日新聞の書評欄で、手嶋龍一氏の新著「スギハラ・ダラー」(新潮社、税込み1680円)の書評を掲載しました。3月号のFACTAの書評とは別に、この本のモデルと目される人々を挙げて、虚実皮膜の間を論じています。
*****
手嶋龍一はカメレオンである。ときに事実を追うハンターとなり、ときに奇想を紡ぐドリーマーになる。その現実と奇想の交点に本書はある。
彼のアバター(分身)が、京都や金沢の茶屋で遊ぶ数寄者の英国情報機関員スティーブン・ブラッドレー、すなわち本書の主人公だろう。
このアバターは、前作『ウルトラ・ダラー』では北朝鮮の偽ドル札を追った。その続編の本書では、金融先物の最先端シカゴと、ユダヤ人難民六千人を救った「日本のシンドラー」杉原千畝を結びつけた。息をのむような離れ業だ。
そこに浮かぶのは、マネーの本質である「越境性」――すなわち国民経済を担保とするマネーが、国境を越えたグローバル性を得ようとする矛盾である。
ギリシャなどPIIGSと言われる財政危機の国々の「ソブリン・リスク」が世界を震撼させている今、これはぞっとするほどアクチュアルなテーマだ。
リーマン危機で戦後の通貨制度を定めたブレトンウッズ体制が揺らぎ、一九七一年に変動相場制に移行したドルが基軸通貨の座を維持できるかどうか、試されている。
GDP(国内総生産)比の累積債務残高が200%に接近する日本も、潜在的には被告台に立たされている。グローバル化を拒んだ円が国際通貨の座を失いかけているからだ。
本書が単なる奇想でないのは、現実のモデルという錨があるためだ。それを憶測しながらでないと、虚実の境に立つ本書を読み解く楽しみは半減する。
杉原千畝が単なる人道派の外交官ではなく、敵国ロシアの背後でインテリジェンス工作に身を挺していたことは紛れもない事実である。
ソ連の暗号を解読し、冷戦期にソ連のスパイ工作を暴露した「ヴェノナ」作戦が、フィンランドと日本の戦時中の交信を傍受して突破口をみつけたように、ソ連に呑みこまれる直前のバルト海の情報戦争は熾烈を極めた。
杉原ビザで救われて神戸にたどりつく難民の少年アンドレイは、シカゴ・マーカンタイル取引所のドンとなったレオ・メラメドだろう。その親友となる日本人相場師、雷児はたぶん是川銀蔵がモデルだろうが、そのスケールはむしろアメリカからスイスに亡命した伝説のトレーダー、マーク・リッチのほうがふさわしい。
シカゴが表なら、リッチは裏である。ベルギー系ユダヤ人の出身で、今日の石油投機の基礎を築いた。七九年のイラン革命後に禁輸を破って、イラン産石油をイスラエルに密輸している。アメリカの逆鱗に触れ、暗殺対象になった。
カストロのキューバ、内戦のアンゴラ、アパルトヘイトの南アフリカなど、経済制裁の網をくぐる密輸の裏には、常にリッチの影がちらつく。アルカイダなどの国際テロ組織も、その地下ルートに塊茎のごとく連なっている。
マネーの「越境性」はそこに聖なる秘密がある。欠席裁判で天文学的な懲役判決を受けたリッチは、クリントン政権末期に巨額の政治献金を積んで大赦を勝ちとった。その彼が長年の沈黙を破って、雑誌編集者のインタビューに応じ、なぜ生き残れたかを語った本(The King of Oil ; The Secret Lives of Marc Rich)が昨年出版された。
やはりと言うべきか、彼の生命を守ったのはイスラエル情報機関だった。
本書にも、イスラエルを防衛しようとマネーの聖域に身を投じる美少女ソフィーが出てくる。それもリッチのアバターと言えよう。マネーの聖性は地下に潜む。
ちょっくらテレビ出演
3月18日には講演会もあるし、創刊4周年でもあるので、恥ずかしながらテレビに出演します。2時間番組ですが、うさぎさんと小生を除いて、あとは学者の方々。テーマは政治ですが、これだけ景気が悪いと、経済絡みの話題も出てくるでしょう。
朝日ニュースターの「ニュースにだまされるな」3月6日(土)放送です。
◆番組名
「ニュースにだまされるな」
◆テーマ
~政治とカネ小沢問題の背景は?~
◆ゲスト
阿部重夫氏(ファクタ編集長)
石田英敬氏(東京大学情報学環教授)
浦野広明氏(立正大学教授・税理士)
山口二郎氏(北海道大学教授)
(あいうえお順)
◆司会
中村うさぎ(作家)
金子勝(慶応大学教授)
◆放送日
3月6日(土)22時00分~23時55分(初回放送)
3月7日(日)16時00分~17時55分(再放送)
3月10日(水)21時00分~22時55分( 〃)
3月11日(木)14時00分~15時55分( 〃 )
3月11日(木)25時00分~26時55分(〃)
NHKラジオに出演します
解説委員の大島春行さんに頼まれて、ちょっとNHKラジオ(第一)に出演します。3月3日(水)の「私も一言!夕方ニュース」の一コーナー。6時半からだそうです。
テーマは「アメリカのトヨタ批判をどう読むか」。トヨタ問題は一体何を意味しているのか?情報のプロがアメリカの置かれている現状を踏まえて解析する、といった内容になるようです。
ご興味のある方はどうぞ。
あと、可能だったらTwitterのFACTAアカウントで、しゃべった内容を追っかけツイートするかもしれません。
あなたもジョン・テイラー教授に”直撃”質問を!
3月18日(木)のジョン・テイラー教授の来日講演会「脱デフレ処方箋」に先立ち、FACTAはTwitterで教授に聞きたいことを募集してます(投稿内容はこちらからご覧いただけます)。
スタンフォード大の教室にバーチャルで座り、世界有数のエコノミストに質問できる貴重な機会です。FACTAは5日に教授に事前に会って、18日の講演や次号の誌面にそれを反映させる考えです。
投稿者の中から、抽選で5名様にFACTA半年分無料購読をプレゼントします。投稿はFACTAサイトの右側にあるバナーもしくは、Twitterの投稿画面からハッシュタグ「#FACTAforum」を付けてツイートしてください。なお、投稿はこのページへのトラックバックおよびメール(taylor@facta.co.jp)でも受け付けています。
さあ、勇気をふるって直撃!
※当選者にはTwitterのダイレクトメッセージ機能もしくはメールでお知らせします。
米国トヨタ自販 レンツ社長の責任転嫁
豊田章男社長の米議会公聴会を前に、レンツ社長が証言した。テレビで一部を視聴したが、ひでえもんだ、と思う。
日本の本社にすべて責任転嫁。「リコールは自分に権限がなかった」「技術的な問題も日本任せ、自信はあるが細かいことには答えられない」というのがレンツ社長の証言だった。自分の責任逃れのための証言で、要するに「もっと自分に任せればこんなことにはならなかった」とせびっているだけだ。こういう人間に証言させたトヨタの甘さは目を覆いたい。
米国社会を知っていれば、自動車のディーラーに二流の人間が多いことはわかっているべきだ。レンツは三流である。トヨタの失敗は、こういう保身しか考えない人間を厚遇し、最後は裏切られたことだろう。
小生はナショナリズムは蛮習だと思っている。それでも、涙ながらにトヨタを非難した米国人女性のあざとさを見抜けない米議会もマスメディアも下の下だと思う。彼らのさもしい恫喝根性は憎むべきだ
しかし、トヨタの経営は合理性の追求にあったはずなのに、合理性においてすでに負けていたのではないか。これでは、クレーマーたちの没論理を打ち返せない。
レンツに証言させるという決断を下したのは、稲葉アメリカ・トヨタ社長や本社の章男社長、張冨士夫会長のいずれだったのか。その罪は経営者として万死に値する。
日銀が投げつけた「ゼロ回答」
ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)の名物コラムが恥をかかされた。マーケット関係者なら必読の「ハード・オン・ザ・ストリート」2月17日付(日本語版の記事)で、マキャベリストの菅直人財務相が、日銀に「コアの消費者物価上昇率を1%」とする事実上のインフレ・ターゲティングを迫る発言をした機会をとらえて、他の先進国が何年も前から採用してきた政策の方向に「日本もやっと動き出した」と評したからだ。が、翌18日の政策決定会合後の記者会見で、白川方明日銀総裁はWSJの期待を一蹴してみせた。
会見では国債金利が上昇する事態になっても「金融政策運営が財政ファイナンスを目的としていない」と日銀は挙手傍観するという驚くべき内容だ。また「インフレ目標を採用しているかどうかは、意味のある論点ではなくなってきている」と勝手な印象を口にし(WSJが言及したことは意味がある論点ではないのか?自分だけ意味がないと言っている)て議論をすりかえ、「物価動向だけに過度の関心が集まる結果、物価・金融以外の金融・経済の不均衡を見過ごしている」と堂々たる責任転嫁を行った。いよいよ、菅財務相のジャブや、FACTAのような批判に敵意むきだしである。
正体見たりだろう。デフレに目を背ける白川日銀の姿勢があらわで、前庭だけきれいにしておけば、実体経済がどうなろうと構わないのだろうか。金融政策の出動要請に事実上のゼロ回答である。この頑迷ぶりは病的ですらある。
既にご案内の通り、FACTAが3月18日にジョン・テイラー教授を呼んだ講演会を開くのも、きちんとした議論が盛り上がるようにしたいからだ。さらに、事前に様々なご意見やご質問を受け付けるために、「Twitter」を使った仕組みも用意しました。Twitterのアカウントをお持ちの方は、是非このサイトの右側に表示されているバナーからご投稿ください(※この議論のハッシュタグは「#FACTAforum」です)。お寄せいただいたご投稿には、編集部の公式アカウントやこのブログを使って返信するつもりです。もちろん、メール(taylor@facta.co.jp)でも受け付けていますので、幅広いご意見・ご質問をお寄せください。
講演会の詳細はこちらをご覧ください。
3月号の編集後記
毎年2月5日になるとお呼びがかかる。34年前のこの日、ロッキード事件の号砲が鳴り、「首相の犯罪」を追うマラソン取材が始まった。社会部の国税担当記者だった私も、夜討ち朝駆けで目ばかり光る“餓狼”と化した。往時の取材先、磯辺律男・東京国税局長(のち国税庁長官、現在は博報堂相談役)やその元部下たちを囲んで、国税記者クラブのOB記者が集う会が「二五会」である。
▼懐かしい。私は記者で最年少だったから、ここでは永遠に「坊や」である。いまだに往生際悪く取材に血眼なのは私ひとり。見渡せば、みな悠々自適の老後だが、年々病を得たり鬼籍に入ったりで、このごろは一人二人と欠けてきた。確かにあのころは、検察や警察、国税当局と社会部が“蜜月”の関係で、ともに「巨悪を討つ」正義を信じていた時代だった。されど、正義もまた老いる。
▼最近、退屈紛れに原始浄土仏典のひとつ『阿閦仏国経』を読んでいる。阿閦と書いて「アシュク」と読む。怒らずとか、動かずという意味らしい。阿弥陀仏の西方浄土、視(み)よ」と言う。もの知りのアーナンダ(阿難)が上を見あげたが、虚空しか見えない。須菩提は「上を向いて空を視るごとく観ぜよ」と言った。
▼はぐらかしみたいだが、阿閦仏は信じる人の想念のなかに住まう。メディアもそうだ。正義は想念にしか現われない。新潮社の月刊情報誌「フォーサイト」が3月で休刊する。私もかつて少し寄稿したから、一抹の寂しさを感じる。宙に浮く書き手と読み手たちはどうするのだろう。二五会のように雑誌も一つまた一つと欠けていく。タイトルの「先見」の志は継承したい。携帯電話を真似て「乗り換え割」でもやりましょうか。詳しくはお問い合わせを。
日銀「デフレ・ターゲッティング」の立証
FACTAでは、3月18日のジョン・テイラー教授(スタンフォード大学、元米財務次官)の講演会「脱デフレ処方箋」の開催に先がけ、金融政策に関する意見や質問を受け付ける仕組みを準備中です。近日中にオープンするので、関心のある人はお楽しみに。
まずは、議論が少しでも盛り上がるように、1月号の記事「白川日銀は『デフレ誘導』」を特別にフリー公開します。下記はオンラインに掲載している「読みどころ」の引用です。
OECD 事務総長が発破をかけたからか、11月20日に政府は「緩やかなデフレ状況にある」と宣言しました。しかし3週間前に日銀はCPや社債の買い取り完了を発表して、リーマン危機後の緊急措置の「出口政策」へ動くなど、直前まで白川総裁がデフレ宣言など考えてもいなかったことがうかがえます。先進国の中でも最悪の35兆円にのぼるGDPギャップ(総需要と総供給の落差)が財政を圧迫、失業者を増やしているのに、それを埋める金融政策を出し渋り、鳩山首相との会談前日に発表した新型オペも「広い意味での量的緩和」とは名ばかり。「インフレ・ターゲッティング」嫌いの白川総裁が、実は「デフレ・ターゲッティング」を実行していることをFACTAが立証します。
講演会の詳細はこちらをご覧ください。
マドセンの日銀批判
2月12日付WSJ(ウォールストリート・ジャーナル)のコラム「ハード・オン・ザ・ストリート」の見出しは「Betting it all over Growth」(成長にすべてを賭けて)だった。
本文はこう始まる。
問題失業の悲惨な高水準、ぱっくり口をあけた財政赤字、借金過多の消費者。
解成長
確かに「成長はすべてを癒す」。今や「ニッポン病」と言っていい日本経済の慢性疾患も、ほとんどすべて成長できないことに起因する。
だから、国民所得統計で10~12月の第3四半期のGDP実質伸び率(成長率)が前期比1・1%(年率換算で4・6%)の伸びと発表され、WSJも「日本の成長率が期待上回る」と珍しく明るいタイトルをつけた。
だが、好況の実感はまったくない。なぜなのだろう。
3週間ほど前の同紙Op-Ed欄に載ったMIT(マサチューセッツ工科大学)国際研究所の上級研究員(シニアフェロー)を務めるロバート・マドセン博士の寄稿記事(1月19日付WSJPlaying Politics With Japan’s Money Supply)が思いだされる。
マドセンは昨年の米外交専門誌「フォーリン・アフェアーズ」誌上で、リーマン・ショック以降の米国の金融危機をめぐって、「週刊東洋経済」のコラムニストでもあるリチャード・カッツと論戦したことで知られる。
今回は90年代の日本の「失われた10年」の再現ではなく、ずっとましだと主張したカッツの記事に対し、マドセンは「今回の危機は北米だけでなく、グローバルな危機であること」、また「90年代日本と今回の危機が、両方とも過剰貯蓄と資産バブルの破裂によってもたらされたという共通点がある」ことを指摘、「今回の危機のほうがもっと深刻」(Worse and Worser)と反論した。
私個人はマドセンの肩をもちたい。両人とも日本経済の素人ではないが、マクロ的視点ではマドセンのほうが納得できるからだ。1月のWSJ寄稿の書き出しはこうだ。
日本経済に再び影を落とすデフレに対し、(日本の)政策は相変わらず機能不全に見える。政治家と財務省は物価の下落は中央銀行が解決すべき金融の問題であると言い、他方で日銀は財務当局こそ経済をリフレートすべきだと主張している。BOJのほうが誤っている。政府からの独立性を示すのに、またもや不適切な機会と手法を選んでいるのだ。
日本の中央銀行は、物価安定(大半のエコノミストが消費者物価の年間上昇率を1~2%と定義している)を維持するという第一の義務を達成できないというロング・レコードを持っている。1998年に財務省から独立を得て以来、日銀は一度もその目標を達成していないのだ。グローバルな経済バブルが、石油や金属、その他の輸入品の価格を押し上げた99~06年の間も、日本経済はデフレで劣化していたのだ。それから2年後、バブルがはじけ、国際物価が下落し始めると、日本のCPI(消費者物価)はまたもやマイナスに落ち込んでしまった。
マドセンの主張はほぼ、FACTAが続けてきた日銀批判のキャンペーンと同じである。日銀の御用学者、あるいは日銀OBがいくら白川方明総裁に肩入れして、FACTAの記事を封じ込めようとしても、国際的な論壇では日銀は「被告台」に立たされている。それをちゃんと報じない国内メディアも情けない。
FACTAが3月18日にジョン・テイラー教授(スタンフォード大学、元米財務次官)を呼んで講演会を開くのも、「本石町の奥の院」日銀は何をなすべきか議論を起こしたいからだ。バンクーバーの冬季五輪やサッカーのアジアカップを見ていると、スポーツではすでに日本は二流国。経済学でも一度もトップリーグに顔を出したことがない。その日本が、いかにトンチンカンな中央銀行を抱えているか、すこしでも感じている人は論戦に参加していただきたい。
この編集長ブログでも、プロモーションも兼ねて積極的にとりあげていきましょう。最新の3号(2月20日発売)では、マドセンの指摘する歪んだ「日銀の独立性」について取り上げていますから、ぜひご一読を。そのうえで講演会とコロキアムにもご参加いただければ幸いです(講演会の詳細はこちらをご覧ください)。
ウィルフレッド・セシジャー「湿原のアラブ人」のススメ――滅ぼされた「エデンの園」

彼らはマアダン(葦のアラブ人)と呼ばれた。チグリス下流の丈の高い葦が密生した湿原に住み、葦を編んだ家を建て、小舟で漁業や運送を営んでいた。
14世紀に西アフリカから現在の北京まで旅したイブン・バットゥータも、1326年冬にここを通った。「大旅行記」には追い剥ぎとして登場する。
砂漠の遊牧民との落差にこの大旅行家は目をみはったが、本書の著者も1945年から5年間、ベドウィンとアラビア半島のルブ・アルハリ砂漠を横断する旅をしたあと、ここにやってくる。
「囲炉裏の火に照らされた横顔、雁の鳴き声、餌を求めて飛びこんでくる鴨、暗闇のどこかから聞こえてくる少年の歌声、列をつくって水路を移動していくカヌー、枯れた葦を燃やす煙のむこうに沈んでいく深紅の太陽」……。
彼はエチオピア生まれの英国の元軍人で、北アフリカや中東で大戦に参加したが、戦後は探検家になり、51年から58年まではイラク南部で暮らした。
おそらくマラリアが猖獗を極め、夜は蚊や蚋などに悩まされたろうに、そうした苦痛を毛ほども見せない。凡百の文化人類学の野外調査と違うのは、その詩情と無告の民への優しさだろう。
さながら葦の平原に身を没してしまうように、彼はオクスフォード出身の英国貴族の出という出自を捨て、野生に帰りたかったのではないか。
この葦の湿原には、かつて「エデンの園」があったとの伝説もある。なるほど砂漠と荒野だらけの中東では、ここは楽園に見えたのかもしれない。
そしてバプテスマのヨハネがイエスに施した「洗礼」も、この葦の原に残るグノーシス系のマンダ教が流水に三度身を浸す洗礼を中心儀礼としているため、この地に起源があったのではないかと言われている。
だが、「葦のシャングリラ」は今は幻だ。わずか50年前の風景なのだが、セシジャーが耽溺した水の桃源郷はもうない。サダム・フセインが干上がらせたのだ。
80年代のイラン・イラク戦争で、南部シーア派がイランと通じて「獅子身中の虫」となることを恐れたサダムは、90年代にダムを築いてチグリス、ユーフラテスの河流を変え、この水郷地帯を滅ぼしてしまった。
おそらく「バーミアンの石仏」爆破に匹敵する歴史的な暴挙だった。追いたてられた貧しいマアダンの末裔が、首都バグダードのスラム「サウラ地区」に流れこみ、今なおテロが続くイラクの震源地になっているのは、なんという皮肉だろう。
セシジャーが葦の原を離れた3週間後に、イラクは革命で王政が倒れた。彼はついに再訪がかなわず、03年8月24日に93歳で没した。
ホモセクシュアルの性向といい、過酷な気候に耐えたスタミナといい、彼は紛れもなく「アラビアのローレンス」の後裔である。本書で残念なのは、セシジャーが撮った美男のアラブ人少年や青年の写真の多くが「コスト」を理由に割愛されたことだ。
割礼したペニスや、カテドラルのようなムーディフ(葦の家)の白黒写真には、明らかに彼の美意識と官能が反映している。つくづく惜しい。
(熊本日日新聞2009年12月掲載)
高橋洋一・竹内薫「鳩山由紀夫の政治を科学する」のススメ

豊島園での奇妙な事件で一時蟄居を余儀なくされていた「埋蔵金男」高橋洋一氏の復活第二弾の本である。昨年はあのスキャンダルだけでなく、自転車でつまずいて足を折るなど個人的にも色々災難につきまとわれただけに、今年はとにかく無事を祈りたい。
09年11月号(10月20日発売)のFACTA編集後記で書いたように、彼の現場復帰は10月刊行の「恐慌は日本の大チャンス」(講談社)で著者名を明記したことから本格化した。豊島園の一件はそこで説明されている。警察官僚による意図的(?)なリークが、彼のライターとしての「抹殺」にならなかった証明が、これらの本だと言えよう。
今回の「鳩山由紀夫の政治を科学する」(インフォレスト、800円)も、副題が「帰ってきたバカヤロー経済学」とあるように、同社が昨年5月に出した「バカヤロー経済学」の続編である(「『バカヤロー経済学』のススメ――ホームズとワトソンの漫才」参照)。前編が彼の名を秘していたのに対し、今回は堂々と彼の名を共著者として出している。講談社から本を出した後、高橋氏は田原総一朗氏のラジオ番組やテレ朝の「サンデーモーニング」にも出演、メディア的にはもう支障がなくなったようだ。
両編とも対談形式で、東大理学部物理学科を卒業したサイエンスライターの竹内氏が、同じく東大理学部数学科と経済学部を卒業した「先生」高橋氏に、経済学(というより経済そのもの)の虚実の教えを乞うスタイル。2人とも「理系脳」なだけに、同じく東大工学部計数工学科を卒業して米スタンフォード大学でオペレーションズ・リサーチ(OR)を専攻した鳩山首相の思考回路を、ORで読み解こうという趣向である。
ORやゲーム理論、陰関数などが出てくるが、数式を使うような野暮はしない。中身は「理系脳」2人による漫才である。本の腰巻きには、学帽とガウン姿の2人の写真がシャレで載っているが、ほんとに「理系漫才」をやったら受けるのではないかと思うほど、呼吸がぴったりあっている。しかも現下の鳩山政権の不可解な行動を明快に解いてくれるから、数学にも経済学にも素人であるモノグサ諸兄には、笑って学べる楽しい本である。いっそのこと「宇宙人」宰相も入れて、「てんぷくトリオ」みたいにやれば面白いかもしれない。
ふたりとも学歴も知識も申し分ないはずなのに偉ぶらない。最年少で公認会計士試験を通ったというイヤミが売りの、何の役にも立たない女性ハウツー本作家の駄本が、ベストセラーになるなら、この本のほうがずっとお薦めである。途中経過を言わず、結論をぽんと言うだけだから、忙しくて結論だけ知りたい人にはうってつけかもしれない。
ただし、本書では最後にオチとして「フォーク定理」が出てきて、その説明をあえてしない。「囚人のジレンマ」を知っている人は、非協力(裏切り)でナッシュ均衡が成立することを知っている。が、無限回の繰り返しゲームになると協力が均衡解になる。それがなぜフォーク(ロア)定理と呼ばれるかを知っていれば、最後にニヤリと笑える仕組みである。