
リーマンの牢獄 【2】前編
新井将敬自殺で「第二の人生」暗転
再就職は政治家秘書と思い定めた途端、気鋭の論客政治家が自殺。さっそく頓挫して、地域のためになろうと下町の信組に飛び込んだ。外資が売り込む金融商品の目利き役から、また証券界に引き寄せられ、食物連鎖で上位の米大手証券へ三段跳び。=有料記事、1 万3300字
第2章大洪水のあと〈前編〉
――齋藤さん、おはようございます。だいぶ秋も深まってきました。やはり奥信濃は寒いですね。娑婆では、紅葉は今が真っ盛りといったところです。浅間山はうっすらと雪化粧していますけど、刑務所内は残念ながら季節感がまるでありませんね。
「やあ、アバターさん。ようこそ。お会いするのが楽しみになってきましたよ。
長野刑務所は夏なら涼しくて快適なんですが、最大の難点は冬の寒さなんです。独房には暖を取る手段がまるでありません。メリヤスの下着と囚人服を重ね着するだけが防寒ですから、寒くて手がかじかんで、本のページを繰るのも苦痛なほどです」
――否応なく、自分と向き合うことになりますか。
「とんでもない。刑務所では自分と向き合うことすら自由にできません。何しろ瞑想のために目を閉じることすら、懲罰の対象になりかねませんから。先日、目をつぶって考えこんでいた囚人に、看守がこう怒鳴っているのが聞こえました。
〈おい、寝てんじゃね~、起きろ!〉
その受刑者は寝ていませんでした。心を落ち着けようとしていただけなのに……」
――厳しい環境ですが、先日の話の続きをお願いしましょう。山一證券が自主廃業に追い込まれて、社員全員が失職を告げられた時点からですよね。
社内調査報告書に愕然
「いまだにテレビ画像でよく流れる、あの野澤正平社長の号泣会見で〈社員は悪くありません〉と何度も言ってますでしょう。では、社員が悪くなければ、誰が悪いのか。いったい誰が何をしたんだ、その説明が全くない。社員はもちろん、家族そして顧客その他多くの方々が、あのとき全容を解明してほしいと思っていたでしょう。
社長会見後に僕自身も、赤坂支店時代に支店長だった大和田正也氏に電話して〈全容解明と山一再興に動くべきではないか〉と提案したこともありました。しかし〈山一にこだわり、その再興を考えるよりも、一人一人が力強く前進すべきだ〉という大和田氏の言葉に納得し、自分の道を歩む決意を固めたのです」
――翌1998年4月に嘉本隆正常務を中心とする社内調査委員会が『社内調査報告書~いわゆる簿外債務を中心として~』を公表します。読みましたか。
「あれを読んだのはずっと後になってからです。ペーパーカンパニーを使った〈飛ばしスキーム〉などの詳細を知って愕然としました。ここまで腐っていたのか、ここまでひどかったのか、山一證券には屋台骨などなかった……こんな明らかな犯罪行為、証拠隠滅行為が、ノルマに苦しむ多くの証券マンの目を盗み、長期にわたり行われていたなんて。あまりの衝撃に悲しみというよりも、怒りを覚えました。
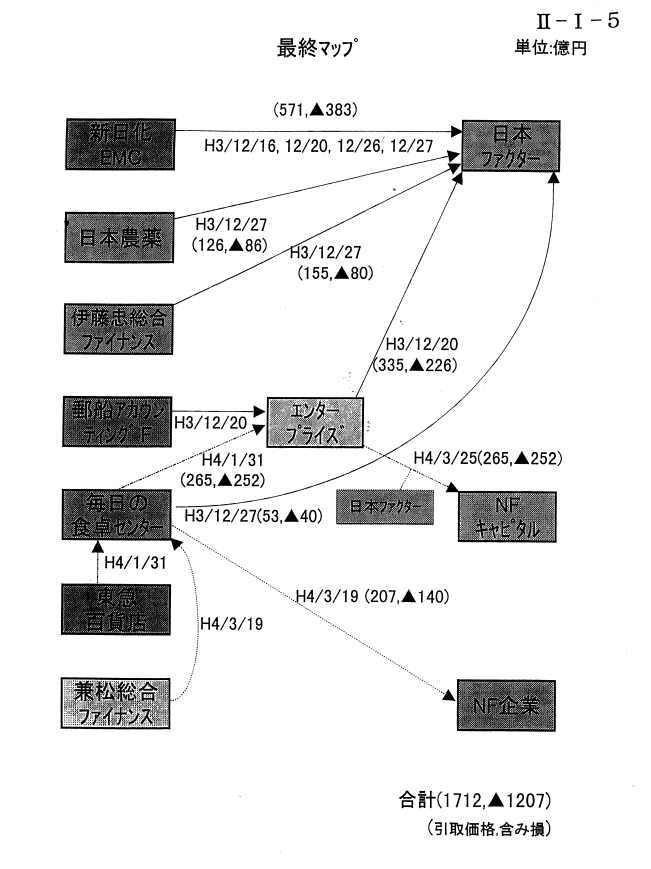
そして服役中の2013年には、読売新聞記者だった清武英利氏が書いた『しんがり山一證券最後の12人』(講談社)が出版されます。独房で読んだため、驚いても声は出せず、酒を呑んで憂さ晴らししたかったけど、それもかないませんでしたが、よくぞここまで書き残してくれたと感謝したかった。清武氏はあの号泣会見をこう書いています。
日本の大企業の社長が泣きながら頭を下げる写真は全世界に配信された。米紙ワシントン・ポストはその写真を添えて、こんな社説を掲げた。
〈Goodbye, Japan Inc.(さよなら、日本株式会社〉
確かにそれは、日本の終身雇用と年功序列の時代が終わったことを告げる涙だった。
僕もまったく同感です。山一自主廃業の是非などではない、もっと大きな時代の流れを汲み取らなければならなかったということだと思います。資本、土地、そして労働も、自由競争にさらされることになったんです。新しい時代は、山一の元社員がそれぞれ切り拓かなければならない。その責任を負ったという気負いがありました。いまは屈辱にまみれていますけど、これからの舞台の主演は一人一人の社員であり家族なんだ、と」

受賞した清武英利氏の『しんがり』
――齋藤さんは証券界から足を洗おうと考えたのですか?
「僕は次に何をすべきかわからなかった。すぐに就職活動へと頭を切り替えることができなかったんです。社員全員が解雇されるのは98年3月末になっていたので、少し吞気に構えていたかもしれませんね。妻からも言われました、大丈夫?ちょっとのんびりしすぎてるんじゃないのって。
端境期の35歳、しかし慌てず
当時の僕は35歳と微妙な年齢でした。京都伏見支店には妻子を連れて赴任していたので、このまま京都に住むのか、東京へ戻るべきか、決めなければならない。結局、東京に帰ることにしましたが、江戸川区のベイサイドエリアに5800万円で購入したマンションがあり、賃貸に出していて妻も共働きでしたので、住宅ローンの返済で汲々としていたわけじゃないんですが、山一株買い支えのために社内融資制度を利用した借金1000万円が残っていました。この借金を少しずつ返済することにしましたが、心理的に重荷でしたね。
ハローワークは一度しか行きませんでした。野澤社長が〈(社員たちが)再就職できるよう、お願いします〉と必死の形相で訴えたせいで、2万件を超す求人が来ていると聞いていたので、それも安心材料だったのかもしれません」
――正確には12月4日までに寄せられた求人案件は1325社、約1万6000件でした。これに対し98年1月時点の正社員7490人に契約社員なども加えると、山一の求職者は1万550人だったわけですから、数字の上では誰も路頭に迷わずに済む計算でした。『しんがり』には、山一社員が再就職に困らなかったデータとして、正社員の4分の3にあたる5608人が98年10月末までに転職先を決めたとあります。
しかし求人の多くは35歳以下の若手の専門職に集中していたようで、〈つぶしがきかない〉36歳以上の中高年はなかなか働き口が決まらなかった。齋藤さんの年齢はその端境期にあたります。あなたが新川の山一證券本社まで求人情報を見に行ったのはいつですか。
「山一には顧客からの預かり資産が24兆円もありましたから、お客さまからの引き出し対応に全社が忙殺されました。僕は最後まで信頼してくれたお客さんに挨拶回りを済ませ、支店に詰めかけた預かり資産の清算業務が一段落したところで、ようやく自分の職探しを始めることができた。それは97年の暮れも押し詰まってからでした。


