EDITOR BLOG

「オリンパス」の風化と嫌な空気
FACTAがオリンパス事件を最初に報じて2年余りが経ち、早くも事件が風化し始めているようだ。事件から引き出されたはずの教訓が、まるで生かされていない事例がぽつぽつと表れているのだ。
ある大手商社はオリンパス事件の発覚直前に社外取締役制度を採り入れ、コーポレート・ガバナンスに一家言を持つ人物を招いた。ところがせっかく招いた人物がガバナンスについて積極的に発言したことがよほど気に入らなかったらしく、社外取締役を解任したくなった。おおっぴらに解任すれば目立つため、社外取締役の任期をわずか2年と定め、任期が到来したこの4月にクビを切った。
ガバナンス問題の専門家からは「月に1~2回の出社に限られる社外取締役が社内の事情を把握するには時間がかかるのに、任期が2年とは短すぎる」との声が上がっている。
社外取締役に招かれるのはもっぱら官僚OBになった。社外取締役や監査役はこれまでにも増して官僚の天下り先となっている。別の大手商社では社外取締役に、外務省出身でプロ野球の「飛ぶボール」問題で火だるまになった加藤良三・日本野球機構コミッショナーが就いている。飛ぶボール問題で加藤コミッショナーがどのように振る舞ったのかを見れば、官僚OBが社外取締役の責任をどの程度積極的に果たすのかはかなり怪しい。企業は社外取締役制度を採り入れたと言っても、形だけなのだ。
こんな話もある。ある企業法務系の専門誌ではコーポレート・ガバナンスをテーマとした論文を専門家に依頼して掲載したが、論文作成に当たって出版社から付けられた注文は「オリンパスについては触れないで欲しい」というものだったそうだ。
損失隠しに手を染めた旧経営陣に対する有罪判決が下った今、「いつまでもオリンパスを叩き続けるのは生産的ではない」という考え方で“オリンパスに触れるな”と言うのなら頷けるが、そうではないらしい。
オリンパスの不正会計を見逃した新日本監査法人とあずさ監査法人に対し、日本公認会計士協会が7月に「お咎めなし」とした時もそうだ。プレスリリースの表題は「精密機器の製造販売事業会社の審査結果の公表について」。表題にも本文にも、新日本やあずさの名前は見当たらず、オリンパスの「オ」の字も出ていない。
何だろうか、この嫌な空気は。
周囲の雰囲気や意向を忖度して口をつぐみ、見て見ぬふりをしてこっそり丸く収めようとするのは、やはり日本人や日本企業が抱えている病理的な部分だ。これでは組織も社会も根腐りしてしまうことを、日本人や日本企業はオリンパス事件を通じて改めて考えさせられたはずではなかったか。
FACTAはオリンパス事件を通じ、ガバナンス問題だけでなく、会計監査の問題や内部告発など、様々な問題を根こそぎ暴いた。しかし上に記した事例を見る限り、日本社会はオリンパス事件を経てなお、何も変わっていないのだ。この貧しい成果をジャーナリズムの勝利とは到底呼べない。
(この記事は本日ロイターに配信したものです)
武富士(TFK)更生計画に関する質問状2 Jトラスト宛て
武富士の管財人に質問状を送ると同時に、昨年、更生会社のスポンサーになったJトラストの藤澤信義社長にも質問状を送った。
Jトラストへの質問状は以下の通り。
Jトラスト株式会社
代表取締役藤澤信義様
TFK更生計画に関する質問状
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。弊誌FACTAは調査報道を中心とした月刊誌で、LM法律事務所の小畑英一弁護士が管財人を務めた武富士、ロプロなどのほか、管財人代理を務めた日本航空、SFCGなどの経営破たんと企業再生について、度々報じたことがあるのでお見知りおきかもしれません。弊誌の綿密な調査報道は、日本振興銀行の木村剛元会長や、オリンパスの菊川剛元社長の逮捕、起訴につながったことは、関係当局や内外メディアでもよく知られ、政界、官界、経済界に多くの読者を持つ雑誌となっております。
さて、今回はTFK(旧武富士)の更生計画について、A&PフィナンシャルからJトラストにスポンサー契約を切り替えた件を追跡取材しています。ご承知のようにA&P代表である崔潤氏から、小畑管財人およびJトラストの藤澤信義代表取締役に対し、東京地裁に民事訴訟が提起されていますが、これに関連して以下の5点につき、事実確認およびご見解をお尋ねしたいと考えました。お忙しいところ恐縮ですが、当時の経緯などについてご返答をいただけましたら幸いでございます。
① 武富士スポンサー選定の第一次入札で、御社のほかA&P、TPG、サーベラスの計4社に絞られた後、御社が一番札だったにもかかわらず外されたと噂されていますが、それは事実ですか。外された理由は何だったと考えますか。
② 2011年4月に武富士のスポンサー選定入札から降りて以降、あらためて小畑管財人側と接触を始めたのはいつか。
③ 同年11月に韓国金融監督院がA&Pに対し営業停止処分を行う可能性があると韓国紙が報じた後、A&P代表の崔潤氏と接触し、どのような折衝が行われたのでしょうか。その仲介に泉信彦管財人代理はどう関わっていましたか。
④ 同年12月19日時点までA&Pフィナンシャルと武富士支援について協働体制を協議していたにもかかわらず、その後、A&P側への通告等なしに小畑管財人との間で単独支援を決めてしまったのは信義則上問題がなかったのか、その見解をうかがいたい。
⑤ 崔潤氏が小畑管財人と藤澤代表取締役を相手取って起こした民事訴訟では、小畑管財人とJトラストが組んで、A&P外しのために12月20日の50億円不払いでスポンサー解除の理由づくりを行ったと主張され、録音資料などの証拠が提出されていますが、これにはどう反論しますか。
以上でございます。ご回答は直接面談、ファクス、メール、電話などいかなる形でも構いません。ただ、記事は次号(8月20日刊行)掲載を予定しておりますので、まことに恐縮ですが、締め切りの都合上、8月13日(火)を期限とさせていただきます。この件に関しては小畑管財人にも関連質問をさせていただいております。
お手数ですが、よろしくご一考のほどお願い申し上げます。
敬具
8月8日
これに対し、Jトラストおよび藤澤信義氏の代理人であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から8月12日にファクスで回答があった。
ファクタ出版株式会社
月刊FACTA発行人兼編集主幹
阿部重夫様
TFK更生計画に関する質問状の件
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
(担当・弁護士檀柔正・弁護士佐藤剛史)
前略
当職らは、崔潤氏からJトラスト株式会社及び藤澤信義氏に対して現在東京地方裁判所に提起されている民事訴訟につき、Jトラスト株式会社及び藤澤信義氏の訴訟代理人を務めております。
さて、貴社がJトラスト株式会社代表取締役藤澤信義宛に2013年8月8日に送付された「TFK更生計画に関する質問状」につきまして、当職らは、Jトラスト株式会社及び藤澤信義氏の委嘱を受けて、Jトラスト株式会社及び藤澤信義氏に代わり、ご連絡申し上げます。今回、頂戴したご質問につきましては現在訴訟係属中であるため、回答を差し控えさせていただきます。
また、今後、本件に関して、Jトラスト株式会社及び藤澤信義氏に対するご連絡事項がございましたら同社および同氏でなく当事務所宛にご連絡ください。
以上、ご了解のほど宜しくお願いいたします。
両回答とも事実上のノーコメントだが、記事にも書いたように、小畑弁護士の回答のほうが“脅し”文句を含んでいるが、どこが事実と違うのかの具体的な指摘がない。
武富士(TFK)更生計画に関する質問状1 小畑英一管財人宛て
FACTA最新号(13年9月号)では、巻頭記事に「武富士『更生』逆転劇の闇」を掲載しています。この記事では、武富士の管財人である小畑英一弁護士(LM法律事務所)に対して、弊誌は質問状を送りました。小畑氏の回答とともに、このブログで公開します。
まずFACTAの質問状から。
LM法律事務所
小畑英一先生
TFK更生計画に関する質問状
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。弊誌FACTAは調査報道を中心とした月刊誌で、小畑弁護士が管財人を務めた武富士、ロプロなどのほか、管財人代理を務めた日本航空、SFCGなどの経営破たんと企業再生について、度々報じたことがあるのでお見知りおきかもしれません。弊誌の綿密な調査報道は、日本振興銀行の木村剛元会長や、オリンパスの菊川剛元社長の逮捕、起訴につながったことは、関係当局や内外メディアでもよく知られ、政界、官界、経済界に多くの読者を持つ雑誌となっております。
さて、今回はTFK(旧武富士)の更生計画について、A&PフィナンシャルからJトラストにスポンサー契約を切り替えた件を追跡取材しています。ご承知のようにA&P代表である崔潤氏から、小畑管財人およびJトラストの藤澤信義代表取締役に対し、東京地裁に民事訴訟が提起されていますが、これに関連して以下の5点につき、事実確認およびご見解をお尋ねしたいと考えました。お忙しいところ恐縮ですが、当時の経緯などについてご返答をいただけましたら幸いでございます。
①2011年12月20日夜にA&Pフィナンシャル側に対して武富士のスポンサー契約について解除事由が生じたと伝える以前に、他のスポンサー候補と何らかの形で接触していた事実があるか(12月12日付ロイター通信報道等で少なくともTPGと接触していた事実が窺われるが、それについての見解も含めて)。
②泉信彦管財人代理(またはアドバイザー)が同年12月8日にA&P側と接触し、Jトラストとの協働に向けて協議を始めているが、これは小畑管財人の指示又は容認の下で行われたものか。
③同年12月20日に行われたA&Pと小畑管財人との協議ではJトラストも入れた協働支援体制について少なくとも方向性が確認されているが、その後、スポンサー契約が正式に解除される12月28日までの間、A&Pを蚊帳の外に置いた形でJトラストの単独支援へと話がまとまっていった経緯について、その理由は。また信義則上問題がなかったについての見解は。
④泉信彦氏との管財人代理あるいはそれに類する契約は現在も続いているのか(契約が終了しているのなら、その時期は)。
⑤管財人業務の一部について「クレディエンス」から出向者の受け入れを行っているようだが、これはいかなる契約の下で行われているものか。また、その契約期間、契約金額等はどうなっているのか。契約時期によっては泉信彦管財人代理(またはアドバイザー)の関係先に該当した可能性があり、その際、利益相半取引に当たる恐れがあるが、それについてのご見解をうかがいたい。
以上でございます。ご回答は直接面談、ファクス、メール、電話などいかなる形でも構いません。ただ、記事は次号(8月20日刊行)掲載を予定しておりますので、まことに恐縮ですが、締め切りの都合上、8月13日(火)を期限とさせていただきます。この件に関してはJトラスト側にも関連質問をさせていただいております。
お手数ですが、よろしくご一考のほどお願い申し上げます。
敬具
8月8日
これに対し、8月12日にFACTA編集部にファクスで回答書が届いた。
回答書は以下の通りである。
ファクタ出版株式会社
阿部重夫殿
更生会社TFK株式会社
管財人小畑英一
同管財人代理
弁護士柴田裕之
回答書
前略
当職は、更生会社TFK株式会社の管財人でございます。
さて、貴殿より、平成25年8月8日付「TFK更生計画に関する質問状」との書面を拝受しましたが、同書面にも記載されているとおり、現在、A&Pフィナンシャル等との間で訴訟手続が係属していることから、同書面起債の質問事項へのご回答は差し控えさせていtだきます。
なお、同質問事項には、事実と明白に異なる内容が多数含まれておりますので、この点、念のため申し添えいたします。
以上
『ライス回顧録』のススメ――熊本日日新聞寄稿
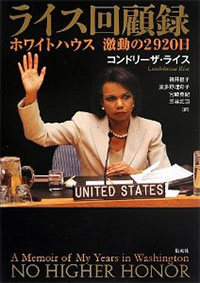 熊本日日新聞の書評欄で私が担当している「阿部重夫が読む」のコラムで、ブッシュ大統領の最側近だったコンドリーザ・ライスの『ライス回顧録』を書評しました。巻末に解説を書いている手嶋龍一氏から勧められました。イラク侵攻の03年、拙著の中公新書『イラク建国』で米軍統治が失敗するだろうと予言しただけに、その当事者である回顧録の書評は、むしろ使命かと思って引き受けました。
熊本日日新聞の書評欄で私が担当している「阿部重夫が読む」のコラムで、ブッシュ大統領の最側近だったコンドリーザ・ライスの『ライス回顧録』を書評しました。巻末に解説を書いている手嶋龍一氏から勧められました。イラク侵攻の03年、拙著の中公新書『イラク建国』で米軍統治が失敗するだろうと予言しただけに、その当事者である回顧録の書評は、むしろ使命かと思って引き受けました。
ところが、どっこい、2段組みで696ページもあって、7月下旬にズシリと重い本が届いてから、フーフー言いながら読みました。すでに第一期ブッシュ政権の国務長官だったコリン・パウエル、国防長官だったドナルド・ラムズフェルドの回想録を読んでいたので、細部の比較が面白く、ディテールが好きな人間には、いくらでも読み応えがあります。どこか、別荘地の緑陰で涼風に吹かれながら、どっちの言い分が正しいのだろうと想像をたくましくしたいところですが、あいにくそんな稼業ではない。
この暑いのに別件でソウルまで飛んで取材、かの地もうだるように暑く、とんぼ返りした翌日に書評締め切りという綱渡りの日程でした。ま、どうにか読み終えて、ライスという優等生の限界が透けて見えたのは収穫です。米国の大統領とか、国務長官のポストは、およそ個人の能力を超えた過酷な仕事なのかもしれません。ふと、マキャベリの「フォルトゥーナ」と「ヴィルトゥ」が思い浮かびました。
前者を「運」と訳すのも、後者を「徳」と訳すのも、『君主論』と『ディスコルシ』の趣旨とはずれてしまうのですが、やはりそこに残る政治の割り切れなさの世界に、ライスも呻吟したのだと言えましょう。
*****
歴史の一回性と決断の是非
コンドリーザ・ライス『ライス回顧録ホワイトハウス激動の2920日』
(集英社4400円+税)
スタンフォード大学教授からワシントンに乗り込み、ブッシュ大統領の最側近として国家安全保障担当補佐官と国務長官をつとめたコンドリーザ・ライスの自叙伝である。その経歴自体、ハーバード大学教授からニクソン政権に入り、米中接近とベトナム戦争終結を果たした「冷戦外交の鑑」ヘンリー・キッシンジャーに匹敵する。
彼女の輝かしい軌跡はしかし苦渋に満ちている。9・11テロの惨事を防げなかった国家安全保障の元締めとして、またアフガニスタンとイラクの泥沼に苦闘した外交の元締めとして。
原題「これ以上の栄誉はない」(No Higher Honor)からも、「されど」というアイロニーの倍音が聞こえる。歴史の一回性のもとで下した決断が、是だったか非だったか。自伝を執筆しながら彼女の胸を噛んでいた問いは、それ一つだったに違いない。
その問いにどう答えるか。古代ローマのギリシャ人歴史家、プルタルコスの顰みに倣おう。主著「対比列伝」(英雄伝)はローマ人(今)とギリシャ人(昔)の対比だが、アイデアは素晴らしい。絶対の規範のない政治の世界では、相対的な物差ししかないからだ。結果がすべての政治においては、人がなし得るのはタラレバしかない。
「ブッシュの戦争」が壮大な失敗だとしたら、どこで誰が何を誤ったのか。ことごとに内部対立したブッシュ政権の4人――チェイニー副大統領やラムズフェルド国防長官らネオコン派と、パウエル国務長官やライスらハト派の死闘から、それが窺えるはずだ。
「私は国務長官として、世界の現状が課してくる制約に常に自覚的だった。“可能性の技術”を実践しようと肚を決めていた」
本書の末尾にある言葉だ。もちろん、19世紀ドイツの鉄血宰相、ビスマルクの「政治とは可能性の技術である」を踏まえている。しかしそこに限界が見える。彼女は複雑に絡み合った難題に直面すると、数多くの「可能性」の中から忍耐強くベストの解を探しあてようとする。が、こんがらがった結び目を一刀両断にしたがるラムズフェルドにはこう映った。
「ライスは、省庁間の意見の違いを大統領に解決してもらうのは、自分の個人的落ち度になると思っていたのだろう。〝勝者〟と〝敗者〟が生まれるような、明快な決定を強要するのを避けた」(『真珠湾からバグダッドへラムズフェルド回想録』)
予定調和は「角の立つ問題」の後回しとツジツマ合わせを生む。しかしライスの回顧録は、口出しを嫌がるラムズフェルトの独善と狭量を批判し、責任転嫁を指弾している。
「ドン(ラムズフェルド)とジェリー(ブレマー・イラク連合暫定施政当局代表)の関係がうまくいっていないのは、ドンが戦後イラクのことを傍観していたからだ」
2006年、彼女はバグダッドを視察、深い絶望を覚えた。「大統領、私たちが今やっていることはまるで機能していません。本当に。失敗しようとしているんです」。チェイニーは沈黙していた。
気になる記述がある。同年10月、彼女は第一次政権の安倍首相と会談した。ブッシュが好感を持った小泉前首相と対比して安倍首相は「控えめで感情を見せず、形式のなかに本音を隠してなかなか奥が見透かせない」日本人の典型だが、北朝鮮に限っては「とても強硬な姿勢を見せた」と評している。オバマ政権の安倍〝冷遇〟の兆しが垣間見える。ポスト・オバマが誰になろうが、「木を見て森を見ぬ」日本への懐疑はワシントンに定着しているのだ。
フィリップ・K・ディックの処女作を翻訳しました
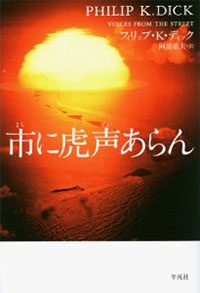 8月13日(同9日配本)に平凡社からフィリップ・K・ディックの幻の処女作を翻訳した「市に虎声あらん」(2400円+税)を出版します。
8月13日(同9日配本)に平凡社からフィリップ・K・ディックの幻の処女作を翻訳した「市に虎声あらん」(2400円+税)を出版します。
彼は映画「ブレードランナー」や「トータル・リコール」「マイノリティー・リポート」の原作者として知られるSF作家ですが、本来は純文学志向でした。この作品は25歳になる1952-3年に書いた普通小説で、カルトやマッカーシズム、核実験などを背景にした不思議な作品です。
終末観の漂う表紙は一見、夕日のように見えて、実は太平洋上で行われた核実験の写真です。現代のアミターユス(阿弥陀)はこういう来迎図で出現するのかもしれません。
一読、こんな若くしてすでに完成された作家だったという驚き。処女作らしく、後年のテーマがすべてぶちこまれています。しかも、ジョイスを模した前衛的手法を試みていて、そのショッキングなバイオレンス描写は、SFでは見せなかった彼の一面です。
それにしても事件取材の切った張ったの日々に、「酔狂」にも翻訳?そんな暇がよくあったな、とお叱りを受けそうです。
FACTA創刊から丸7年を過ぎ、余裕ができて「余技」に走ったわけではありません。原文を読んで、訳してみるかと思い立ったのはもう5年前になります。当時はまだ現役の編集長で、てんてこ舞いの日々でした。
確かに四半世紀前にディックのSFを2冊翻訳したことがあります。しんどくて、こんな辛気臭い作業など二度とやるまいと思いました。それから、スクープを追うほうが並みのミステリーを読むより面白くなり、現実の事件の推理と駆け引きとスリルの日々で、何も振り返らなくなりました。
でも、小説とはまるきり無縁の、殺伐たる資本の世界をひた走っていると、ヤマギシ会に材をとった女仕置人みたいなカルト小説が絵空事に見えてしかたがない。世界はもっとリアルで激烈なのに、その興奮を薄口にするのはもったいない。
そこに、埋もれていたディックの処女作が世に出てきました。一読して、ほかに訳す人など出てこないと思ったのが第一です。もう半世紀以上も前の世界なのに、リアルに人声と荒い息が聞こえる。
ときに酔眼朦朧の夜更け、あるいは寝ぼけ眼の早朝、一日二ページのペースでぼちぼち翻訳していきました。そこに何か見知らぬ世界が出現すると信じて。
そういう寡黙な作業は、取材の過程とそう変わりません。スクープからも翻訳からも、世界の「開かれ」Lichtungがあっていい。ここにはもう一つのアメリカが、くっきりと捉えられています。ご笑覧ください。もし気に入ったら、誰かにご紹介もお願いします。
週刊ポスト連載 伊藤博敏「黒幕」に期待する
 20年来の畏友であるフリーランス・ライターの伊藤博敏氏が、満を持して連載を開始した。
20年来の畏友であるフリーランス・ライターの伊藤博敏氏が、満を持して連載を開始した。
題して「黒幕」――主人公である石原俊介氏は4月に亡くなった情報誌「現代産業情報」の発行人で、事件取材に携わるジャーナリストの間では知る人ぞ知る存在だった。私もバブル崩壊後の90年代に彼を知り、たびたび謦咳に接し、ときに銀座の飲み歩きに付き合ったから、その通夜に参列した。
晩年はFACTAが追及した日本振興銀行をめぐる対立もあり、「恩知らず」と言ったという話も聞こえてきたから、出入り禁止(自粛?)状態だった。「兜町の石原ですが」とかかってくる電話も絶えていた。
伊藤氏から昨年、ガンで入院したとの話を聞いて、「そろそろ会おうかな」と思っていた矢先の訃報だった。80年代バブルから90年代のバブル崩壊にかけては、石原氏がもっとも輝いていた時代だった。その裏情報に、どのメディアも歯が立たない時代が確かにあったのである。
兜町のオフィスは、彼のメガネにかなったジャーナリストだけ出入りを許され、新聞もテレビも週刊誌も一流の事件記者なら、一目置かずにはいられない存在だった。どこであんな情報を入手できるのか、それが悔しくて夜も眠れぬ日が続いた。
没後、「現代産業情報」は廃刊となり、最終号は伊藤氏の追悼と廃刊の弁が掲載されていた。月2回、あのグレーのニュースレターが来なくなると、やはり寂しい。途方もなく大きな穴があいた気がする。
世間的には一介の情報屋だが、警察も検察も目を凝らしていた。彼の真の姿を書けるのは、伊藤氏のほかにはありえない。「現代産業情報」を継ぐのでは?と言われたほど、それを支える人物の一人だったからだ。
実は彼から、連載タイトルの相談を受けた。「黒幕」はやや大げさすぎ、私のつけた仮題のひとつは「影法師」だった。週刊誌では迫力が乏しいと採用にならなかったが、じぶんを大きく見せるという意味で、石原氏の実像は「影法師」に近かったと思う。
伊藤氏の仮タイトルは「最後の情報屋」である。「最後」に彼の思いがこもる。ネット掲示板やツイッターなどSNSの横行で、情報屋の存在意義は薄れた。「現代産業情報」も最後のほうではパワーの衰えが目立ち、喉元をえぐるようなエグい情報が離れていたことを示していた。
情報がカネになる時代は終わったのか。その問いは他人事ではない。伊藤氏とともにわれわれも、また大手メディアも、自らを顧みながら生きる道を探さなければならないのだろうか。連載が悲調を帯びるのは自然のなりゆきである。
ちょうど連載開始直後、アマゾンCEOのベゾフが、名門紙ワシントン・ポストを買収したと報じられた。どこも大変なのだ。人知れぬ情報はまだいくらも埋もれているはず、と信じるしかない。