EDITOR BLOG

高橋洋一「財投改革の経済学」のススメ2
日本経済新聞の11月25日付朝刊書評欄に、以前このブログで紹介した高橋洋一氏の著作「財投改革の経済学」が載っていた。学術書の体裁をとっていて、出版社の東洋経済新報社も部数を期待していなかったと思うから、こういう形で評判になることは著者のためにも、また日本の政策立案者(ポリシー・メーカー)たちにとってもいいことだと思う。
それにつけても、自民党の財政改革研究会(会長・与謝野馨前官房長官)が11月21日に発表した「中間とりまとめ案」はいささか大人げなかった。この手の中間報告には珍しく、敵意むきだしで「霞が関埋蔵金伝説」批判が書かれている。
「埋蔵金」という言葉自体、UFOや幽霊話などとともに、民放がよく流すこけおどし番組を連想させるもので、それに「伝説」とつけているから、よけいウソというニュアンスがこもっている。これは消費税引き上げ反対の民主党にあてつけたようでいながら、与謝野氏や財務省の宿敵、高橋氏がこの著作で主張している特別会計の「離れですき焼き」論を揶揄したものだろう。
しかし高橋氏の論拠は、04年の経済財政諮問会議で提示された特別会計の資産負債差額(清算バランス)に基づいて、「見えない資産」が50兆円あるとはじき出している。この清算バランスを正面から論じることなく、頭ごなしに「埋蔵金伝説」と罵倒しているのはいかがなものか。どうも与謝野氏の「高橋憎し」の私情が先に立って、論議になっていない気がする。
さて、11月14日にはバーナンキFRB議長が講演し、金融政策の透明性を高めるための追加措置を実施すると発表した。バーナンキ議長は、中央銀行が物価安定の数値目標を明示する「インフレ目標」論者だが、インフレ目標の導入は当面見送り、その代わりに3年先まで(現行は2年先まで)の経済見通しを年4回公表する(現行は年2回)。市場がFRBの政策意図を汲みやすくするのが狙いで、20日から実施の運びとなった。
英国やオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、スウェーデン、スペイン、韓国などに続いて、世界最大の経済大国の金融政策が「インフレ目標」の手法を採用するかどうかは、日銀にとって他人事ではない。ECB(欧州中央銀行)もすでにインフレ目標に準じた金融政策を実施しており、日銀が世界の孤児とも見えかねないのは、小泉政権時代に福井日銀が「政府に手足を縛られまい」と総力で抵抗したからだ。
今回、バーナンキFRBが、サブプライムなどによる市場の混乱もあって「インフレ目標」見送りを余儀なくされたため、日銀はほっと胸をなでおろしているという。インフレ目標論者のキング・イングランド銀行総裁が、ノーザン・ロックの取り付け騒ぎで非難を浴びたことも、日銀の溜飲を下げたようだ、
しかし、代替措置を見る限り、マクロ経済のパフォーマンスは金融政策が鍵を握り、インフレ目標によって市場に予測を共有させるにしくはないというバーナンキ議長の基本的な考え方が揺らいだとは思えない。11月20日に発表された向こう3年間の経済見通しを見ると、事実上のインフレ目標として機能し、ここから逆算される短期金利の指標フェデラルファンド(FF)レートは4.6~4.1%の範囲で、現状(4.5%)はその上限に近く、下げ余地があるとも見えるのだ。
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 実質GDP | 2.4-2.5 | 1.8-2.5 | 2.3-2.7 | 2.5-2.6 |
| 前回 | 2.25-2.5 | 2.5-2.75 | ||
| 失業率 | 4.7-4.8 | 4.8-4.9 | 4.8-4.9 | 4.7-4.9 |
| 前回 | 4.5-4.75 | 約4.75 | ||
| PCEインフレ率 | 2.9-3.0 | 1.8-2.1 | 1.7-2.0 | 1.6-1.9 |
| 前回 | なし | |||
| コアPCEインフレ率 | 1.8-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.6-1.9 |
| 前回 | 2-2.25 | 1.75-2 |
数字は、4Qの前年同期比。失業率は最終四半期の平均。
高橋氏の「財投改革の経済学」のもうひとつの目玉は、彼自身がプリンストン大学でFRB議長になる前のバーナンキ教授の謦咳に接し、その翻訳「リフレと金融政策」(バーナンキの著作の翻訳としてはエーベルとの共著である教科書「マクロ経済学」以外で唯一)の訳者であるという立場を生かして、「最適金融政策」とは何かを論じていることだろう。
数年前に日本の経済学界を騒がせたインフレ目標をめぐる論戦は、われわれ門外漢にもほとんど得るところがないほど低調なものだった。東大の教授連も日銀や民間のエコノミストも、誰ひとりインフレ目標がなぜ必要なのかを理論的に説明できない。賛成論者は欧州などで趨勢になりつつあるというファッション論でしかなかったし、反対論者は過去の理論を並べたてて反対の論拠とするだけだった。
本尊のひとり、バーナンキの主要業績とされている大恐慌分析ひとつ翻訳されていないし、バーナンキの同僚マイケル・ウッドフォードの主著「利子と価格」も未訳であることが、論戦の低調を裏付ける。あれでどうしてインフレ目標論の是非を論じられるのか、不思議でならなかった。が、理由が分かったのは、業を煮やして「利子と価格」の744ページもある原著を買ってみてからである。
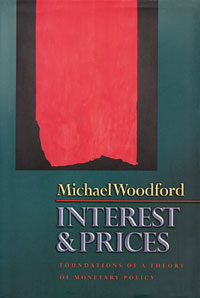 恥かしながら私には歯が立たない。そういう経験をしたのはこれで2冊目、フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンスタインの「ゲームの理論と経済行動」以来である。相当高度な数学の素養がないと、延々と続く数式に耐えがたくなる。両著とも英語の原書を買ってみたが、途中で投げ出してツンドク状態である。
恥かしながら私には歯が立たない。そういう経験をしたのはこれで2冊目、フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンスタインの「ゲームの理論と経済行動」以来である。相当高度な数学の素養がないと、延々と続く数式に耐えがたくなる。両著とも英語の原書を買ってみたが、途中で投げ出してツンドク状態である。幸い、私は専門のエコノミストではないからさぼっているが、一知半解のエコノミストたちは明らかにてあてずっぽうを並べ立てている。冗談で高橋氏に「どうせなら、ウッドフォードを訳したら」と言ったら。出版社が首を縦に振らないそうだ。なんとなれば、まず売れない(難解すぎて)、そして数式が理解できる人は日本語を必要としない、からだそうだ。日本の経済学とはその程度らしい。
「財投改革の経済学」では、そのウッドフォードの立論に基づいて数式で最適金融政策を導きだそうとしている。「利子と価格」にも第八章に「最適金融政策ルール」という章があり、高橋氏にそれに準拠したのかと尋ねたら、むしろプリンストンでの講義録に準拠しているという。
その議論を上手に説明する自信はない。高橋氏の記述に従えば、最適金融政策とは「経済に発生するショックに対して経済厚生の損失を最小化する政策」であり、家計の効用最大化を中央銀行の損失関数の最小化に置き換え、これを「インフレーションとGDPギャップの二次関数」で表すという。
マクロ経済の全体構造からみると、最適金融政策は、総需要曲線と総供給曲線のもとでこの中央銀行損失関数を最小化することによって得られる。これは「ラグランジュ乗数法」(制約条件のもとでの最小、最大の解法)によって解が得られるのだそうだ。高橋氏はここで、「裁量」と「コミットメント」に分ける。
裁量とは「金融政策が経済主体の期待に与える影響を所与として政策を実行することをいい、民間主体の期待を所与のものと外生化して、ラグランジュ乗数法によって最小解を求める」が、コミットメントとは「金融政策が経済主体の期待に与える影響を内生化し、それを考慮に入れて政策を実行することをいい、民間主体の期待を内生変数としてラグランジュ乗数法で最小解を求める」ことだという。
インフレ目標とは後者を指す。前者は金融政策の目標達成に責任を取る明確なものでなく、「曖昧で信認が得られないと、予想形成に及ぼす効果も不確定になる」として、高橋氏はコミットメント解からインフレ目標ルールと思える数式を導きだす。少なくとも私にとって、こういうロジックは新鮮だった。
政策論と言うより政治論のような、中途半端なインフレ目標論争とは次元が違う。水準の低い金融政策論はもう聞きあきた。財革研のような低次元の小股すくいでなく、ウッドフォードの数式の是非を問い、高橋氏に正面からチャレンジする論争を望みたい。
12月号の編集後記
FACTA最新号(12月号、11月20日発行)の編集後記を掲載します。フリー・コンテンツの公開は26日から。お楽しみに。
*****
無人の野を歩んで、不安に耐えられる人はそう多くない。茫々と地の果てまで道もなく、案内もいない。響くのは自分の足音だけ。調査報道も似ている。6カ月前、山田洋行疑惑を初めて報じたときはそうだった。元専務や本社の写真すらない。リアリティーは文章の中だけだ。自ら掘り出すスキャンダルとは、がらんどうの無音室で声を発するようなものだった。
▼でも、今は検察が“解禁”したから、どの新聞も思い切り書き飛ばしている。名誉毀損のリスクも、賠償訴訟のリスクもなし。人のあとからついていくのは楽なのだ。そのかわり、スクープの恍惚もないし、予見のときめきもない。時の権力者に徒手空拳で挑む恐怖もないし、他人の人生をぶち壊して覚える慙愧(ざんき)の念もない。
▼あれほど意気揚々としていた標的が、見る影もなくやつれて被疑者になっていく。それを見て快哉を叫びたくはない。スクープは逮捕にたどりついたらノーサイド。相手に恨まれたとしても、痛みを心の奥で抱えて、原野の電信柱のようにぽつんと立っていたい。
▼さて、トークイベント第2回として「FACTAフォーラム」を開こう。前回は手嶋龍一氏と参院選直前に政治を論じたが、今度は生命保険。年金不安が高まって「もう国には頼らない」とはいうが、自力で設計できるのだろうか。対面販売の生命保険をインターネットで売る試みが始まろうとしている。大手生保出身の出口治明氏(ネットライフ企画社長)を招き、敏腕セールスマンでファイナンシャルプランナーの大坪勇二氏と論じてみよう。12月3日19時30分から、東京の秋葉原UDX南ウイング6階のUDXカンファレンスで。参加費は一般4000円、本誌ご購読者と学生の方は2000円。詳細とお申し込みはウェブサイトで。
今度は「生命保険」でトークイベント
7月の参院選直前、本誌コラムニストの手嶋龍一氏とトークイベントをしたのが好評でしたので、12月3日(月)に第2回を開きます。今度のテーマは生命保険。それもちょっとひねって「生命保険はネットで買えるか」――。
「保険見直し本舗」なんてトランクスをはいて、亀田大毅を破ったボクシングのチャンプがいましたが、年金データ問題など公的年金の先行きに不安が広がるなかで、自分の生命保険も見直してみたいという人が増えています。
そういうニーズに応える保険の販売方法として、インターネットで保険を売る試みが本格的に始まろうとしています。年末から年初にかけて2社が金融庁の認可を受けてスタートしそうなので、このタイミングで「ネット生保」の可能性を探る議論をしてみたい。
パソコンなら、デルでもHPでも好きなパーツを組み合わせてネットで注文できます。しかし保険の仕組みははるかにややこしい。契約書の頭が痛くなるような細字と項目、そして何十年も先を見越した複雑怪奇な特約を知る人には、よほどのことがなければお得な商品をみつけるのは至難のわざと思えます。
それをテーラーメード化できるのでしょうか。「国にはもう頼れない」とみんな口にしますが、自力の設計は容易ではありません。では、対面販売で売り込まれるものが本当にいいのでしょうか。保険のセールスマンやセールスウーマンを見ていると、あのコストが保険料を高くしている気もします。
もともと、最先端のネットマーケティングに生命保険を乗せられるかどうかに興味がありました。ネット生保に挑むネットライフ企画の出口治明社長は、彼が日本生命の大蔵省担当やロンドン支店長だった時代からの知り合いで、会社を辞めて東大で恩返しのお手伝いをしていたのに、この新たな試みに身を投じた人です。インドのムガール朝の始祖バーブールの本を紹介してくれるなど、なかなかの教養人でもありました。その胸のうちをぜひ尋ねてみたい、というのがこのイベントを企画した出発点です。
ただ、私は日経の金融記者出身ではありますが、保険セールスの現場まではよく知りません。ここはセールスのプロ、それも凄腕の方をお招きし、新旧の保険販売を比較して、論戦を戦わせていただこうと思います。こちらはベテラン・セールスマンでファイナンシャル・プランナーの大坪勇二氏(ホロスプランニング東京オフィス長)をお招きしています。中南米や旧共産圏、アジアなどを放浪し、マッサージ師から大道芸までユニークな経験をお持ちの方です。司会役の私も辺境好きですので、ウマがあうかもしれません。
トークイベントの詳細は以下の通りです。本誌ご購読者に限りません。生命保険の未来に関心をお持ちの方は、業界人も素人さんも、ぜひふるってご参加を。
◇
トークイベント「生命保険はネットで買えるか?」
■概要
日時:2007年12月3日(月)19:30~21:30(開場 19:00)
会場:東京・秋葉原UDXカンファレンス RoomA+B
定員:120名(先着順)
参加費:定期購読会員2000円、一般4000円、学生2000円
■パネリスト
出口治明氏
(ネットライフ企画株式会社代表取締役)
1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当。生命保険協会において初代の財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に従事。ロンドン現地法人社長、国際業務部長、公務部長などを経て、同社を退職。2005年より東京大学総長室アドバイザーを勤めた。07年より早稲田大学大学院講師(非常勤)。著書の『生命保険入門』では、生保の真実を鋭く指摘し業界内で話題になった。
大坪勇二氏
(株式会社ホロスプランニング東京オフィス長、ファイナンシャルプランナー)
1964年九州生まれ。86年大学を休学し、世界を放浪(南米、北米、旧共産圏、アジア)。88年から鉄鋼メーカー・総合商社で9年間経理と人事を担当。 97年ソニー生命保険株式会社に入社、2003年エグゼクティブライフプランナー。05年株式会社ホロスプランニング東京オフィス創設に参画、オフィス長に就任。HPC®(ブレインズ株式会社開発によるヒアリングを主体とする顧客との信頼関係を短時間で構築する手法)研修講師として大手証券会社等多数実績を持つ。FP業界での起業グループ「キーストーンアライアンス」副代表を務め、IFA(インディペンデント・フィナンシャル・アドバイザー)等海外の新しい潮流を日本に取り入れることに熱中している。CFP®。02年MDRT日本会大会委員長、04年同国際委員長。MDRT7回会員(COT2回)。
→詳細・お申込みはこちらから
覆水盆に返らず――出戻り小沢氏
読者の方から大連立について数行でもコメントを、というご要望が寄せられました。
実はTBSラジオの「大沢悠里のゆうゆうワイド」で、月曜から水曜まで3回、この問題でコメント、というか、まあ感想を問われまして、私見を披露しました。一言でいえば、ジャーナリズムの側も翻弄され、小沢氏の辞意撤回とその裏で進んでいた大連立構想を軽々しく批評するのには躊躇せざるをえません。
こういうとき、あまり気のきいたこと、訳知り顔のことを言う人は、信じる気になれません。秦の王政(のちの始皇帝)に招かれた挙句に殺された吃りの貴公子、韓非の言葉を借りれば、「乱をもって治を攻むる者は亡び、邪をもって正を攻むる者は亡び、逆をもって順を攻むる者は亡ぶ」です。
つまり、政治の要諦は秘密にあるとはいっても、「お国のため」を名分にしたアクロバチックなサプライズでは、誰もついてこないし、わが身を滅ぼすということでしょう。ナベツネさんは奇をてらいすぎで、冗談で言えば、巨人軍がリーグ優勝しながら日本シリーズに出られなかった憂さ晴らしを、こんなところでしてもらっては困ります、ということでしょう。
小沢さんも、福田さんも、元の鞘には収まらないでしょう。政治に逆戻りなんてない。大連立は自民一党支配への郷愁で、中選挙区制にすれば公明、社民、共産などみなハッピー。そういう既得権みたいな思考が、永田町の各党には底流としてあって、大連立はいかにも後ろ向きの発想です。
先輩の田勢さんが言うように、法案が一本も通らず、国政が停滞しているのは事実。でも、政争となれば政治家ほどエゴな人たちはいない。血が騒いで国民などそっちのけ、ましてや自分の選挙にかかわることですから、国政停滞なんて常に口実か隠れ蓑にすぎません。
さて、次号をどうするか。大沢さんには言いましたが、日替わり政局で誌面は大混乱、綱渡りの日々です。いまは締め切り期間で、連日のように帰宅は午前4時すぎ。木曜はラジオは勘弁していただきました。どの雑誌の編集長も、過労死すれすれで悲鳴をあげているのではないかしらん。
高橋洋一「財投改革の経済学」のススメ 1
 著者の名を見て、おや、と思った人は、相当な永田町・霞が関通である。彼は小泉・安倍政権の知恵袋だった財務省出身の官僚なのだ。だからこそ、安倍政権の崩壊直前、内閣府参事官の職を事実上追われる身となった。詳しくは、安倍晋三氏と同じ山口出身である元テレビ朝日政治部長の末延吉正氏(立命館大学客員教授)の手記「我が友・安倍晋三『苦悩の350日』」(月刊現代11月号)を参照。
著者の名を見て、おや、と思った人は、相当な永田町・霞が関通である。彼は小泉・安倍政権の知恵袋だった財務省出身の官僚なのだ。だからこそ、安倍政権の崩壊直前、内閣府参事官の職を事実上追われる身となった。詳しくは、安倍晋三氏と同じ山口出身である元テレビ朝日政治部長の末延吉正氏(立命館大学客員教授)の手記「我が友・安倍晋三『苦悩の350日』」(月刊現代11月号)を参照。
偶然とはいえ、その当人が一月も経たないうちに、自ら設計した「改革」の手の内を示す本を出版したのだから、これは手に取らずにはいられない。小泉・安倍政権の改革とは何だったか、凡百の駄本を読むより、当事者が書いたこの一冊を読めば、それで事足りるからである。
本の帯に竹中平蔵・慶応大学教授の推薦の弁――「今後、公的金融システムに関する分析や政策論議において、本書は間違いなく改革の基本バイブルとなる」という言葉が載っているが、当然だろう。竹中氏が立て板に水で語る政策論は、高橋氏のアイデアによるところが多いからだ。
現に10月30日、竹中氏は来年、慶応大学創立150年記念で誕生する大学院システム・デザイン・マネジメント研究科とメディア・デザイン研究科の記念シンポ(司会・村井純教授)で講演して、「政治家でなく学者として」プロモーションに励んでいたが、そこで得々と語った成長万能路線は、高橋氏のライジング・タイド(上げ潮)を見事に踏襲していた。
高橋氏とはもう15年近くの付き合いだから、ここで書評を試みたい。でも、本書は小泉・安倍政権の改革アジェンダのほとんどを網羅しているのだ。財政・財投改革、郵政民営化、特殊法人改革から金融政策論まで広すぎて小生の手に余る。そこで、最後の章の「他の政策への影響」だけに絞ろう。
まず政府資産・負債管理政策。ここにめっけものの数字がある。国の貸借対照表から浮かびあがる特別会計の「見えない資産」である。これまであるあると言われてきたが、霞が関の「隠しポケット」が、本書で裸にされている。かつて塩爺、こと塩川正十郎が言った「母屋(一般会計)でおかゆ、離れ(特別会計)ですき焼き」の実態はこれなのだ。
高橋氏のデータは、05年4月27日の経済財政諮問会議で明らかにされた数字に基づいている。これは各特別会計について、継続中の事業をのぞき新規事業を行わないという前提ではじきだした資産負債差額(清算バランス)の推計額である。
それによると、特会に隠された主な「見えない資産」、つまりプラスの清算バランスは
財政融資資金特別会計53兆円(現在価値23兆円)
国有林野事業特別会計4・5兆円(同4・5兆円)
労働保険特別会計6・5兆円(同5・1兆円)
空港整備特別会計2・3兆円(同1・9兆円)
自動車損害賠償保証事業特別会計1・2兆円(同0・7兆円)
当時の奥田委員が「こんなにあるのか」とのけぞったという数字だ。道路特別会計にもこの「見えない資産」があるのに、経財諮問会議には数字を公表しなかった。新規の道路需要がそれほど増加していないことを考えると、独自財源が余剰する可能性が高く、「見えない資産」は10兆円以上あるという。
省庁はこうした特会の隠し資産を手付かずにしておいて、一般会計から国費を繰り入れている。高橋氏の指摘では、労働保険特会は資産負債差額4・2兆円は、責任準備金8・0兆円に対し50%以上あり、保険料が高すぎるおそれがある。空港整備特会も同じだ。資産負債差額が2・3兆円もあるだけに、一般会計からの繰入額も空港使用料も「ぼったくり」の可能性があるという。
高橋氏は「離れですき焼き」は計50兆円規模とみる。民主党が知ったらほくそ笑むだろう。消費税1%引き上げで税収が1兆円の増収になるが、50兆円も「隠しポケット」に抱えていながら、一銭もたくわえを崩さずに消費税引き上げが通るはずもない。
皮肉なことに、高橋氏のこの本は消費税引き上げ論を覆す決め手になるのだ。
この書評の続きは次回に書こう。金融政策論までとても手が回らない。
田淵節也氏と青木昌彦氏
1日から野村證券元会長の田淵節也氏の「私の履歴書」の連載が日経で始まった。取材等でお世話になった。思い出したのは、日経ビジネスで4回連載のインタビューを載せたことである。証券不祥事などで国会に呼ばれ、苦労したあとだったが、さまざまな苦悩を洗い流したような静かな表情が忘れられない。
今回の履歴書でも、初回から食道がん手術2回、目の下の腫瘍に放射線治療したことを書いている。あのゆっくりした口調そのものの淡々とした文章だ。
最後にお会いしたのは何年前だろうか。笹川平和財団の定期刊行物に田淵さん自身がインタビュアーになるコラムがあって、私がインタビュイーになるという、いつもとは逆の立場になった。日産ゴーン論などを語ったのが恥ずかしい。そのお礼に行ったのが最後で、ご病気とうかがって遠慮したままになっている。近況の写真が元気そうなので安堵した。
田淵氏も書いているように、昨日連載が終わったスタンフォード大学名誉教授の経済学者、青木昌彦氏の「私の履歴書」は出色だった。60年安保の全学連のエピソードが面白い。故唐牛健太郎とあんなに親しかったのかと驚いた。
先月19日、履歴書を手伝った日経の元編集委員のパーティーで青木氏の顔をお見かけした。いつ書くかと最後まで期待したのが、桐島洋子氏とのエピソードである。あれだけ全学連時代のことを率直に書くのだから、新藤兼人が愛人乙羽信子を書いたように書くのかなと思っていたが、結局肩透かしだった。
エコノミストの大半はそれを期待していたのではないか。でも、やはり相手が生きていては書きにくいのだろう。今の奥さんに気兼ねした、とも漏れ伝わってくる。
自叙伝は常にヴェールに包まれる。残念だが仕方がない。